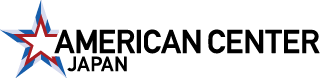米国プロファイル
アメリカ合衆国のポートレート - 第6章「多様な教育制度」
アメリカでは、1つの学校が官民の複数の機関の支持を得て成り立っていることもあり、アメリカの教育を一口で語ることは難しい。たとえば、私立高校でも、カリキュラムは州政府の基準に従い、科学の授業は連邦政府の資金援助を受け、スポーツチームは地元の公共施設で練習をする、といったケースがある。
このように複雑ではあるが、アメリカの教育の概要を述べることはできる。
アメリカの高校以下の児童・生徒の9割近くは、公立の初等・中等学校に通っている。これらの公立学校には授業料がなく、運営資金は地方税・州税に頼っている。従来、小学校は幼稚園から8年生までであるが、場所によっては小学校が6年生までで、7年生から9年生まではミドルスクールまたはジュニア・ハイスクールとなっている地域もある。同様に、中等学校すなわちハイスクールは、従来9年生から12年生までであるが、これも10年生からの場合もある。
公立学校に行かない児童・生徒の大半は、授業料を払って私立学校に通っている。アメリカの私立学校の5校に1校は、宗教団体が運営している。そのような学校では、通常の学科のほかに、宗教の授業がカリキュラムに組み込まれている。(公立学校には宗教の授業はない。公立学校におけるお祈りの問題については第4章を参照。)このほかに、ホームスクーリングといって、親が家庭で子どもを教育する例があり、全体数は少ないものの、その数は増えている。
アメリカには全国的な学校制度はない。また、メリーランド州アナポリスの海軍士官学校のような士官学校を除けば、国立の学校もない。しかし、連邦政府が指導し、資金を提供する連邦教育プログラムには公立校と私立校が参加しており、連邦政府教育省がこれらのプログラムを監督している。
アメリカでは、相互に関連する科目について高等教育を提供する4年生の学校をカレッジという。たとえば、リベラルアーツ・カレッジには文学・語学・歴史・哲学・科学、ビジネス・カレッジには会計学・投資・マーケティング等の講座がある。カレッジの多くは独立した機関であり、ふつう4年間の課程を修了した者には学士号を授与する。しかし、総合大学(ユニバーシティ)の一部として存在するカレッジもある。通常、大規模な総合大学には、複数のカレッジ、大学院、1つ以上の専門大学院(法律大学院、医学校など)、及び1つ以上の研究施設がある。(アメリカ人は、カレッジも総合大学も「カレッジ」と呼ぶことが多い。)
どの州にも州立大学があり、いくつものカレッジや総合大学の大規模なネットワークを運営している州もある。たとえば、ニューヨーク州立大学は、ニューヨーク州内60カ所以上にキャンパスがある。また、市立大学を運営している市もある。2年制のジュニア・カレッジやコミュニティ・カレッジのある地域も多く、こうしたカレッジは、高校と4年制大学との橋渡し的な役割を果たしている。通常、ジュニア・カレッジでは、大学2年までの単位を、地元で安い授業料で取得することができる。
公立の初等・中等学校と異なり、公立のカレッジ、総合大学の学生は、ふつう授業料を払わなければならない。しかし、公共の援助をそれほど受けない私立大学に比べると、公立大学の授業料はかなり安い場合が多い。公立、私立を問わず、連邦政府の学資ローンを受けて大学にいく学生は多いが、卒業後ローンを返済しなければならない。
アメリカのカレッジ、総合大学の約4分の1は、宗教団体が運営する私立大学であるが、その大半は、信教にかかわらず誰にでも門戸を開いている。宗教色のない私立大学も多い。公立、私立を問わず、大学は資金源として、学生が納める授業料、篤志家からの寄付金、政府の補助金の3つに依存している。
公立大学と私立大学の教育の質には、明らかな違いはない。たとえば、カリフォルニア州やバージニア州の公立大学は、アメリカ北東部の優秀な私立大学8校から成るアイビーリーグと同等のレベルにあるとされている。しかし、どの大学も平等というわけではない。評判の高い大学の卒業生が、就職の際に明らかに有利になることもあり得る。したがって、知名度の高い大学は入学の競争が激しくなることもある。
大学生は、自分の専攻分野の授業と、必修ではない選択科目の授業をとる。アメリカのカレッジ、総合大学には、合計1,000以上の専攻分野があると推定されている。
ハワイからデラウェア、アラスカからルイジアナまで、アメリカ50州では、各州が独自の法律で教育を規制している。各州に共通する規則もあれば、州によって異なるものもある。
●どの州も子どもの就学を義務付けているが、義務教育の年齢は異なる。16歳までを義務教育とする州が多いが、18歳としている州もある。したがって、アメリカの子どもは必ず、少なくとも11年間は教育を受けることになる。子どもは、性別、人種、宗教、学習障害、身体障害、英語会話能力、国籍、移民資格にかかわらず、教育を受けることができる。(不法移民の子どもには公教育を受ける権利を与えないことを州に許可する法案を支持している議員もいるが、まだそのような法律は存在しない。)
●州政府が中心になって教材を選択している州もある。たとえば、どの教科書を州の資金で購入するかを、州の委員会が決める場合がある。他の州では、そのような決定は各地の学校関係者に任されている。
アメリカには全国的なカリキュラムはないが、全国ほぼすべての初等・中等学校で教えられている科目がいくつかある。小学校では、ほぼ例外なく、数学、国語技能(読解・文法・作文・文学)、習字、科学、社会(歴史・地理・公民・経済)、体育を教えている。コンピュータの使い方を教えている学校も多く、各科目の授業にコンピュータが組み込まれている。
中等学校では、必修科目(アメリカ史1年間、文学2年間等)のほかに、大学のような選択科目がある。人気のある選択科目には、舞台芸術、自動車教習、料理、工作(工具の使い方、木工、機械修理)などがある。
1950年代までは、必修科目が多く、選択科目はあまりなかったが、1960年代・70年代に、生徒の選択の範囲を広げる傾向が強まった。しかし、1980年代には、親も教育者も、こうした状況を見直し始めていた。アメリカの子どもたちの数学・読解・科学の標準テストの平均点が、徐々に、しかし確実に下がってきたことと、選択科目の増加との間に、関連があるのではないかと考えられたためである。
これと時を同じくして、大学の入試担当者や企業の管理職が、「読み・書き・算数」の基礎ができていない高校卒業者がいる、との不満を述べるようになった。1980年の国勢調査では、アメリカの成人の約99%が、読み書きができると述べている。しかし批判派は、17歳のアメリカ人の約13%が「機能的文盲」であると主張している。機能的文盲とは、印刷物を読んで理解したり、企業の採用申込書に書き込んだりする日常的な読み書きの作業ができないことをいう。
専門家は、1980年代初めに、テスト平均点の低下について、考えられるあらゆる原因を調査した。その1つとして挙げられたのがテレビで、あまり質の高いテレビ番組がないと非難された。また、アメリカの子どもたちのテレビ視聴時間は週平均25時間にも上り、テレビを見すぎているという批判もあった。教師の給料が安すぎるために優秀な教師がやめてしまいがちなこと、生徒が全員卒業できるように授業のレベルを下げていることなどを理由に、教育委員会も批判された。
アメリカの中等教育を悩ます問題の原因として単一の要因を特定することができないのと同様、単一の解決法を特定することもできなかった。連邦政府教育省は、この問題を検討するための全国委員会を設立した。この委員会は1983年に、1日の授業時間と年間授業日数の増加、生徒全員に適用される新しい必修科目カリキュラムの作成(英語4年間、数学・科学・社会各3年間、コンピュータ科学6カ月間)、及び各科目の評価基準の引き上げなどを勧告した。その結果、多くの学校がカリキュラムや評価を厳しくし、以来、アメリカの子どもたちのテスト成績は上昇を続けている。
1989年、ブッシュ大統領と全米50州の各州知事が、2000年までに達成されるべき次の6つの目標を設定し、アメリカの教育改革への動きをさらに推進した。
- 子どもたち全員が、就学時には、学習する準備ができていること。
- 高校生の9割が高校を卒業すること。
- 児童・生徒全員が、いくつかの主要な時点において、必修科目を習得していること。
- アメリカの子どもたちの数学・科学の成績が世界で最もすぐれていること。
- アメリカの成人全員が識字能力を持ち、市民として、労働者として機能する技能を持っていること。
- すべての学校から麻薬と暴力を排し、学習を促進する規律正しい環境を提供すること。
連邦議会は、各州の目標達成を援助するために連邦補助金を提供する「ゴールズ2000」という制度を設立した。1996年にはこうした努力の成果が見られるようになり、アメリカの高校生の86%が高校を卒業し、数学・科学の全国テスト成績は1評価段階上昇し、4歳児の50%が就学に備えたプログラムに参加するようになった。
一方で、数学、科学、英語、歴史の各科目で全国評価基準を設定する努力も続いており、クリントン大統領もこれを強く支持している。大統領は1996年の全国州知事会教育サミットでのスピーチで、「生徒に多くを期待すること、学習する自信を持たせること、学習の成果を評価すること、そしてよい成果に報奨を与えるだけでなく、生徒自身に責任を持たせることが、最も重要だと思う」と語った。
成績の問題に加えて、アメリカの学校は新たな課題に直面している。それは、ほとんどあるいは全く英語を話せない移民の子どもたちの流入にどう対処するかという課題である。アメリカの学校は、子どもたちのさまざまな文化を反映したカリキュラムを要求する声に対応しなければならない。また、生徒たちが労働市場に備えた基礎技能を身につけることを保証するとともに、十代で母親になる女生徒など特殊な状況にある生徒たちのニーズをも考慮しなければならない。
アメリカの学校は、アメリカの教育制度の多様性を反映した各種対応策をとっている。外国語としての英語を教える教師の雇用・訓練が大幅に増えているほか、地域によっては2カ国語教育を行う学校が設立されている。また、従来の欧州文化中心のカリキュラムに、アフリカ、アジア等の文化に関する教材を加えるようになっている。
アメリカの生徒の4割近くは高等教育機関へ進学しないが、学校ではこれらの生徒たちにも認識技能を教えている。「必要知識習得に関する委員会」が最近発表した報告書は、次のように述べている。「かつてアメリカでは、頑健な体と労働意欲と高卒の学歴があれば、社会人としての生活を始めることができた。しかし、そういう時代は終わった。十分な思考力、継続的な学習の意志、そして知識を実用化する能力が、アメリカの若者の将来と事業の成功と経済発展の新たなカギである。」
アメリカは、若者のうち高等教育を受ける者の占める割合では、世界の工業国の中でも第1位である。法律、医学、教育、技術といった職業につくには、その第1歩として大学教育が要求される。今日、アメリカ人の6割以上が、情報の取扱を必要とする職業についており、通常そうした仕事には高卒の学歴では不十分である。その他の職業では、必ずしも大卒の学歴が要求されることはないが、大卒の方が就職できる可能性が高く、また給料も高くなる。
アメリカにおける大学教育の広範な普及は、1944年に遡る。この年、連邦議会は、俗に「GI法案」と呼ばれる法案を通過させた。(GIとは「government issue(官給)」の略で、アメリカ軍兵士のことをGIと呼ぶ。GI法案は、第2次世界大戦後、アメリカ軍兵士たちに奨学金を提供することを定めたもの。)1955年までに、第2次世界大戦と朝鮮戦争の退役軍人200万人以上が、GI法案による奨学金で大学に行った。その多くは貧しい家庭の人たちで、GI法案がなければ大学に行く機会がなかったと思われる。この制度が成功を収めたことで、誰が大学へ行くべきかということについてアメリカ人の考え方が変わった。
これとほぼ並行して、アメリカの大学生に占める女子の割合が着実に増えていった。1950年には、全米の大学の学位授与数の24%が女子学生に対するものだったが、1993年には女子学生への学位授与数が全体の54%を占めた。また1950年代・60年代に人種差別制度が撤廃されると、アフリカ系アメリカ人の大学進学者数が記録的に増えた。しかし、アフリカ系アメリカ人の大学進学率は、アメリカ人全体に比べると、依然として低い。1992年に高校を卒業したアフリカ系アメリカ人のうち47.9%が大学に進学したが、全国の高校卒業者の大学進学率は61.7%だった。
アメリカの大学も、高校の場合と同様に、必修科目を廃止して選択科目を増やしすぎているとの批判を受けることがある。1980年代半ばにアメリカ大学協会が発表した報告書では、大学生全体に一定の共通知識を教えることを要求している。また全米教育研究所が発表した同様の報告書「Involvement in Learning」は、大学のカリキュラムが「過度に・・・職業志向」になっているとの結論を述べている。同報告書は、大学教育はもはや、従来アメリカ民を結ぶ絆となってきた「共通の価値観と知識」を学生の中に育む役割を果たしていない可能性がある、と警告している。
これらの報告書が発表されたのは、一般教育からの離反の傾向と時を同じくしている。一般教育より、特定の職業のための準備を目的とする専攻を選ぶ学生が増えた。1992年には、学士号の51%が、ビジネス・経営、コミュニケーション、コンピュータ・情報科学、教育、技術、医療科学の各分野で授与されている。
こうした傾向がもたらす疑問は、あらゆる工業国の教育哲学に当てはまる。すなわち、画期的な技術の進歩と高度な専門化の時代に、幅広い知識とすぐれた論理・伝達能力を持つゼネラリストがまだ必要とされるのだろうか、という疑問である。そして、その答が「イエス」であるなら、大学がそのようなゼネラリストをさらに多く生み出すことを奨励するため、社会が何らかの対策をとるべきなのか。アメリカの教育関係者も、他の諸国の教育関係者と同様、これらの疑問について討論を続けている。
*上記の日本語文書は参考のための仮翻訳で、正文は英文です。