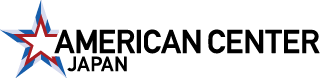米国プロファイル
アメリカ合衆国のポートレート - 第5章「アメリカの産業」
カルビン・クーリッジ大統領は1925年に、「アメリカのビジネス(本分)はビジネス(商売)である」と述べた。これは、まさに的を射た発言である。「本分」を「最大の関心事」と言い換えれば、この発言が、アメリカの繁栄を支えている起業家精神というものを端的に表していることがわかる。
この章では、アメリカの最初の産業である農業、アメリカ式大量生産、労働運動、及び経済制度について述べる。
アメリカの農業は、この200年間に大きく変貌した。アメリカ独立戦争(1775~83年)当時は、人口の95%が農業に従事していたが、今日の農業人口は全体の2%に満たない。アメリカの農場の85%は個人または家族の所有だが、個人・家族所有の農地は全体の64%にすぎない。残りは大小の企業が所有しており、農業及び関連産業は、「アグリビジネス」と呼ばれる一大産業となっている。しかし、こうした変化にもかかわらず、農業はアメリカの生活における不変の要素であり、アメリカで生産される食糧は、安全、豊富、かつ廉価である。
農民たちは、アメリカの歴史の初期に国の気風を確立した。農民の生活は不安定な天候や市場に左右されるため、一般に言われるほど完全な自給自足ではなかったが、彼らが示した個人主義と平等主義は、社会の称賛を受け、模倣された。
開拓が東から西へ広がるに従い、アメリカの農業は、世界でもほとんど類を見ない豊かさと多様性を備えるようになった。これは今日に至るまで変わらず、主として豊富な土地と自然の恵みによるものである。西部の一部地域が雨の少ない砂漠になっている以外、アメリカ各地とも、降雨量に差はあるが、雨に恵まれている。また必要があれば、河川や地下水を利用した潅漑ができる。特に中西部は、平地やなだらかな丘陵が広がっているため、大規模農業に最適である。
アメリカのほとんどの地域では、土地が広すぎる上に労働力が足りないため、地主階級が大農園を所有し農民の大半が小作人となる英国式の制度は定着しなかった。北アメリカの農業は、多数の家族経営の農場を中心に発展した。こうした農場は、村落の周辺に集まるのではなく、広範囲に散らばり、孤立する傾向があったため、農民の個人主義と自立が促進された。
新しい技術を進んで受け入れるのがアメリカの農民の特徴の1つであり、19世紀を通じて次々と新しい道具や発明が導入された。例えば、穀物の刈入れには手鎌に代わって枠付の鎌や大鎌が登場し、さらに1830年代にはサイラス・マコーミックが発明した自動刈取り機がそれに取って代わった。南北戦争(1861~65年)の頃までには、干し草作り、脱穀、草刈り、耕耘、種まきといった作業は機械化されており、その結果、生産性が大きく向上した。
農業生産の増大に貢献したもう1つの要素は、19世紀後半に移民がミシシッピ川を越えて急速に広がっていったことである。連邦政府は、「自営農地法」をはじめとするさまざまな法律により、国内移住を奨励した。1862年に制定された同法は、移民に一戸につき65ヘクタールの「自作農場」をわずかな価格で与えるというもので、家族経営による小規模な農場という、現在のアメリカの農業の形態の基礎を作り上げた。
機械の発明や農業優遇策の効果が行き過ぎた時期もあった。南北戦争後、過剰生産が深刻な問題となった。需要が供給に追いつかず、農産物の価格が下落した。1870年代から1900年前後は、アメリカの農民にとって特に苦しい時期だった。
1862年に農務省が設立されると共に、連邦政府が農業に直接関与するようになり、政府が農民に土地の生産性向上策を指導することもあった。20世紀初めに農業が一時繁栄した後、1920年代には農産物の価格が下がり始めた。1930年代の大恐慌でさらに価格が下がり、1932年には、平均すると1920年代の3分の1以下となった。その結果、何万もの農家が破産に追い込まれた。今日の農業政策の多くは、1930年代の苦境と、ニューディールによる救済策に遡ることができる。
今日の農業政策は、複雑な各種の法律から成る。過剰生産が農産物価格を下落させるとの理論に基づき、場合によっては政府が農家に補助金を出して減産を指示することもある。産物によっては、政府の融資、つまり「価格支持」を受けるための担保となる。議会が定めた「目標価格」と実際の販売価格との差額を払い戻す不足払い制度もある。また西部諸州の農民は、連邦政府のダムや用水路から低料金で水を引くことができる。
価格支持や不足払いが適用されるのは、穀物、乳製品、綿花などの基礎産物に限られ、連邦政府の補助の対象とならない作物も多い。農業補助金制度は、大規模農家にとって最も有利であり、農場の大規模化・少数化を促進するものとして批判されている。例えば、最近のある1年間を見ると、数の上では全体のわずか5%にすぎない、売上高25万ドル以上の農家が、政府の農業補助金の24%を受けている。農業における政府の役割を抑制し、農家への補助金を削減しようとする動きが広がっている。しかし、有力な利害関係者が現行の農業政策を支持しており、議会では農業政策の変更の提案を巡って激しい論議が起きている。
概してアメリカの農業は成功を収めてきた。アメリカにおける食糧の消費者価格は、多くの工業国に比べて低く、また、耕地の3分の1では輸出用の作物が作られている。1995年には、農産物の輸出が、輸入のほぼ2倍となった。
しかし、農業の成功の裏には犠牲もある。環境保護派は、アメリカの農業は人工肥料や除草剤・殺虫剤の過度の使用によって環境を破壊していると主張する。州および連邦政府は、水・食糧・大気等の資源を慎重に保護しているが、有害な農薬が、時としてこれらの資源を汚染している例も見られる。
一方、全国各地の研究所では、科学者が長期的な解決法を求めて研究を続けている。彼らは、遺伝子接合などの革新的な技術により、有害な化学薬品を使わずに、害虫のつかない、成長の速い作物を開発することを目指している。
アメリカの自動車王ヘンリー・フォードは、1922年に出版した自伝「My Life and Work」の中で、「どれだけ安く物を作れるか」、「金銭は主人か下僕か」、「なぜ貧困に甘んじるのか」といった質問を各章の題にしている。
これらは、何世代にもわたってアメリカの実業界・産業界の指導者の心をとらえてきた質問である。その答を求めて実業家たちは、より多くの製品を、より安く作り流通させ、より大きな利益を上げることを目指してきた。そして、かなりの部分、それを実現してきた。
アメリカでは、商工業が発展した19世紀から20世紀初めに起った数回の移民ラッシュにより、人口が急速に増えた。人口の増加は、安定した労働力を供給するのに十分だったが、経済を圧迫するほどではなかった。
産業の発展を支えたもう1つの要素として、アメリカの特徴である起業家精神が挙げられる。アメリカの起業家精神は、神は勤労を喜ぶとする清教徒あるいはプロテスタントの倫理観に基づく宗教的な背景を持つという見方もある。しかし、特に19世紀後半及び20世紀初頭の「追いはぎ成金」のような、アメリカの一部の事業家の冷酷さは、宗教心とは相容れるものではないとの意見もある。
18世紀後半に、アメリカの製造業は工場制度を採用し、大勢の労働者を1カ所に集めて働かせるようになった。これに加えて、新たな「アメリカ方式」として大量生産が行われるようになった。大量生産方式は、1800年頃、火器製造業で初めて採用された。この新方式は、精密工学技術を使って、製造業を、交換可能な部品の組立に変身させた。その結果、最終製品の製造が工程化できるようになり、工員はそれぞれ別個の作業を専門に行うようになった。
1830年代に始まった鉄道建設は、アメリカに新時代をもたらした。1862年には、議会が最初の大陸横断鉄道用に公有地を確保することを決定し、鉄道建設のペースに拍車がかかった。鉄道は広大なアメリカの各地域を結び、世界初の大陸横断市場を創出するとともに、移民の広がりを促進した。また鉄道の建設は、石炭・鉄・鉄鋼の需要を生み出し、南北戦争後の重工業の急速な発展に貢献した。
1890年の国勢調査で、初めてアメリカの工業生産高が農業生産高を上回った。以後、アメリカの工業は急成長時代を迎えた。1913年には、アメリカは世界の工業生産の3分の1以上を占めていた。
同年、自動車製造業者ヘンリー・フォードが、コンベヤ・ベルトで部品を作業者に運ぶ自動組立ラインを導入した。この革新的な技術は、効率を向上させ、労務費の大幅な削減を可能にした。また、これを契機に、工場経営者は、より効率が高く、よりコストの低い作業方法を実現するため、作業過程を研究するようになった。
コスト削減により、労働者の賃金が上昇し、消費者価格は下がった。アメリカ製の製品を購入できるだけの余裕を持つ国民が増えていった。20世紀前半の、自動車、冷蔵庫、台所のレンジなどの消費財の大量生産は、米国民の生活に革命をもたらした。
しかし一方で、自動組立ラインは、労働者にさまざまな影響を与えるものとして批判され、チャーリー・チャップリンの映画「モダン・タイムス」(1936年)では風刺の対象となった。近年、工場経営者は、製造のスピードや効率と共に、製品の品質も重要であること、また作業に飽きた、気力のない労働者は作業の質が落ちることを再発見した。自動車工場をはじめアメリカの多くの工場では組立ラインを改変し、「品質サークル」と呼ばれるようなチームが1台の車を最初から最後まで担当し、時には作業員が異なった種類の作業もするような制度を導入している。
アメリカが、20世紀に起きた2つの世界大戦で、他の国が被ったような惨害を免れたことは、幸運だった。1945年の第2次世界大戦終結までに、アメリカは世界で最も高い生産性を誇り、「メード・イン・USA(アメリカ製)」という言葉は、品質の高さを示す代名詞となっていた。
20世紀のアメリカでは、いくつかの産業で浮き沈みが見られた。長くアメリカの経済を支えてきた自動車産業は、外国勢による挑戦に直面し、厳しい戦いを強いられている。また、衣料品産業も、安価な労働力を有する国々との競争により衰退した。これに対し、航空機、携帯電話、マイクロチップ、宇宙衛星、電子レンジ、高速コンピューターをはじめとする新たな産業が登場し、繁栄している。
現在台頭している産業の多くは、高度に自動化され、従来の産業に比べて少ない労働力で操業できる傾向がある。ハイテク産業の成長と、旧来の産業の衰退は、製造業に従事する労働者の比率の減少をもたらした。今や、サービス産業が経済を「支配」し、一部では、アメリカを「脱工業化」社会とする見方もある。製品を作る代わりに、サービスを売る産業としては、娯楽、レクリエーション、ホテル、レストラン、通信、教育、オフィス管理、銀行・金融等が挙げられる。
アメリカは歴史上、孤立主義外交を推進した時代があるが、商業の分野では、総じて強力な国際主義を貫いている。アメリカのビジネスの存在は、外国でさまざまな反応を引き起こしてきた。一部の国では、国民が自らの文化の「アメリカ化」に反発し、また、アメリカ企業が外国政府に対し、自国の利益よりアメリカの政治的・経済的利益を優先するよう圧力をかけていると非難する国もある。他方、アメリカ製品やアメリカからの投資を、自国の生活の質を向上させる手段として歓迎する人々も多い。
アメリカの投資家は、他国の経済に新規資本を投入することによって、予測することが不可能な影響力を発揮することができる。アメリカ国内では、自国の企業が外国に投資することで、将来の競争相手を育てているのではないかという懸念が見られる。こうした懸念の背景として、第2次世界大戦後のアメリカ政府の政策が日本経済の復興を促進したこと、またアメリカ企業が日本に対して技術供与や品質管理等の実務を教える専門家を派遣し、その後日本がこうした分野で、きわめて利益率の高い新たな水準を達成したことが言及されている。このような状況にもかかわらず、1993年に北米自由貿易協定(NAFTA)が批准され、アメリカが依然として国際貿易に積極的であることが改めて確認された。
1800年頃発展した工場制度は、労働条件を飛躍的に変えた。雇用者は、もはや従業員と肩を並べて仕事をすることはなく、会社の経営者となった。製造工程は機械が行うようになり、熟練労働者は一般労働者と同レベルの扱いを受けるようになり、不況時には賃金の低い新米労働者と交替させられることすらあった。
工場制度が普及するに従って、労働者は自らの利益を保護するために労働組合を組織し始めた。初めて定期的に集会を行い、組合費を徴収したのは、1792年にフィラデルフィアの製靴労働者が組織した組合である。その後まもなく、ボストンの大工と革職人、そしてニューヨークの印刷業者等も、組合を結成した。組合員は、自分たちが正当と思う賃金を自ら設定し、それよりも低い賃金を支払う雇用者の下では働かないこととし、さらに雇用者に対し、組合員のみを雇用するよう圧力をかけた。
これに対し、雇用者側は裁判で争った。裁判では一般に、労働者による共同行為は、その雇用者及び地域に対する違法行為となる共同謀議であるとの判決が下された。ところが、1842年、マサチューセッツ州最高裁判所が、労働者が平和裡に組合活動を行うことは違法ではないとの判決を出した。この判決は広く受け入れられ、その後長年にわたり、組合は、違法行為となる共同謀議に対する告発を恐れる必要がなかった。組合は、その活動を賃金闘争のみにとどめず、1日10時間労働の推進や児童就労への反対運動にまで広げていった。これらの運動に対し、一部の州議会では、好意的な反応が見られた。
1865年から1900年にかけて、工業生産は飛躍的な伸びを示し、特に重工業の分野で雇用が大幅に拡大した。しかし、こうした新しい労働者たちは、不景気の時代にはその影響を受けることになった。ストライキが日常的に行われ、時には暴力が伴うこともあった。多くの州議会で、労働者を鎮圧するための共同謀議取締りに関する法律が新たに通過した。
これに対抗し、労働者たちは全国規模の組織を結成した。その1つである労働騎士団(ナイツ・オブ・レーバー)は、1880年代に組合員を15万人にまで増やしたが、その後、各新聞が、騎士団員は危険な急進主義者であると報じたために、急速に崩壊した。これに比べ、1886年、葉巻製造組合の指導者だったサミュエル・ゴンパースが設立したアメリカ労働総同盟(AFL)は、強固な組織となった。職能別組合とその組合員から構成されたAFLは、1904年までには組合員数が175万人にまで膨れ上がり、国内で最有力の労働組織となった。
ヨーロッパで、多数の労働者が資本主義の廃絶を求め、革命主義組合に加入していた頃、アメリカの労働者の大多数は、自らも協力して築いた富が、労働者にもより多く分配されるべきであると提唱したゴンパースに追随した。これに対し、AFLの方針に反対する43の組織の代表によって1905年に設立された組合、世界産業労働者組合(IWW)は、より急進的な活動を行った。IWWの目的は、ストライキ、ボイコット、あるいはサボタージュという行為によって資本主義を転覆させることだった。同組合は、第1次世界大戦へのアメリカの参戦に反対し、戦時中、銅の生産を休止しようと試みた。1912年、IWWの組合員数は10万人のピークに達したが、第1次大戦中及び戦後、連邦政府による組合幹部の刑事訴追や、急進主義に反対する国民感情をきっかけとして、1925年までにはほぼ解散状態となった。
1900年代の初頭、AFLと革新主義運動(第3章を参照)の代表との間で連合が結ばれ、両組織は共同で、労働者救済のための、州及び連邦レベルの法律制定に向けて運動を行った。その結果として各州で、児童労働の禁止、女性の労働時間の制限、及び労災保険制度の設立に関する法律が可決された。また、連邦レベルでは、議会が、児童、鉄道労働者及び船員を保護する法律を可決し、大統領府に労働省が設立された。労働組合は、第1次世界大戦中に長足の進歩を遂げ、1919年1月までには、AFLの組合員数は300万人以上となった。
1920年代に入ると、労働組合は、それまで以上に力をつけたかに見えた。しかし、ロシアで起った共産主義革命は、アメリカでも革命が勃発するのではないかという恐怖、いわゆる「赤の恐怖」をもたらした。一方で、全国各地では、労働者による賃上げを求めるストライキが起こっていた。これらのストライキが共産主義者や無政府主義者によって指揮されていると考える者もいた。革新主義運動の時代には、アメリカでは、どちらかといえば労働組合に同情する国民感情が見られたが、今や労働組合は敵となった。裁判所は再び組合活動を制限し始めた。
大恐慌時代になると、振り子は再び組合側に振れることになった。フランクリン・ルーズベルト大統領は、ニューディール政策の一環として、「忘れられた人々」、すなわち土地を失った農民や職を失った労働者を救済することを公約した。議会は、労働者が組合に加入し、団体交渉を行う権利を認めた。さらに、組合と雇用者の間の争議を解決する組織として、全国労働関係委員会を設立した。
その後まもなく、AFL内の熟練工と一般の産業労働者の間に緊張が高まり、新たな労働組織として産業別組合会議(CIO)が設立された。この新しい組織は急速に成長し、1930年代後半には、AFLを凌ぐ組合員数を有するようになった。
恐慌が雇用に及ぼした影響は、1941年にアメリカが第2次世界大戦に参戦するまで続いたが、参戦によって、航空機、船舶、武器、その他の軍事物資を生産するために、工場では労働者を必要とするようになった。1943年までには、1,500万人の男子が従軍し、アメリカは労働力不足となる。その結果、当時の社会的傾向に反し、女性が不足した労働力を補うようになった。まもなく、防衛工場で働く労働者の4人に1人は女性となった。
第2次世界大戦後、賃上げ要求のストライキが全国各地で発生した。雇用者側は、労働組合の力が強すぎると訴え、議会もこれを認めた。議会は、雇用者に組合員のみの雇用を義務付ける「クローズド・ショップ」協定を禁止する法律を採択し、また雇用後に労働者の組合参加を義務付ける協定を禁止する「労働権法」を各州が制定することを許可した。1955年には、AFLとCIOが合併して、AFL-CIOという新組織が生まれた。
近年、労働者の組合参加率が低下している。その理由としては、労働組合の砦だった重工業の衰退と、オートメーション化による「ブルーカラー」労働者の減少等が挙げられる。しかし、労働組合は依然としてアメリカの経済・政治における一大勢力であり、労働条件は着実に改善されてきた。
一方、労働力に占める女性の割合が、これまでにない水準に達している。また、アメリカの労働時間は平均して週に35~40時間であるが、標準と異なる労働形態の人たちが増えている。これには、パートタイム、「フレキシタイム」(例えば週5日間、1日7~8時間働くかわりに、1日10時間労働で週4日間働く)、電話やコンピューター、ファクシミリを利用した「在宅勤務」などがある。
アメリカが独立を宣言した1776年に、スコットランドの経済学者アダム・スミスが、アメリカの経済発展に多大な影響を及ぼす著書「国富論」を書いた。他の多くの思想家と同様、スミスも、資本主義制度において人は生来利己的であり、富と力を得るために商工業に従事すると考えた。スミスの独創的な点は、そうした活動は生産の増加と競争の強化につながり、その結果商品が広く流通し、商品価格が下がり、雇用が創出され、富が拡大するため有用であると主張したことである。人は自らの富を増すという狭い利己心に基づいて行動するかもしれないが、「見えざる手」が彼らを導いて社会全体の富と進歩に寄与させるとスミスは説いた。
アメリカ国民の大半は、経済大国としてのアメリカの発展は資本主義以外の制度の下ではあり得なかったと信じている。資本主義は、自由企業説としても知られ、通商への政府の干渉は最小限に抑えられるべきであるというスミスの考えに基づいている。
アメリカの歴史のごく初期から、人々は事業の設立または拡張に融資をすることによって利益を得られることに気づいていた。今日でも、アメリカの中小の起業家は、ふつう友人・親類あるいは銀行から融資を受ける。しかし、比較的規模の大きい企業は、株式や債権を売って資金を得ることが多い。こうした取引が行われる場所が、株式取引所あるいは株式市場である。
1531年、ベルギーのアントワープで初めての株式取引所が設立された。株式市場制度は1792年にアメリカに持ち込まれ、大きく発展した。中でもニューヨークのウォール街にあるニューヨーク株式取引所は、アメリカの金融の中心となっている。
週末と休日を除き、株式取引所では、毎日極めて活発な取引が行われる。概して、株式価格は比較的低く、それほど裕福でない国民でも、配当金による利益を期待して株式を購入することができる。また、時とともに株式価格が上昇し、株の売却で利益を得ることも可能である。もちろん、株式の発行企業が必ずよい業績を上げるという保証はなく、企業の業績が悪ければ、配当金は少額またはゼロとなり、株式の価格も下がることがある。
アメリカのビジネスのこうした側面は、アダム・スミスも予測できたことであるが、スミスの予測を超える状況もあった。前述のように、19世紀のアメリカの産業発展は、労働者に犠牲を強いた。工場主は、危険かつ不衛生な労働環境で、労働者を低賃金で長時間働かせ、貧困家庭の子どもたちを雇った。また雇用差別が行われ、黒人や一部の移民は雇用を拒否されたり、極めて望ましくない環境で働くことを強制されたりした。事業主は、政府の監視の欠如を最大限に利用し、独占体制の形成、競争の排除、高価格・低品質の製品の販売といった手段を通じて富を築いた。
こうした悪質な行為を目にした国民は、労働組合や革新主義の影響も受けて、19世紀後半には、全く拘束のない自由な資本主義への信仰を修正するようになった。1890年には、シャーマン反トラスト法(独占禁止法)が制定され、独占企業解体への第1歩となった。1906年には、議会が、食品・薬品の正しい表示と肉類の検査を義務付ける法律を制定した。大恐慌時代には、ルーズベルト大統領と議会が、経済危機克服を目的とする法律を制定した。その中には、株式販売を規制する法律、各種産業の賃金及び労働時間の規則を定めた法律、食品・薬品・化粧品の製造・販売に対する規制を強化する法律などがある。
ここ何十年かの間にアメリカでは、アダム・スミスの哲学は、企業の個々の決断が自然環境に及ぼす累積的な影響を考慮していないとする意見が出てきた。その結果、環境保護庁をはじめとする連邦機関が新設され、企業が大気や水を汚染せず、十分な緑を確保するための新しい法律・規制が生まれた。
こうした法律・規制はアメリカの資本主義を、ある作家の言葉によると「自由に走り回る馬」から「手綱と鞍をつけた馬」に変えた。今日、アメリカで販売されている製品で、何らかの政府規制の影響を受けていないものはほとんどない。
政治的保守派は、事業に対する政府の規制が多すぎると考え、企業が従わなければならない規則の一部は不必要であり、コストがかかると主張する。そうした批判に応えて、政府は、企業に提出させる書類を減らしたり、企業に細かい操業規則を課す代わりに企業が達成すべき総合的な目標・基準を制定するなどの努力をしている。
今日の事業に課せられる規則・規制は、時として煩雑ではあるが、それでも野心のある者は夢を実現し、時にめざましい業績を挙げている。そうした起業家の1人が、ビル・ゲイツである。彼は1975年、20歳でマイクロソフトというコンピューター・ソフトウェアの会社を設立した。それからわずか20年間で、マイクロソフトは、世界各地で社員2万人を擁し、年間純益20億ドルを超える世界最大のソフトウェア会社に成長した。
*上記の日本語文書は参考のための仮翻訳で、正文は英文です。