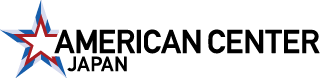国務省出版物
権利章典 – 残酷あるいは異常な刑罰
 過大な保釈金を要求したり、また過大な罰金を科したりしてはならない。 また残酷で異常な刑罰を科してはならない。
過大な保釈金を要求したり、また過大な罰金を科したりしてはならない。 また残酷で異常な刑罰を科してはならない。
権利章典の原本に記載された保障事項のうち、余りにも多くが、犯罪被疑者の保護に関連していることを、奇妙に思う人もいるだろう。憲法修正第4条は、捜索や逮捕には令状の交付を義務づけ、憲法修正第5条は、大陪審による起訴を義務づけ、被告人に対して同じ罪状で重ねて刑事責任を問うことを禁じる「二重の危機」の原則を採用するとともに、自己に不利な証言を強制されることから保護し、「適正な法手続き」を保障している。憲法修正第6条は、陪審による裁判と訴追内容について説明を受け、法廷で証人と対決できる権利、弁護人の支援を受ける権利を保障している。そして憲法修正第8条は、公正な裁判の結果、有罪の判決を受けた場合でも、科される刑罰は犯した罪に見合うものでなければならないことを保障している。交通違反で100万ドルの罰金が科されたり、小切手偽造の罪で手を切断されたり、違法賭博の罪で死刑にされたりしてはならない。繰り返すが、有罪判決を受けた者に与えられた権利であっても、尊重されなければならない。これは、民主主義社会が刑事司法制度を信頼し、この制度自体が政治的弾圧の手段として悪用されないようにするためである。これは理想であり、現実が理想に若干届かないとしても、権利章典による保護は、依然として、民主主義社会が目指して努力すべき基準としての役割を果たしている。
「人を打ち殺した者は必ず死刑に処せられる。……隣人の身体に害を与えた者は、本人が加えたのと同じ危害を受けねばならない。侵害には侵害を、目には目を、歯には歯を―。もし、人の身体に害を与えたら、自らも同じようにされなければならない」 |
旧約聖書のこの一節や、コーランの同じような一節は、ひどい懲罰を科しているようにみえるが、実際には刑罰についての新しい考え方―犯した罪に釣り合う刑罰―を提唱するものである。犯罪者は、犯した罪に見合う方法で処罰を受けるべきである。あくまでも「目には目を」であり、「目には、目と腕と脚を」ではなかった。今では常識的な知恵と言えるこの考えが、欧州で完全に受け入れられるまでには数百年もかかることになった。古代から18世紀の啓蒙運動の頃まで、君主政府は、恐ろしい拷問や、時間をかけた極度の苦痛を伴う死刑など、残忍な形の刑罰を頻繁に用いた。それは犯した罪とはまったく釣り合わない刑罰だった。18世紀に入っても、英国では、死刑が適用できる犯罪は200種類以上もあり、そうした犯罪の大半は、些細な窃盗とか、木を切り倒したとか、飼育場のウサギを盗み出すとか、いわば所有物に対する犯罪だった。
現代の感覚からすると、刑罰の形態とそれに対して適用される犯罪のリストは、身の毛がよだつ、ぞっとするものばかりだ。古代アテネでは、紀元前7世紀のドラコン法典が、あらゆる犯罪の刑罰を死刑と定めた。それから2世紀後、ローマの十二表法は、農民の作物を刈り取ったり、偽証したり、都市で夜間に騒ぎを起こすなどの犯罪に、死刑を科した。ローマ人は、十字架での磔刑(たっけい=はりつけの刑)、海中での溺死、生き埋め、撲殺、串刺しなど、死刑を執行するさまざまな方法を考え出した。親を殺した死刑囚は、犬、雄鶏、毒蛇、猿と一緒に袋に入れられ、水中に沈められた。
中世には、死刑の執行に拷問を伴うことが多かった。英国の封建領主たちは罪人を溺死させる穴や絞首台を所有し、どちらも、重罪のみならず、軽微な罪に対しても用いられた。反逆罪の場合、女は火あぶりにされた。男は絞首刑にされ、絶命する前に綱から切り落とされ、内臓をえぐられ、四肢を切断された。自白を拒む者は、胸に重い石を乗せるという方法で拷問を受けた。拷問の執行人は、最初の日に、被疑者にわずかなパンを与え、次の日には、わずかな汚水を与えた。それを、被疑者が自白するか死に至るまで続けた。1531年に英国国王は、死刑執行に適した手段として、釜茹での刑を承認した。ほとんどすべての死刑執行は、大衆の見世物として、そしてまた、法を犯すと恐ろしい結果が待っているよという見せしめとして、公開で行われた。
「自分を騎士にとりたててくれた国王に対する反逆の罪により、彼は絞首台に引き出され、ハワーデン城に捕らえられていた紳士を殺害した罪により、絞首刑に処され、その暗殺により厳粛なキリストの受難を冒涜したとがによって四肢を焼かれ、君主である国王の殺害を各地で企てたとがによって国中にその死体の各部をばら撒かれる」 |
死刑以外にも、英国法では、それより軽いさまざまな刑罰が規定されており、それらの中には、身体への烙印、耳の切除、流刑植民地への追放などが含まれている。さらに、国王政府の当局者たちは、ほとんど良心の呵責を感じることなく、さまざまな方法で容疑者を尋問した。そして多くの被疑者たちは拷問の苦痛から一刻も早く逃れたい一心で、全く犯してもいない罪を自白した。新世界への移民たちはこの英国規定を植民地に持ち込んだ。ただし、植民地では人手が足りなかったため、特に軽微な犯罪を中心に死刑の執行は急速に減った。働ける人間は余りにも貴重だったので、ウサギの窃盗などの微罪で働き手を失うわけにはいかなかった。例えば、マサチューセッツの清教徒たちは、あらゆる形の窃盗罪について死刑の適用を廃止した。「マサチューセッツ自由法典」(Body of Liberties)(1641年)は「身体への刑罰については、非人道的、野蛮ないし残酷なものを、われわれの間では認めない」と明言した。
米国革命(独立戦争)の時期まで、ほとんどの植民地は、死刑を科す法律を備えていた。それを適用する犯罪は、放火、海賊行為、反逆罪、謀殺、獣姦、侵入盗、強盗、強姦、馬泥棒、奴隷の反乱、通貨偽造だった。刑の執行方法は、通常、絞首刑によった。植民地の中には、もっと厳しい刑法を持つところもあった。だが、記録を見ると、いずれの州でも、裁判官や陪審員は、たとえそれが死刑を適用できる犯罪であっても、実際に死刑を科したのは、最も凶悪な犯行の場合だけに限っていたようである。
鞭打ちや水中に沈める刑罰や恥辱の柱(公共広場の柱に囚人を鎖でつなぎ、人々がののしる)などは、いくつかの植民地で日常的に行われていたが、もっと恐ろしい拷問や刑罰は、急速に米国から姿を消していった。これは、母国で起きていた改革派の運動から影響を受けたもので、英国では、残虐な制度に反対する世論が起きていた。米国革命の際、残酷で異常な刑罰の構成要件とは何かという大論争が起き、それは、合衆国憲法と権利章典の草案作成時に至るまで続いた。多くの点でこの議論は、死刑が残酷で異常な刑罰にあたるかどうかに関する現代の論争の先駆けとなった。
憲法修正第8条は、1689年の英国の権利章典第10条に規定された禁止事項を、ほぼ逐一踏襲している。この英国の権利章典第10条は、その後、ジョージ・メーソンによってバージニア権利章典(1776年)に、さらに1787年、連合会議によって北西部領地条令に盛り込まれた。合衆国憲法に関する論議の中で、いくつかの州から、合衆国憲法案は個人の権利を守るには不十分だという反対意見が上がった。マサチューセッツでは、批准会議に参加した代表者の1人が、憲法案は刑罰の形式に制限を加えておらず、理論的には、拷問台やさらし首台を使っても合法であることを指摘した。バージニアでは、パトリック・ヘンリーが、拷問が用いられる可能性に懸念を表明した。この2人とも、実際には、より広範な人権規定の憲法への盛り込みを主張していたが、同時に、英国の歴史で余りにもはびこっていた残虐行為を防止する必要性も認識していた。
「英国の権利章典が残酷で異常な刑罰の禁止を規定したのは、刑罰自体に行き過ぎや違法性があったので対処したのだろうか。それとも、野蛮で忌まわしい形の刑罰だったから反発したのだろうか。あるいは、その両方だったのだろうか。その正しい解釈はともかく、建国の父たちが、その文言を借りて憲法修正第8条に盛りこんだ意図は、疑いもなく拷問やその他の残酷な刑罰を非合法化することにあった」 |
残酷で異常な刑罰に関する論争には、死刑を非合法化すべきかどうかという議論も含まれていた。西欧の哲学者、たとえばイマニュエル・カントの著作は米国でもよく知られており、「罪と罰の釣り合い」という、彼が取り上げた旧約聖書の概念は大きな影響を与えていた。しかし、死刑に反対したイタリア人のチェザーレ・ベッカリーアなどの改革派の著作も影響力を持っていた。ベッカリーアは、法律が過酷なせいで、しばしば犯罪者は「一つの罪に対する刑罰を避けようとして、さらに罪を重ねる」と考えていた。例えば、鶏を盗むなどの軽微な犯罪で厳しい刑罰に処される可能性がある場合、その刑罰を逃れるために逮捕を避けようとして、もっと大きな犯罪に及んでしまうことがある―というのである。
当時、死刑廃止を熱心に支持する声が上がり始めた。新しい共和国の成功は、市民の美徳に立脚すべきであり、多くの人が恐怖政治の特徴と見なしていた過酷な刑事法典への恐怖心によるものであってはならないと主張する人々がいた。独立宣言の署名者の1人であるベンジャミン・ラッシュは、「死刑は君主政府の自然の所産である」と明快に述べた。アレクサンダー・ハミルトンのような保守主義者でさえ、「残虐さを旨とする考え方は、嫌悪を起こさせる」と述べ、死刑は共和制の価値観と行動様式を損なうものだと考えた。
1789年、合衆国憲法の下で開催された初の連邦議会では、提案された残酷で異常な刑罰に対する禁止規定案について、ほとんど論議はなかった。ニューハンプシャーのサミュエル・リバモアだけが詳細な意見書を発表した。
本条項は、大いに人間性を表明しているようであり、その重要性については、異議を申し立てるものではない。しかし、この条項の内容は無意味と思われる以上、私にはこれが必要なことだとは思えない。……残酷で異常な刑罰は科すべきではない、としているが、時には絞首刑を行う必要もあるし、鞭打ちや、場合によっては耳を削ぐ刑に値する悪人もいる。しかし、これらの刑罰が残酷だからという理由で、将来にわたって、それを科すことが出来なくなってもいいのだろうか。もしもっと寛大な形で邪悪を正し、これに手を染めないように人々を抑えるための方策を考案できれば、立法府がそれを採択するのは非常に思慮深いことだろう。しかし、そうなるという何らかの保証が得られるまで、この種のいかなる宣言によっても、必要な法律の制定が妨げられるべきではない。」 |
リバモアの意見は、議論の文脈の中で理解する必要がある。彼は、総論としては、人道的な刑罰に反対しなかった。むしろ彼が問題にしたのは、それが効果的かどうかだった。この中で彼は、社会が変化するにつれ倫理規範も変化する、という観念に言及したのである。ある時代には、引き回して、八つ裂きにすることは、反逆罪に対する適切な刑罰と考えられていた。そして、これが残酷であり、恐ろしい苦しみを与えるという事実の故に、政府に対する最も重大な犯罪への報復にふさわしい、と当時の人々は考えていた。立法府は犯罪を防止し、処罰するために適切なあらゆる手段を行使する権利を保持しているが、非人道的な刑罰を科すことはないだろう、と信じるリバモアは、18世紀の米国では少数派だった。これに対して、大多数の人々は、政府に一定の制限を課すことを望んだ。権利章典の起草者たちも、建国世代の多くの人々も、政府にはそれほど大きな信頼を寄せていなかった。彼らは、制約を受けない政府がどのよう
権利章典のほかの項目と違って、「残酷で異常な刑罰」という問題で、連邦最高裁が判断を下した判例は比較的少ない。米国では、拷問が刑罰として公認されたことは一度もなかった。この問題に触れたわずかな記録は、地方当局が自白を得ようとして、肉体的虐待を加えたことぐらいである。過剰な保釈金や罰金に該当するような事例は時折あったが、この問題に関する試金石としての明確な一線は存在しない。むしろ連邦最高裁は、この問題については、事実審裁判所の判断に委ねるのが一番であり、被告人が苦しめられていると感じれば、救済を求めて訴えることができる、という見解を示してきた。
国民の間でも、裁判所でも議論が重ねられてきた争点は、死刑そのものを憲法修正第8条に違反するとして禁止すべきかどうかについてだった。憲法修正第8条の文言との関連で、連邦最高裁が取り上げた最初の審理は、死刑そのものの当否ではなく、その執行方法をめぐる問題だった。1878年に連邦最高裁は、囚人を死刑にする方法として銃殺隊を使うことを是認し、その10年ほど後には、電気椅子の使用を認めたが、これは人道的な死刑執行方法だというので導入されたものである。それからおよそ100年後の現在、「人道的な」死刑執行方法である致死注射に異議が申し立てられているが、これについて、連邦最高裁はまだ審理していない。要約すれば、死刑が存続する限り、拷問や明らかに残酷な方法ないしは異常な方法が用いられない限り、執行手段は州政府に任せる、というのが連邦最高裁の姿勢である。連邦最高裁自身も極めて消極的な形ではあったが、1970年代に死刑廃止論争に関わった。そして現在の死刑論議が公共政策論争の中で再び大きな役割を果たす気配があるため、連邦最高裁も間もなく、再びこの論争に巻き込まれることになりそうである。
20世紀に入ってから最初の20年間に、米国は死刑を科すことができる連邦犯罪の数を減らし、いくつかの州では死刑を完全に廃止した。その後、死刑廃止運動は足踏みしたが、1960年代初めに至り、死刑をめぐる論争が再び国中の関心を集めた。この新たな死刑廃止運動が力を得た理由の一つは、他の国々で同じ運動が勝利を収めたことにあった。
第二次世界大戦後間もなく、改革派は、1948年の世界人権宣言の起草に際して、文明国の目標として死刑の廃止を推進した。欧州諸国の中には、ノルウェーのように、すでに死刑を廃止していた国もわずかながらあったし、死刑の適用に一定の制限を加えることに合意した国もあった。年を重ねるにつれて、多くの国が、年少者、妊婦、高齢者への死刑の適用を禁じ、死刑を科すことができる犯罪の数を減らす多国間協定への署名を始めるようになった。
最終的には、死刑の全廃を目指す3つの国際条約が起草された。そのうちの1つは1983年に、残る2つの条約はその6年後に起草された。これら3つの議定書には50カ国以上の国々が署名している。ニュールンベルク裁判が多数のナチ関係者に死刑を宣告してから半世紀たった今、国際法は、戦争犯罪や人道に対する犯罪の訴追で死刑の適用を除外している。近年、独裁者の圧政を打倒した多くの国々では、民主的に選出された議会が成立させた最初の法律の一つが、死刑の廃止だった。なぜなら、以前の専制政府のもとでは、死刑の執行が国民を服従させる重要な手段となっていたからである。
米国は、死刑の廃止を目指すこの3つの議定書に署名していないが、それには数多くの理由がある。その1つは、連邦最高裁が死刑そのものを、残酷で異常な刑罰を禁じる憲法修正第8条に違反する、と裁定していないという単純な事実である。従って、死刑を科すかどうかは、連邦犯罪については連邦議会に委ねられ、50州およびコロンビア特別区の管轄権下での犯罪については、州とコロンビア特別区の手に委ねられている。全体の4分の3の州は、まだ死刑を科しているが、残りの州は廃止している。こうした連邦主義的な側面は、国全体を律する刑法を国会が定める国にとっては、しばしば理解するのが難しい。しかし米国の連邦制度では、合衆国憲法に違反しない限り、原則として、各州は独自の刑法を自由に定めることが認められている。ただし、連邦議会が連邦政府の管轄権を勝ち取った地域は、例外として除かれる。
米国で死刑が存続している最も大きな理由は、おそらく、死刑が妥当かどうかについて、米国民の総意がまとまっていないためだろう。この問題では、死刑の完全な廃止を望むという人から、死刑はよいことであり、もっと行うべきだと考える人まで、幅広い意見が存在する。米国人の大多数の意見は、おそらくこの両極端の中間に落ち着くだろう。すなわち、一方には死刑が国家を殺人に関与させることを残念に思う人もいるし、死刑がなければ憎むべき犯罪を抑止できないかもしれないと懸念する人もいるのである。ロバートL・シェビン元フロリダ州法務長官は、この考え方を巧みに表現し、次のように述べている。「人間が善であり、思いやりの心を持つことができると考えれば、死刑は悲劇である。人間が邪悪であり、邪悪で堕落した行為をする存在だと考えれば、死刑は必要となる」
死刑に反対する人々の理由はさまざまである。誰であれ人を死に追いやることは非人道的だ、と考える人々がいる。この考え方によれば、罪を犯す者は投獄し、他人に危害を加えないようにすべきだが、生命はすべて神聖なものであり、たとえ有罪判決を受けた犯罪者でもそれは変わらない。死刑は非道徳的だという認識が、人々を死刑反対に走らせる、何よりも大きな理由である。
2つ目の理由は死刑は最終決着であり、無実の人が死刑を執行される懸念があるという点である。500年以上前、イングランドの首席裁判官だったジョン・フォーテスキューは「20人の犯罪者が死刑を免れた方が、1人の無実の人間が有罪の判決を受けて死刑になるよりも、ましだ」と述べた。ある人物が間違って有罪とされて投獄された場合でも、間違いが判明すれば、この人物は釈放される。収監されていた時間を償うことは、誰にもできないが、少なくともこの人物は、生きて残りの人生を楽しむことができる。死刑を執行してしまえば、誤審を正すことはできない。
3つ目の理由は、刑罰の通常の規範からみて、死刑は無益で無駄と思われることである。ただし、「例外」が一つだけある。反対派は、死刑は抑止力にならない、と主張する。なぜなら、死刑に相当する罪を犯す者が、実際の犯行時に、どのような結果になるかを考えることは、滅多にないからだ。冷血なプロの殺し屋は、犯行時に処罰を逃れられると信じて、刑罰については気にかけていない。夫が自分を裏切っていることを知った妻は、不当な扱いに怒り狂い、復讐したいと考える。激情に駆られる最中に、自分の行動がどのような報いを招くかなど、ほとんど念頭にない。
先述の「例外」だが、死刑に反対する論者によれば、死刑によって満たされる唯一の目的は、報復だそうである。つまり、容認された社会的行動から逸脱した者に対して、社会が与える復讐である。死刑反対論者は、刑罰の必要性は否定しないが、それは文明的なものであるべきだと考えている。すなわち、基本的に報復のために誰かを死刑に処すことは、彼らの見解では野蛮なのである。彼らは、「復讐は我が物である、と主は仰せられた」という聖書の一節に、宗教的な裏づけを求めている。
4つ目の理由は、死刑の適用が明らかに公平でないことである。陪審員は、たとえ死刑に相当する犯罪で有罪と判断しても、女性に死刑を科すことには消極的である。公民権運動の支援者たちは、アフリカ系米国人やそのほかの少数派に属する被告人が関わる犯罪では、同じような事件での白人被告人の場合に比べて、死刑が科せられる割合が非常に高い、と主張している。
さて逆に、死刑擁護派は、反対のことを主張する。彼らは、何よりも刑罰は犯罪に見合ったものでなければならない、と言う。人の命を故意に奪った場合、社会が求める最低限の要求が死刑である、と。犠牲者が死んでいるのに、殺人者が刑務所の中で人生を全うすることを許すのは、不公平ではないか、という論拠である。
第2に、犯罪があまりにも凶悪なため、一般国民の道義心をなだめる方法は死刑しかない場合がある、という。殺人者が犠牲者を拷問したり、性的に暴行したときや、特別に恐ろしい手段を使って犯罪が行われたりした場合、その犯人は道徳的に扱われる権利をみな失うことになる。狂犬病にかかった動物を始末して、社会に対する脅威を取り除くのと同じように、特定の犯罪者は永遠に「始末」されるべきだ、と死刑支持派は言うだろう。
第3に、死刑支持派は、死刑が抑止力として役立つことを信じている。プロの殺し屋や一時的に嫉妬で錯乱した人を止めることは、確かにできないが、軽微な犯罪者に分別があれば、さらに重い罪を犯すことを防ぐことができる。死刑支持派は、米国と英国では、侵入強盗が滅多に銃を携帯していないことを指摘する。捕らえられた場合、単なる住居不法侵入に対する刑罰は、武装強盗よりもかなり軽く、銃を持っていなければ、犯罪者は家人や警察に対して武器を使うこともない。これは、法による抑止が機能しているしるしだ、と彼らは考えている。
第4の主張は、報復に関わるものである。死刑を支持する人々は、報復が悪いとは全く考えていない。犠牲者の家族には、殺人者が処罰を免れなかったこと、殺人者が罪のない命を奪った以上は今度は自分の命を失うことを、知る権利がある。さらに、報復の必要を満たす刑罰を国家が科さなければ、民間人が自分の手に法を握り、米国社会は自警団社会になってしまうだろう―というのである。
死刑擁護派が答えることの最も難しい論議が、誤審の問題である。彼らは、ひとりの無実の人間が死刑に処せられるよりは、罪のある20人を自由の身にする方がいいという、フォーテスキュー卿の意見には賛成しないものの、間違いは起こりうる、という点は認めている。死刑擁護派は、どれほど完璧な制度を作ろうとも、間違いは常に発生する、と主張する。彼らは、罪のある20人を生きて釈放すること自体が、社会に対する犯罪だと主張する。時には間違って有罪にされ、命を奪われる人が出ることは、不幸なことではあるが、社会を守るために支払う必要がある犠牲である、というのが彼らの主張である。
州の刑事司法制度の多様性と、判決規準が気まぐれで一定していないこと、そして少数派の人々が関わる訴訟で死刑が科される比率が異常に高いことから、ついに連邦最高裁が行動に踏み切り、審理に着手した。1960年代に連邦最高裁に上訴された数多くの訴訟は、死刑制度がいかに不備であるかを明らかにした。多くの事案で連邦最高裁は、死刑の違憲性という中核的な問題に触れる必要もないまま、技術的な問題で有罪判決を覆すことができた。そしてついに判事たちは、この問題に取り組まなければならないと判断した。
「これらの事案で死刑を科し、これを執行することは、合衆国憲法修正第8条および第14条に違反する残酷で異常な刑罰に当たる、と当裁判所は裁定する。従って、各事案の判決は、宣告された死刑判決をそのままにしている以上、これを取り消し、その事案は再審理のため差し戻される。」 |
連邦最高裁判事の意見は僅差で割れていたが、1972年6月、まったく予想外の略式意見によって連邦最高裁は、全米で収監されていた約600人の囚人の死刑判決を無効としてしまった。「ファーマン対ジョージア州事件」で、過半数の判事が、「当時存在していた」死刑制度を科すことは残酷で異常な刑罰の禁止規定に違反する、と裁定したからである。死刑廃止論者たちは喜んだが、彼らは裁判所の意見を誤って解釈した。判事の過半数は、死刑そのものを違憲だと言ったのではなく、それを適用する法的手段が非理性的で、恣意的であるため、憲法修正第8条に違反している、と判断したのである。
死刑そのものに反対する人々にとって、きわめて遺憾なことに、その後数年のうちに、それまで死刑を科していた37州のすべてが州の法律を改正し、ファーマン事件の意見で示された憲法上の基準を満たそうとした。1976年に連邦最高裁は、実際に使える基準を明確にするために、これら新たな州法を見直し始めた。そして最終的に、「グレッグ対ジョージア州事件」で、ジョージア州の改正死刑法を支持する判断を示した。この新法は、陪審裁判において、陪審員がまず有罪か無罪かを判定し、被告が有罪とされた場合、刑罰について、別途、評決を行うことを規定していた。陪審員も、非陪審裁判の判事も、事件の状況から責任軽減事由や責任加重事由を考慮しなければならなくなった。そして州最高裁は、過剰ないしは不釣合いな刑罰を防ぐため、すべての死刑判決について、自動的に再審査することになった。
「グレッグ対ジョージア州事件」(1976年) 「われわれが審理した事案は、犯罪への制裁に関する穏当な基準についての一般市民の認識が、最終的なものでないことを明らかにしている。刑罰は、憲法修正第8条の根底的な概念である『人間の尊厳』とも調和しなければならない。少なくともこれは、刑罰が『過剰』であってはならないことを意味する。個別性との関係(特定の罪を犯した特定の被告人に適用する刑罰としての死刑の妥当性)よりむしろ、概念的な関係(本件の場合だと、そもそも謀殺の制裁として死刑を科すことができるか)において刑罰の形態を考えるとき、それが『過剰』であるかどうか調べる上で2つの側面がある。第1に刑罰は、不必要で、理不尽な苦痛を伴うものであってはならない。第2に刑罰は、犯罪の重大さと著しく不釣合いであってはならない」 |
連邦最高裁は、人間の尊厳に関する現代の考え方は、死刑の廃止を求めている、という主張を却下した。立法府は、もしそうしようと思えば、報復説、あるいは抑止説に基づいて死刑を正当化することができるし、判決機関は、明確に規定された法定基準に従って、死刑を命じることができる。連邦最高裁判事の中で死刑そのものが憲法違反と考えたのは、ウィリアム・ブレナンとサーグッド・マーシャルの2人だけだった。
連邦最高裁が1972年に出した最初の判断に対しては、大きく異なる死刑制度の存在や、恣意的でしばしば差別的な死刑適用、明確に適用できる憲法上の基準の欠如などから、一定の支持が集まった。しかし、大多数は死刑そのものが違憲であるとは考えず、各州がこの極刑を科す方法だけが問題だと思っていた。改定された州法は、こういった問題の多くを回避するものだった。また、今では死刑を科すすべての州で、自動的な再審理が義務づけられ、死刑適用の一貫性と、不公平な裁判の回避が、ある程度確保されている。
それでも、その後の連邦最高裁の判断の多くは、硬直した死刑宣告のやり方を避けようとして、連邦最高裁が最初に反対していた不確定要素を再び取り入れた。ウォーレン・バーガー連邦最高裁長官は、1970年代に審理されたいくつかの死刑事案で、死刑は特別な刑罰であり、従って可能な限り個別の扱いを検討しなければならない、と主張したが、それは疑問の余地なく正しい意見だった。これは、判事や陪審員が、さまざまな責任軽減事由と責任加重事由の双方、もしくはどちらかを、十分に検討しなければならないことを意味する。この手続きを合理的なものにすべく、各州は努力を重ねたが、結局、死刑を科すかどうかという判断には、概して主観的な決心が伴う。ある殺人が凶悪だと陪審員が判断すれば、しばしば死刑を正当化することができるだろう。陪審員がある被告に同情的だと、死刑を科すことを避けるための責任軽減事由を見つけ出すだろう。
ほかの権利についての議論で見てきたように、時間の経過とともに状況が変化するのに応じて、憲法の意味も変わる。ある時代には適切と思われることが、別の世代にとっては全く違って見えることもある。憲法の解釈にあたって米国の司法制度は、憲法の文言と、そしてある程度まで憲法起草者の意図に縛られるものの、裁判所は、憲法の文言を同時代の社会にふさわしい形で適用することに努めてきた。
歴史上の事実から明らかなように、18世紀末の米国と欧州では、死刑の効能に懸念を示す少数の声はあったものの、大多数の人々は、特定の犯罪に対する合法的な刑罰として死刑を受け入れていた。米国の多くの人々、過半数と言ってもいい人々が、今も死刑を受け入れている。死刑に対する一般市民の態度に大きな変化がおきていない、と連邦最高裁が述べてから、まだ10年も経っていない。変化は始まったのかもしれないが、どこまで変化するか判断するのは難しい。
変化を促す要因の1つは、連邦最高裁が規定した指針に従って、州の控訴裁判所が死刑判決を厳しく精査しているにもかかわらず、調査によれば、いまなお死刑判決が少数派に属する被告人に下される比率が高いことである。
2つ目の要因は、予想をはるかに上回る数の冤罪が明らかになったことである。多くの場合、貧しい被告人は、刑法に精通していない国選弁護人から不十分な法的支援しか受けられない。最近、いくつかの法科大学院のプロジェクトで、法律学の学生チームを編成し、十分な資金のある法律家チームであれば審理の前に行っていたはずの調査を行い、有罪判決を受けた人物が罪を犯していなかったことを証明する決定的な証拠を見つけ出した。
このような調査だけでは、死刑制度の信頼性に疑問を投げかけることができないとしても、技術の進歩は、まさにそれを可能にしている。近年、DNA鑑定により、米国中で、文字通り数十件に上る死刑判決が覆された。強姦の被害者から採取した物的証拠を使って、ほぼ確実に加害者を特定することができる。そして、強姦殺人の罪で死刑執行を前にしていた男性数人が、審理の時点では実施が不可能だったDNA鑑定の結果、加害者ではないことが証明されて釈放された。強姦以外の事件では、かつての血液検査は、被告人のコートに付着していた血液が被害者と同じ血液型であるかどうかしか証明できなかった。新しい鑑定方法を使えば、その血液が特定の人物のものかどうかまで正確に突き止めることが出来る。繰り返すが、これらの新しい検査方法を使うことによって、判決が覆されてきたのである。
この種の証拠の出現は、死刑廃止論者の主張を補強するだけでなく、リベラル派と保守派の双方の死刑支持者たちにも影響を及ぼす。民主国家の刑事司法制度の根幹にあるのは、その制度は公正に機能し、間違いはほとんどなく、すべての人が法の前で平等な裁きを受けるはずだ、という認識である。だが、過去数年の間に、米国では多くの人々にとって、死刑制度には欠陥があり、それを補修しなければならない、ということが明白になった。
「何が残酷で、何が異常な刑罰かを定義する指針は、われわれの良心以外には何も存在しない。今日は公正であると見なされる刑罰も、明日には残酷と見なされるかもしれない。つまりわれわれは、絶対的なものを扱っているのではない。従ってわれわれの判断は、われわれの信条、生い立ち、そして人格の持つ高潔さへの信頼の度合いが形作るモザイクから湧き出すものにならざるを得ない」はならない」 |
2000年に、保守派のジョージ・ライアン・イリノイ州知事は、同州の死刑執行の一時凍結を命じて、国中を驚かせた。それまで、余りにも誤審が多かったので、新たに死刑を執行する前に、念のための措置として、裁判が公正に行われたのか、被告人が弁護士から適切な助言を得られたのか、すべての証拠が熟考された上で慎重に死刑が考慮されたのか―などの点を確認する必要がある、というのが、同知事の言い分だった。ほかの州の知事や議員たちも、自分の州の死刑制度について精査を求めた。
連邦最高裁は、死刑そのものには異議を唱えないが、未成年者(成人として審理されれば死刑判決を受けるかもしれない者)や、知的障害者などの特定グループに対する死刑の適用に疑問を投げかける、いくつかの訴訟を審理することに同意している。2002年6月に連邦最高裁は、2件の判決を下したが、そのさい、連邦最高裁判事たちが死刑に関する論争を審理し、そのうち少なくとも数人は、死刑適用の公正さに対して世間で高まる懸念を、同じように持っていることを判決は示唆した。このうちの一つの事案で、連邦最高裁判事の過半数は、知的障害者に死刑を執行することは、まさに残酷で異常な刑罰に当たるという考え方で世論がまとまっていることを認めた。自分の犯罪や刑罰の本質さえ理解していない者に対して刑罰を科すべきではない、というのは英米コモンローの主な特徴の一つとなっている。精神異常は、厳罰の適用に対する弁護として長年認められてきており、精神異常の犯罪者は死刑に処すのではなく、施設に収容されてきた。
別の一件の事案では、連邦最高裁は判事自らの選択で死刑判決を下す権限を厳しく制限し、陪審員に対して死刑判決を下す際の、より大きな権限を与えた。これによって市民感情の及ぼす影響が強まる、と主張することもできる。だがそれは、アントニン・スカリア判事によれば、米国の刑事司法制度の中核にある陪審員の権限と責任を、強化することでもなる。
現在行われている再評価が、死刑の廃止につながるかどうか判断するのは難しい。しかし少なくとも再評価作業によって、あらゆるものの中で最も厳しい形態のこの刑罰が、より客観的で公正な方法で適用されるようになるはずである。21世紀初めの現時点での米国では、死刑は、残酷で異常な刑罰を禁じた憲法修正第8条違反とは見なされていないものの、その誤った適用は、違反なのである。
参考文献:
- Larry Charles Berkson, The Concept of Cruel and Unusual Punishment (Lexington, Mass.: D.C. Heath & Company, 1975)
- Charles L. Black, Jr., Capital Punishment: The Inevitability of Caprice and Mistake (2nd ed., New York: W.W. Norton, 1981)
- Walter Burns, For Capital Punishment: Crime and the Morality of the Death Penalty (New York: Basic Books, 1979)
- John Laurence, A History of Capital Punishment (New York: The Citadel Press, 1960)
- Michael Meltsner, Cruel and Unusual: The Supreme Court and Capital Punishment (New York: Random House, 1973)
- Louis P. Pojman and Jeffrey Reiman, The Death Penalty — For and Against (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 1998)
*上記の日本語文書は参考のための仮翻訳で、正文は英文です。