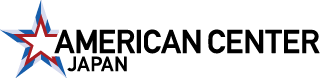国務省出版物
権利章典 – 被告人の権利
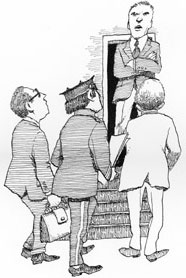 人々が自身の身体、家屋、書類および所有物の安全を、不当な捜索や逮捕・押収から、確保する権利を、侵害してはならない。 宣誓や確約に裏打ちされた相当な根拠に基づいていない限り、また捜索する場所、および逮捕・押収する人物や物品が明示されない限り、どんな令状もいっさい発行してはならない。
人々が自身の身体、家屋、書類および所有物の安全を、不当な捜索や逮捕・押収から、確保する権利を、侵害してはならない。 宣誓や確約に裏打ちされた相当な根拠に基づいていない限り、また捜索する場所、および逮捕・押収する人物や物品が明示されない限り、どんな令状もいっさい発行してはならない。
大陪審の告発、または起訴がない限り、人はだれも死刑に値する犯罪の責任やその他の重大な犯罪の責任を負わされることはない。 ・・・また人はだれも、同一の犯罪で、生命や身体の危険に重ねてさらされることはない。 また人はだれも、どんな刑事事件であれ、自分に不利な証言を強制されることはない。また人はだれも、適正な法手続きによらないで、生命、自由、または財産を奪われることはない。・・・
すべての刑事訴訟で被告人は、公平な陪審による迅速な公開裁判を受ける権利と、・・・訴追の内容と理由につき告知を受ける権利とを持つ。 被告人はまた、自分に不利な証人と対決し、自分に有利な証人を得るために強制的な手続きを取る権利と、自分の弁護のために弁護人の支援を受ける権利とを持つ。
どの州も、適正な法手続きによらないで、相手がだれであり、その人の生命、自由または財産を奪ってはならない。・・・
陪審裁判は犯罪で起訴された被告に与えられる個人的権利の一つだと、われわれは通常、考えている。陪審裁判はまた、これまで見てきたように、個人と同時に、国民全体にも属する、制度としての権利でもある。しかし陪審裁判は、これまで独裁政権下で極めて明白だったように、個人に対する公正さを保障するという規範により律せられないときには、無意味なものとなる。不法に押収された証拠の採用を裁判官が許可したり、被告人が弁護士に面会もできずに、自分に不利な証言を強制されたり、被告人が自分に有利な証人の喚問申請を認められなかったりするなら、それは「適正な法手続き」という基準を満たす裁判とは言えない。権利章典の起草者たちは、このことを、植民地時代の経験からだけではなく、英国の歴史からも知っていた。英国は、1215年にジョン王がマグナカルタに署名して以来、一貫して、法の支配を拡大していくことに努めてきた。
今日、われわれは、諸権利と個人の自由との関係を強調しがちだが、犯罪で起訴された被告人の権利のように、最も個人的と見なされる権利でさえ、依然として地域社会に根ざしている。米国史において諸権利は、個人を地域社会の規範から免除するよう意図されてはいない。むしろそれは、責任ある自由を促し、各人を「恣意的な」権力に束縛されないために存在する。表現の自由の分野で、権利章典は、個人の利益と同時に、地域社会のためにも、反対意見を自由に聞くことができる余地を作り出している。あらゆる種類の権利は、権力のすべてを掌握している中央政府が、人々の日常生活に不当に干渉することから、地域社会を守る役割を果たしている。諸権利は、地域社会と個人を、ともに自由にする。
被告人の権利に関して、「適正な法手続き(デユー・プロセス・オブ・ロー)」の基本的概要は憲法に明記されている。その詳細な内容は、過去2世紀以上にわたって、地方、州および連邦の各級裁判所の審理の過程で洗練されてきた。取り上げられてきた問題の多くは、余りにもささいな手続きに関するものであり、退屈だと言う人もいるだろう。しかし、フェリックス・フランクファーター判事(Felix Frankfurter)が、かつて述べたように、「米国の自由の歴史は、少なからず、手続きの歴史である」連邦最高裁判所の同僚である、ロバート・H・ジャクソン判事(Robert H. Jackson)も同じ意見で、「適正な法手続き」がほかに何を意味しようと、手続き上の公正さこそ「一切の妥協なしに要求されているものだ」と、かつて述べている。
では、「法の適正な手続き」とは何なのだろうか。その意味について完全に一致した考え方はないが、過去2世紀以上にわたり、裁判所は、この言葉が手続き上だけではなく、法律そのものや実体上の権利をも包含するという判断を示してきた。「適正な法手続き」は、刑事司法制度の健全性を保つために、憲法が創設したものであり、それを裁判所が解釈し、また、立法府によって補強してきたのである。それはあらゆる訴訟で、あらゆる被告人が全く同じように扱われるという意味ではない。そうではなく、被告人は誰でも、起訴内容が何であれ、一定の手続き上の権利が認められていることを意味する。それが保障するのは、結局のところ被告人は、法の規則にのっとり、公開の場で、しかも、制度が公正に機能していると、人々が安心できる方法で実施される公正な裁判を受けられたのだ、ということを保障される。これは簡単にできそうに思えるが、米国や、ほかの国々の刑事訴訟手続きの歴史を見れば、そう簡単なことではないことがわかる。このような制度は、人権に確信を持つ民主主義社会だけで発展させることができる。もちろん軍事裁判は、これとは異なる制度である。便宜上、この論文では、一般の裁判所に提訴される大多数の事案について論じることにする。
独立戦争の時期に、被告人の権利についての概念は、英国よりも米国においてはるかに進歩を遂げた。1776年の独立戦争の後、議会を通過した最初のいくつかの州法を見ると、驚くほど現代的な権利が多く盛り込まれていることがわかる。これらの諸権利には、合理的な理由による保釈の権利、法廷外での自白の排除、訴追内容を知る権利、死刑相当の犯罪は大陪審の起訴によること、陪審による裁判―などの項目が含まれており、これらの多くが、結局は権利章典(1791年)に盛り込まれた。しかし権利章典は、1920年代までは、連邦政府にしか適用されず、刑事訴訟の大部分は、州法に基づき州裁判所で審理されていた。と言うわけで、20世紀初期の米国には、刑事訴訟の手続きについては、二つの異なる制度が存在したのである。
つまり、一方には、件数は少なかったが、連邦犯罪(つまり、連邦議会の制定法が規定する犯罪)があった。これは、連邦捜査官が少数規模で捜査し、権利章典の厳格な要件に従って、連邦裁判所が審理した。さらに比較的早い時期から、被告人が貧しすぎて弁護人を雇えない場合には、裁判所が、被告人の弁護人を地元の弁護士会から選任していた。少なくとも連邦段階では、「適正な法手続き」には、弁護人が必要だという考え方が、20世紀初頭までに十分確立されていた。
そしてまた他方には、州の裁判所があった。州犯罪(すなわち、州議会制定法が規定する犯罪)が、地方ないしは州の警察により捜査され、地方ないし州の地方検事により訴追されたが、こうしたプロセスでは、連邦で認められる権利は適用されず、州政府の法令のみが適用された。そして悲しいことに、大部分の州では、司法手続き上の権利はほとんど存在せず、たとえあったとしても厳格には執行されないのが現実だった。捜索はしばしば、令状なしに行われた。逮捕された者は、弁護士の立ち会いがないまま、警察の威圧的な尋問を受けた。弁護士を雇う金がない場合は、弁護人なしに裁判を受けた。多くの州では、被告人に、公判で証言を拒否する権利はなく、もし証人台に立たないことにすれば、その沈黙が被告人の有罪の「証拠」として利用された。そして有罪となった場合、控訴する権利がないことが多かった。
米国は連邦制度を採っているので、法律は、連邦政府と州の間で異なるだけでなく、州ごとにも異なる。連邦法が州に明らかに優先する、と憲法で詳しく規定していない領域では、州に大きな自由裁量を認める慣行になっており、これには、犯罪の捜査や起訴などの業務が含まれていた。20世紀初頭まで、連邦裁判所は、州の裁判手続きや裁判の結果を再審理する権限を、憲法から自分たちには与えられていない、という前提で動いていた。注目すべきことは、多くの州の司法手続き上の指導基準は、連邦政府と同じように個人の権利を保護する内容だったことである。しかし、どのような状況でも公正と言える裁判から、裁判のまねごとでしかないものまで、さまざまな裁判が存在していた。連邦裁判所がついに介入りすることになったのは、後者のような問題のある裁判がきっかけだった。そしてそれが、半世紀にわたる米国の刑事訴訟手続きの見直しにつながることになった。
「一点の疑いもない潔白そのものの男でも、起訴および法廷審理の恐ろしいまでの厳粛さに圧倒され、自分自身の主張を立証できないかもしれない。彼は、自分に不利な証言をする者に対して反対尋問を行ったり、その証言の矛盾や根拠が薄弱だと指摘したり、相手の主張を適切に取り込み、自分の意見を加えて反駁することは、まったく不得手かもしれない」 |
1931 年、アラバマ州で8人の黒人の若者(「スコッツボロ・ボーイズ」)が2人の白人少女をレイプしたとして起訴された。彼らは無罪だったかもしれないが、大恐慌時代の最南部地域の人種差別の激しい雰囲気の中で、自分自身を弁護する知識も能力もなかったのは確かである。8人全員が裁判にかけられ、有罪となり、死刑が宣告されたが、裁判は1日もかからない、見せかけだけのものだった。彼らを弁護するために判事が選任した弁護人たちは、法廷に顔を出しただけですぐ姿を消し、ほとんど何もしなかった。司法をないがしろにしたこの茶番劇が北部の新聞に伝わり、ニュースになると、市民的自由の擁護団体が、直ちに控訴のための効果的な助言を行い、この事件を連邦の裁判制度に移して、連邦最高裁判所にまで持ち込むことに成功した。
(Powell v. Alabama)での判決理由(1932年) 「弁明を聞いてもらう権利は、弁護人に聞いてもらう権利を含まなければ、多くの場合、ほとんど何の役にも立たないだろう。たとえ教育を受け知的レベルが高くても、普通人の場合、法律の分野の能力はわずかしかない、あるいは全くないことがある。犯罪で告発されても、起訴状が正当かどうかを、自分では判断できないのが普通である。被告人は、証拠規則に精通しておらず、弁護士の助けがなければ、彼は、起訴事実が適切かどうかも不明のまま、法廷に臨むかも知れず、その場合、有罪とされるかもしれない。証拠能力のないものや、争点に無関係な証拠、あるいはそのほかの理由で証拠として認められない証拠を根拠に有罪になるかもしれない。被告人は、たとえ完全な抗弁材料を持っていても、十分な抗弁を準備する能力と知識に欠けている。被告人は、自分に対する訴訟手続きの各段階で、弁護人の手助けを必要とする。手助けがないと、被告人は有罪ではないにもかかわらず、無罪を立証する方法を知らないために、有罪判決を受ける恐れがある。知的な人々でさえそうであるなら、無知で無学の人々は、なおさらそうである」 |
「パウエル対アラバマ州事件」は、次の二つの点で注目に値する。一つは、この事件が契機になって、連邦裁判所に、州の刑事司法制度を監督するという新しい使命を担わせたことである。連邦裁判所は、合衆国憲法修正第14条の「適正な法手続き」条項が、州に明確に適用されるものとして州の制度を監督した。連邦裁判所の使命は、その当時もその後も、各州の刑事訴訟手続きをすべて同じにすることではなかった。むしろ連邦裁判所は、「適正な法手続き」を保障するために憲法が要求している最低限の権利保護を定義しようと試みた。例えば、一部の州では、陪審員の数は12人だが、特定の種類の裁判については、陪審員の数がそれより少ない州もある。連邦裁判所は、公正さに関する最低限の基準を裁判と陪審が遵守している限り、こうした州によるこのようなばらつきは許される、という判断を示してきた。
二つ目の注目点は、パウエル事件が、死刑を科すことができる犯罪の裁判では、憲法上弁護士の有力な支援が求められる、というルールを確立したことである。アラバマ州事件の弁護士は、法廷にただ顔を出しただけで、依頼者の弁護を全く行わず、事実上あらゆる意味で、欠席したも同然だった。連邦最高裁判所は、単に被告人が弁護人を持つだけではなく、弁護人は本当の支援、つまり、連邦最高裁判所の言い回しによれば、有効な助言を被告人に提供しなければならない、という判決を下した。
しかし、パウエル事件で判断を下した連邦最高裁判所は、なお、各州の自治権を認めた連邦制度に、強い信任を与えていた。連邦最高裁判所は、監督機能を拡げる意思を持っていたが、その速度はきわめて遅かった。そして「適正な法手続き」を余りにも無視し、連邦最高裁判所として看過できないほどひどい訴訟があった場合だけ、監督権を行使した。例えば1936年に、連邦最高裁判所は、激しく殴られ、拷問を受けた後に殺人を犯したと自白した、3人の黒人男性の有罪判決を覆した。「ブラウン対ミシシッピ州事件」(Brown v. Mississippi)(1936年)の判決で、チャールズ・エヴァンズ・ヒューズ連邦最高裁判所長官(Charles Evans Hughes)は、強要された自白を州が採用したことは、「適正な法手続き」条項の違反に当たる、として州を非難した。同判事は、拷問は「正義感に反する」と同時に、「われわれ国民の伝統と良心に深く根ざし、基本的なものとして位置づけられている」原則を踏みにじったと判示した。
この事件でも連邦最高裁判所は、権利章典が明白に保障した保護を拡大しようとはせず、合衆国憲法修正第14条の「適正な法手続き」条項に判断の根拠を求めた。連邦最高裁判所は、州が自分たちの裁判の構成に関して裁量権を持つことを明示した。採用した手続きがどのようなものでも、「適正な法手続き」という理念が求める公正の原則に適合している限り、州は陪審裁判を行う必要さえないことを明示したのである。
「ブラウン対ミシシッピ州事件」(Brown v. Mississippi)での判決理由(1936年) 「州が、陪審裁判を省略できると言っても、裁判を神盟裁判に代えることができるわけではない。拷問台と拷問部屋を証人席の代わりにすることはできない」 |
パウエル事件判決は、死刑に相当する犯罪では、州は被告人に弁護人をつけなければならない、というルールを確立した。しかし、死刑を伴わない重罪の裁判で、貧しい被告人に弁護人の援助を付与すべきかどうかという問題には触れなかった。この問題は、1963年、米国史上、最も有名な事件の一つとされる訴訟で解決を見た。それは、「ギデオン対ウェインライト事件」(Gideon v. Wainwright)だった。
浮浪者のクラレンス・アール・ギデオン(Clarence Earl Gideon)は、ビリヤード場で強盗を働いたとして有罪判決を受けていた。彼は、公判で無罪を主張し、弁護人をつけてほしいと裁判官に求めた。米国憲法によって弁護人を持つ権利が自分に保障されていると信じていたからだ。裁判官は、この事件の場合、フロリダ州法では、ギデオンに弁護人をつけてもらう権利はない、と答えた。ギデオンは、自己の弁護に最善を尽くしたが、主に状況証拠によって有罪となった。彼は刑務所で図書館に通い、控訴する方法を調べ、最初はフロリダ州連邦最高裁判所(彼の申し立ては棄却された)へ、その後、連邦連邦最高裁判所へ上訴した。
ギデオンの「貧困者訴訟」(訴訟救助)が連邦最高裁判所に提訴されたのは、まさに「ウォーレン・コート」が「適正な法手続き条項の改革」を行っている真最中だった。当時、連邦最高裁判所は、アール・ウォーレン(Earl Warren)長官の指揮の下で、合衆国憲法修正第14条の「適正な法手続き」条項は、権利章典に見られる「適正な法手続き」の要素もまた「内に包んでいる」との判断を下す過程にあった。連邦最高裁判所は、合衆国憲法修正第6条の弁護人の支援を受ける権利が盛り込まれるべきかどうか、まだ判断を下していなかった。このためギデオンの上訴は、その判断を下す好機となった。貧困者の訴訟を受け入れる場合は常にそうであるように、連邦最高裁判所はギデオンの代理を務める弁護人を選任した。それはワシントンで最も著名な弁護士の一人で、後に連邦最高裁判所判事となるエイブ・フォータス(Abe Fortas)だった。「法律事務所というところは、訴訟準備に何千ドルもの費用をかけながら、たとえ1セントも弁償されなくても、連邦最高裁判所からこの種の依頼を受けることは大変な名誉なことだと考えるものである」
フォータス弁護人は口頭弁論で、被告人の財力にかかわりなく被告人が弁護人の援助を受けることができなければ、真に公正な裁判ではあり得ないし、「適正な法手続き」の要件を満たすこともできない、と判事たちを説得した。連邦最高裁判所はこれに同意し、その判決で、この基本的権利を、重罪で起訴されるすべての被告人に適用することにした。それから数年後、ウォーレン・バーガー長官(Warren Burger)の下、連邦最高裁判所は、この保護を禁固刑につながる軽犯罪事件にも拡大した。
「クラレンス・アール・ギデオンという世間では知られることもないフロリダ州の受刑囚が、刑務所の独房で、仮に鉛筆と紙で連邦最高裁判所に熱心に手紙を書き始めなかったならば、そして連邦最高裁判所が、仮に、毎日受け取るすべての郵便物の束の中の、しかも1通の稚拙な請願書の中に、救済を受ける権利を見出す手間を惜しんだならば、米国の巨大な法制度は、それまで通りの機能を続けていたことだろう」 しかし、ギデオンは実際にその手紙を書き、実際に連邦最高裁判所は彼の事件を調べた。彼は有能な弁護人の助けを得て再審理を受け、無罪判決を勝ち取った。ギデオンは、犯してもいない罪で2年間服役した後、釈放された。そしてそれ以来、米国の法律の歴史のすべての流れが変わった。 |
* * * * *
弁護士の重要な役割は、犯罪で起訴された被告人の権利を守ることだと考えられているが、起訴された者を保護するための成文化された権利の束がなければ、弁護士一人で法廷に立っても、ほとんど役に立たないだろう。例えば、刑事裁判でどのような証拠を採用できるかは、合衆国憲法修正第4条で確立された違法な捜索および押収に対する保護規定によって決められている。ここでもまた、18世紀の、英国の支配下での入植者たちの経験が、建国世代の人々の具体的な関心事を形成したのである。
英国の法律では、警察が個人の住居を捜索するには、令状の発給が必要とされていたにもかかわらず、英国の植民地政府は、「捜査援助令状」(writs of assistance)と呼ばれる一般令状に依存した。これは、ほとんどあらゆる場所のあらゆる物を捜索できる許可を当局者に与えた、一般令状の概念は、ヘンリー8世治世下のチューダー王朝時代までさかのぼるが、その広範な権限に対する抵抗が、18世紀初頭に増大し始めた。批判派は、一般令状を、「あらゆる人々の住居を、面識のない者による立ち入りと捜索にさらす、全国民に対する奴隷バッジだ」と攻撃した。しかし、政府は依然として一般令状を使用した。そしてそれは、国王政府と米国の入植者たちの間の大きな摩擦の原因となった。一般令状の問題点は、対象を特定していないことにあった。例えば1763年に、英国では、国務大臣によって典型的な令状が発行された。それは風刺的な新聞、「ザ・ノース・ブリテン」(The North Briton)の筆者と印刷人と出版人を、名前を特定することなく、「入念に捜査」し、関連文書を押収するよう命じる令状だった。この結果、少なくとも5軒の家が捜索され、49人(ほとんどは無実)が逮捕され、何千もの書物と文書が押収された。英国中にこの令状に対する反対が広まり、政府は徐々にその使用を控えざるを得なくなった。
一般令状に関して(1762年) 「証拠を確保するために、名前が明記されてない令状によって個人の住居に立ち入ることは、『スペインの異端審問』より悪質である。このような法律の下で、英国人は1時間たりとも生きたいとは思わないだろう」 |
一般令状の使用は母国で制限されたにもかかわらず、米国植民地では依然として広く使われ、大英帝国に対する植民地の主な不満の一つとなっていた。マサチューセッツ植民地議会の一員、ジェームズ・オーティスは、「捜査援助令状」に反対する有名な演説の中で、それらは「法の基本原則、住居の特権に違反し、・・・[それは]これまで 英国の法律書の中で発見された専制権力の最悪の道具であり、英国の自由を最大限に破壊するもの」であると非難した。独立戦争後、各州は、そのような令状の執行を制限するさまざまな法律を制定した。そしてジェームズ・マディソンが権利章典を起草した時、合衆国憲法修正第4条が、この令状の使用に関する一層の制限を明記した。
合衆国憲法に基づき令状を取得するためには、警察は、逮捕しようとする特定の人物や捜索しようとする場所を明示する手持ちの証拠を提出しなければならない。必要なのは、逮捕、押収される対象物の具体性である。単に「その家に住んでいる男」というのではなく、逮捕すべき人物の名前を特定しなければならない。警察は、密輸品、麻薬、武器というように、捜索の対象が何かを明確にする必要があり、ただ容疑者の家を捜索したいことを示すだけでは認められない。令状を取得するためには、警察は、合衆国憲法修正第4条が述べる「相当な理由」を示す必要がある。これは、ある家に密輸品があるとか、特定の人物が実際に罪を犯したという、圧倒的な証拠を意味するのではない。警察が示さなくてはならないのは、どちらかと言えばその人物が特定の違法行為を犯した可能性があること、その建物を捜索すれば、犯罪に関する特定の証拠が得られる可能性があること―である。
合衆国憲法修正第4条は、これらの規定の執行については、全く触れていないので、長年にわたり各州の警察は、どのような令状も全く持たずに、あるいは相当な理由も明示せずに、しばしば実際に家宅捜索や逮捕を行ってきた。連邦最高裁判所は、連邦の法執行官は憲法の高い基準に従わなければならないと判示し、「(違法収集証拠の)排除の法則」として知られる原則を作った。この基準に基づき、正当な令状なしに違法に押収された証拠は、法廷に提出できないことになった。連邦裁判所が権利章典の適用範囲を州にも拡大した際、この違法収集証拠の排除の法則もまた、州の警察と裁判所に適用された。
(Mapp v. Ohio)での判決理由(1961年) 「[異邦収集証拠の排除の原則がなければ]、不当な捜索を受けることはないと、いくら保障しても、単なる『決まり文句』に過ぎず、何の価値もない。それは、計り知れないほど貴重な人間の自由の特権として言及するに値しないものになるだろう。そしてまた、この原則がなければ、国家によりプライバシーを侵されない自由は、つかの間に消えてしまう。また、強制的に証拠を収集するあらゆる野蛮な手段からの自由という、概念的な絆からもきれいに切り離され、この連邦最高裁判所が高く評価する『秩序ある自由という概念に内在する』自由にも値しないものとなるだろう」 |
一部にはこの「証拠排除の原則」を批判する人々もいる。例えばカードーゾ連邦最高裁判所判事は、かつて、この原則があるがために「巡査がへまをすれば、犯罪者は自由になる」という有名な言葉を残したが、しかしこの原則のみが、合衆国憲法修正第4条の必要条件を遵守する唯一の手段であるという点について、一般的に意見は一致している。この規定は、あらゆる権力を擁している国家に、確実にルールに従って行動させることを保障するものである。ルールに従わなければ、たとえ被疑者が実際のところ罪を犯していても、違法に押収した証拠を用いて被疑者を訴追することはできない。これは、一部の者には行き過ぎに見えるかもしれないが、警察の適正な捜査を保障するという、より高度の善をもたらす。
合衆国憲法修正第6条の弁護人の支援を受ける権利もまた、刑事事件において誰も「自分自身に不利な供述」を強要されないという、一部の学者が「偉大な権利」と名づけてきた合衆国憲法修正第5条の権利と、しばしば結びつけて論じられてきた。この権利の起源は、中世の教会裁判所の審問手続きや英国の星室裁判所に対する異議の申し立てにさかのぼる。17世紀後半までに、「誰にも自らを罪に陥れる義務はない」という原則が、英国のコモンロー裁判所で採用された。その後、人は自分の行為に対するいかなる質問にも答える必要がない、という意味にまで拡大された。国家は、ある人を訴追することができるが、その人に訴追手続きに協力せよと要求することはできないのである。米国植民地はこの原則を、是認されたコモンローの一部として持ち込んだ。そして多くの州が、それぞれの初期の権利章典に、この原則を盛り込んだ。マディソンはこれを、連邦の「権利章典」を起草した時に、当然のこととして書き入れたのである。
1950年代初期、この特権は激しい非難にさらされた。というのも、米国国内の共産主義活動を議会で準司法的に審理する「非米活動委員会」の公聴会で、「自己負罪」(自分に刑事責任を与えるような不利な証言をすること)を理由に、証人たちがマッカーシー上院議員の質問に答えることを拒否したからである。「合衆国憲法修正第5条をたてにする」ことが、人々の頭の中で共産主義者と結びつき、メディアの解説者たちは、誰でも真に無実なら、法廷や調査委員会でも証人席に立ち、ためらうことなく真実を語るだろう、と主張した。大衆紙は、この憲法上の権利は、犯罪者だけを保護するとして、これを修正することの是非を論じる記事を載せた。
しかし、連邦最高裁判所は、この権利を広義に解釈し続けてきた。それは、19世紀の後半、自らに不利な供述を拒否する権利(自己負罪拒否特権)は、あらゆる刑事裁判と、後に刑事裁判で採用される可能性のある民事訴訟での供述にも、等しく適用されると定めたとき以来の、連邦最高裁判所の姿勢だった。この特権は、絶対的ではない。たとえそれが有罪を立証することになるものであっても、指紋採取、血液採取、音声録音、そのほかの物理的な証拠の採取や、飲酒検査を受けることを、拒否することはできない。しかし、公判で、被告人には黙秘する権利がある。被告の沈黙に対する悪意ある発言は、それが裁判官であれ検察官であれ、憲法上の特権を侵すことになる。
被告人は供述を強制されないが、自主的に告白することはできる。その供述は、証拠として用いられる。実際、激情や薬の影響で罪を犯したような刑事事件の多くは、常習犯でない限り、容疑者は進んで自白する。古いコモンローの規則には、拷問や脅迫、誘導、約束の結果として行われる供述を、禁止する規定がある。この規則は、1884年に連邦最高裁判所により、憲法の一部として再確認された。現代では、1950年代の「赤の恐怖」(いわゆる赤狩り)にもかかわらず、連邦最高裁判所は、いかにして権利章典の制約を尊重しながら、職務を果たすかに関して、より詳細な指針を警察に与えるための基準の改良を行ってきた。
連邦最高裁判所は、供述は自主的でなければならず、肉体的な暴行や精神的な虐待の結果であってはならないことを強調した。連邦最高裁判所は、その後、合衆国憲法修正第5条の特権と、合衆国憲法修正第6条の弁護人の助けを受ける権利を結びつけた。これは、被告人が黙秘権を含む自分の権利について最初に説明を受けた時のみ、その後の自白が証拠として認められる、という理由によるものだった。
「エスコビードウ対イリノイ州事件」での判決理由(1964年) 「われわれの憲法は、被告が自己負罪拒否特権に関して、弁護人の助言を受ける権利を支持する形でバランスを取っている。・・・およそ維持する値打ちのある制度であるならば、被告人が弁護人と相談することを認められるとこれらの諸権利に気づき、それを行使するようになる、などと恐れるべきではない。もし、憲法上の権利の行使が法執行制度の有効性を妨げるようなことがあれば、その時は、その制度に何か大きな誤りがあるのである」 |
その後、1966年に連邦最高裁判所は、「ミランダ対アリゾナ事件」で、画期的な判決を下した。警察と下級裁判所は、憲法上のすべての要件が、司法手続きのどの時点で満たされたかを判断するのに役立つ、より明確なルールを望んでいた。そして連邦最高裁判所は、ミランダ判決でそのルールを示した。アール・ウォーレン連邦最高裁判所長官によれば、被疑者は、逮捕されたときに、黙秘する憲法上の権利があることを、明瞭かつ誤解の余地がない言葉で、知らされるべきであること、また、そのときから供述することはすべて、後に法廷で当人に不利な証拠として使われる可能性があることを、知らされる必要があるのだ、という。さらに、警官は被疑者に対し、弁護人の助けを求める権利があること、また、弁護人を依頼する資力がなければ国が弁護人をつけることを、告げる必要もある。警察の取り調べが弁護士の立ち会いなしに行われた場合は、ウォーレン長官は、次のように警告している。すなわち、「被告人が自己負罪拒否特権と弁護人の助けを受ける権利があることを知りながら、自分の判断でそれを放棄したことを証明する、重い責任が政府にはある」
「ミランダ事件」の判決の後、裁判所に対して、犯罪者に甘いという非難の嵐が巻き起こったが、ほどなく、ミランダ判決が基本的に健全なものであることが明らかになった。国内の、より進歩的な警察は、直ちに、自分たちは何年も同じような手続きに従って捜査してきたが、そのために、犯罪の捜査や事件の解決がうまくいかなかったことはない、と発表した。自白をしたい重罪犯は、いずれにしても自白した。そうでないときは、被疑者を見つけ出し有罪判決を得るために、一段と効果的な警察捜査が必要になるだけのことだった。ミランダ判決が犯罪を助長するのではないかという批判に対し、ラムゼイ・クラーク司法長官は、「裁判規則が犯罪を引き起こすのではない」と述べた。検察官の多くもこれに同意した。そのうちの一人は、「裁判所の判断と訴訟手続きの変更が犯罪発生率に与える影響は、アスピリンが脳腫瘍におよぼす影響と同じようなものだ」と述べた。
人が罪を犯した場合、裁判所は、そして憲法も、ほとんど何もすることができない。裁判所と憲法、そして社会の人々の関心事は、警察が容疑者を逮捕した時、「適正な法手続き」もなしに刑務所に送られたり、死刑を宣告されたりしないことである。犯罪防止は、立法府と、行政府の責任である。しかし合衆国では、立法府と行政府は、憲法の規定の制限内でそれを行わなければならない。憲法の起草者たちは、横暴な君主が裁判所をどのように悪用するかを十分知っていたため、法の解釈と適用については、裁判所に完全な独立性を与えるように最善を尽くしてきた。 また、憲法の起草者たちは、体制に政治的に敵対する人々を迫害するために、刑法がどのように利用されるかを見てきていたため、極めて重大な決断をした。犯罪で起訴された者に対して、その人の同輩の一般社会人による公正で迅速な陪審裁判を含む、「適正な法手続き」を構成する多くの権利を与えようとした。それだけでなく、すべての制度は、犯罪で起訴された者は一点の疑いもなく有罪が立証されるまでは無罪である、という前提に基づくべきだ、と主張したのである。民主主義社会では、犯罪で訴追されたとき、自分が無罪であることを立証する必要はまったくない。むしろ、有罪を立証する責任、しかも十分な説得力をもってそれを証明する責任は、国家にある。
犯罪者の中には、証拠をうまく隠し、警察が証拠を挙げられずに、法の裁きを逃れる者も出てくるのではないだろうか。その答えは、「イエス」である。それは、「適正な法手続き」を守ろうとする制度のために、われわれが支払う代償の一つである。 時には犯罪者が自由の身になることもあるかもしれない。だが、われわれの目標は、無実の人が一人たりとも誤って処罰されることがないようにすることである。制度は完全なものではないが、その理想は実際に機能しているのである。人々の権利を保護するためには、民主主義における「適正な法手続き」は、単なる言葉以上のものでなければならない。
参考文献:
- David J. Bodenhamer, Fair Trial: Rights of the Accused in American History (New York: Oxford University Press, 1992)
- Jacob W. Landynski, Search and Seizure and the Supreme Court (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1966)
- Leonard W. Levy, Origins of the Fifth Amendment (New York: Oxford University Press, 1968)
- Anthony Lewis, Gideon’s Trumpet (New York: Random House, 1964)
- Melvin I. Urofsky, The Continuity of Change: The Supreme Court and Individual Liberties, 1953-1986 (Belmont, CA: Wadsworth Press, 1989)
- Samuel Walker, Popular Justice: A History of American Criminal Justice (New York: Oxford University Press, 1980)
*上記の日本語文書は参考のための仮翻訳で、正文は英文です。
Rights of the Accused
(The following article is taken from the U.S. Department of State publication, Rights of the People: Individual Freedom and the Bill of Rights.)
The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.
– Fourth Amendment to the U.S. Constitution
No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury . . . nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall he be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor deprived of life, liberty, or property, without due process of law. . . .
– Fifth Amendment
In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial by an impartial jury...and to be informed of the nature and cause of the accusation; to be confronted with the witness against him; to have compulsory process for obtaining Witnesses in his favor, and to have the Assistance of Counsel for his defense.
– Sixth Amendment
Nor shall any State deprive any person of life, liberty,
or property, without due process of law….
– Fourteenth Amendment
We normally think of a trial by jury as one of the individual rights afforded to persons accused of a crime. It is also, as we have seen, a right that is institutional as well – one that belongs to the people as a whole as well as to the individual. But jury trials, as has been all too evident in dictatorships, can be meaningless unless that trial is governed by rules that ensure fairness to the individual. A trial in which the judge allows illegally seized evidence to be used, or in which the defendant has no access to an attorney, is forced to testify against himself, or is denied the ability to bring witnesses favorable to his cause, is not a trial that meets the standard of due process of law. The men who drafted the Bill of Rights knew this, not only from their experience during the Colonial era, but also from the history of Great Britain, which ever since the signing of the Magna Carta in 1215 had been committed to expanding the rule of law.
Today we tend to emphasize the relationship of rights to individual liberty, but even those rights which are most identified as individual – such as the rights of persons accused of crimes – still have a community basis. Rights in American history are not designed to free the individual from community norms; rather, they exist to promote a responsible liberty, to allow each and every one to be free from arbitrary power. In the areas of free expression, the Bill of Rights carves out a space where dissenting voices may be freely heard, both for the benefit of the individual as well as for the sake of the community. Rights of any kind are the community's protection against the unwarranted interference in daily life by an all-powerful central government. Rights liberate both the community and the individual.
Regarding the rights of the accused, the basic outlines of due process are spelled out in the Constitution, and their specifics have been refined in local, state, and federal courtrooms for more than two centuries. Many of these questions seem to deal with minute, some would even say mundane, details of procedure. But as Justice Felix Frankfurter once declared, "The history of American freedom is, in no small measure, the history of procedure." His colleague on the Supreme Court, Justice Robert H. Jackson, agreed, and once noted that whatever else "due process" might mean, procedural fairness "is what it most uncompromisingly requires."
What is due process of law? There is no absolute agreement on the meaning, and over the past two centuries courts have found that the phrase encompasses not only procedural but substantive rights as well. For our purposes, due process of law is what the Constitution, as interpreted by the courts and supplemented by legislation, has created to protect the integrity of the criminal justice system. It does not mean that in every case every defendant is treated identically. Rather, every defendant, no matter what the charge, is entitled to certain processes to ensure that at the end of the day, he or she will have had a fair trial, conducted under the rules of law, openly, and in such a manner that the public can rest assured that the system is working fairly. While this sounds simple to accomplish, the history of criminal procedure in the United States and elsewhere shows that it is not. Only in democratic societies confident of their rights can such a system develop. Military justice is different, out of necessity – this essay treats of the vast majority of cases referred to civil courts.
* * * * *
At the time of the American Revolution, the concept of the rights of the accused had progressed much further than in Great Britain. If we look at the first state laws passed after the American Revolution of 1776, we find a surprisingly modern list of rights, which included a right to reasonable bail, the exclusion of confessions made out of court, the right to know the charges, grand jury indictments in capital cases, trial by jury, and others, many of which would eventually be included in the Bill of Rights (1791). But the Bill of Rights applied only to the federal government until the 1920s, and criminal cases were for the most part tried in state courts under state law. The result was that in the early 20th century there were two separate systems of criminal procedure in the United States.
On the one hand, there were a small number of federal crimes (that is, crimes defined by Acts of Congress), which would be investigated by the small force of federal investigators, and tried in federal courts under the strict requirements of the Bill of Rights. Moreover, relatively early on, if the defendant was too poor to hire a lawyer, the court would appoint one from the local bar to represent him. At least on the federal level, the notion that due process required a lawyer was well established by the early 20th century.
On the other hand, were the state courts, in which state crimes (defined by acts of the state legislature) were investigated by local or state police, prosecuted by local or state district attorneys in state courts, and in which only state provisions, not federal rights, applied. And the sad fact of the matter is that in most states, there were few procedural rights, and even the ones that existed were not stringently enforced. Searches could often be carried out without a warrant; persons arrested could be subjected to intimidating police interrogation without the presence of a lawyer; if they did not have the money to hire an attorney, then they could be tried without a lawyer; in many states defendants did not have the right to refuse to testify at their trials, and if they decided not to take the stand, their silence could be used as "proof" of their guilt; and if found guilty, they often did not have the right of an appeal.
Because the United States is a federal system, laws do vary not only between the federal government and the states, but from state to state. In those areas where the Constitution does not spell out a clear federal supremacy, the practice has been to allow the states great leeway in how they conduct their business, including investigation and prosecution for crime. Until the early 20th century, federal courts operated on the assumption that the Constitution did not give them any power to review either the procedures or the results of state trials. One should note that in many states, procedural guidelines were as protective of individual rights as that of the federal government. But a wide spectrum existed, ranging from trials that would, under any circumstances, be considered fair to those that could only be described as mockeries of justice. It was one of these latter that finally moved the federal courts to intervene, and which over the next half-century led to a redefinition of criminal procedure in the United States.
William Rawle, a Philadelphia lawyer (1825)
The most innocent man, pressed by the awful solemnities of public accusation and trial, may be incapable of supporting his own cause. He may be utterly unfit to cross-examine the witnesses against him, to point out the contradictions or defects of their testimony, and to counteract it by properly introducing it and applying his own.
The eight young black men (the "Scottsboro boys") who were charged with raping two white girls in Alabama in 1931 may have been innocent, but in the racially charged atmosphere of the Deep South during the Depression they certainly had no knowledge or ability to defend themselves. All eight were tried, found guilty, and sentenced to die in sham trials lasting less than a day. The lawyers assigned to defend them by the judge did little more than show their faces in the courtroom and leave. When news of this travesty of justice reached northern newspapers, civil liberties groups immediately volunteered to provide effective counsel on appeal, and succeeded in moving the case into the federal court system and up to the U.S. Supreme Court.
Justice Oliver Justice George Sutherland, in Powell v. Alabama (1932)
The right to be heard would be, in many cases, of little avail if it did not comprehend the right to be heard by counsel. Even the intelligent and educated layman has small and sometimes no skill in the science of the law. If charged with crime, he is incapable, generally, of determining for himself whether the indictment is good or bad. He is unfamiliar with the rules of evidence. Left without the aid of counsel he may be out on trial without a proper charge, and convicted upon incompetent evidence, or evidence irrelevant to the issue or otherwise inadmissible. He lacks both the skill and knowledge adequately to prepare his defense, even though he have a perfect one. He requires the guiding hand of counsel at every step in the proceedings against him. Without it, though he be not guilty, he faces the danger of conviction because he does not know how to establish his innocence. If that be true of men of intelligence, how much more true is it of the ignorant and illiterate, or those of feeble intellect.
The case of Powell v. Alabama is notable for two things. First, it launched the federal courts on a new mission, that of overseeing the criminal justice system in the states, and they did this under the Due Process Clause of the Fourteenth Amendment, which specifically applies to the states. It was not then, and never has been, the mission of the federal courts to ensure that criminal procedure in every state is identical to that in every other state. Rather, the courts have attempted to define the minimum protection of rights that the Constitution demands to ensure due process. While some states, for example, have 12-person juries, other states have lesser numbers for certain types of trial. These variations are permissible, the courts have held, so long as the trial and the jury adhere to minimal standards of fairness.
Second, Powell established the rule that in capital cases, those in which the death penalty could be imposed, effective assistance of counsel is constitutionally required. The lawyers in the Alabama case did no more than show up; they did nothing to defend their clients, and for all practical purposes might as well have been absent altogether. Not only must a defendant have a lawyer, the Court ruled, but that lawyer must provide real assistance, or as the courts have put it, effective counsel.
But the Court that ruled in Powell still believed strongly in a federal system, and while it was willing to extend its oversight function, it did so slowly, and only when confronted with a case that so offended it that the justices could not ignore the breach of due process. In 1936, for example, the high court overturned the convictions of three black men who had confessed to committing murder only after they had been severely beaten and tortured. In Brown v. Mississippi (1936), Chief Justice Charles Evans Hughes denounced the state's use of coerced confessions as a violation of due process. Torture "revolted the sense of justice," and violated a principle "so rooted in the traditions and consciences of our people as to be ranked fundamental."
Here again the Court was not ready to extend the protection of explicit Bill of Rights guarantees, but relied on the Due Process Clause of the Fourteenth Amendment. It made clear that states had great leeway in how they structured their trials; they did not even have to have jury trials provided whatever procedure they did adopt conformed to the principles of fairness demanded by the ideal of due process.
Chief Justice Charles Evans Hughes, in Brown v. Mississippi (1936)
Because a state may dispense with a jury trial, it does not follow that it may substitute trial by ordeal. The rack and torture chamber may not be substituted for the witness chair.
Although Powell established the rule that states had to provide counsel in capital cases. It did not address the question of whether counsel had to be provided to indigent defendants in felony cases that did not carry the death penalty. That issue would not be decided in the United States until 1963, in one of the most famous cases in American history – Gideon v. Wainwright.
A drifter, Clarence Earl Gideon, had been convicted of robbing a pool hall. At his trial he maintained his innocence, and asked the judge to assign him a lawyer, since he believed the Constitution of the United States assured him of that right. The judge responded that under Florida law he was not entitled to a lawyer in this case. Gideon did the best job he could defending himself, but was found guilty primarily on the basis of circumstantial evidence. In prison he went to the library and looked up how to appeal his case, first to the Florida Supreme Court (which turned him down), and then to the U.S. Supreme Court.
As it turned out, Gideon's "pauper's appeal" (in forma pauperis) arrived at the Court in the midst of the "due process revolution" of the Warren Court. The Supreme Court, under the leadership of Chief Justice Earl Warren, was in the process of determining that the Due Process Clause of the Fourteenth Amendment also "incorporates" other elements of due process found in the Bill of Rights. The Court had not yet determined whether the Sixth Amendment right to counsel was to be incorporated, and Gideon's appeal gave it the opportunity to make that decision. And as it does whenever it accepts a pauper's appeal, the Court assigned counsel to represent Gideon, in this case one of Washington's most prominent attorneys, Abe Fortas, later to be a member of the Court itself. (Law firms consider it a high honor when asked by the Court to do this type of service, even though they are not reimbursed a cent for the thousands of dollars they expend in preparing the case.)
At oral argument, Fortas convinced the justices that there could never be a truly fair trial, and that the requirement of due process could never be met, unless a defendant, no matter what his or her financial resources, could have the services of an attorney. The Court agreed, and in its decision extended this basic right to all persons charged with a felony. A few years later, the Court under Chief Justice Warren Burger, extended this protection to misdemeanor charges that could lead to a jail sentence.
Attorney General Robert F. Kennedy on the Gideon case (1963)
If an obscure Florida convict named Clarence Earl Gideon had not sat down in his prison cell with a pencil and paper to write a letter to the Supreme Court, and if the Court had not taken the trouble to look for merit in that one crude petition among all the bundles of mail it must receive every day, the vast machinery of American law would have gone on functioning undisturbed.
But Gideon did write that letter, the Court did look into his case; he was retried with the help of a competent defense counsel, found not guilty, and released from prison after two years of punishment for a crime he did not commit – and the whole course of American legal history has been changed.
* * * * *
The role of the lawyer is considered central to protecting the rights of a person accused of a crime, but the lawyer standing alone would be of little use were it not for the bundle of codified rights that are there for the accused person's protection. What evidence may be used in a criminal case, for example, is governed by the protections against unlawful search and seizure established in the Fourth Amendment. Here again the colonists' experience under British rule in the 18th century shaped the concerns of the Founding generation.
Although British law required that warrants be issued for the police to search a person's residence, the British Colonial government relied on general warrants, called writs of assistance, which gave officials a license to search almost everywhere for almost everything. The notion of a general warrant dated back to the Tudor reign under Henry VIII, and resistance to its broad reach began to grow in the early 18th century. Critics attacked the general warrants as "a badge of slavery upon the whole people, exposing every man's house to be entered into, and searched by persons unknown to him." But the government still used them, and they became a major source of friction between His Majesty's Government and the American colonists. The problem with the general warrant was that it lacked specificity. In England in 1763, for example, a typical warrant issued by the Secretary of State commanded "diligent search" for the unidentified author, printer, and publisher of a satirical journal, The North Briton, and the seizure of their papers. At least five houses were subsequently searched, 49 (mostly innocent) people were arrested, and thousands of books and papers confiscated. Opposition to the warrants was widespread in England, and the opposition gradually forced the government to restrict their usage.
Chief Justice Sir Charles Pratt, on general warrants (1762)
To enter a man's house by virtue of a nameless warrant in order to procure evidence, is worse than the Spanish Inquisition; [it is] a law under which no Englishman would wish to live for an hour.
Despite its restriction in the mother country, the use of general warrants remained widespread in the colonies, and constituted one of the colonists' major complaints against Great Britain. In a famous speech against the writs of assistance, James Otis, a member of the colonial Massachusetts assembly, charged that they went "against the fundamental principles of law, the privilege of house. . . . [It is] the worst instrument of arbitrary power, the most destructive of English liberty, that was ever found in an English law-book." Following the Revolution, the states enacted a variety of laws limiting the use of such warrants, and when James Madison drafted the Bill of Rights, the Fourth Amendment spelled out further restrictions on the use of warrants.
In order to get a warrant under the U.S. Constitution, police must present evidence in their possession pointing to a specific person they wish to arrest or a place they wish to search. And they must be specific. The person must be identified by name, not just "the man who lives in that house." Police must specify what it is they are searching for – contraband, drugs, weapons – and not just indicate that they wish to search a suspected person's house. In order to get that warrant, they must have what the Fourth Amendment identifies as "probable cause." This does not mean overwhelming proof that there is contraband in a certain house or that a particular person did in fact commit a crime. Rather, they must show that it is more likely than not that the person did commit a specific illegal act, and that it is more likely than not that a search of the premises will yield particular evidence of a crime.
The Fourth Amendment is silent about any enforcement of these provisions, and for many years police in the states often did, in fact, search houses and arrest people either without having any warrant at all or having secured one without really showing probable cause. Courts held that federal law enforcement officials had to abide by the high standards of the Constitution, and created what came to be known as the "exclusionary rule." Under this standard, evidence seized without a proper warrant could not be introduced at a trial. When the federal courts expanded the reach of the Bill of Rights to apply to the states as well, they also applied the exclusionary rule to state police and trial courts.
Justice Tom Clark, in Mapp v. Ohio (1961)
[Without the exclusionary rule] the assurance against unreasonable searches would be "a form of words," valueless and undeserving of mention in a perpetual charter of inestimable human liberties. So too, without that rule the freedom from state invasion of privacy would be so ephemeral and so neatly severed from its conceptual nexus with the freedom from all brutish means of coercing evidence as not to merit this Court's high regard as a freedom "implicit in the concept of ordered liberty."
Although there have been some critics of the exclusionary rule – Justice Cardozo once famously said that because of the rule "the criminal is to go free because the constable has blundered" – there is also general agreement that it is the only means to enforce the requirements of the Fourth Amendment. It makes sure that the state, with all the power behind it, plays by the rules. And if it doesn't, then it cannot use evidence illegally gained in prosecuting a person, even if that person is in fact guilty. While this may seem extreme to some, it serves a higher good – ensuring the proper behavior of the police.
* * * * *
The Sixth Amendment right to counsel is also often tied to what some scholars have called "the Great Right" in the Fifth Amendment that no person shall be compelled in any criminal case to be a "witness against himself." The origins of the right go back to objections against the inquisitorial proceedings of medieval ecclesiastical tribunals as well as the British Courts of Star Chamber. By the late 17th century, the maxim of nemo tenetur prodere seipsum – no man is bound to accuse himself – had been adopted by British common law courts and had been expanded to mean that a person did not have to answer any questions about his or her actions. The state could prosecute a person, but could not require that he or she assist in that process. The colonies carried this doctrine over as part of the received common law, and many states wrote it into their early bills of rights. Madison included it as a matter of course when he drafted the federal Bill of Rights.
The privilege came under heavy criticism during the early 1950s, as witnesses refused to answer Senator McCarthy's questions at hearings of the congressional "Un-American Activities" committee, a quasi-judicial inquiry into Communist activity in the United States, on grounds of possible self-incrimination. "Taking the Fifth" became associated with Communists in the public mind, and commentators asserted that a truly innocent person would not hesitate to take the stand and tell the truth in criminal trials or before investigating committees. The popular press carried articles on whether this constitutional right, which allegedly sheltered only guilty persons, ought to be amended.
The Court, however, continued to take an expansive view of this right, as it had since the late 19th century, when it had defined the privilege against self-incrimination to apply to any criminal case, as well as to civil cases where testimony might later be used in criminal hearings. The privilege is not absolute; persons may not refuse to be fingerprinted, to have blood samples, voice recordings or other physical evidence taken, or to submit to intoxication tests – even though all these may prove incriminating. But at a trial, the accused has the right to remain silent, and any adverse comment on a defendant's silence, by either judge or prosecutor, violates the constitutional privilege.
* * * * *
Although an accused person may not be forced to testify, he or she may voluntarily confess, and the confession may be used in evidence. In fact, in many criminal cases resulting from acts of passion or drugs where the perpetrator is not a career criminal, the suspect is eager to confess. The old common law rule against confessions obtained by torture, threats, inducements, or promises had been reaffirmed as part of constitutional law by the Court in 1884. In modern times, in spite of the "Red Scare" of the 1950s, the Supreme Court continued to refine the test to give police greater guidance in how to carry out their responsibilities while still respecting the strictures of the Bill of Rights.
The court emphasized that confession must be voluntary, and not be the result of physical abuse or psychological brutality. Then the Court tied the Fifth Amendment privilege to the Sixth Amendment's right to counsel, on the grounds that only if the accused is first informed of his rights, including the right to remain silent, can an ensuing confession be admissible.
Justice Arthur Goldberg in Escobedo v. Illinois (1964)
Our Constitution strikes the balance in favor of the rights of the accused to be advised by his lawyer of his privilege against self-incrimination. . . . No system worth preserving should have to fear that if an accused is permitted to consult with a lawyer, he will become aware of, and exercise, these rights. If the exercise of constitutional rights will thwart the effectiveness of a system of law enforcement, then there is something very wrong with that system.
Then in 1966, the Supreme Court handed down the landmark ruling of Miranda v. Arizona. Police and lower courts had wanted a clear rule to help them determine when all the constitutional requirements had been met, and in Miranda the Court gave them that rule. According to Chief Justice Warren, a person under arrest had to be informed in clear and unequivocal terms of the constitutional right to remain silent, and that anything said at that point could be used against him later in court. In addition, the officers had to tell the suspect of the right to counsel and that if he or she had no money to hire a lawyer, the state would provide one. If the police interrogation continued without a lawyer present, the chief justice warned, "a heavy burden rests on the Government to demonstrate that the defendant knowingly and intelligently waived his privilege against self-incrimination and the right to counsel."
The Miranda decision unleashed a storm of criticism of the Court for its alleged coddling of criminals, but within a short time the basic soundness of Miranda became clear.
The more progressive police departments in the country lost little time in announcing that they had been following similar practices for years, and that doing so had not undermined their effectiveness in investigating or solving crimes. Felons who wanted to confess did so anyway; in other cases, the lack of a confession merely required more efficient police work to find and convict the guilty party. As to charges that the decision encouraged crime, Attorney General Ramsey Clark explained that "court rules do not cause crime." Many prosecutors agreed, and one commented that "changes in court decisions and procedural practice have about the same effect on the crime rate as an aspirin would have on a tumor of the brain."
The Court – and the Constitution – can do very little should a person commit a crime. Their concern, and the concern of the society, is that when the police apprehend a suspect, that man or woman is not sent to jail or condemned to die without due process of law. The prevention of crime is the responsibility of the legislative and executive branches, who make the laws and retain the ultimate responsibility for enforcement. But in the United States they must do so within the parameters drawn by the Constitution. Because the Framers knew too well how the courts could be perverted by an overbearing monarch, they did their best to give the courts complete independence in interpreting and applying the law.
And because they had seen how the criminal law could be used to persecute political opponents of the regime, they made a fateful decision. Not only would they provide persons accused of a crime that bundle of rights that constitute due process, including a fair and speedy trial by one's peers, but they insisted that the entire system rest on the assumption that a person accused of a crime is considered innocent until proven guilty beyond the shadow of a doubt. In a democratic society, no person should have to prove that he or she is innocent when accused of a crime. Rather, the burden is on the state to prove guilt, and to do so convincingly.
Will some criminals escape justice because they have hidden their tracks well and the police cannot make a case? Yes, and that is one of the prices we pay for a system that insists on due process. An occasional criminal may go free, but our goal is to ensure that no innocent person is wrongfully punished. The system is not perfect, but its ideals do in fact govern. Due process in a democracy must be more than a mere phrase if the rights of the people are to be protected.
For further reading:
David J. Bodenhamer, Fair Trial: Rights of the Accused in American History (New York: Oxford University Press, 1992).
Jacob W. Landynski, Search and Seizure and the Supreme Court (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1966).
Leonard W. Levy, Origins of the Fifth Amendment (New York: Oxford University Press, 1968).
Anthony Lewis, Gideon's Trumpet (New York: Random House, 1964).
Melvin I. Urofsky, The Continuity of Change: The Supreme Court and Individual Liberties, 1953-1986 (Belmont, CA: Wadsworth Press, 1989).
Samuel Walker, Popular Justice: A History of American Criminal Justice (New York: Oxford University Press, 1980)