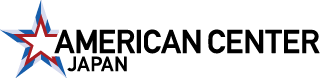国務省出版物
権利章典 – プライバシー
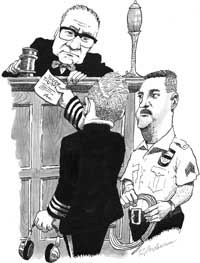 不当な捜索や逮捕・押収から、人々が自分の身体、家屋、書類および所有物の安全を確保する権利を、侵害してはならない。
不当な捜索や逮捕・押収から、人々が自分の身体、家屋、書類および所有物の安全を確保する権利を、侵害してはならない。
この憲法の中で、特定の権利が列挙されているからといって、国民の保有する他の権利を否定したり、軽視したりしたものと解釈してはならない。
どの州も合衆国市民の特権や免責権に制約を加える法律を制定したり、施行したりしてはならない。またどの州も、適正な法手続きによらないで、相手がだれであれ、その生命、自由、または財産を奪ってはならない。
権利とは、絶対的なものであると考えられることが多いが、決して不動のものでもなければ、不変のものでもない。言論の自由は、たいていは、人々が自分の考えを発言する権利を持つことを意味するが、そのための手段と、自分の考えを述べるべき機会は、時代とともに変化する。その結果、権利の性質もまた、変化する。技術の進歩と社会や文化の進化が、特定の権利についての考え方に影響を及ぼすこともある。このような変化が、それらの権利をどう定義するかを決定することがある。その点でプライバシーの権利ほどの好例はほかにない。この権利は、合衆国憲法に規定されてはいないが、裁判所と国民は、この権利に憲法上の地位を与えてきた。
「自宅で安全に過ごす英国人の権利に関して」(1763年) 「どのような極貧の者でも、自分の小屋の中では、国王のあらゆる力に抵抗することが許される。その小屋はもろく、屋根はきしみ、風に吹きさらされ、嵐が吹きこみ、雨漏りがするかも知れない。だが、英国王が入ることはできない。兵士たちは誰も、そのあばら家の敷居をまたごうとはしない」 |
ピットの有名なこの言葉は、つい最近まで人々がプライバシーの根幹と考えていたもの、つまり、個人の住居内では、政府の力も及ばず、誰からも干渉を受けない権利があることを要約したものである。
米国では、合衆国憲法修正第4条により、国民は自分の住居内での安全を保障される権利を持つという考えが確立されている。この考えは、合衆国憲法修正第3条の「所有者の承諾なしに、だれの家屋であろうと、軍の兵士を宿営させてはならない」という条文によって補強されている。のぞき見から守られることや、個人の振る舞い、行動が公衆の目にさらされ、話題にされることから保護されるという意味のプライバシーは、産業時代の産物である。古代から実に18世紀に至るまで、独居、世間との隔絶、あるいは自分だけの空間という意味でのプライバシーは、富裕層や貴族を除けば、無縁のものだった。大多数の人々は小さなあばら家に住み、しばしば家族全員が一つの部屋で寝ていた。実際、法的概念としての「プライバシー」はもともと、個人の氏名や肖像画を無断で使用するという、一種の名誉毀損を指す言葉だった。
しかし、西洋社会が豊かになり、中産階級が発達して、より大きな家に住めるようになり、家族の一員がそれぞれ自分自身の空間を持てるようになるにつれ、プライバシーの意味もまた変化した。いまやプライバシーは、個人としての存在の問題となり、公的生活の舞台裏での行為は、直接自分にかかわるものでない限り、第三者が口をはさむことではないと見なされるようになった。政府も、メディアも、実際そのほかのどのような人々も、国民の私生活に一切かかわるべきではない、とされるようになったのである。
プライバシーは、その近代的な意味において、個人という概念に大いに関係している。それは属人的な権利であり、集団や社会の権利ではない。政治学者ローダ・ハワード(Rhoda Howard)は、「プライバシーがなければ、人は社会的役割から切り離され、本質的に価値ある存在としての人間個人の意識を高めることができない」と述べている。その逆もまた然りである。個人としての存在という意識がなければ、プライバシーの必要性を認識することはできない。
プライバシーは、ほかの多くの権利と同様に、民主主義と直接的に関係している。人間は、他人との会話や交流を必要とすると同時に、自分自身だけの時間と空間も必要とする。プライバシーは、孤立や逃避ではなく、むしろ、一人でいることや、自分の好きな数人と一緒にいることを自ら選択する願望である。例えば、刑務所の独房での監禁生活はプライバシーには当たらないが、山の中を一人で、あるいは友人とともに歩き回ることは、まさにこの言葉の意味を想起させる。独りでいれば、政府や市場の圧力から解放され、じっくり考えることができる。全体主義に関する古典的小説『1984年』の中で、プライバシーが廃止され、政府の目がどこでもすべてを監視している世界を描いたジョージ・オーウェルは、自由とプライバシーがどのような関係にあるかを誰よりもよく理解していた、と言えるだろう。
プライバシーは、合衆国憲法の中で具体的に言及されてはいないが、建国の父たちがこの概念を知り、重んじていたことは明らかである。例えば、独立戦争の数年前、マサチューセッツ州が、住宅所有者に対し、前年の自宅での飲酒量を徴税官に報告することを義務づける物品税を法制化した時、人々は直ちに、家は自分の城であり、持ち主が自分の家の中で何をしたかなどに、政府が口出しすべきではないと抗議した。
「人は誰でも自分自身が居住する家屋内で安全を保障されるべきである。これは、英国憲法の根幹である。自宅は、通常、自分の城と呼ばれ、犯罪事件でない限り、保安官でさえ、本人の同意なしに立ち入ることは法律で許されていない。 」 |
プライバシーの概念は、ジョン・ロックならびにトマス・ジェファーソンそのほかの建国の父たちの政治哲学に見出すことができる。「フェデラリストペーパーズ」、通称「ザ・フェデラリスト」中の論文10号と51号では、プライバシーの概念が称賛されている。そして合衆国憲法に盛り込まれた自由とは、政府からの自由にほかならなかった。合衆国憲法修正第4条は、ほかにどんな意味があろうと、個人の自宅でのプライバシーを、政府による不当な侵入から明確に保護している。「プライバシー」という言葉を使用しなかったことについて言えば、明示することなく、むしろ暗黙のうちに保護されている権利は、プライバシーだけではなかった。人々が誤解しないようにするため、マディソン(James Madison)は、合衆国憲法修正第9条で、特定の権利が列挙されているからといって、そのほかの言及されていない権利を人々が放棄したという意味では全くない、と指摘している。
19世紀中頃まで、平均的な米国人を呼び止めてプライバシーの意味を尋ねれば、答えは、恐らく、住居への不可侵権に集中していたことだろう。南北戦争の後、米国は何百万人もの移民を都市部に受け入れ始め、生活環境はますます混雑し、過密になった。現代都市において空間は非常に貴重なものである。そしてプライバシーの概念も人々の生活環境が変わるにつれて、変化し始めた。技術の進歩もまた、プライバシーを脅かした。電話の出現により、人々は他人の家まで行かなくても、そこに入り込めるようになった。以前は、相手と会話をするためには、その相手の家まで行く必要があった、つまり、物理的にそこにいなければならなかった。いまでは電話をかければ、会話ができる時代になった。このほかにも、値の張らないカメラや安価な窓ガラスなどの技術的発明により、人々は、文字通り他人の家をのぞき見し、他人の私事をせんさくできるようになった。
19世紀後半、プライバシーに対する最大の脅威となったのは、日刊新聞の台頭だった。日刊新聞の編集者たちは、貧しい人々が金持ちや有名人の社交生活にまつわる記事を読みたがることに気がついた。金持ちや有名人の行いを公にするだけでなく、私生活上の弱みを暴露することにより、新しいメディアは、彼らの評判を台無しにすることもできた。従って、プライバシーに関する法律は当初、主として、名声が失墜される問題を中心に扱った。法律は、人の私生活に出しゃばる者や記者などが、他人の面目を失墜させる形で私生活を公表しないようにするために用いられた。
このように人の信望が脅かされるようになったことから、1890年、ボストンの若い弁護士、サミュエル・D・ウォーレン(Samuel D. Warren)とルイス・D・ブランダイス(Louis D. Brandeis)の二人は、この問題をテーマに論文を執筆した。二人は、旧来のコモンロー上のプライバシー侵害事項は、産業革命によって生じた現代的な要素を含む形に拡大すべきだ、と主張した。二人の提案は法律学者らによって検討されたものの、当座は、ほとんど何の変化も起きなかった。当時の米国人は、技術の進歩が自分たちの生活にもたらした変化に対応する途上にあり、現代生活がどれほど個人の生活を侵害するかについて、まだ認識していなかった。
しかし、1920年代の初頭、連邦最高裁判所は、プライバシーに関する憲法上の権利について考察するようになった。当時のプライバシーに関連する問題は、最近の関心事からはやや的が外れているように見えるものの、当時の司法判断が、憲法上のプライバシーに関する現在の定義の基礎となっている。例えば、ある事件で連邦最高裁判所は、適切な令状なしに私的文書を押収した連邦捜査官を処罰する判断を示した。ウィリアム・R ・デイ(William R. Day)判事は、もしこのような行為を警察が市民に対して行えるなら、「(自宅における)安全を保障される権利を宣言した合衆国憲法修正第4条の保護規定は、憲法から削除されたも同然である」と説明した。
合衆国憲法修正第4条に加えて、合衆国憲法修正第14条の「適正な法手続き(デュー・プロセス)条項(Due Process Clause)」もまた、プライバシーの法的根拠になっている。連邦最高裁判所の解釈では、「適正な過程条項」は、主として刑事訴訟に関わる手続き上の権利について言及しているだけでなく、個人の自由に関する「実体的」権利を含んでいる。これに関連し、ジェームズ・C・マクレイノルズ(James C. McReynolds)判事は、外国語教育を禁じる州法を違憲とした判決で、ここで言う自由とは「単に、身体的束縛からの自由だけではなく、個人が契約を結び、あらゆる普通の職業に就き、結婚し、家庭を築き、子供を育て、自分自身の良心に従って神を崇拝する権利、そして自由人が幸福を秩序ある形で追求するために不可欠なものと、コモンローで長い間認められてきた特権を享受する権利」を含むものだと述べている。マクレイノルズが列挙した問題は、基本的には、結婚、育児、良心という、私的な事柄である。
プライバシーの問題に最も大きな影響を及ぼしたのは、電話という新技術から生じた訴訟に関連して表明された意見だった。警察は、犯罪行為に関与していると疑った人物の会話を、盗聴という形で聴き取るようになっていた。この裁判で被告人たちは、盗聴は、合衆国憲法修正第4条が保障する令状なしに捜索されない権利を侵害する、と主張した。これに対して、連邦最高裁判所の多数意見は、盗聴は物理的に建物の外で行われたものであり、従って捜索は行われていない、と判断した。
連邦最高裁判所には、このような意見に反対する判事もいた。35年前、プライバシーに関する画期的な論文を共同執筆したルイス・D・ブランダイス(Louis D. Brandeis)判事は、反対意見を書いた。そして彼のプライバシーに関する一般的な見解、とりわけ盗聴に対する見解が、最終的には勝利することになる。
(Olmstead v. United States)での反対意見(1928年) 「電話が盗聴される時は常に、電話線の両端にいる者のプライバシーが侵害される。あらゆる話題に関する両者の会話は、それが適正で、内密で、法廷で責任を問われない性質のものであっても、盗み聞きされる……」 |
わが国の憲法の起草者たちは、幸福の追求のために望ましい条件を確保しようと努めた。彼らは、人間の精神的な本質、感情、そして知性の重要性を認識していた。彼らは、物質的な物の中には、人生の苦しみ、喜び、そして満足などのほんの一部しか見出せないことを知っていた。彼らは、米国人の持つ信条、思想、感情、感覚を擁護しようとした。彼らは、政府との関係では、誰からも干渉されない権利、最も包括的で、文明社会で最も尊敬されている権利を、国民に付与してくれた。この権利を守るためには、政府による個人のプライバシーに対する不当な侵害は、すべて、どのような手段が用いられようと、合衆国憲法修正第4条の違反と見なされなければならない。
ブランダイス判事は、合衆国憲法修正第4条の起草者たちが、「プライバシー」という言葉を具体的に用いなかったことも、また、盗聴について言及しなかったことも、重要ではないと考えた。それはそうだ、当時、電話がまだ発明されていなかったのに、起草者たちにそんなことができるわけがない。ブランダイスたち判事が追求したのは、言葉の「文字通りの」意味ではなく、憲法起草者たちが意図したこと、つまり、政府は人々に干渉すべきではない、ということである。侵害の「方法」は問題ではなく、侵害があるかないかという事実が重要だった。
結局、ブランダイス判事のこの考えが優勢となり、1960年代に連邦最高裁判所は、盗聴は憲法で保障されたプライバシーの権利の侵害にあたる、という判決を下した。ポッター・スチュワート(Potter Stewart)判事が述べたように、合衆国憲法修正第4条は「人々」を守るのであって、「場所」を守るのではない。人々が自分の家の中と同じようなプライバシーを期待することが合法的なら、そのプライバシーを守るために憲法による保護が必要となる。
さまざまな技術の変化により、1960年代半ば、プライバシーの問題で先駆的な役割を果たした訴訟が起きた。この訴訟は、現代のプライバシーに関するすべての議論の土台となっている。19世紀に「道徳十字軍(Moral Crusaders)」はコネチカット州で、避妊具の使用や避妊具に関する情報の普及を禁じる法律を成立させた。1960 年まで、たいていの人々はこの法律を無視していたが、法文上はそのまま残されていたので、避妊治療を行う医療クリニックは、社会の保守層がいつの日か、この法律を持ち出してくるのではないかと懸念していた。そして、心配していたことが、ついに起きた。避妊に反対するグループが、産児制限に関する情報とその用具を提供していた「家族計画連盟(Planned Parenthood)」運営の医療クリニックを起訴するよう、コネチカット州政府に働きかけたのである。
1965 年になるまで、連邦最高裁判所は、合衆国憲法修正第14条が規定している「適正な法手続き条項」を適用することには、ためらいがちだった。1930年代にルーズベルト政権が、連邦最高裁判所は意に染まない法律を、同条項を用いて違憲認定していると攻撃し、裁判の危機的な状況が生まれて以来、同条項の実質的な適用は、極めて限定されていたからである。さらに、コネチカット州政府が起訴したのが、個人の家屋ではなく、医療クリニックだったことからも、合衆国憲法修正第4条の適用は、適切とは言えなかった。それでもなお、連邦最高裁判所は、1965年の「グリズウォルド対コネチカット州事件」で、「家族計画のような内輪の私的な決定に、州政府が関与することを、人々は望んでいるだろうか」という疑問に取り組んだ。答えは、明らかに否だった。なぜなら、これは個人的なことであり、私的な決定なので、州が介入する筋合いの事柄ではないからだ。ダグラス判事は、コネチカット州法を憲法違反とし、クリニックが避妊についての情報を配布する権利を支持する判断を示す中で、「プライバシーは、憲法で直接的に言及されていないが、ブランダイス判事が一世代前にはっきりと表明した憲法上の保護を享受する」と述べた。ダグラス判事は、次のように述べている。「権利章典に盛り込まれた特定の保障事項には、それらの保障自体が作り出しているあいまいな領域があり、それが諸保障に生命と実体与えている……。さまざまな保障が、プライバシーの領域を生み出しているのである」これは独創的な見解だったが、ダグラス判事は、適正な法手続きという憲法上の重要な概念に、直接、言及したわけではないが、その後数年も経たないうちに、連邦最高裁判所はこのほかのいくつかの訴訟を扱う中で、適正な法手続き条項に含まれる自由の権利という概念を、プライバシーの憲法上の根拠とする見解を、実際に採用した。
グリズウォルド裁判で連邦最高裁判所は、産児制限についての情報と、情報を利用する決断は、私事であると裁定したのに続き、その数年後、女性が妊娠中絶を行なう権利をめぐる訴訟で、プライバシーの権利をさらに拡大する判断を示した。(1973年の)「ロウ対ウェード事件」(Roe v. Wade)の判決は、過去1世紀半以上にわたり、連邦最高裁判所が下した判決の中で最も大きな議論を呼ぶもので、いまでも中絶反対派は、連邦最高裁判所が憲法解釈を完全に誤ったと考えている。一方、中絶擁護派は、この訴訟で連邦最高裁判所が示した妊娠中絶支持の姿勢は、プライバシーの概念の論理的な拡大であり、合衆国憲法修正第14条に含まれる自由の権利のより具体的な特定だと主張している。その後の裁判で連邦最高裁判所は、妊娠中絶の問題を何度も扱うことになったが、基本的な見解の相違は依然として続いている。しかし多くの人々は、妊娠中絶を許すべきかどうかよく分からないという人も含めて、オコーナー連邦最高裁判事の次のような見解に賛成するだろう。
「ペンシルベニア州南東部計画出産協会対ケイシー事件」 (Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey) での判決理由(1992年) 「憲法は、政府が踏み込むことのできない個人の自由の領域があることを約束している。……自由の核心にあるのは、存在、意義、宇宙、そして人間の生命の神秘に関する自分自身の概念を、定義する権利である。これらの事柄に関する信条が、国家の強制により形づくられるなら、個人の特性を明確に定義することはできないだろう」 |
* * * * *
プライバシーに関する認識の変化と、再び技術の進歩がその大きな駆動力となっていることを如実に示す最近の出来事は、個人の意思の尊重が拡大し、医療を拒否する権利、つまり死を選択する権利も含まれるようになったことである。1990年に連邦最高裁判所は、かつて審理したこともないような事件に直面した。それは、死ぬ権利の訴えである。実際これは、国民にとっても比較的新しい争点であり、過去30年間に医療技術が驚くべき発達を遂げたことから生じた問題と言える。1960年代までは、重大な事故や病気で死ぬと思われた人々の命を、最近は救えるようになった。もっとも、こうした医療技術には、かなりの限界とマイナス効果がいくつかあった。新しい技術の進歩によって「生かされている」人々の生命の質は極めて劣り、医療装置に縛りつけられて生きるよりも、死ぬ方がましだと決意する人も出てきた。
ウィリアム・H・レンクィスト(William H. Rehnquist)連邦最高裁判所長官は、合衆国憲法修正第14条の適正な法手続き条項に盛り込まれている個人の自主性の保障規定に由来するとして、憲法は死ぬ権利を擁護しているとの判決を下した。これまで一連の諸判決は、「法的能力をもつ者は、憲法で保障されている自由権を保持しており、本人が望まない医学治療を拒否することができる」という原則を支持していると、レンクィスト長官は述べた。それから数年のうちに、死ぬ権利という新しい形のプライバシーは、50 州すべての法体系に、制定法としても、司法手続きとしても組み込まれた。そして連邦議会は、「患者の権利」法案を成立させ、連邦資金を受けている病院に対して、治療の拒否に関しては、患者の命令に従うことを義務づけた。
「ワシントン州対グラックスバーグ事件」(Washington v. Glucksberg)での 判決理由(1997年) 「適正な法手続き条項は、適正な法の手続き以上のものを保障し、またこの条項が保護する『自由』には、身体を拘束されないこと以上の自由が含まれている。これまでの長い一連の裁判で、われわれ連邦最高裁判所は、権利章典で保障されている特定の自由に加えて、同条項によって特別に保障されている『自由』には、結婚する権利、子供を育てる権利、自分の子供の教育としつけを監督する権利、夫婦間のプライバシー権、避妊具を使用する権利、肉体的尊厳の権利、および妊娠中絶の権利が含まれていることを判示してきた。また連邦最高裁判所は、望まない生命維持治療を拒否するという伝統的な権利を、適正な法手続き条項は保障しているという立場をとってきたし、またそれを強く示唆してきた」 |
この新しいタイプのプライバシーの範囲をめぐって、現在、活発な論争が行われている。末期患者が自らの意思で治療拒否を選択した場合、それを認めるべきだという意見にたいていの人々は賛成しているが、個人の意思の尊重という概念を拡大し、医師による自殺ほう助もそこに含めるべきだ、と主張する人々もいる。自分の命は自分自身のものであり、命についてどのような選択をしようとも、つまり、生を選ぼうと死を選ぼうと、それは個人の決めることであり、私事であるべきだ、というのが彼らの主張である。この考えは、まだ広く受け入れられてはおらず、現在、大きな政策上の争点となっている。ただし、どちらの立場の人でも、個人の意思は権利の一つであり、そこにはプライバシーの保護が含まれている、ということでは、意見が一致している。
「プライバシーの権利」(1890年) 「瞬時に映像を記録する写真と新聞企業が、私生活と家庭生活の神聖な領域に侵入してきている。数多くの機械装置によって『密屋でささやかれていたことが、家の屋上から大声で吹聴されるだろう』という予言が現実のものになりかけている」 |
ブランダイス判事は、盗聴事件の判決やそれ以前に書いた論文で、技術の進歩によって、政府は、国民の電話や会話を盗聴できるようになると不気味な警告を発したが、それのみならず、政府は、いずれ個人の家の中に入らなくとも、国民の手紙や文書を調べる力を持つようになるだろう、とさえ述べた。同判事は、政府がこうした技術を使用することを心配したが、現代においては、人々は政府だけではなく、そのほかの分野からも、プライバシーに対する脅威が忍び寄っていることに気づき始めている。これは、プライバシーの権利に関して、非常に興味ある疑問を提起している。
本書で論じた、ほとんどすべての権利の狙いは、最初から一貫して、個人を政府の力から守ることだった。言論の自由は、多くの人から支持されない意見の表明を政府が抑圧したり、そのような発言をする人を処罰したりしないことを保障する。宗教の自由は、政府が国教を作らないこと、あるいは、ほかの人とは異なる信仰を持つ人の自由な活動を制限しないことを保障する。新聞は政府による検閲から守られ、また被告人の権利は、刑事裁判において政府が適正な法手続きに従うことを求めている。憲法も権利章典も、政府以外の主体が個人の自由を侵害した場合にどうするかという問題については、取り組んでいない。議会はこれまで、民間の主体が有色人種の市民的自由を脅かした一定の事例においては対応してきた。だが、今やわれわれは、米国に限らず、広く「情報化時代」と呼ばれる時代におけるプライバシーの問題に直面している。
技術の進歩がまたも、今度はコンピューターとインターネットという形で、人々が自分自身に関する情報を管理する能力を、凌駕しかけている。ほんの一例だけ挙げると、米国では、健康保険に入っているほとんどの国民が、民間の保険会社を使っている。それらの保険会社が医師の医療サービスに対して支払い請求する際、医師たちは、病気の特徴、その進行状況、薬物や手術などの治療内容に関する詳細な書類を提出しなければならない。このような情報は、その後、コンピューターに入力され、時が経つにつれ、個人の健康に関する極めて詳細な記録が蓄積されることになる。
一部の人々が、こうした情報を入手する必要があることに、疑いの余地はない。保険会社は、報告に不正がなく、医療行為が請求通り実施されたことを確認する必要がある。新しい医師が治療を引き継ぐ場合には、患者の過去の病歴を見る必要があるかもしれない。しかし、そのほかの誰に一体、個人の医療記録の閲覧を許すべきなのか。将来の雇用主に認めるべきだろうか。潜在的な顧客に関する一般情報を求める保険会社はどうなのか。病気の治療法を発見するためにデータベースを構築しようとする医学研究者はどうか。コンピューターのデータベースがいったん構築されると、それに関する完全な防衛手段を講じることは、ほとんど不可能である。さらに、クレジット会社などのように、得意先や顧客についての情報を収集する企業の多くは、集めた情報は自分たちのものだと考え、本人の許可もなしに、自由に売ることも、あちこちにばらまくことも出来る、と考えている。個人の病歴や金銭上の記録は、誰のものなのか。 それは本人なのか、それとも仕事相手の会社なのだろうか。
われわれは、今や、ヒトゲノムの解読やDNA の分類などの技術的進歩のお蔭で、個人に関するさらに多くの情報を入手できる時代に入りつつある。DNA 検査が、犯罪捜査の大きな進歩に貢献したことに疑いの余地はない。犯人の有罪を立証する上で手助けになるだけではなく、間違って告訴され、恐らくは犯していないことで有罪とされた人々の、無実を証明することにも役立っているからである。
しかし、ヒトのDNAには、その人が特定の病気にかかりやすいかどうか、また特定の社会的行動を起こしやすいかどうかまで識別する遺伝子標識(マーカー)が含まれていると考える研究者もいる。このような情報に誰がアクセスすべきなのか。統計上の確実性から程遠い状態であっても、特定の遺伝子配列がもたらすとされる傾向に基づいて決定を行うべきだろうか。個人の身体に関する情報を、誰が所有するのか。これもまたプライバシーの一形態ではないのか。しかし、このプライバシーの領域への主な侵入者は、目下のところ政府ではなく、生物学的研究を専門とする民間企業なのである。
パソコンとインターネットへの接続は、電話やテレビと同じようなスピードで急速に普及してきている。インターネットは、どんな人でも、財産の多少にかかわらず、ほかの人々に意見を聞いてもらえるという、今までに考案された通信手段の中で最大の公開討論の場として称賛されている。しかし、パソコンを持っている人なら誰でも証言するように、絶えず迷惑メールを送りつけられ、サーバーのホームページ上で大量の広告攻めに遭う。ハッカーは、個人だけでなく、企業のコンピューターにも侵入して、ウイルスを撒き散らし、個人レベルでも企業レベルでも、大きな損害をもたらす。しかしそれは、単に金銭的損害の問題だけではない。個人のコンピューターは、私的なメッセージを作成し、特定の受け手に送る個人的な機器のはずではないのか。望むと望まないとにかかわりなく、どのような情報や、メッセージ、勧誘を画面に送り込むかを決める権利は、パソコン所有者は別として、一体誰が持っているのだろうか。
今日、米国人を初めとする工業先進国の人々が論議するプライバシーの権利とは、概念的には何世紀も前からある古い権利であると同時に、それを脅かす技術とほとんど同じくらいに急速に進化している権利である。ジョージ・オーウェルが全知全能の政府につけた名前を借りれば、人々は「ビッグ・ブラザー」が自分たちについて余りにも多くの情報を集め、それを自分たちに不利益をもたらすために使わないかと、懸念している。しかし、人々は、政府に対して心配するのと同じくらいに、企業、医療機関、それに犯罪者たちが、インターネット上で集めた情報を用いて、自分たちのプライバシーを脅かすこともまた、心配している。
連邦議会は、「電子工学通信プライバシー法」を含む多くの法令を制定して情報上のプライバシーを守ろうと試みた。しかし問題は、入手できる情報の量が幾何級数的に増加していることであり、その速度がネット上のアクセスを管理し、規制する手段が追いつかないほど速いということである。
今日では、実に多くの入手可能な情報が存在しているため、少々賢い人なら、インターネットにアクセスし、狙った人物の社会保障番号さえ入手すれば、交通違反歴や、信用状況、買い物の傾向など、その個人に関するあらゆる種類の情報を手に入れることが出来る。そして十分な情報が集まれば、その人物の社会的な特徴を「盗む」ことさえできる。礼儀と教養を兼ね備えた人々は、依然として構わずにほっておいてもらう権利を大切にしている。しかし、新しい情報化時代に、この権利をどのようにして守っていくかについては、まだ答えが出ていない。
参考文献:
- Ellen Alderman and Carolyn Kennedy, The Right to Privacy (New York: Knopf, 1995)
- David H. Flaherty, Protecting Privacy in Surveillance Societies (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1989)
- Richard F. Hixson, Privacy in a Public Society (New York: Oxford University Press, 1987)
- Philippa Strum, Privacy: The Debate in the United States since 1945 (Fort Worth: Harcourt Brace, 1998)
- Alan F. Westin, Privacy and Freedom (New York: Athenaeum, 1968)
*上記の日本語文書は参考のための仮翻訳で、正文は英文です。
Privacy
(The following article is taken from the U.S. Department of State publication, Rights of the People: Individual Freedom and the Bill of Rights.)
The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated...
– Fourth Amendment to the U.S. Constitution
The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by the people.
– Ninth Amendment to the U.S. Constitution
No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law….
– Fourteenth Amendment to the U.S. Constitution
Rights, while often perceived as absolute, are never static or unchanging. Freedom of speech means that people for the most part have the right to say what they think, but the means by which they say it, the opportunities they may have to express themselves, do change over time, and as a result the nature of the right also changes. Technological developments, as well as social and cultural evolution, may affect how we think of particular rights, and these changes may also determine how those rights are defined. No better case exists than the right to privacy, a right that is not mentioned in the Constitution, and yet a right that the courts and the people have invested with constitutional status.
* * * * *
Sir William Pitt, Earl of Chatham, on the right of an Englishman to be secure in his home (1763)
The poorest man may in his cottage bid defiance to all the forces of the Crown. It may be frail – its roof may shake – the wind may blow through it – the storm may enter – the rain may enter – but the King of England cannot enter; all his forces dare not cross the threshold of that ruined tenement.
Pitt's famous comment sums up what until recently many people saw as the heart of privacy, the right to be let alone within one's home, safe from the powers of the government. In America, the Fourth Amendment to the U.S. Constitution establishes this notion that the people have a right to be safe in their own homes, and it is a notion reinforced by the Third Amendment's command that soldiers shall not be quartered in private residences. The notion of privacy as security from prying, from having one's personal behavior or business displayed in public for all to see and comment on, is the invention of the industrial age. In ancient times, and indeed up to the 18th century, privacy in the sense of solitude, isolation, of space for one's self, was unknown except for the rich or the nobility. Most people lived in small, bare housing, the entire family often sleeping together in one room. Indeed, as a legal concept, "privacy" originally referred to a form of defamation, the appropriation of one's name or picture without that individual's permission.
But as Western society grew wealthier, as a middle class grew with the means to afford larger houses where members of a family could have separate spaces of their own, the meaning of privacy also changed. Now it became a matter of individuality, of people assuming that what they did beyond the arena of public life was no one's business except their own. Neither the government, the media, nor in fact anyone else had any business knowing about their private life.
Privacy, in its modern meaning, is very much related to individuality, and is a right of the person, not of the group or the society. "Without privacy," the political scientist Rhoda Howard has written, "one cannot develop a sense of the human individual as an intrinsically valuable being, abstracted from his or her social role." The opposite is also true: Without a sense of individuality, there can be no perception of a need for privacy.
Privacy, like most rights, relates directly to democracy. Human beings have a need both for discourse and interaction with others, as well as time and space for themselves. Privacy is not isolation or exile, but rather a self-chosen desire to be alone or with a few other people of one's choice. Solitary confinement in prison, for example, is not privacy, but wandering alone or with a friend in the mountains conjures up what we mean by the word. In solitude we can think through ideas, free from pressures of the government or the market. George Orwell understood perfectly the relationship of freedom and privacy when in his classic novel of totalitarianism, 1984, he abolished privacy and substituted the all-seeing omni-present eye of the government.
Although privacy is not specifically mentioned in the Constitution, it is evident that the Founding Generation knew and valued the concept. A few years before the Revolution, for example, Massachusetts enacted an excise tax that required homeowners to tell the tax collectors how much rum had been drunk in their houses the prior year. The people immediately protested, on the grounds that a man's home was his castle, and what he did there was none of the business of the government.
Pamphlet Protesting excise tax in Massachusetts (1754)
It is essential to the English Constitution, that a Man should be safe in his own House; his House is commonly called his Castle, which the Law will not permit even a sheriff to enter into, but by his own Consent, unless in a criminal case.
The idea of privacy could be found in the political philosophy of John Locke, as well as that of Thomas Jefferson and others of the Founding Fathers. Federalist Papers 10 and 51 laud the idea of privacy, and the liberty embedded in the Constitution was that of liberty from the government. Whatever else it may mean, the Fourth Amendment clearly protects the privacy of the individual in his or her home against unwarranted governmental intrusion. As for the failure to mention privacy by name, it was not the only right that is implicitly rather than explicitly protected, and to make sure that people did not misunderstand, Madison in the Ninth Amendment pointed out that the listing of certain rights did not in any way mean that the people had given up other rights not mentioned.
* * * * *
Up until the middle of the 19th century if one had stopped the average American and asked what privacy meant, the answer surely would have centered on the inviolability of the home. Starting after the Civil War, the country absorbed millions of immigrants into its cities, creating more crowded and congested living conditions. Space in a modern city is at a premium, and the notion of privacy began to change as people's living conditions changed. Technology also threatened privacy, as the telephone made it possible for people to enter other people's homes without going there. One used to have to go to someone's home, to physically be there, in order to converse; now one merely had to call. Other technological inventions such as inexpensive cameras and cheap window glass made it possible for people to literally look into others' homes and pry into their affairs.
The greatest threat to privacy in the late 19th century came from the rise of daily newspapers, whose editors discovered that the poorer classes loved to read about the social lives of the rich and famous. Not only could their doings now be made public, but in exposing private foibles, the new mass media could also ruin reputations. Thus, at first, the law of privacy dealt primarily with reputation, and the law was used to keep busybodies, reporters, and others from publicizing private aspects of a person's life in such a way as to humiliate them.
It was this threat to reputation that led two young Boston lawyers, Samuel D. Warren and Louis D. Brandeis, to write an article in 1890 urging that the old common law proscriptions on invasion of privacy be expanded to include the modern forms generated by the Industrial Revolution. Although legal scholars and others discussed the proposal, little happened at the time. Americans were still getting used to the differences that technology had made in their lives, and had not yet recognized just how intrusive modern life could be.
Beginning in the 1920s, however, the Supreme Court began to conceive of a constitutional right of privacy, and if the issues involved seem a little removed from current concerns, these decisions nonetheless lay the foundation for the current constitutional definition. In one case, the Court chastised federal agents for seizing private papers without an appropriate warrant. If police could act this way against a citizen, Justice William R. Day explained, then "the protection of the Fourth Amendment declaring his right to be secure [in his home] might as well be stricken from the Constitution."
In addition to the Fourth Amendment, the Fourteenth Amendment's Due Process Clause also provides a legal basis for privacy. According to the interpretation given by the Court, "due process" not only refers to the procedural rights associated primarily with criminal cases, but also includes "substantive" rights relating to personal liberty. Thus in a case striking down a state law prohibiting the teaching of foreign languages, Justice James C. McReynolds held that this liberty included "not merely freedom from bodily restraint but also the right of the individual to contract, to engage in any of the common occupations, to marry, to establish a home and bring up children, to worship God according to the dictates of his own conscience, and generally to enjoy those privileges long recognized at common law as essential to the orderly pursuit of happiness by free men." The issues McReynolds listed are basically private matters – marriage, child-rearing, conscience.
The most far-reaching statement came in a case engendered by the new technology of the telephone. Police had taken to listening in on – wire-tapping – conversations of people they suspected of criminal activity. When the accused persons claimed that the wiretaps had violated their Fourth Amendment right to be free of searches without warrants, the majority of the Court said that the taps had physically been outside of the building, and therefore no search had taken place.
Some members of the Court disagreed, and although Justice Louis D. Brandeis – the same man who 35 years earlier had co-authored that seminal article on privacy – wrote in dissent, eventually his views on privacy in general, and wire-tapping in particular, would prevail.
Justice Louis D. Brandeis, dissenting in Olmstead v. United States (1928)
Whenever a telephone line is tapped, the privacy of the persons at both ends of the line is invaded, and all conversations between them on any subject, and although proper, confidential, and privileged, may be overheard. . . .
The makers of our Constitution undertook to secure conditions favorable to the pursuit of happiness. They recognized the significance of man's spiritual nature, of his feelings, and of his intellect. They knew that only a part of the pain, pleasure, and satisfactions of life are to be found in material things. They sought to protect Americans in their beliefs, their thoughts, their emotions and their sensations. They conferred, as against the Government, the right to be let alone – the most comprehensive of rights and the one most valued by civilized men. To protect that right, every unjustifiable intrusion by the Government upon the privacy of the individual, whatever the means employed, must be deemed a violation of the Fourth Amendment.
Brandeis considered it irrelevant that the Framers of the Fourth Amendment had not used the word "privacy" specifically, nor had they mentioned wire-tapping. How could they, since telephones had not been invented! What he and others have sought is not the literal meaning of the words, but what the Framers intended – namely, that government should leave people alone. The manner of intrusion did not matter; the fact of it did.
Eventually Brandeis's view prevailed, and, in the 1960s, the Court ruled that wire-tapping did violate a constitutionally protected right of privacy. As Justice Potter Stewart explained, the Fourth Amendment protects people not places. If people have legitimate expectations of privacy, such as in their home, then they may invoke the protection of the Constitution to ensure that privacy.
Changes in a different kind of technology triggered the leading case in privacy in the mid-1960s, a case that is at the base of all modern privacy discussion. In the 19th century moral crusaders had secured passage of laws in the state of Connecticut banning either the use of birth control devices or the dissemination of information about them. Although by 1960 most people ignored these laws, they remained on the books, and family-planning clinics worried that social conservatives might someday invoke their use. That is exactly what happened when one anti-contraception group induced the government of Connecticut to prosecute a clinic run by Planned Parenthood that dispensed information about birth control, as well as the devices themselves.
Because the use of substantive due process had been limited following the court crisis of the 1930s, in which the Roosevelt administration had attacked the Court for using due process as a means of striking down legislation it did not like, the Supreme Court as late as 1965 hesitated to use the Fourteenth Amendment's Due Process Clause. Moreover, the Fourth Amendment was not appropriate here, because the object of the government's prosecution was not a private home but a medical clinic. Nonetheless, in Griswold v. Connecticut (1965) the Court asked the question – Did the people want the state to be involved with intimate private decisions about family planning? The answer was clearly no, because this was a personal matter, a private decision, in which that the state had no business intruding. Justice Douglas, in striking down the state law and upholding the right of the clinic to dispense birth control information, declared that privacy, even though not mentioned directly, nonetheless enjoyed the constitutional protection that Justice Brandeis a generation earlier had proclaimed. "Specific guarantees in the Bill of Rights," he declared, "have penumbras, formed by emanations from those guarantees that help give them life and substance. . . . Various guarantees create zones of privacy." While creative, Douglas's opinion did not directly address the important Constitutional concept of due process. However, within a few years and via several other cases, the Court in fact adopted the notion of liberty interests in the Due Process Clause as the constitutional basis for privacy.
Following the decision in Griswold that information about birth control, and the decision whether to use it, constituted a private matter, the Court in a case involving a woman's right to have an abortion, a few years later extended the right of privacy. Roe v. Wade (1973) has been the Court's most controversial decision in over a century and a half, and opponents of abortion believe that the Court totally misconstrued the Constitution; defenders of choice argue that the court's pro-abortion stance in this case is a logical extension of the concept of privacy as well as the more specific liberty interest contained in the Fourteenth Amendment. In subsequent cases, the Court and its members have returned to this issue and the basic division still exists, but many people, even those who are unsure of whether abortions should be permitted, would agree with Justice O'Connor's views.
Justice Sandra Day O'Connor, in Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey (1992)
It is a promise of the Constitution that there is a realm of personal liberty which the government may not enter. . . . At the heart of liberty is the right to define one's own concept of existence, of meaning, of the universe, and of the mystery of human life. Beliefs about these matters could not define the attributes of personhood were they formed under compulsion of the State.
* * * * *
The latest manifestation of changes in how privacy is perceived, and how technology is again the driving force, is the extension of personal autonomy to include a person's right to refuse medical treatment and, in effect, choose to die. In 1990, the Supreme Court confronted an issue it had never heard before, a claim for a right to die. In fact, it was a relatively new issue for the nation as a whole, arising from the amazing explosion of medical technology in the previous three decades. People who up until the 1960s would have been expected to die from severe accidents or illnesses could now be helped, although this technology had significant limits as well as some negative effects. Some people kept "alive" through this new technology may have very little quality of life, and may decide that they would rather be dead than lead a life tied to medical machinery.
Chief Justice William H. Rehnquist found that the Constitution protected a right to die, deriving from the guarantees of personal autonomy embedded in the Fourteenth Amendment's Due Process Clause. A long line of decisions, he held, support the principle "that a competent person has a constitutionally protected liberty interest in refusing unwanted medical treatment." Within a few years, this new form of privacy, the right-to-die, had become statutorily and judicially embedded in the laws of all 50 states, and Congress had passed a patients' rights bill that required hospitals receiving federal funds to obey patient directives in regard to refusal of treatment.
Chief Justice William H. Rehnquist, in Washington v. Glucksberg (1997)
The Due Process Clause guarantees more than fair process, and the "liberty" it protects includes more than the absence of physical restraint. In a long line of cases, we have held that, in addition to the specific freedoms protected by the Bill of Rights, the "liberty" specially protected by the Due Process Clause includes the right to marry, to have children, to direct the education and upbringing of one's children, to marital privacy, to use contraception, to bodily integrity, and to abortion. We have also assumed, and strongly suggested, that the Due Process Clause protects the traditional right to refuse unwanted lifesaving medical treatment.
There is a major debate going on now as to the extent of this new version of privacy. While most people agree that terminally ill people ought to be allowed to decline treatment if they so choose, some groups argue that the notion of personal autonomy ought to be expanded to include physician-assisted suicide. One's life, they argue, is one's own, and what people choose to do with that life, whether they choose to live or die, ought to be a matter of their own decision, a private matter. This view has not gained widespread acceptance, and it is a major policy issue at the moment; yet both sides still agree that personal autonomy as a form of protected privacy is a right.
* * * * *
Samuel D. Warren and Louis D. Brandeis, "The Right to Privacy" (1890)
Instantaneous photographs and newspaper enterprise have invaded the sacred precincts of private and domestic life; and numerous mechanical devices threaten to make good the prediction that "what is whispered in the closets shall be proclaimed from the house-tops."
In his opinion in the wire-tapping case, as well as in the earlier article he had written, Justice Brandeis sounded a dire warning that technology would give the government the power not only to eavesdrop on people's telephonic or even spoken conversations, but someday to examine their papers and documents without ever entering their home. While Brandeis worried about the government using this technology, in modern times people have begun to see such threats to privacy as coming not just from the government, but from other sources as well. This raises a very interesting question about the right of privacy.
In nearly all of the rights discussed in this book, the original and continuing aim has been to protect the individual against the government. Freedom of speech ensures that the government will not silence unpopular expressions or punish those who utter them. Freedom of religion guarantees that the government will not establish a church or somehow restrict the free exercise of those whose faith is different from that of others. The press is protected against government censorship, while the rights of the accused require the government to adhere to fair procedures in a criminal trial. Neither the Constitution nor the Bill of Rights addresses the question of what happens when non-governmental actors infringe upon individual liberties. Congress has acted in certain instances when private actors have threatened the civil liberties of people of color, but we now, and not only in the United States, face the issue of privacy in what many are calling the "Information Age."
Once again technology, this time in the form of computers and the Internet, threatens to overwhelm the ability of people to control information about themselves. To take but one example, in the United States most people who carry health insurance do so with a private company. In order for these companies to reimburse physician services, the doctors have to file forms detailing the nature of the illness, its progress, and the steps taken to counter it, such as medication or surgery. This information is then entered on computers, and as the years go by a very detailed record of a person's health accumulates.
There is no question that some people need to have access to this information. The insurance company must make certain there is no fraud, and that services billed have in fact been delivered. If a new doctor takes over the case, he may need to review the patient's past history. But who else, if anyone, should have access to a person's medical records? Should prospective employers? Should insurance companies seeking generalized information about prospective clients? Should medical researchers seeking to build a database in an effort to discover a cure for a disease? Once a computer database is created, it is almost impossible to maintain total security over it.
Moreover, many firms that gather information about their business clients and customers – such as credit-card companies – believe the information belongs to them and that they are free to sell it, or otherwise distribute it, without the permission of the individual. To whom does one's medical history or financial records belong – the individual, or companies with whom he or she does business?
We are now entering an era of even greater information becoming available about an individual thanks to such advances as the mapping of the human genome and DNA classification. There is no doubt that DNA detection has proven a major advance in criminal investigation, helping not only to prove the guilt of some perpetrators but also the innocence of people wrongly accused and perhaps even convicted of crimes they did not commit.
But some researchers believe that a person's DNA contains markers that show whether that person is prone to certain diseases and perhaps even to some kinds of social behavior. Who should have access to this information? Should decisions be based on the alleged proclivity of a certain gene sequence, a situation that is far from a statistical certainty? Who owns the information about one's body? Is this also not a form of privacy? The main invader of this zone of privacy, however, at present is not the government, but private companies specializing in biological research.
The personal computer and access to the Internet are rapidly becoming as common as the telephone or television. The Internet has been hailed as the greatest public forum ever devised, in which any person, no matter what his wealth, can be heard by others. But as anyone who owns a computer can testify, one is constantly bombarded by unwanted messages on one's e-mail, and by a barrage of advertisements on server home pages. Hackers can invade personal as well as industrial computers, and the unleashing of computer viruses can wreak havoc at both the individual and corporate level. But it is not just a question of monetary damages. Should not one be able to view one's computer as a personal instrument, one in which private messages may be composed and sent to specific recipients? Who has the right, besides the owner, of determining what information, what messages, what solicitations, will land on one's screen, wanted or not?
Today, when Americans and others in the industrialized world talk about a right to privacy, they are talking about a right that while it may be centuries old in concept, is evolving almost as rapidly as the technology that threatens it. People are worried that "Big Brother," to use Orwell's name for an omniscient government, will know too much about them, and use that information to their detriment. But as much as they are worried about government, they are also worried about threats to their privacy from business, from the medical establishment, and from criminals who may use information collected over the Internet to harm their interests.
Congress has attempted to protect informational privacy through a number of statutes, including the Electronics Communications Privacy Act, but the problem is that the amount of information available is growing at an exponential rate, far faster than the means to control and regulate access. There is so much information available today that a clever person, armed only with access to the Internet and a person's Social Security number, can secure all sorts of information about that person, including traffic violations, credit report, purchasing habits, and more and, with enough information, even "steal" that person's public identity. The right to be let alone is still valued highly by civilized people; how they will protect that right in the new Information Age remains to be seen.
For further reading:
Ellen Alderman and Carolyn Kennedy, The Right to Privacy (New York: Knopf, 1995).
David H. Flaherty, Protecting Privacy in Surveillance Societies (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1989).
Richard F. Hixson, Privacy in a Public Society (New York: Oxford University Press, 1987).
Philippa Strum, Privacy: The Debate in the United States since 1945 (Fort Worth: Harcourt Brace, 1998).
Alan F. Westin, Privacy and Freedom (New York: Athenaeum, 1968).