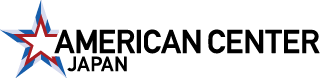国務省出版物
権利章典 – 出版の自由
議会は、・・・言論、あるいは出版の自由を制約する・・・ 法律を制定してはならない。
出版の自由は、国民から大切にされている権利だが、それが個人と制度の双方に関わっているという点で、その他の国民の自由とは異なる。出版の自由は、一市民が自分の考えを発表する権利だけでなく、出版・放送メディアが、政治的な意見を発表したり、ニュースを取材し報道したりする権利にも適用される。それゆえ、出版の自由は民主主義社会の基盤の1つであり、20世紀の米国のコラムニスト、ウォルター・リップマンが述べているように、「出版の自由は特権ではなく、偉大な社会における必要不可欠な要件である」。確かに、社会がますます複雑になるにつれ、人々は、現在の世界情勢や、意見・政治的思想に遅れをとらないように、ますます新聞、ラジオ、テレビに頼るようになる。出版の自由がどれほど重要であるかは、反民主的な勢力が国を奪取するとき、しばしば最初に起こす行動が報道統制であることからもわかる。
「出版の自由の必要性について」(1787年) 「われわれの政府の基盤が、国民の意見である以上、第1の目的は、国民の権利を守ることである。新聞のない政府と、政府のない新聞のどちらをとるか、もしその判断を任されたなら、私は,瞬時のためらいもなく、後者を選ぶだろう」 |
言論の自由と出版の自由の起源は、ほぼ似通っている。なぜなら、政府に対する批判は、文書にせよ口頭にせよ、英国法では処罰の対象となっていたからだ。活字にされたものが真実であるかどうかは、まったく関係なかった。政府は政府に対する批判そのものを、害悪と見なしていた。なぜなら、そうした批判は、公職者の高潔さと信頼性に、疑問を投げかけることになるからだ。真に自由な出版への前進、すなわち、政府の報復を恐れることなく、国民が自分の意見を発表できる自由への歩みは、滞りがちだった。18世紀半ばに、偉大な英国の法律評論家、ウィリアム・ブラックストーン卿は、出版の自由は、自由国家の本質にとって不可欠ではあるが、その制限は可能であり、また制限すべきだ、と明言した。
「英国の法律に関する解説」(1765年) 「英国法においては、冒とく的、非道徳的、反逆的、分離主義的、扇動的ないしは中傷的な誹謗は処罰されるが、このような法体系の下で、適切と見なされるような出版の自由は、決して妨げられたり、侵害されたりすることはない。出版の自由は、自由な国家の本質にとって、間違いなく不可欠である。しかしそれは、出版以前にはどのような規制もしてはならない、という意味であり、ひとたび出版された後も、刑事上の訴追を免れるという意味ではない。すべての自由人は、公の場で、気分が赴くままに感情を表出する確たる権利を有する。それを禁ずることは、出版の自由を壊すことになる。しかし、不適切で、迷惑で、あるいは違法なものを出版した場合は、自らの無謀が招いた当然の結果を受け入れなければならない」 |
上述の「冒とく的、非道徳的、反逆的、分離主義的、扇動的ないしは中傷的な誹謗」とは、どのようなことを意味するのだろうか。本当のところを言えば、政府がこう定義する、と言えば、そうなるのである。要するに、たとえ政府の政策や指導者に対する穏健な批判文書であっても、投獄やそれ以上の重い処罰を受けることがあり得るということである。そうした主観的な判断においては、真実であることは何の意味も持たなかったのである。
米国に植民地を築いた人々は、大西洋を越えて、英国のコモンローを新大陸に持ち込んだ。植民地の官吏は、彼らの本国の上司たちと同様に、出版の自由に寛容ではなかった。1735年、ニューヨークのウィリアム・コスビー総督は、新聞発行人ジョン・ピーター・ゼンガーを扇動的誹謗罪で起訴した。コスビー総督は、ある重要な裁判で、自分の利益に反する判決を下した裁判官を解任したが、ゼンガーがこれを批判したことが扇動的誹謗罪に当たると見なした。ブラックストーン卿が明確に述べた前述の伝統的原則に照らせば、ゼンガーにはその批判を表明する権利はあったが、それがもたらす結果に直面しなければならなかった。しかし、ゼンガーの弁護士、アンドリュー・ハミルトンは、ゼンガーが出版した内容が真実であることを理由に、無罪放免にするよう陪審団を説得した。英国法であれ米国法であれ、真実であることが誹謗罪に対する完全な弁護手段として受け入れられるまでには、その後何年も要したが、この裁判は、政治的に重要な先例を樹立したと言える。米国の陪審員たちが、真実のみならず、意見を発表した者に対して、有罪とすることに消極的だったため、植民地の総督たちにとって、自分たちを批判する者に扇動的誹謗罪を適用して訴追することは次第に困難になった。米国の独立革命の時期までに、法律の条文があったにもかかわらず、出版者は英国国王とその植民地総督を、容赦なく攻撃した。
憲法修正第1条の出版の自由条項の草案者たちが、ゼンガー裁判の教訓をそこに組み込もうとしたかどうかについては、議論の余地がある。というのも、独立した米国諸州のほとんどすべての州が、出版に関する規定も含めて、英国のコモンローを採択したからだ。1798年、米国がフランスと準戦争状態にある中で、扇動防止法が議会を通過し、米国大統領、および米国政府を誹謗したという理由の訴追に対して、真実を盾として弁護することが認められた。しかしこの法律は、ジェファソン率いる共和党への対抗策として、利己的な党利党略のために施行されたものだった。その結果、連邦党を支持していた判事たちは、英国の判事と同様に、真実を盾に弁護することを容認した条項を無視して、政府批判の発言を誹謗として処罰した。その一例が、バーモント州の新聞発行人、マシュー・ライアンズが訴追された事件である。ライアンズは、当時のジョン・アダムズ大統領を、「ばかげた虚飾への際限のない欲望、卑しいへつらい、わがままな強欲」とこきおろした。この言論を理由にライアンズは、1,000ドルの罰金刑を課せられ、その罰金の原資を稼ぐため、4ヵ月間も刑務所で惨めな苦役を強いられることになった。
扇動防止法は、1801年に失効した。連邦政府は、南北戦争中に行われた少しばかりの制限を除けば、19世紀を通じて、憲法に規定された出版の自由条項の侵害にあたることは一切行わなかった。誹謗罪は徐々に、刑法より、むしろ民法上の問題となり、もっぱら著名人が、自分の評判を守るため訴訟を起こす目的で使われるようになった。第1次世界大戦中に、議会は、別の扇動防止法を通過させた。言論の自由の章で述べたように、その法律を根拠に起こされた裁判は、主として言論の自由の問題として扱われ、それが、「明白かつ現在の危険」という基準の誕生につながった。出版の自由については、その後、それほど意義のある展開はなかったが、1930年代初頭になりようやく、言論の事前の規制という論議が再び高まってきた。真の自由な報道を目指す新聞は、最高裁に強力な味方を見出した。最高裁は、合衆国憲法修正第1条に含まれる「・・・あるいは出版の自由」という単純な言葉を、出版の自由の強力な盾に変えたのである。
現在につながる出版の自由条項関連の判決は、1931年に行われた「ニア対ミネソタ州事件」という画期的な裁判から始まった。この裁判は一見、ブラックストーン卿による事前の規制の禁止の焼き直しに過ぎないように見えるが、実際には、同卿の見解を基盤として、その上に強力で独立した報道を築く最初の一歩だったのである。
ミネソタ州は、「悪意があり、恥ずべき、あるいは名誉を傷つける」出版物を公共の害悪として規制する、ほかの州と似たような州法を制定していた。しかし、ミネソタ州の州法は、サタデイ・プレスという特定の新聞を発行禁止にする目的で制定されたものだった。同紙は、黒人やその他の人種グループを攻撃する人種差別主義的な記事だけでなく、地元の政治家や財界大物の腐敗を暴くシリーズも掲載していた。ミネソタ州裁判所は、待ってましたとばかりに同紙を発禁処分にしたが、同紙は最高裁に上告した。最高裁のチャールズ・エバンズ・ヒューズ長官は、(それまで、連邦議会にのみ適用されていた)憲法修正第1条の出版の自由条項を州政府にも適用し、戦時の緊急事態を除き、どのような政府も、新聞社に対して憲法で保障された発表の自由の権利を制約することはできない、と言い渡した。このことは、新聞社が、ほかの理由でも罰せられたり、名誉棄損で市民から訴えられたりすることもない、という意味ではない。しかしこの裁判は、それから30年以上も後になって、近代的な出版の自由の支柱を確立した2つの重要な成果に至る基礎を築いたのである。
その最初の出来事は、1960年代の公民権運動から生まれた。当時、大部分の州の法律は、事実上、記事の事前規制をまったく義務づけていなかったが、活字となった記事が悪意に満ちていたり、事実誤認があったりした場合は、名誉棄損で民事訴訟を起こすことができた。アラバマ州モンゴメリでは、公民権活動家と警察が衝突する事件が続いた。ある公民権運動グループと一部の活動家たちは、ニューヨーク・タイムズ紙に、「高まる声に耳を傾けよ」という見出しの全面意見広告を掲載した。この広告は、公民権活動家が直面している困難な状況を詳しく報じ、彼らの大義を支援するための資金を募るものだった。事件の一方の当事者、アラバマ州モンゴメリのI・ B・サリバン警察本部長は、この広告記事の中では名指しされていなかったが、広告記事の中に自分の公務遂行上の名誉を傷つける事実の誤りがあったとして、ニューヨーク・タイムズ紙を訴えた。地元の陪審団は、サリバン本部長の訴えを認め、同紙に対し、サリバン本部長に50万ドルの賠償金を支払うよう命じた。
サリバン本部長が同紙を訴えたのは、記事の誤りが多かった(例えば、マーチン・ルーサー・キング・ジュニア牧師の投獄回数は7回と記述されていたが、実際は4回だった)からではなく、南部の人々が、公民権闘争の中で、メディアを自分たちの敵対者だと見なしていたからである。デモ参加者たちが殴打され、逮捕されるたびに、メディアは、その記事を全米のほかの地域だけでなく、世界中に報じた。ニューヨーク・タイムズ紙は、米国内の有力紙というだけではなく、全米で最も部数が多く成功している新聞の1つだった。もし、ニューヨーク・タイムズ紙が、厳しい罰金(50万ドルと言えば、1964年当時は大金だった)を科せられるとすれば、それよりも弱小で、経営基盤の弱い新聞社は、公民権運動について報じることに、二の足を踏まざるを得ないだろう。言い換えれば、そのような判決が確定すれば、憲法修正第1条が保障した出版の自由に対して、「ぞっとする」ような、ひどい影響をもたらすことになるだろう。
最高裁は、この地裁の決定を棄却しただけではなく、判決の中で、英国法から継承した記事の事前規制の禁止という領域を大きく踏み越えた。最高裁は、公職者と彼らの任務の遂行に関する限り、一切の記事を免責にしたのである。その例外は、新聞社が記事の内容に真実でないことがあることを知りながら、その公職者の評判を傷つけるという悪意を抱いて報道した場合だけに限定された。この判決は、新聞に対して、何でも活字にすることを容認しているわけではない。また、誹謗を理由に、市民個人が新聞を訴える権利を依然として認めている。しかしながらこの判決は、出版の自由に関する重要な問題に答えた。それは新聞が、政府と公職者について、十分かつ自由に報道することができるということである。報道の中には、ついうっかり犯したという軽率な誤りが時折あるが、これは問題ではない。最高裁が述べているように、ニュースを「激しく追跡する」あまり、しばしば誤りが起きる。しかし、市民に対しては情報を提供する必要があり、そうした仕事を行う新聞社に対して、誹謗罪をちらつかせて脅すことは許されないことなのである。
「ニューヨーク・タイムズ紙対サリバン事件」(1964年) 「われわれは、この裁判の審理にあたり、米国民が次のような原則を深く信奉しているという背景を考慮する。すなわち、公的な問題の議論は、規制されることなく、力強く、広く開かれたものであるべきであり、それは、政府と公職者に対して激しく、辛らつで、ときには不快なほど痛烈な攻撃を伴う場合もある、ということである。本件の広告記事は、現代の主要な公的課題のひとつに関する不満と抗議の表明であり、明らかに憲法の規定によって保護されるべき条件を備えていると思われる。問題は、記載された事実の誤りのいくつかによって、そしてまた、被上告人が主張する名誉棄損によって、その憲法上の保護が失われるかどうかである。修正第1条が保障していることに関する権威ある解釈は、判事であれ、陪審団であれ、政府の官吏であれ、真実について誰かが何らかの判断基準を示すという例外を認めることを、一貫して排除してきた。とりわけ、意見を表明する者に真実の証明という重荷を課すという例外を認めることはなかった。憲法上の保護は、開陳される思想や信条の真実性、人気あるいは社会的有用性によって左右されない。・・・公職者の評判が傷つくことが、事実関係の誤り以上に、自由であるべき言論を弾圧する正当な理由とはならない。・・・公的な言動に対する批判は、それが効果的であり、公人としての信用を傷つけたという理由だけで、憲法上の保護を失うことはない」 |
さて、現代の出版の自由をめぐる第2の柱となる出来事は、いわゆる「ペンタゴン・ペーパーズ(国防総省秘密報告書)」に関する裁判である。この訴訟は、ベトナム戦争への米国の介入に反対する国防総省の一人の文官によって、報告書が外部に持ち出され、出版されたことに端を発する。この報告書は、1967年に命じられた大規模な政策見直しの一環として作成された。この中には、その当時の東南アジアにおける軍事活動に関する機密事項は含まれていなかった。しかしこの文書は、リンドン・ジョンソン政権下の米国が、当時の政策立案者たちの偏見や判断ミスにより、どのようにしてベトナムへの関与を深めていったかを暴露するものだった。ホワイトハウスの主は、ジョンソンからリチャード・ニクソンに代わっていたが、新大統領は、国家安全保障上の悪影響を及ぼしかねない、との理由で、文書の公表に反対した。
1971年6月13日、ニューヨーク・タイムズ紙は、ペンタゴン・ペーパーズの掲載に踏み切った。政府は直ちに記事差し止めの仮処分申請を行い、これが地裁で認められると、今度は、ワシントン・ポスト紙が、同じ文書の掲載を始めた。政府がワシントン・ポスト紙への掲載を中止させるため裁判所に訴えると、今度はボストン・グローブ紙がバトンを受け取り、それを掲載した。こうした事前の規制の可否をめぐり、下級審の判断が割れていたこと、そして政府がこの問題の決着を急いだことから、最高裁は、この問題を緊急に取り上げることで合意した。裁判の仕事は、ときに遅すぎるという批判を受けているが、このときの最高裁判事たちは、驚くべき速さで動いた。金曜日に裁判の審理を決め、翌土曜日には口頭弁論を行い、週明けの火曜日には決定を下した。ニューヨーク・タイムズ紙が文書掲載を開始してから、わずか17日後だった。
判決文は、政府が新聞を検閲したり、結果として政府に都合の悪そうな情報の公表を阻止したりすることは一切できないということを、改めて明確に述べるものだった。最高裁判事のうち3人は、そもそも、政府が下級審で記事差し止めを認められるべきではなかったとし、報道の事前規制につながる政府の行動を容認した下級審を批判した。最高裁は、どのような状況においても、報道の事前規制を課してはならないとまでは判示しなかった。戦時中のような非常事態のもとでは、「明白に」機密性のある情報は、依然として除外されたが、ペンタゴン・ペーパーズに含まれた情報が、そうした部類に入らないことは明白だった。
「ニューヨーク・タイムズ紙対合衆国事件」(1971年)での同意意見 「このような情報の暴露により、深刻な影響が出るかもしれない。しかし、それだけで、報道の事前規制を承認する根拠には、まったくならない。・・・憲法修正第1条のひときわ重要な目的は、政府が都合の悪い情報を抑圧するという、広く行われていた行為を禁止することだった。ベトナムにおける米国の姿勢については、いまも国内で大規模な議論が続いている。公的な問題に関する開かれた議論と討論は、われわれの国の健康にとって不可欠である」 |
ダグラス判事のこの見解に、誰もが賛成したわけではない。のちに駐ベトナム大使となったマックスウェル・テイラー元将軍は、この最高裁の判決に対して、政権内の多くから噴出した怒りを表明した。テイラー元将軍は、市民の知る権利は、「良き市民となり、その義務を果たすために必要なもの」に限られており、それ以上のことを知る権利はない、と明言した。しかし最高裁判決の目的は、まさしく、市民に自らの義務を果たさせることにあった。ダグラス判事は、ベトナムでの米国の役割について、重要な国民的議論が行われている、と指摘した。市民が重要な情報の開示を拒否されたら、どのようにして義務を果たし、この議論に知的に参加することができるのかと。
しかしながら、ニューヨーク・タイムズ紙やワシントン・ポスト紙やその他の主要各紙は、いずれも一個人ではなく、数千人もの従業員を擁し、数百万ドルにも上る資産を持つ大企業である。このような、しばしば企業の形態をとる報道機関に大きな自由を許容することは、国民の権利とどのような関係があるのだろうか。ここで、言論の自由の章で取り上げた、市民の義務についてのブランダイス判事の次の言葉を想起する必要がある。「国民の公的な議論は、政治的な義務である。これは、米国政府の基本原則であるべきだ」。判事はこう述べた。しかし、市民が議論に加わり、市民としての義務を果たすには、情報が与えられなければならない。正確な情報は、常に政府から直接もたらされるとは限らず、自主的な情報源から提供されるかも知れない。自由と民主主義が維持されるかどうかは、そのような情報源が完全に自主的で恐れを知らない立場をとれるかどうかにかかっている。
「(エドマンド)バークは、議会には3つの階級があると述べた。しかしあそこの記者席には、その3つの階級を合わせたよりも、はるかに重要な『第4階級』が座っているではないか、と彼は言った。しゃれたスピーチでもないし、機知に富んだ表現でもない。しかしそれは文字通りの事実であり、いまの時代、われわれにとって非常に重要な発言である」 |
バークが報道機関を「第4階級」と呼んだのは、報道が世論に及ぼす影響力は、国の統治において重要な源泉となっている、という意味だった。現代社会では、自由な報道の役割について、われわれの見方は変わってきてはいるが、それでも依然として、半ば制度的な存在として見ている。ポッター・スチュアート連邦最高裁判事は、報道の自由の役割は、腐敗を摘発し、政治プロセスを正直なものに保つ上で、不可欠なものだと考えた。スチュアート判事の同僚、ウィリアム・O・ダグラス判事もこの見方に同調し、報道機関は、「国民の知る権利」を可能にするものであり、「知る権利は、国民による統治プロセスのカギを握っている」と述べている。
自由な報道の役割について(1975年) 「自由な報道の保障は、本質的に、憲法の構造的な規定である。権利章典のそのほかの条項の大半は、個人の特定の自由や特定の権利を擁護している。・・・それに対して、自由な報道の条項は、その保障を制度的な規模にまで拡大している」 |
報道機関が、この構造的な役割をいかに果たしているかを示す良い例が、刑事訴訟制度である。被告人の権利の保障については、ほかの章に譲り、ここでは除くとして、司法の執行手続きがまともに機能しているのかどうかを、市民は知る必要がある。裁判は公正に行われているのだろうか。手続きは迅速に行われているのだろうか。それとも、手続きが遅れて、誰かが苦しんではいないか。ごく平均的な市民には、わざわざ地元の裁判所に行き、法廷を傍聴する時間はないし、ケーブルテレビで、数時間もかかる法廷中継を見る暇さえない。通常は、朝刊であれ、夕方のテレビやラジオのニュースであれ、メディアの報道を通じて裁判についての情報を知ることになる。だから、もしメディアが法廷取材を阻まれれば、「国民による統治プロセスに不可欠な」情報を提供できなくなる。
しかし、公正な裁判の必要性については、どうだろうか。犯罪が特別に凶悪な場合、地元の感情が過敏になっている場合、情報過剰で公正な陪審団の選定に支障を来たす恐れがある場合には、報道機関を排除すべきなのだろうか。最高裁によれば、その答えはノーである。ウォーレン・E・バーガー最高裁長官は、「言論や出版の事前規制は、最も重大で、容認の余地のない修正第1条の侵害である」と述べている。いま述べたような問題に関しては、被告弁護人や担当検察官へのかん口令、市民感情の影響が少ない場所への裁判地の移動、陪審団の隔離など、判事たちはあらゆる手段を講じることができるのである。
報道機関による裁判取材を扱った主要な裁判としては、「リッチモンド新聞社対バージニア州事件」(1980年)が知られている。そしてこの裁判によって、国民の知る権利が、自由な報道機関の努力によって確立した。ひとりの男性が殺人容疑で逮捕された。ところが裁判では、さまざまな問題から、審理は3度も無効となった。そこで4度目の裁判が始まったとき、判事、検察、被告側弁護士は、そろって傍聴人と報道陣を法廷から排除することで合意した。
地元のリッチモンド新聞社は、法廷の決定を不服として、最高裁に上告した。この重要な判決で、最高裁は、憲法修正第1条と第6条、すなわち報道の自由と公正な裁判を受ける権利の二つは互いに両立し得るとの判断を示した。憲法修正第6条による「迅速で開かれた裁判」の保障は、単に英国の星室裁判所のような密室裁判から被告人を守るだけでなく、一般国民が裁判を傍聴する権利も保障している。しかし、実際上、バージニア州全体はおろか、リッチモンド市の全市民ですら、裁判に立ち会うのは、明らかに不可能だった。そこで、報道陣が裁判の進行を報道し、裁判が公正に行われたことを確かめる手助けをすることが、認められる必要があった。
「リッチモンド新聞社対バージニア州事件」(1980年) 「権利章典は、公開を前提として行われてきた裁判の、長い歴史を背景に成立した。一般国民が裁判に立ち会うことは、当時、訴訟手続きそれ自体の重要な側面と見なされていた。『自ら進んで参加するできるだけ多くの国民の前』で裁判を行うことは、『英国の自由な統治制度の計り知れない貴重な利点』のひとつと考えられていた。言論と出版などの自由を保障することにより、憲法修正第1条は、国民が誰でも裁判に参加する権利を擁護し、またそれを通じて、明記されたこれらの保障に意味を与えている、とも読み取ることができる。『憲法修正第1条は、報道機関や個人の自己表現を守ることを超え、公共の一員が入手し得る情報源を、政府が制限することまで禁じている』。言論の自由には、何らかの聞く自由が伴う。いま法廷は、さまざまな文脈の中で、情報や思想を受け取る権利として、修正第1条に言及してきた。このことは、裁判の文脈に関して言えば、まさに言論と報道の自由を保障する修正第1条こそ、その条項が採択された当時まで長年公開されていた裁判を、政府が安易に即決で密室にすることを禁じていることを意味している。『なぜなら、修正第1条の文言に、あいまいなところはない。・・・自由を愛する社会という文脈の中でその明快な文言を読み取り、最も広範囲にわたる命令として、それを受け入れるべきである』」 |
この事件は、刑事裁判だったが、同じ考え方が民事裁判にも適用できる。オリバー・ウェンデル・ホームズ(最高裁判事1902~1932年)は、国民の監視により、裁判の適切な執行を保障することができるとして、次のように述べている。「(民事)裁判は、公衆の面前で行われることが望ましい。それは、市民間の論争が公共の関心事であるからではない。裁判を執行する者は常に、市民は誰でも、公的任務がいかに遂行されるか自分の目で見て満足する必要があるのだ、という公的な責任感を持って行動することが重要だからである」
近年の技術の進歩により、国民による裁判の傍聴という概念は、新しい舞台に持ち込まれるようになった。現在、法廷にカメラを持ち込むことは、憲法上の権利として認められてはいないが、多くの州で、裁判の放送を認める法律が制定されている。テレビ放送が始まった当初は、カメラが大きすぎたり、強い照明が必要だったり、全員にマイクをつける必要があるなど、裁判の中継放送は現実には不可能だった。しかし今日では、いくつかの小型カメラを、ほとんど見えないように配置して、法廷全体を撮影できるようになり、その操作は建物の別室か、あるいは外部に駐車した中継車から行えるようになった。裁判のテレビ中継は試験的に始まったものの、非常に大きな人気を博した。現在では「法廷テレビ」として知られる米国のケーブルテレビ網が登場し、裁判とともに、弁護士や法律学の教授による解説を放送している。この場合メディアは、国民と司法制度をつなぐ役割を果たし続けており、しかも新しい方法により視聴者は、法廷で起きていることをよりよく理解できるようになっている。
(同様に、連邦議会の上下両院の議事進行、同公聴会、州議会の各審議も、通常C-SPANなどのケーブルテレビ網で放送されている。これもまた、メディアが、国民と政府の仕事を結びつけている例である。)
修正第1条の言論と出版の自由条項から導き出された「知る権利」という概念は、米国の政治・司法思想のなかで、比較的新しいものである。しかし、ここでも、民主主義とそれに伴う自由は、静止状態にあるのではなく、社会自体の変化につれて進化していく概念であることがわかる。「国民の知る権利」は、報道の自由と密接に関わっているが、同時にそれは、より広範な民主主義的な関心に基づいている。もしわれわれが、エイブラハム・リンカーンが定義したように、民主主義を「人民の、人民による、人民のための政治」であると考えるなら、政府の関心事は、実は、国民の関心事であり、まさにそこにおいて、報道の自由の構造的役割と、市民の民主主義的な関心が交差することになる。これは単純な命題ではない。国民も報道機関も、政府部内で起きているすべてのことを、必ずしも知る必要はない。国家安全保障、外交、そして政策形成過程の内部討議にかかわる事柄は―理由は説明するまでもないが―その時即座に国民の監視の下にさらすべきではない。修正第1条に関する権威、ロドニー・A・スモラ法科大学院教授は次のように述べている。「民主的な政府は、大きく開かれた透明性のある政府でなければならない。しかし最も開かれた民主的な政府でも、状況によっては、適切に機能する上で一定の秘密性、機密性を必要とする。」
これは常識的な意見に聞こえるが、実際には、2つの競合する力が働いている。民主社会においても、あらゆるレベルの政府役人は、どちらかといえば国民や報道機関に、すぐには情報を提供したがらない傾向がある。他方、報道機関は、世論を味方にして、合法的に必要と思える以上に情報を取ろうとするものだ。この緊張を解消するために、連邦議会は1967年、「情報公開法」(Freedom of Information Act:通称FOIA)を成立させた。この法律は、国民に情報を開示するための既存の連邦法がしばしば逆用されている、と非難する報道機関や公益団体の要請に基づいて成立した。この法律の解釈にあたり、裁判所は、国民に情報を開示するのは当たり前の原則であり、連邦政府機関は迅速かつ誠実に、国民の情報開示の要請に応えなければならないという判断を一貫して示してきた。連邦法を補足する形で、各州は、州政府の活動とその記録に関して、同じような情報公開の法規を成立させた。
こうした法整備によって、個々の市民と報道機関は、FOIAに基づく情報開示の請求ができるが、実際には、請求のほとんどすべては報道機関によるものである。個人レベルでは、たとえ調査活動の訓練を積んだ人でさえ、このFOIAの情報開示請求を使って追跡できる手がかりは限られている。それに対して、大勢のスタッフを持つ新聞社やテレビ局は、いくつものチームを編成して問題に取り組むことができる。彼らには、膨大な資料のコピー代を支払う資力もある。明白なことだが、紙の印刷メディアであれ、電波の放送メディアであれ、政府のすべての業務を調べたり、あらゆる裁判を取材したり、議会のすべての公聴会について報道したりすることは不可能である。しかし、まさに不可能だからこそ、自由な報道が民主主義にとって不可欠なのである。個人は、通信社が配信し、地元紙が提供する報道の集積を享受することができ、テレビで公聴会や裁判を見ることも、あるいはインターネット上で、数多くのニュースや論評のサイトを見ることもできる。人類がまだ小さな村落に住んでいたころ以降、本人が望みさえすれば、個人が政府の活動についてこれほど詳しく知ることができる時代は、かつてなかった。こうして得た知識によって人々は、賢い投票を行い、各種の提案に関する賛成ないし反対の請願書に署名し、議会に意見書を送り、全体として、市民の義務を果たすことができるようになる。そしてこれは、自由な報道の存在なしには不可能だろう。
しかし、報道が行き過ぎるという可能性はないだろうか。いかなる自由にも行き過ぎがあれば、許可制につながりかねない。政府の腐敗を暴く報道の仕事に対して、多くの人々が拍手を送る。しかし同時に、あらゆる公職者とその人格について、すべてを知りたがることから生じるプライバシーの侵害を嘆く声も出ている。この懸念は現実のものであり、それに対する答えは、主に裁判所が出してきた。裁判所は、一方では、憲法修正第1条の適用範囲を広げながら、同時に一定の制約を課した。報道機関は、こうした制約が課されるたびに、それは憲法で保障された報道の自由を何らかの形で侵害する、として不満を表すことが多い。だが全体として、そのような制約のほとんどは、自由な報道も通常の社会的制約から完全に自由というわけではない、という常識的な考え方を反映している。こうした制約には、刑事事件の訴追の証拠として国が必要とする場合、記者の取材源を秘匿する権利が制限されることや、政府関係者ではなく民間人が名誉棄損を受けたときは民事訴訟上の責任が発生すること、あるいは、刑務所など一部の政府施設への立ち入りが制限されることなどが含まれる。このほか報道機関は、米軍の軍事作戦の展開に際して、記者が前線取材を拒否されていることについて苦情を申し立ててきた。恐らくこの問題の最良の判断基準は、このような制約が誰か個人に課せられたときに、それが道理にかなっているかどうかである。そしてたいていの場合、こうした制限は筋が通っている。個人が刑務所の構内を歩きまわったり、戦闘の最前線まで出て行くことは、それが誰であれ、それを是認する説得力のある理由を見つけることは難しい。われわれは、報道機関がわれわれのために情報を集めてくれることを期待しているが、その能力には限度があることもまた認識している。
報道機関が、公職者のプライバシーを侵害しているという批判も続いている。つまり、そうした人たちの職務を遂行する能力にはほとんど、あるいはまったく関係のないことを報道しているという批判である。近年、とりわけインターネットとケーブルテレビが普及したこともあり、大統領を筆頭に、政府関係者の私生活について、際限のない報道が行われている。こうした風潮がどこまで続くのか、またこのままでいいのかという議論が盛んに行われている。人目を引く興味本位の報道に、多くの人が迷惑だと眉をひそめている。なぜならそういう人々は、公私の間に明確な一線を引き、公的な振る舞いには隈なく光を当てても、私的な生活は完全に無視すべきだと考えているからである。しかし、そういった公私の区別などできないと言う人たちもいる。男性であれ、女性であれ、私人としてどのような生活を営んでいるかがその人の道徳的な人格を決める鍵であり、有権者は公職者を選挙で選ぶとき、まさにそのような点を考慮する権利がある、というわけである。
1980年代末、大統領選への出馬を考えていた一人の上院議員に愛人がいたことを記者たちが暴いた。その記事により、その議員が抱いていた、さらに上の地位へという夢は完全に葬り去られた。上院議員は、「このようなことは、建国の父たちが200年前に意図していたことではない」と、新聞を非難した。確かに彼の非難は正しいと考えた人も多かったが、実際には、建国の父たちの一部も、この手の暴露趣味の新聞に執拗につきまとわれていた。アレクサンダー・ハミルトンとトマス・ジェファソンも、それぞれの愛人関係が辛らつな記事のネタにされた。しかし2人とも、新聞を封じることが解決策だとは考えなかった。
ハミルトンは、これらの記事に対して、自分も新聞を利用して対応した。彼はマリア・レイノルズとの愛人関係を認める一方、そのほかの自分に対する非難には反論した。ハミルトンは不慮の死の直前、誹謗罪で有罪となったニューヨークの出版社を擁護した。彼は、報道の自由の価値を強く擁護しつつ、次のように述べている。「報道の自由は、善良な動機と正当な目的であれば、罰せられることなく、真実を公表する権利によって成り立つ」。一方、ジェファソンは、自分が使っていた奴隷の一人、サリー・ヘミングズとの関係についての報道に対し、沈黙を守った。ジェファソンは、新聞に載っているのは、自分や自分の味方に対する非難ばかりだと思っていた時でさえ、民主主義社会における自由な報道の必要性について、自分の信念を貫き通した。ジェファソンは、「彼らは新聞の紙面を、嘘と中傷と無礼で埋め尽くしている。それでも私は、彼らが嘘をつき、中傷する権利を守るだろう」と友人に語っている。
20世紀初頭、新しい技術の出現が、自由な報道の役割についての古くからの真理と前提条件を一変させた。例えば、長年にわたり、ラジオとテレビは、メディアとしてあまり保護されてこなかった。それは、電波の割り当てができる局の数は技術的に厳しく限定される、という誤解があったせいである。その結果連邦議会は、電波は公共の所有物であり、特定の周波数を使って放送を行うためには放送免許が必要だと判断し、裁判所もそのような考え方を支持した。こうしてラジオ放送局と、そして後にはテレビ局は、放送免許と引き換えに、一定の政府の規制に従わなければならなくなった。その規制により、放送局はニュース取材や論評の放送に際して、しばしば制約を受けた。しかし、ケーブル放送や衛星放送の発達は、放送は限られた資源だという考え方に終止符を打った。そして放送メディアは、伝統的な活字メディアと完全に肩を並べるようになった。
インターネットの登場は、多くの疑問を提起している。それに答えが出るのは、何年も先のことになるだろう。史上初めて、一個人が、最少額の投資で、地元の人々だけでなく、世界中の人々に向けて自分の意見を発信できるのだ! 一人の人間には、新聞社やテレビ局のような取材能力はないかもしれないが、意見を発信することについては、それを聞きたい人に対して、極めて大きな声で叫ぶことができる。それどころか、個人でインターネットのニュース・サービスを作り、政治、天気、株式市場、スポーツ、ファッションなどに特化した最新ニュースを提供している人もいる。活字メディア、放送メディアに加えて、いまや世界は、報道の第3の柱、オンライン・サービスを持つようになったのである。
国民の権利という見地からすれば、ニュースが多すぎて都合が悪いなどということはない。米国の多くの新聞の題字には、「汝に真実を知らしめ、真実により汝は自由にならん」という聖書からの引用が記されている。建国の父たちは、自由な報道は、個人を政府から守るために不可欠なものと見なしていた。報道の自由とは、個人が市民として義務を果たすために必要な情報を提供するものだ、とブランダイス判事は定義した。報道機関による情報の収集・伝達の分野ほど、権利の性格が急速に変化している分野は、多分、ほかにはないだろう。しかしその使命は、常に同じである。修正第1条の出版の自由条項は、民主主義と国民を守る構造的な砦であり続けるだろう。
参考文献:
- Fred W. Friendly, Minnesota Rag (New York: Random House, 1981)
- Elizabeth Blanks Hindman, Rights & Responsibilities: The Supreme Court and the Media (Westport: Greenwood Press, 1997)
- Anthony Lewis, Make No Law: The Sullivan Case and the First Amendment (New York: Random House, 1991)
- Lucas A. Powe, Jr., The Fourth Estate and the Constitution: Freedom of the Press in America (Berkeley: University of California Press, 1991)
- Bernard Schwartz, Freedom of the Press (New York: Facts on File, 1992)
*上記の日本語文書は参考のための仮翻訳で、正文は英文です。
Freedom of the Press
(The following article is taken from the U.S. Department of State publication, Rights of the People: Individual Freedom and the Bill of Rights.)
Congress shall make no law . . . abridging the freedom of speech, or of the press.
- First Amendment to the U.S. Constitution
Although a cherished right of the people, freedom of the press is different from other liberties of the people in that it is both individual and institutional. It applies not just to a single person's right to publish ideas, but also to the right of print and broadcast media to express political views and to cover and publish news. A free press is, therefore, one of the foundations of a democratic society, and as Walter Lippmann, the 20th-century American columnist, wrote, "A free press is not a privilege, but an organic necessity in a great society." Indeed, as society has grown increasingly complex, people rely more and more on newspapers, radio, and television to keep abreast with world news, opinion, and political ideas. One sign of the importance of a free press is that when antidemocratic forces take over a country, their first act is often to muzzle the press.
Thomas Jefferson, on the necessity of a free press (1787)
The basis of our government being the opinion of the people, the very first object should be to keep that right; and were it left to me to decide whether we should have a government without newspapers, or newspapers without a government, I should not hesitate a moment to prefer the latter.
* * * * *
The origins of freedom of speech and press are nearly alike, because critical utterances about the government, either written or spoken, were subject to punishment under English law. It did not matter whether what had been printed was true; government saw the very fact of the criticism as an evil, since it cast doubt on the integrity and reliability of public officers. Progress toward a truly free press, that is, one in which people could publish their views without fear of government reprisal, was halting, and in the mid-18th century the great English legal commentator, Sir William Blackstone, declared that although liberty of the press was essential to the nature of a free state, it could and should be bounded.
Sir William Blackstone, Commentaries on the Laws of England (1765)
Where blasphemous, immoral, treasonable, schismatical, seditious, or scandalous libels are punished by English law … the liberty of the press, properly understood, is by no means infringed or violated. The liberty of the press is indeed essential to the nature of a free state; but this consists in laying no previous restraints upon publication, and not in freedom from censure for criminal matter when published. Every freeman has undoubted right to lay what sentiments he pleases before the public; to forbid this is to destroy the freedom of the press: but if he publishes what is improper, mischievous, or illegal, he must take the consequences of his own temerity.
But what constituted "blasphemous, immoral, treasonable, schismatic, seditious or scandalous libels"? They were, in fact, whatever the government defined them to be, and in essence, any publication even mildly critical of government policy or leaders could lead to a term in prison or worse. In such a subjective judgment, truth mattered not at all.
The American colonists brought English common law across the Atlantic, and colonial officials had as little toleration for the press as did their masters back home. In 1735, the royal governor of New York, William Cosby, charged newspaper publisher John Peter Zenger with seditious libel for criticizing Cosby's removal of a judge who had ruled against the governor's interests in an important case. Under traditional principles as enunciated by Blackstone, Zenger had a right to publish his criticism, but now had to face the consequences. However, Zenger's attorney, Andrew Hamilton, convinced the jury to acquit Zenger on the grounds that what he had published was true. Although it would be many years before the notion of truth as a complete defense to libel would be accepted in either English or American law, the case did establish an important political precedent. With American juries unwilling to convict a man for publishing the truth, or even an opinion, it became difficult for royal officials to bring seditious libel cases in the colonies. By the time of the Revolution, despite the laws on the books, colonial publishers freely attacked the Crown and the royal governors of the provinces.
Whether the authors of the Press Clause of the First Amendment to the Constitution intended to incorporate the lessons of Zenger's case is debatable, since nearly all the new American states adopted English common law, including its rules on the press, when they became independent. When Congress passed a Sedition Act in 1798 during the quasi-war with France, it allowed truth as a defense to libels allegedly made against the president and government of the United States. The law, however, was enforced in a mean and partisan spirit against the Jeffersonian Republicans. Federalist judges in effect ignored the truth-as-defense provision, and applied it as their English counterparts would have done, punishing the very utterance as a libel. As one example, Matthew Lyons, a Vermont newspaper publisher, criticized President John Adams for his "unbounded thirst for ridiculous pomp, foolish adulation, and selfish avarice." For these comments, he received a $1,000 fine and languished in jail for four months until he could raise the funds to pay the fine.
The Sedition Act expired in 1801, and the federal government, with the exception of some restrictions during the Civil War, did nothing to violate the Press Clause for the next century. Libel gradually became more a matter of civil than criminal law, in which prominent individuals took it upon themselves to institute lawsuits to protect their reputations. Congress passed another Sedition Act during World War I, and as noted in the chapter on free speech, cases arising out of that act were treated primarily as speech and gave rise to the clear-and-present-danger test. But in terms of a free press, we do not get any significant developments until the early 1930s, when the doctrine of prior restraint was reinvigorated. In developing a truly free press, newspapers found they had a powerful ally in the Supreme Court, which turned a single phrase, "or of the press," (contained in the First Amendment to the U.S. Constitution) into a potent shield for press freedom.
* * * * *
Modern Press Clause jurisprudence begins with the landmark case of Near v. Minnesota in 1931, and while, at first glance, it would appear to do little more than restate Blackstone's views on prior restraint, in fact it is the first step in building upon that doctrine to create a powerful and independent press.
The state of Minnesota had passed a law, similar to laws in other states, that authorized the suppression as a public nuisance of any "malicious, scandalous or defamatory" publications. In this case, however, the law had been passed to shut down a particular newspaper, the Saturday Press, which in addition to carrying racist attacks against blacks and other ethnic groups, had also carried a series of exposes about corrupt practices by local politicians and business leaders. The state court gladly shut down the Saturday Press, which in turned appealed to the Supreme Court. There Chief Justice Charles Evans Hughes applied the reach of the First Amendment Press Clause to the states (it had previously applied only to Congress), and reiterated the idea that no government, except in the case of a wartime emergency, can curtail a newspaper's constitutional right to publish. This did not mean that newspapers could not be punished on other grounds, or sued by individuals for defamation. But it laid the groundwork for two significant developments more than three decades later that are the pillars on which a modern free press stands.
The first grew out of the civil rights movement in the 1960s. At that time most states had laws that in effect imposed no prior restraints, but did allow civil suits for defamation of character if the information printed was malicious or even just in error. There had been clashes between civil rights advocates and police in Montgomery, Alabama, and a group of rights organizations and individuals took out a full page advertisement in the New York Times entitled "Heed Their Rising Voices," which detailed the difficulties civil rights workers faced and asked for funds to help the cause. Although I.B. Sullivan, the police commissioner of Montgomery, Alabama, was not mentioned by name in the ad, he nonetheless sued the Times on the basis that the ad contained factual errors that defamed his performance of his official duties. A local jury found for Sullivan, and awarded him damages of $500,000 against the Times.
Sullivan had gone against the newspaper not because the errors amounted to very much (one sentence said that Dr. Martin Luther King, Jr., had been jailed seven times, when in fact it had only been four), but because Southerners saw the press as an adversary in the civil rights struggle. Every time protesters were beaten or arrested, the press reported it not only to the rest of the nation but to the world. The Times was not only the foremost newspaper in the country, but also one of the largest and most successful. If it could be punished with a heavy fine (and $500,000 was a great deal of money in 1964), then smaller and less prosperous papers would have to think twice about reporting on the civil rights movement. To allow the judgment to stand, in other words, would have a severe "chilling" effect on the First Amendment right of a free press.
Not only did the high court overturn the judgment, but in doing so it went a great deal further than the simple prior restraint rule that had been inherited from Great Britain; it did away with any punishment for publication when the stories involved public officials and the performance of their duties, except when a paper, knowing something was untrue, nonetheless printed it with the malicious intent of harming the official's reputation. While not allowing the press to print anything at all, and while still granting private citizens the right to sue for libel, the decision addressed a major issue of a free press, namely, its ability to report on government and governmental officials fully and freely. That there might be inadvertent mistakes from time to time would not matter; as the Court explained, mistakes often happen in the "hot pursuit" of news. But the citizenry needed to be informed, and threats of libel against a newspaper for doing its job could not be allowed.
Justice William Brennan, Jr., in New York Times v. Sullivan (1964)
We consider this case against the background of a profound national commitment to the principle that debate on public issues should be uninhibited, robust, and wide-open, and that it may well include vehement, caustic, and sometimes unpleasantly sharp attacks on government and public officials. The present advertisement, as an expression of grievance and protest on one of the major public issues of our time, would seem clearly to qualify for the constitutional protection. The question is whether it forfeits that protection by the falsity of some of its factual statements and by its alleged defamation of respondent. Authoritative interpretations of the First Amendment guarantees have consistently refused to recognize an exception for any test of truth – whether administered by judges, juries, or administrative officials – and especially not one that puts the burden of proving truth on the speaker. The constitutional protection does not turn upon the truth, popularity, or social utility of the ideas and beliefs which are offered. . . . Injury to official reputation affords no more warrant for repressing speech that would otherwise be free than does factual error. . . . Criticism of their official conduct does not lose its constitutional protection merely because it is effective criticism and hence diminishes their official reputations.
The second modern pillar is the so-called Pentagon Papers case, arising out of publication of documents pilfered from the Defense Department by a civilian employee who opposed American involvement in the Vietnam War. The papers were part of a large-scale review that had been ordered in 1967, and they carried no secret information relating to current military activities in southeast Asia. They did, however, expose the mindset of the policy planners as well as errors in judgment that had led to the growing American commitment during the administration of Lyndon Johnson. Although a new president now sat in the White House, Richard Nixon nonetheless opposed the publication of the papers, on the grounds that it might adversely affect national security interests.
The New York Times began publication of the Pentagon Papers on June 13, 1971, and when the government secured a temporary injunction shortly afterwards, the Washington Post started publication of its copy of the Pentagon Papers. After the government went to court to stop the Post, the Boston Globe picked up the baton. Since the lower courts disagreed on whether such a prior restraint could in fact be imposed, and since the government wanted to resolve the issue quickly, the Supreme Court agreed to take the case on an expedited basis. Although there have sometimes been criticisms of the judiciary for its slowness, the justices moved with astounding speed this time. They agreed to take the case on a Friday, heard oral argument the next day, and handed down their decision the following Tuesday, only 17 days after the Times had begun publication.
The decision provided the clearest statement yet that government had no business trying to censor newspapers or prevent the disclosure of what might prove embarrassing information. Three of the justices believed the government should never have gotten injunctions in the lower courts, and criticized the lower courts for condoning such an effort at prior restraint. While the Court did not say that in no circumstances could prior restraint be imposed (the exception of clearly sensitive information during emergencies such as wartime remained in place), it was clear that the material in the Pentagon Papers did not fall into that category.
Justice William O. Douglas, concurring in New York Times v. United States (1971)
These disclosures may have a serious impact. But that is no basis for sanctioning a previous restraint on the press. . . . The dominant purpose of the First Amendment was to prohibit the widespread practice of governmental suppression of embarrassing information. A debate of large proportions goes on in the Nation over our posture in Vietnam. Open debate and discussion of public issues are vital to our national health.
Not everyone agreed, and former general and ambassador to Vietnam Maxwell Taylor expressed the resentment of many in the government at the Court's decision. A citizen's right to know, he declared, is limited "to those things he needs to know to be a good citizen and discharge his functions," and nothing more. But the whole purpose of the Court's decision was, in fact, to allow the citizen to do his duty. Justice Douglas pointed out that there was an important national debate going on over the American role in Vietnam. How were citizens to do their duty and participate intelligently in this debate if they were denied important information?
* * * * *
The New York Times, the Washington Post, and other major newspapers, however, are not individuals, but large corporations, with thousands of employees and assets that run into the millions of dollars. How does giving such great latitude to the press – often in the form of business entities – relate to the rights of the people? One needs to recall the words of Justice Brandeis about the duties of a citizen, discussed in the chapter on Free Speech, "that public discussion is a political duty; and that this should be a fundamental principle of the American government." Yet in order to enter that discussion, to carry out one's responsibilities as a citizen, one must be informed. Accurate information will not always come directly from the government, but may be offered by an independent source, and the maintenance of freedom and democracy depends upon the total independence and fearlessness of such sources.
Thomas Carlyle on the press (1841)
Burke said that there were Three Estates in Parliament; but, in the Reporters' Gallery yonder, there sat a Fourth Estate more important far than they all. It is not a figure of speech, or witty saying; it is a literal fact, – very momentous to us in these times.
By calling the press a "fourth estate," Burke meant that its abilities to influence public opinion made it an important source in the governance of a nation. In modern times, we see the role of a free press differently, but still in quasi-institutional terms. Justice Potter Stewart saw the role of a free press as essential in exposing corruption and keeping the political process honest. His colleague on the high court, William O. Douglas, echoed this sentiment when he explained that the press enables "the public's right to know. The right to know is crucial to the governing process of the people."
Justice Potter Stewart, on the role of a free press (1975)
The Free Press guarantee is, in essence, a structural provision of the Constitution. Most of the other provisions in the Bill of Rights protect specific liberties or specific rights of individuals. . . . In contrast, the Free Press Clause extends protection to an institution.
A good example of how the press fulfills this structural role involves the criminal justice system. Aside from the protection of the rights of the accused, discussed in other chapters, the citizen needs to know if the administrative processes of justice are working. Are trials fair? Are they conducted with dispatch or are there delays that cause hardships? But the average person does not have the time to go down to the local courthouse and sit in on trials, nor even spend hours watching the telecast of some trials on cable television. Rather information is gathered from the press, be it the morning newspaper or the evening television or radio news. And if the press is barred from attending trials, then it cannot provide that information which "is crucial to the governing process of the people."
But what about the necessity for a fair trial? If the crime is particularly heinous, if local emotions are running high, if excessive publicity may damage the prospects for selecting an impartial jury, then should not the press be excluded? According to the Supreme Court, the answer is no. "Prior restraints on speech and publication," according to Chief Justice Warren E. Burger, "are the most serious and least tolerable infringement on First Amendment rights." Judges have a variety of means at their disposal to handle such issues, including gag orders on the defense and prosecution lawyers, change of venue (location) to a less emotional environment, and sequestering of juries.
The key case in press coverage of trials is known as Richmond Newspapers, Inc. v. Virginia (1980), and it solidified the people's right to know through the efforts of a free press. A man had been arrested for murder, and through a variety of problems, there had been three mistrials. So when the fourth trial began, the judge, prosecution, and the defense attorney all agreed that the courtroom should be closed to both spectators and the press.
The local newspaper filed suit challenging the judge's ruling, and in a major decision the Court balanced the interests of the First and Sixth Amendments against each other – the right of a free press as against the right of a fair trial –and found that they were compatible. The Sixth Amendment guarantee of "a speedy and public trial" meant not only the protection of the accused against secret Star Chamber trials, but also the right of the public to attend and witness the trial. Since it was manifestly impossible for all of the people of Virginia, or even of Richmond, to attend the trial, then the press had to be admitted to report on the proceedings, and to help ensure that the trial had been carried out fairly.
Chief Justice Warren E. Burger, in Richmond Newspapers, Inc. v. Virginia (1980)
The Bill of Rights was enacted against the backdrop of the long history of trials being presumptively open. Public access to trials was then regarded as an important aspect of the process itself; the conduct of trials "before as many of the people as chose to attend" was regarded as one of "the inestimable advantages of a free English constitution of government." In guaranteeing freedoms such as those of speech and press, the First Amendment can be read as protecting the right of everyone to attend trials so as to give meaning to those explicit guarantees. "The First Amendment goes beyond protection of the press and the self-expression of individuals to prohibit government from limiting the stock of information from which members of the public may draw." Free speech carries with it some freedom to listen. In a variety of contexts this Court has referred to a First Amendment right to receive information and ideas. What this means in the context of trials is that the First Amendment guarantees of speech and press, standing alone, prohibit government from summarily closing courtroom doors which had long been open to the public at the time that Amendment was adopted. ''For the First Amendment does not speak equivocally. . . . It must be taken as a command of the broadest scope that explicit language, read in the context of a liberty-loving society, will allow."
Although this case dealt with a criminal trial, the same philosophy applies to civil trials as well. Oliver Wendell Holmes (a Supreme Court justice from 1902 to 1932) commented that public scrutiny provided the security for the proper administration of justice. "It is desirable," he wrote, "that the trial of [civil] causes should take place under the public eye, not because the controversies of one citizen with another are of public concern, but because it is of the highest moment that those who administer justice should always act under the sense of public responsibility that every citizen should be able to satisfy himself with his own eyes as to the mode in which a public duty is performed."
Recent technological developments have brought the notion of public attendance at a trial into a new setting. Although at present there is no constitutional right to have cameras in the courtroom, many states have passed laws that permit the broadcasting of trials. When television first began, this was impracticable because of the size of the cameras, the necessity for bright lights, and the need to connect everyone to a microphone. Today, the entire courtroom can be covered by a few small cameras that are practically hidden, with controls in an adjacent room or in a parked van. Although begun as an experiment, TV coverage of trials has proven quite popular, and there is an American cable television network known as Court TV that broadcasts trials as well as commentary by lawyers and law professors. In this instance, the media continue to serve as the intermediary between the public and the justice system, but in a new way that gives the viewer a better sense of what is happening.
(In a similar manner, proceedings of both houses of Congress, congressional hearings, and state legislatures are normally carried on cable networks, in particular C-SPAN, another example of the media serving to connect the people with the business of the government.)
* * * * *
The concept of a "right to know" inferred from the First Amendment Speech and Press Clauses is a relatively new one in American political and judicial thought, but once again we can see democracy and its attendant liberties not as a static condition, but one that evolves as society itself changes. The "people's right to know" is intimately involved with press freedom, but it rests upon the broader concerns of democracy. If we take democracy to mean, as Abraham Lincoln put it, a "government of the people, by the people, and for the people," then the government's business is in fact the people's business, and this is where the structural role of a free press and the democratic concerns of the citizenry intersect. It is not a straightforward proposition. Neither the people nor the press ought to know everything that goes on in the government. Matters relating to national security, foreign affairs, and internal debates about policy development are not, for obvious reasons, amenable to public scrutiny at the time. As law school professor Rodney A. Smolla, an authority on the First Amendment, has written, "Democratic governments should be largely open and transparent governments. Yet even the most open and democratic government will in certain settings require some measure of secrecy or confidentiality to function appropriately."
While this sounds commonsensical, the fact of the matter is that there are two competing forces at work. On the one hand, government officials at every level, even in a democratic society, would just as soon not share information with the press or the public; on the other, the press, backed by the public, often wants to secure far more information than it legitimately needs. To resolve this tension, the U.S. Congress passed the Freedom of Information Act, commonly called FOIA, in 1967. The law passed at the behest of press and public interest groups who charged that existing federal law designed to make information available to the public was often used to just the opposite effect. As the law has been interpreted, the courts have consistently ruled that the norm is for information to be made public, and that federal agencies must respond promptly and conscientiously to requests by citizens for information. Supplementing the federal law, all states have passed similar Freedom of Information statutes, regarding the workings of state government and its records.
Under the law, both individual citizens and the press may file FOIA requests, but in practice the vast majority are submitted by the press. One individual, even a trained researcher, can track down only a limited number of leads upon which to base an FOIA request, while newspapers and television stations, with large staffs, can put teams to work on a problem; they also have the resources to pay for the copying costs of large numbers of documents. Clearly it is beyond the capacity of the media, print as well as broadcast, to investigate every governmental transaction, cover every trial, report on every legislative hearing, but that very impossibility is what makes a free press essential to democracy. An individual can benefit from the combined coverage that goes out on wire services or is published by the local press, watch hearings or trials on television, and even benefit from the many news and commentary sites on the Internet. Not since humans lived in small villages has it been possible for a single citizen, if he or she desires, to be so well informed about the workings of the government. This knowledge is what enables that person to cast an intelligent ballot, to sign a petition for or against some proposal, write letters to the legislature, and in general fulfill the obligations of a citizen. And it would be impossible without the presence of a free press.
* * * * *
But can the press go too far? Any liberty carried to an extreme can lead to license. While there are many who applaud the work of the press in uncovering governmental corruption, they also bemoan the invasions of privacy that have accompanied the drive to know everything about all public officials and personalities. The concern is real, and it has been answered primarily by the courts, who have on the one hand expanded the parameters of the First Amendment and, at the same time, placed some limits on it. While news organizations tend to bemoan each and every one of these limits as somehow undermining the constitutional guarantee of a free press, on the whole most of these restraints indicate a commonsense attitude that a free press is not free from all normal restraints on society. These restraints involve limits on reporters keeping their sources confidential when the state needs evidence in criminal prosecutions, liability for civil action in cases where private individuals and not public officials are defamed, and limits on access to certain governmental facilities, such as prisons. In addition, the press has complained that when the United States has been involved in military operations, reporters have been denied access to the front lines. Perhaps the best way to look at this is to ask whether these same restraints, placed on an individual, would make sense, and in most cases they do. It's difficult to conceive of a compelling reason for letting any individual walk around a prison, or stroll up to the front lines of a battle. While we expect the press to gather information for us, we also recognize that there are limits on that ability.
There has also been criticism of the invasion of privacy of public officials, with the press reporting on matters that have little or nothing to do with their ability to conduct the business of their offices. In recent years, particularly with the growth of the Internet and cable television, there have been countless stories about the private lives of government officials, from the president on down, and a lively debate over how far this trend will or should go. The public spectacle is disturbing to many people, who believe there should be a sharp distinction between the public and the private, with full spotlights on the public behavior and a total disregard of the private life. Others respond that there can be no such distinction. How men or women conduct their private lives is a key to their moral character, which in turn is a factor that people have the right to consider when voting for public officials.
In the late 1980s, reporters uncovered a story about a U.S. senator planning to run for president who was having an extra-marital affair. The story sank any hopes he might have had for higher office, and he castigated the press, charging that "this is not what the Founding Fathers had in mind 200 years ago." While his charge struck many people as true, in fact the same type of expose-minded press dogged the footsteps of some of the Founders. Both Alexander Hamilton and Thomas Jefferson found their amorous affairs the subject of vicious press articles, yet neither one thought that the answer lay in muzzling the press.
Hamilton responded to the stories by using the press himself, and while admitting to an affair with Maria Reynolds, refuted other charges against him. Just before he met his death, Hamilton defended a New York publisher who had been convicted in a trial court of libel. Hamilton delivered a ringing defense of the values of a free press, declaring that "the liberty of the press consists of the right to publish with impunity Truth with good motives, for justifiable ends." Jefferson, on the other hand, chose to remain silent about allegations of his liaison with one of his slaves, Sally Hemmings. Yet even when he believed the press was filled with nothing but invective against him and his allies, he maintained his faith in the necessity of a free press in a democratic society. "They fill their newspapers with falsehoods, calumnies and audacities," he told a friend. "I shall protect them in their right of lying and calumniating."
* * * * *
At the beginning of the 20th century, new technology has transformed some of the old verities and assumptions about the role of a free press. For many years, for example, radio and television were treated as less protected parts of the press, since it was erroneously believed that there were severe technical restrictions on how many stations could be carried on the airwaves. As a result Congress decided, and the courts agreed, that the airwaves belonged to the public, and that stations would be licensed to broadcast on certain frequencies. In return for these licenses, radio and later television stations had to submit to certain government regulations that often hamstrung them in their ability to either gather news or to air editorial opinion. The development of cable and satellite distribution systems has put an end to the notion of broadcasting as a limited resource, and the broadcast media has begun to take its full place alongside traditional print media.
The arrival of the Internet raises many questions whose answers will not be known for years to come. For the first time in history, a single person, with a minimal investment, can put his or her views out, not only before the local populace, but before the entire world! While one person may not have the news-gathering capacity of a newspaper or television station, in terms of opinion he or she can shout quite loudly to anyone who wants to listen. Moreover, some individuals have formed Internet news services that provide specialized information instantaneously about politics, weather, the stock market, sports, and fashion. In addition to the print and broadcast media, the world now has a third branch of the press, the on-line service.
In terms of the rights of the people, one can argue that there is no such thing as too much news. Across the masthead of many American newspapers are inscribed the words from Scripture, "You shall know the truth and the truth shall make you free." The Founding Fathers believed that a free press was a necessary protection of the individual from the government. Justice Brandeis saw a free press as providing the information that a person needed to fulfill the obligations of citizenship. Probably in no other area is the nature of a right changing as rapidly as it is in the gathering and dissemination of information by the press, but the task remains the same. The First Amendment's Press Clause continues to be a structural bulwark of democracy and of the people.
For further reading:
Fred W. Friendly, Minnesota Rag (New York: Random House, 1981).
Elizabeth Blanks Hindman, Rights & Responsibilities: The Supreme Court and the Media (Westport: Greenwood Press, 1997).
Anthony Lewis, Make No Law: The Sullivan Case and the First Amendment (New York: Random House, 1991).
Lucas A. Powe, Jr., The Fourth Estate and the Constitution: Freedom of the Press in America (Berkeley: University of California Press, 1991).
Bernard Schwartz, Freedom of the Press (New York: Facts on File, 1992).