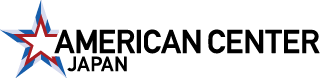国務省出版物
権利章典 – 言論の自由
 議会は・・・言論の自由を制約するような・・・ 法律を制定してはならない。
議会は・・・言論の自由を制約するような・・・ 法律を制定してはならない。
民主主義社会で、何よりも重んじられる権利がひとつあるとすれば、それは言論の自由である。国家から咎められることを恐れることなく、自分の意見を表明し、時の政治的な権威に異議を唱え、政府の政策を批判できることは、自由な国と独裁国家の生活の違いを示す根本的な要素である。国民の権利の神殿ともいうべき連邦最高裁判所で、1932年から1938年までその任にあったベンジャミン・カルドーゾ判事は、言論の自由とは、「そのほかのほとんどすべての自由を保障するための不可欠の条件・・・すなわち基盤である」と述べている。
米国民が、言論の自由は民主主義の核心的な価値だと考えているとしても、さまざまな形の表現を、合衆国憲法修正第1条がどこまで擁護しているかについては、意見が分かれている。例えば、特定の民族や宗教団体に対する、いわゆる「憎悪の演説」も、その自由は擁護されるのだろうか。民衆を今すぐにでも暴力行為に駆り立てるような「好戦的な言辞」も守っているだろうか。わいせつ文書は、合衆国憲法修正第1条の保護の下に入るのか。商業上の表現、つまり広告や消費者向けに企業が出す文書類も、憲法の下で擁護する価値があるのだろうか。過去何十年にもわたり、このような論争が、政府内でも、国民の間でも止むことはなかった。そして多くの分野で、まだ意見の一致は得られていない。しかしながら、それは驚くにはあたらないし、困ったことでもない。自由は、進化する概念であり、自由についての新しい考えが現れるたびに、大論争が続くのである。その時の社会における、合衆国憲法修正第1条による言論の擁護の意義を理解することは、常に大きな課題である。インターネットの登場も、その最新の課題に過ぎない。
言論の自由は、これまでは必ずしも、今日のようにすべてを包含する権利だったわけではない。ウィリアム・ブラックストーン卿が、18世紀中葉に、名著『英国法解説』(Commentary on the Law of England)を著した際、彼は、事前の規制をしないことが言論の自由だと定義した。つまり、個人が自分の信念を述べたり、出版したりすることを政府は止めることはできないが、いったん口にすれば、それが禁止されているたぐいの言論の場合は、処罰の対象になることを意味する。英国人は、古代ギリシャ人と同様に、3つの種類の演説を法律で規制していた。それは扇動「sedition」(政府への批判)と名誉棄損「defamation」(個人への批判)と冒涜「blasphemy」(宗教への批判)であり、これらはすべて「誹謗」(libel)と呼ばれていた。これら3つの中で、政治的自由に最も深く関わっているのが、扇動的誹謗である。なぜなら、ブラックストーンの時代の支配層は、政府や官吏に対する批判は、たとえそれが真実であっても、政府への信頼を傷つけ、ひいては公共の秩序を乱すと信じていたからだ。ブラックストーンによれば、政府は、政府批判の口封じをすることはできないが、実際に批判をした後なら、その当事者を罰することは可能だった。
17世紀と18世紀を通じて、英国国王は、扇動的誹謗罪で数百件の事件を摘発し、しばしば恐るべき刑罰を科した。ウィリアム・トワインは、国民には政府に反抗する権利があると宣言したことで逮捕され、扇動罪と「国王の死を想像した」罪で有罪となった。裁判所は、トワインを絞首刑に処し、去勢し、はらわたを抜き、四つ裂きにしたうえで、首をはねるように命じた。公の場で発言した後、このような刑罰を受ける可能性があるとすれば、事前に言論規制がなくても、それはほとんど意味がなかった。
北米に移住した英国人は、英国の法律を持ち込んだ。しかし、入植後の早い時期から、法の理論と実践、つまり、法律の文面と法律の実際上の運用の間に、食い違いが生じた。各植民地の議会は、言論を統制する法律をいくつも成立させたが、国王総督も、各地の裁判所も、さほど厳格にその規定を適用しなかったようだ。ジョン・ピーター・ゼンガー(「出版の自由」の章で詳述)の著名な裁判によって移民たちは、扇動的誹謗罪の容疑をかけられても、その真実性を争うことができるようになった。今もなお、政府や官吏を批判した人が告発されることはあり得ることだが、被告人は、その批判が真実に基づくという証拠を提出できるようになり、その証拠が正当かどうかの判断は、陪審団の判断に委ねられている。
1791年、合衆国憲法修正第1条(議会は、言論の自由、出版の自由を制限する法律を制定してはならない)を各州が批准したときから第一次世界大戦までに、議会が成立させた言論統制の法律はわずかにひとつ、1798年の扇動防止法(the Sedition Act of 1798)だけだった。これはフランスとの準戦争状態から生じた不備の法律で、3年後には失効した。この法律は当然、各方面から非難されたが、真実性を弁護の理由に認める条項が盛り込まれていたことは、明記すべきである。1861年から1865年の南北戦争中にも、扇動を対象とする細かい規制はいくつかあった。しかし、合衆国憲法修正第1条の言論の自由条項の議論が本格化するのは、1917年の防諜法(the Espionage Act of 1917)と、1918年の扇動防止法(the Sedition Act of 1918)が成立してからである。この論議は公の場で行われ、国民、連邦議会、大統領が参加したが、とりわけ裁判所で大々的に繰り広げられることになった。
連邦最高裁判所で争われた最初のいくつかの裁判は、軍の統制を維持し、政府批判を封じるための戦時中の施策を審理したもので、連邦最高裁判所は当初、これらの施策を承認した。言論の自由は原則だが絶対ではなく、時代によって、とりわけ戦時には、公共の利益のために言論を制限することもできる、と判事たちは考えていたようだ。
「シェンク対合衆国政府事件」(1919年) 「ちらし(パンフレット)で言っていることは、すべて憲法上の権利の範囲内にあるという被告人の言い分は、多くの場所において、平時であればその通りだということはわれわれは認める。しかしあらゆる行為の性格は、それがなされた状況によって変わってくる。言論の自由を最も厳格に擁護したとしても、劇場でウソをついて火事だ!と叫び、パニックを起こす自由は誰にも保障されないだろう。どの訴訟でも問題となるのは、言葉が発せられた状況と、その言葉の性格である。すなわちそれが、明白かつ現在の危険を生じさせるものかどうかである。そのような害悪は、議会の権限をもって阻止されなければならない。言い換えればそれは、切迫性とその度合いの問題である。国が戦争をしているときには、平時には許されたような多くの発言が、国の努力の大きな妨げになることがある。同胞が戦っているとき、そのような発言は許容できないし、いかなる裁判所も、そのような発言を、憲法が擁護する権利と見なすことはできないだろう」 |
ホームズ判事が、「明白かつ現在の危険」を判断基準にしたことは、非常に道理が通っているように見える。確かに言論は自由であるべきだが、それは絶対的な自由ではない。(混雑した劇場で「火事だ!」と叫ぶ人を罰することは当然だという)良識や、戦争という切迫した状況に照らして、言論を制約することが必要になる。この「明白かつ現在の危険」という判断基準は、それから50年近くにわたり、裁判所によって何らかの形で適用されることになる。これは言論の自由の限界を超えたかどうかを判断する上で、便利でわかりやすい基準だったようだ。しかしこの基準をめぐっては、当初から疑問の声があった。米国では言論の自由の伝統は非常に強かったため、政府が反戦派たちを規制しようとしたり、裁判所がそのような措置を容認しようとしたりすることに対して、直ちに批判が噴出した。
言論の自由の歴史上、偉大な代弁者の1人が、温厚なハーバード大学法学教授ゼカリア・チェイフィー・ジュニアである。裕福で社会的に著名な一門の出である教授は、すべての国民が政府の報復を恐れることなく自分の考えを発言する権利を守るために生涯を捧げた。チェイフィー教授は、たとえ戦時体制下で国民感情が高揚しているときでも、自由な言論は守られるべきだという、多くの人々にとって当時も今も急進的と捉えられる考えを述べた。なぜなら、そういうときにこそ国民は、単に政府が国民に言いたいことだけではなく、賛否両論を聞く必要があるからである。
言論の自由(1920年) 「戦時体制下であり、しかも憲法が議会に徴兵権限を与えていることを理由に、自由な言論を無視することもまたできない。合衆国憲法修正第1条は、戦火をくぐりぬけてきたばかりの人たちによって起草された。ここに込められた意味があるとすれば、憲法が議会に特別に付与した権限を制限すべきだ、ということである。というのも、議会はそれ以外の権限は与えられていないからである。そしてこのことは、自由な討論に最も介入しがちな政府の活動、すなわち、郵政事業と戦争行為に適用するべきである」 「言論の自由が本来意味することは、以下のような考えであろう。つまり、社会と政府の重要な役割のひとつは、国民の関心事についての真実を突き止め、それを広く知らせることである。これは、制約がまったくない議論を通じてのみ、実現可能である。なぜなら・・・いったん議論に圧力がかかると、それが誤った側に導かれるか、あるいは正しい側に導かれるかは、偶然に支配されることになる。そして真実は、本来の優位性を失うことになる。しかし、政府にはこの他に別の役割がある。それは秩序の維持、若者の育成、外敵からの攻撃に対する防衛などである。制約のない討論は、時にはこうした政府の役割に干渉することになる。したがって言論の自由と均衡をとる必要が生じるが、その場合も、言論の自由には、非常に大きな重みを置かなくてはならない。合衆国憲法修正第1条は、この政治的な英知の原則に拘束力を与えている」 「従って、戦争行為に直接的かつ危険な影響を及ぼす可能性が明らかでない限り、戦時体制下でも言論は自由であるべきである」 |
チェイフィー教授はこれより前にも、論文でこうした考えを述べていた。そしてシェンク事件でのホームズ判決後に、教授はホームズ判事と面会し、判事が間違っていることを納得させた。この判決後、同じ年に続けて連邦最高裁判所に別の誹謗罪事件が提訴されたとき、法廷は多数決で、「明白かつ現在の危険」という判断基準に照らして、被告人を扇動的誹謗罪で有罪とした。しかし驚いたことに、その基準を作った本人(ホームズ判事)は、その同僚ルイス・D・ブランダイス判事とともに、強い反対意見を表明した。
「エイブラムズ対合衆国事件」(1919年)での反対意見 「意見の表明により告発されることは、私にはまったく論理的だと思える。もし自分の見解や権力に何の疑いも持たず、ある結果を心から欲するなら、当然その望みを司法で表明し、あらゆる反対を一掃するだろう。反対意見を許すということは、その反対を『丸いものを四角にした』というのと同じくらい無力なものと考えているか、あるいは、どんな結果になろうとまったく気にしないか、あるいは、自らの権力や見解を疑っているときであろう。しかし、時の流れとともに、多くの勇ましい信条が次々と覆されてきたことに気がつけば、自分自身の行動の基盤と信じる以上に、人が望みうる究極の効用は、さまざまな考えの自由な交換を通じて、よりよく達成できるということを、深く信じるようになるかもしれない。すなわち、真理か否かの最良の判定は、その考え方が市場競争の中で受容される力を備えているかどうかであり、また、真実を基盤としてのみ、人々は願望を無事に達成できるのである。いずれにしても、それがわれわれの憲法の論理である。人生がみな実験であるように、これもひとつの実験である。毎日のことではなくても、われわれは毎年のように、不完全な知識に基づく預言のようなものに、救済を託さなければならない。そのような実験は、われわれの社会システムに組み込まれてはいるが、永遠に警戒を怠ってはならない。われわれが嫌悪し、万死に値すると思うような意見を規制しようとする試みに対する警戒である。その例外は、緊急な法律上の目的に対する直接の妨げとなる恐れが差し迫っており、米国を救うために直ちに規制する必要がある場合のみである。私は、合衆国憲法修正第1条が、扇動的誹謗罪についてはコモンローをいまも有効としている、という政府の主張に全面的に反対する。私の見るところ、歴史も、政府側の見解を否定している。合衆国は、1798年の扇動防止法に基づいて課した罰金の返還を通じて、長い時間をかけて後悔の念を表してきたと私は考えてきた。『議会は、言論の自由を制約する法律を制定してはならない』という包括的規定に例外を認めることができるのは、邪悪な助言の是正を遅らせ、直ちに危険が生じるという緊急の場合のみである。ここで私が論じていることは、もちろん、意見や主張の表明についてであり、それ以外については述べていない。私の信念をもっと強い言葉で言い表せないのは残念だが、このような告発による有罪判決によって、被告人は、合衆国憲法に基づく権利を剥奪されたのである」 |
エイブラムズ事件でのホームズ判事の反対意見はしばしば、連邦最高裁判所が言論の自由を民主主義社会における重大な権利としてとらえ始めた兆候と見なされている。これによって、民主主義は思想の自由市場で支えられているという考えが提示されたのである。思想によっては、不人気なものも、秩序を揺るがすものも、間違ったものもあるかもしれない。しかし民主主義の下では、これらすべての思想に平等な発言の機会を与えるべきである。間違ったもの、恥ずべきもの、役立たずのものは、民主的な形で進歩を促す正しい思想によって駆逐されると信じるからである。ホームズ判事の言う自由市場の例えは、今なお多くの国民が賞賛している。なぜならこれは、知的自由を支援しているからである。
「思想の市場」という論理は、民主主義の土台のひとつである。国民の決定権も関連している。200年前、トーマス・ジェファソンは、なすべきことを国民が自分で賢明に選択することが民主主義の基盤だ、と信じていた。支配者ではなく国民が、自由に討議し、自由選挙を行うことによって、日々の重要な決定をすべきである。ある集団が、有害なことを考えているとして表現を阻まれれば、次には国民全体も、最善の結論を得るために必要なさまざまな事実や論理に接する機会を奪われるだろう。
ホームズ判事も、ほかの誰も、言論の自由には制限がないとは言わなかった。むしろ、この後すぐに取り上げるが、過去数十年に行われた論争のほとんどが、守られるべき言論と、守られない言論の間の、どこに一線を引くのかという問題に関するものだった。論争の核心には、「この種の言論に、なぜ憲法の保障の傘を差しのべなければならないのか」という疑問があった。意見の一致がほぼ得られている唯一の領域は、合衆国憲法修正第1条の言論の自由条項が、ほかに何を保障するにせよ、少なくとも政治的な発言を保障しているという点である。なぜなら、ジェファソンとマディソンがよく理解していたように、自由な政治的意見の表明なしに、民主的な社会は存在しえないからだ。この見解の論拠であり、また恐らく米国史上で最も偉大な言論の主張が、ルイス・D・ブランダイス判事が、州の扇動的誹謗法がらみの訴訟で述べた意見である。
連邦最高裁判所の多数意見は、明白かつ現在の危機という基準を使って、カリフォルニア州の扇動的誹謗法を合憲と認めた。その理由として多数意見は、「公共の福祉に害をもたらす発言、犯罪を煽る発言、公共の秩序を乱す発言、ないしは、政府組織を根底から揺るがし、その転覆を謀るような発言」によって言論の自由を乱用した者を、州政府は処罰する権限を持つと認めた。ブランダイス判事は、ホームズ判事とともに、この判断に異議を唱えた。ブランダイス判事はその反対意見の中で、合衆国憲法修正第1条と政治的な民主主義を結びつける線を引き、後にカルドーゾ判事が書いたように、言論の自由は、「そのほかの自由の権利のために欠かせない条件」だと位置づけた。
「ホイットニー対カリフォルニア州事件」(1927年) 「これらの問題について、健全な結論を得るために、念頭に置くべきことがある。それは、市民の大多数がまやかしだと思い、また、有害な結果を招く可能性をはらんでいると考える、社会的、経済的、政治的な主義主張を、なぜ政府は禁止する権限を持たされていないのかということである・・・」 「合衆国の独立を成し遂げた人々は、国家の究極の目的は、国民が自由に能力を発揮できるようにすることだと考えていた。そして政府の中では専制的な人たちではなく、協議して慎重に物事を進めて行く人たちが優先されるべきだ、とも彼らは考えていた。彼らは、目的としても手段としても、自由に価値を置いていた。自由が幸せの秘訣であり、そして勇気が自由の秘訣である、と信じていた。自分の意のままに考える自由と、意のままに自分の考えを発言する自由は、政治的真実を発見し広めるために不可欠な手段だと彼らは信じていた。言論と集会の自由がない限り、議論は不毛になる。それらの自由があればこそ、議論によって、たいていは有害な主義主張の流布を防止できる。自由に対する最大の脅威は、人々の無気力だ。公共の場での議論は政治的な義務であり、それこそが、米国政府の基本原則であるべきだ。独立を成し遂げた人々は、こう信じていたのである。彼らは、人間が作ったすべての組織が陥りやすい危険を認識していた。しかし、秩序というものは、違法行為に対する処罰への恐れだけでは守れないことも、彼らは知っていた。そして、思想や希望、創造力を押さえ込むのは危険の元であること。恐怖が抑圧を招くこと。抑圧が憎悪を生むこと。憎悪が政府の安定を揺るがすこと。安全への道は、苦情の申し立てと、救済策について自由に論じる機会の中にあること。そして、邪悪な意見を是正するにふさわしいものは善良な意見であるということ。こうしたことを、すべて彼らは知っていた。彼らは、公の議論を通じて働く理性の力を信じ、法によって強制される沈黙を嫌った。なぜならそれは、最悪の形の議論の押しつけだからである。多数派政権が、ときには暴君と化すことを知る彼らは、憲法を修正し、言論と集会の自由が保障されるようにしたのである」 「重大な被害がもたらされる恐れがあるというだけで、自由な言論と集会への抑圧を正当化することはできない。人々は魔女を恐れ、女性を火あぶりにした。ばかげた恐怖の束縛から人々を解放するのが、言論の機能である。自由な言論への抑圧を正当化するには、自由な言論を行った事により重大な害悪が生じるという合理的根拠がなければならない。感知した危険が切迫している、と信じるに足りる合理的根拠が必要となる。さらに、予防すべき害悪が重大なものであることを信じるに足る、合理的根拠がなければならない・・・」 「革命によって独立を成し遂げた人々は、臆病者ではなかった。彼らは、政治的変革を恐れなかった。彼らは自由を犠牲にしてまで、秩序を重んじようとはしなかった。勇敢で自立心にあふれた彼らは、国民政府樹立の過程で発揮された、自由で大胆な論理的思考の力を信じていた。その彼らにとっては、懸念される害悪の発生が余りにも切迫しており、十分に議論する間もなくその危険が降りかかるかもしれない場合でない限り、言論から生じるどのような危険も、明白に存在するものと見ることはできなかった。議論を通じて、虚偽や誤りをあぶり出す時間があれば、また教育のプロセスを通じて、邪悪を回避する時間があれば、講じるべき解決策は、強制された沈黙ではなく、より多くの言論である。言論抑圧を正当化できるのは、緊急事態のみである。もし権力と自由の間に折り合いをつけるとすれば、そのような原則にしなければならない。私の意見では、それこそが憲法が命じていることである。それゆえ、自由な言論と集会を規制する法律に対して、米国民はいつでも、それを正当化する緊急性がないことを示すことによって、反論する道が開かれているのである」 |
ブランダイス判事にとって、民主主義国家において最も重要な役割は、「市民」の役割であり、その役割の責任を果たすために市民は、重要な問題については誰もが公共の議論に加わる必要があった。意見の開陳や、不人気な意見の表明を恐れていれば、その役割は果たせない。また、さまざまな意見を持つほかの人々が、それぞれの信念を自由に語れなければ、あらゆる選択肢を比較検討することはできない。従って言論の自由は、民主主義の過程の核心にある。
この真実は、あまりにも明白である。それだけに、米国で、これがあまねく受け入れられていないのはなぜだろう、と不思議に思うかもしれない。その理由を見出すのは難しくない。不人気な考えを擁護するためには、市民としての勇気を要するからである。ホームズ判事やブランダイス判事も指摘したように、多数派の人々が、既成の観念に挑戦する意見を聞きたいなどと望むことはめったにないからである。憲法の起草者たちが合衆国憲法修正第1条を草案したのは、まさに多数派が、反対派を沈黙させようとするのを防ぐためだった。自由な思想の原則は、ホームズ判事が書いた有名な言葉にもあるように、「われわれに同意する人々のためではなく、われわれが嫌悪するような考え方のための自由な思想」なのである。
これは、簡単な概念ではない。戦時のような非常時に、民主的手段とはいえ、民主主義の土台を攻撃しようとする人々にそうした行動を認めるのは、容易ではない場合が多い。実際、ホームズ、ブランダイス両判事が残そうとした教訓も、冷戦時代の初期には失われたかに見えた。1940年代末、政府は、力による政府転覆を提唱し、その主張を広める謀議を行ったとしたとして、米国共産党の指導者を起訴した。連邦最高裁判所判事の多数は、1920年代以来、合衆国憲法修正第1条の言論の自由をますます擁護するようになってきたと見られていたが、この裁判では、明らかに姿勢が後退した。連邦最高裁判所は、米国共産党員の主張が、明白かつ現在の危険をほとんどもたらすものではないと認めたものの、共産党員の主張には、社会秩序を破壊する可能性のある「有害な傾向」が見られると裁定した。
一世代前、ホームズ、ブランダイス両判事が、世間の評判が悪い社会主義者たちを擁護したように、今度はヒューゴ・ブラック判事とウィリアム・O・ダグラス判事が、表現の自由と少数派の権利を擁護する守護者の立場に回った。
「デニス対合衆国事件」(1951年)での反対意見 「言論の自由でさえ、憲法上の保護の特権を失うときがある。ある年には無害だった言論が、次の時には、余りにも破壊的な炎を煽ることになってしまい、共和国の安全を守るために、それを差し止めなければならないという事態にもなるだろう。これが、明白かつ現在の危険という基準の意味である。状況が極めて切迫し、その言論によって生じる害悪を避ける猶予がなくなった場合は、言論を差し止めるべきだ。さもないと、国家の強みであるはずの言論の自由が、それを破壊する原因になるだろう。とは言うものの、自由な言論はあくまで原則であり、例外ではない。自由の抑制を合憲と見なすためには、単に恐れを抱いたとか、その言論に対して感情的な反感を持ったというだけでは不十分であり、その言論の内容に対する強い嫌悪感を超えた根拠が必要である。もしその言論を許せば、即座に社会に及びそうな実害がなければならない・・・」 「米国では、(共産主義者は、)人々が望まない思想を売る惨めな商人である。ご覧の通り、彼らの商品は売れ残ったままである。もし司法上の留意に基づいて考えるとすれば、私はこの米国の共産主義者が、その言論を理由に抑制されなければならないほど支配力があるとは思えないし、優れた戦略を展開しているとも言えない。これが、司法上の留意に基づく判断に際しての私の見解である。しかし、こうして反対意見を表明するだけでも、行動する前に事実を知ることがどれほど大切なことかが判る。単なる偏見や憎悪、無意味な恐怖を、この重大な判断の根拠にしてはならない。言論で主張された害悪が切迫しているという危険について、明白で客観的な証明がない限り、言論の自由を犠牲にしてはならない」 |
冷戦時がもたらしたヒステリックな状態が過ぎ去ると、ホームズ判事とブランダイス判事が、そして後には、ブラック判事とダグラス判事が主張したことの中に、英知のあることが理解されるようになった。「悪い」言論への治療は、抑圧ではなく、「良い」言論である。つまり、一連の思想を別の思想で駆逐するということである。確かに今日の世界で、正しく適切だと思われている多くの事柄が、かつては異端とされていた。例えば、奴隷制の廃止や婦人投票権などである。多数派は、自分たちが大事にしている信念を攻撃する過激な思想に対して、常に不快感を抱く。憲法に関する限り、言論は、どれほど不人気のものであっても保護されなければならないということが、米国の民主主義の方針である。1969年、連邦最高裁判所は最終的に、扇動的誹謗という考え方全体に終止符を打った。そして、多数派が破壊的だと糾弾するような思想を主張した者が訴追される可能性は、なくなった。
米国のベトナム介入に対する抗議運動が最高潮に達した頃、自由の擁護派の多くは、米国が戦争状態にあることで、第1次大戦や冷戦中に起きたように、またしても抑圧的な力が野放しになるのではないかと考えていた。最悪の事態を恐れた多くの人々にとって意外なことに、米国はこうした抗議を冷静に切り抜けることができた。だからと言って国民が皆、抗議の声に同調したわけではないし、そういう者たちの一部を黙らせ、投獄してしまうべきだと考えた人がいなかったわけではない。むしろ国民は、民主主義の国では、時には無作法な態度をとったりしても、人々に抗議する権利があることを認めたのである。米国は東南アジアの一角に介入すべきかどうかをめぐって起きている重大な議論の中では、あらゆる声に耳を傾けなければならない、ということを受け入れたのである。
13才のメアリー・ベス・ティンカーをはじめ、アイオワ州デモインの高校生たちは、ベトナム戦争反対のシンボルの黒い腕章をつけて登校した。学校当局は、生徒たちのこの行動が授業を妨害したという理由で、彼らを停学処分にした。しかし実際には、そうした妨害はまったく起きていなかった。学校側が心配したのはむしろ、校内での反戦デモを学校が容認しているように見られた場合の、町当局の反応だった。
ベトナム戦争をきっかけに提訴された非常に重要な裁判の中で、連邦最高裁判所は、政治的な言論に関する限り、高校生たちは、学校の校門をくぐってからも憲法上の権利を失うことはない、と裁定した。むしろ学校が真に市民を養成するための場であるなら、生徒たちにもまた、俗受けしない政治的見解を述べる権利があり、それを学校当局から罰せられることはない、ということを自ら学ぶ機会を持つことが必要なのである。
「独自の活動をする10代のグループがあり・・・私たちは、こういう黒い腕章をつけて、学校へ行くことに決めた。そのころ(1965年)までに、ベトナム戦争に反対する運動が広がり始めていた。その後の運動の様子とは比べものにならないけど、全米でかなり大勢の人が反戦運動に参加していた。すべてが刺激的だったことを覚えている。この素晴らしい考えに加わろうと、誰もが集まってきていた。私はまだ子供だったけど、それでも反対運動の大事な一員だと思われていた。これは大人だけの運動ではなかった。子供たちも尊重されていた。私たちが何か発言することがあると、ちゃんと耳を傾けてもらえた」 「そこで私たちは、こういう腕章をつけて登校するというささやかな行いを計画した。計画は順調に進み、それが大問題になるとはまったく想像もしなかった。これまでにも、こういう小さなデモ活動をしてきて何の事件にもならなかったので、これほど大ごとになるとはまったく思いもしなかった」 「私たちが腕章をつけて登校しようとした前日、代数のクラスで、その話題がどういうわけか持ち上がった。それを知った(男の)先生はカンカンに怒り出し、このクラスの中で腕章をつけて登校するものがあればクラスから追い出す、と言った。その次に知ったのは、教育委員会が腕章着用を禁止する方針を決めたことだった。そして腕章をつけた生徒は、停学処分を受けるのだという・・・」 「翌日私は登校し、午前中ずっと腕章をつけていた。生徒たちはそのことでうわさ話をしていたが、皆好意的で、冷たくする人はいなかった。昼食後私は代数の授業を受けに教室へ入り、席に着いた。先生が教室に入ってきたとき、そこでも皆ひそひそ話をしていた。生徒たちには、次に何が起こるのかわからなかった。すると先生は教室のドアのところに来て、メアリー・ティンカー、廊下に出なさい、と言った。そして私は校長室に呼ばれた」 「校長先生は、敵意丸出しだった。そして学校側は、私を停学処分にした」 〔この一節は、フリープレス(サイモン&シュースター・アダルトパブリッシンググループの一部門)の許可のもと、ピーター・アイアンズ著”The Courage of Their Convictions”(著作権:1988 Peter Irons)から、転載した。〕
|
それから何年も後に、この時とは別の大統領の外交政策に反対する人々が、抗議活動で星条旗を焼き、即座に逮捕された。彼らは、自分たちの法律的立場を弁護し続け、事件は最終的に連邦最高裁判所に持ち込まれた。連邦最高裁判所はその判決で、被告たちの行為は、大抵の米国人にとって言語道断の行いではあるが、やはり「象徴的な政治的言論」にあたり、従って合衆国憲法修正第1条により擁護されると判断した。この裁判で、恐らく最も興味深い意見は、保守派のアンソニー・ケネディ判事のものだろう。ケネディ判事は、自分を含む何百万人の米国人が、旗を焼くという行為に不快感を覚えたとしても、法廷は被告たちを無罪放免にしなければならなかったとして、その理由を次のように述べた。
「テキサス州対ジョンソン事件」での同意意見(1989年) 「われわれ判事が、時には、自分たちの望まない判断を下さなければならないというのは厳然たる事実である。そのように決定するのは、それが正しいからである。正しいという意味は、法と憲法に鑑みて、そう結論せざるを得ないという意味である。われわれは、この法的手続きを余りにも重視しているため、きわめて稀な事件でない限り、わざわざ結論に対する不満を表明することはしない。恐らくそれは、判断を左右する価値ある原則をそこなうことを恐れてのことである。しかし今回の事件は、その極めて稀な事件のひとつである・・・」 「象徴とは往々にして、人それぞれが作り出すものだが、星条旗は、米国人が共有する信条、法と平和への信奉、そして人間の精神を支える自由を、一貫して表現し続けている。今日ここで審理されている事件は、こうした信条には抜き差しならない代償が伴うことを、いやおうなく認識させるものである。星条旗は、それに侮蔑の念を抱く者さえも守っている。これは実に痛恨のきわみだが、曲げられない原則なのである」 |
この判断に対しては激しい抗議があったが、良識ある声が聞かれるようになるにつれ、それも時間とともに収まった。そして言論の自由を守るために、最も辛い思いをしたのは、ベトナム戦争での元米国人捕虜、ジェームズ・H・ウォーナーである。
ワシントンポスト紙への投稿(1989年7月11日) 「私は、(ベトナムでの捕虜の生活から解放され)飛行機から降り立ったとき、視線を上げて星条旗を見つめた。私は息をのんだ。涙が目にあふれてきたが、私は敬礼した。その瞬間ほど、祖国を愛していると思ったことはなかった。・・・私は自由に関しては、妥協できない。星条旗が焼かれるのを見ると傷つく。しかし、星条旗を焼く者たちを罰せよ、と主張する人たちには賛成しない・・・」 「私は、(北ベトナム軍から)受けた尋問の中で、反戦を訴えて旗を焼いている米国人の写真を見せられた時のことを覚えている。『どうだ!』と将校は言った。『おまえの国の連中が、おまえの信じている大義に抗議している。ということは、おまえが間違っている証拠だ』と言った」 「『それは違う』と私は言い返した。『その写真は、私が正しいことの証明だ。私の国では、たとえ自分の意見に反対する人が出現しても、自由であることを恐れないのだ』と説明した。将校は急に立ち上がった。顔は怒りで紫色に変わっていた。拳をテーブルに叩きつけ、『黙れ!』と私を怒鳴りつけた。わめき散らしている将校の目の中に、恐れの混じった苦痛の色を見て、私は驚いた。私はその表情を忘れることができない。また、将校が持ち出した小道具、すなわち星条旗を焼いている写真を逆手に取ってやった満足感も忘れない・・・」 「星条旗を焼く人を処罰するために、憲法を修正する必要はない。彼らが旗を焼くのは、米国を憎んでいるから、自由を恐れているからである。自由という破壊的な思想以上に、彼らを苦しめる効果的な方法はあるだろうか。自由を広めよ。・・・自由を恐れるな。それこそ、われわれが持てる最も有効な武器なのである」 |
悪しき言論に対抗するには、いっそう活発な言論が必要で、言論によって人々が学び、討論し、選択できる機会が与えられるのだ。この70年以上も前にブランダイス判事が残した教訓が、ここで実を結んだのである
もし一般の人々が、制約のない政治的な言論という考えを受け入れるならば、そのほかの表現の形態についてはどうなのだろうか。ヒューゴ・ブラック判事(1937年~1971年在任)が主張したように、合衆国憲法修正第1条が禁じていることは絶対であり、政府はどのような形の言論であっても、検閲したり罰したりすることはできないのだろうか。あるいはある種の言論表現は、言論条項の保護の傘から外れるのだろうか。作家や、芸術家やビジネスマン、偏屈な人やデモ参加者、インターネットの発信者たちは、憲法上の保護を主張して、どんなに攻撃的で人々を動揺させることでも、好きなように発言していいのだろうか。これらの質問に対する簡単な回答はない。国民の合意もなければ、すべての分野の言論における連邦最高裁判所の絶対的な判断もない。国民の感情が変わるにつれて、米国がより多様化し開かれた社会になるにつれて、そしてまた新しい電子技術が米国の生活のすみずみまで行き渡るにつれて、合衆国憲法修正第1条の意味合いも、これまでもしばしばそうであったように、とりわけ政治以外の分野の言論表現をめぐり、再び流動的になっているように思われる。
1940年代の初め、連邦最高裁判所は、かなり断定的な文言で、合衆国憲法修正第1条はわいせつな言論や誹謗する言論、好戦的な言葉、あるいは商業目的の言語の自由は保障していないと言い切った。それでも過去数十年の間に、連邦最高裁判所がこれらすべての争点について審理し、完全な保護に至らないまでも、多くの側面を言論の自由条項の保護の下に置いたのは確かである。これらの連邦最高裁判所判断に、批判がなかったわけではない。そして、連邦最高裁判所がこれらの分野の問題に取り組むのと時を同じくして、公共の場で行う論評の領域でも、混乱や反論が出始めていたといって差し支えないだろう。これもまた当然のことである。連邦最高裁判所が判断を下し、それに国民を従わせることなどできない。むしろ連邦最高裁判所は、しばしば変化し続ける社会的、政治的な慣習の反映である。連邦最高裁判所判事たちは、憲法起草者のそもそもの意図は何だったのかについて模索する一方で、その憲法起草者の精神を、現代生活の現実に当てはめることを試みなければならない。これが比較的容易にできるときもある。しかし、星条旗を焼いた事件などの際のように、困難で議論を呼ぶ見解を連邦最高裁判所が判決で示す時でさえ、どうしてそのような判断が必要だったのか、そしてそれが複雑多彩に織り成した現代生活の中のどこにあてはまるのかについて、何らかの国民的な理解の蓄えが必要である。
連邦最高裁判所と国民にとって難しい課題は、守られる言論と、守られない言論の間のどこに線引きをするかである。たとえば、わいせつなどの分野では、法的な区分線を引こうする努力に、国民の支持は得られていない。なぜなら、わいせつという概念自体が客観的ではなく、簡単に定義できる主題ではないからだ。連邦最高裁判所が言及したように、ある人にとってのわいせつ文書も、別の人にとっては抒情詩かもしれない。ある人を不快にさせても、ほかの人は不快ではないかもしれない。しかしそのような表現は、合衆国憲法修正第1条が守ろうとした種類のものなのだろうか。芸術上の表現は、とりわけ目下の美的感覚や道徳的規範に反する時には、憲法立案者が合衆国憲法修正第1条による保護を意図した種類の表現なのだろうか。
これらと同様に、米国では、金銭が選挙制度に及ぼしているとされる腐敗作用についても、かれこれ20年以上も議論が続いてきた。選挙運動のための資金集めとその使い方を規制し、あらゆる献金者が1人で出すことのできる金額に上限を設けようとする努力は、これまでにも幾度となく行われてきた。しかし連邦最高裁判所は何年も前に、金銭もある意味では言論と同じであり、たとえば、政治的な思想の表現を推し進めるために資金が使われた場合、それを規制することはできないという判断を示した。ここでもまた、公正な選挙など、同じくらい重要とされる民主主義的な他の概念と正面衝突することなく、言論の自由の観念を、どこまで拡大することができるのかが問題になる。
米国民および米国の司法制度が直面する、恐らく最も気の遠くなるような大仕事は、合衆国憲法修正第1条を、どのようにして最新の電子技術に適用していくかである。世界中をつなぐインターネットは、ホームズ判事が述べた「思想の市場」の新しい事例にすぎないのだろうか。やがて世界中のどこの家庭でも、インターネット上の情報にいくらでもアクセスできるようになりそうだ。そして、だれでも自分の言いたいことを、ネットを通じて世界中に伝えることができるようになる可能性は高い。その時、合衆国憲法修正第1条は、時代にそぐわないものになってしまうのだろうか。
米国内では、こうしたさまざまな疑問が法廷で、議会の公聴会で、大統領府の諮問委員会で、大学で、公開フォーラムで、そして家庭の中で議論され続けている。国民の権利の中で、言論の自由ほど大切にされているものはほかにない。そしてまた、意見の変化にこれほど影響を受けやすいものもほかにない。しかしながらブランダイス判事が指摘したように、国民が持つ市民としての責任は、不人気な意見を提示するだけでなく、ほかの人たちが語る信条を聞く機会をも持つことでもある。そうすることにより、最終的に、民主主義のプロセスが機能することを、大多数の国民は認識している。そして国民は、ホームズ判事の考え方を常に快く感じているわけではないが、合衆国憲法修正第1条は、われわれが同意する言論ではなく、われわれが憎悪する言論を守るために存在する、という同判事の言葉には真実があることを認めている。
参考文献:
- Lee C. Bollinger & Geoffrey R. Stone, Eternally Vigilant: Free Speech in the Modern Era (Chicago: University of Chicago Press, 2002)
- Zechariah Chafee, Jr., Free Speech in the United States (Cambridge: Harvard University Press, 1941)
- Michael Kent Curtis, Free Speech: The People’s Darling Privilege (Durham: Duke University Press, 2000)
- Harry Kalven, A Worthy Tradition: Freedom of Speech in America (New York: Harper & Row, 1988)
- Cass R. Sunstein, Democracy and the Problem of Free Speech (New York: The Free Press, 1993)
*上記の日本語文書は参考のための仮翻訳で、正文は英文です。
Freedom of Speech
(The following article is taken from the U.S. Department of State publication, Rights of the People: Individual Freedom and the Bill of Rights.)
Congress shall make no law . . . abridging the freedom of speech....
– First Amendment to the U.S. Constitution
If there is one right prized above all others in a democratic society, it is freedom of speech. The ability to speak one's mind, to challenge the political orthodoxies of the times, to criticize the policies of the government without fear of recrimination by the state is the essential distinction between life in a free country and in a dictatorship. In the pantheon of the rights of the people, Supreme Court Justice Benjamin Cardozo, who served from 1932 to 1938, wrote of free speech that it is "the matrix . . . the indispensable condition of nearly every other freedom."
If Americans assume that free speech is the core value of democracy, they nonetheless disagree over the extent to which the First Amendment protects different kinds of expression. Does it, for example, protect hate speech directed at particular ethnic or religious groups? Does it protect "fighting words" that can arouse people to immediate violence? Is obscene material covered by the First Amendment's umbrella? Is commercial speech – advertisements or public relations material put out by companies – deserving of constitutional protection? Over the last several decades, these questions have been part of the ongoing debate both within the government and in public discussion, and in many areas no consensus has yet emerged. That, however, is neither surprising nor disturbing. Freedom is an evolving concept, and, as we confront new ideas, the great debate continues. The emergence of the Internet is but the latest in a series of challenges to understanding what the First Amendment protection of speech means in contemporary society.
* * * * *
Freedom of speech was not always the all-encompassing right it is today. When Sir William Blackstone wrote his famous Commentaries on the Laws of England in the mid-18th century, he defined freedom of speech as the lack of prior restraint. By that he meant that the government could not stop someone from saying or publishing what he believed, but once a person had uttered those remarks, he could be punished if the type of speech was forbidden. The English, like the ancient Greeks, had established legal restrictions on three types of speech – sedition (criticism of the government), defamation (criticism of individuals), and blasphemy (criticism of religion) – each of which they called "libels." Of these three, the one that is most important in terms of political liberty is seditious libel, because ruling elites in Blackstone's era believed that any criticism of government or of its officials, even if true, subverted public order by undermining confidence in the government. While the government, according to Blackstone, could not stop someone from criticizing the government, it could punish him once he had done so.
During the 17th and 18th centuries, the British Crown prosecuted hundreds of cases of seditious libel, often imposing draconian penalties. When William Twyn declared that the people had the right to rebel against a government, he was arrested and convicted of sedition and of "imagining the death of the King." The court sentenced him to be hanged, emasculated, disemboweled, quartered, and then beheaded. Given the possibility of such punishment after publication, the lack of prior restraint meant little.
The English settlers who came to North America brought English law with them, but early on a discrepancy arose between theory and practice, between the law as written and the law as applied. Colonial assemblies passed a number of statutes regulating speech, but neither the royal governors nor the local courts seemed to have enforced them with any degree of rigor. Moreover, following the famous case of John Peter Zenger (discussed in the chapter on "Freedom of the Press"), the colonists established truth as a defense to the charge of seditious libel. One could still be charged if one criticized the government or its officials, but now a defendant could present evidence of the truth of the statements, and it would be up to a jury to determine their validity.
From the time the states ratified the First Amendment (Congress shall make no law…abridging the freedom of speech, or of the press…” in 1791, until World War I, Congress passed but one law restricting speech, the Sedition Act of 1798. This was an ill-conceived statute that grew out of the quasi-war with France and which expired three years later. Yet although this act has been widely and properly condemned, one should note that it contained truth as a defense. During the American Civil War of 1861-1865, there were also a few minor regulations aimed at sedition, but not until the Espionage Act of 1917 and the Sedition Act of 1918 did the real debate over the meaning of the First Amendment Speech Clause begin. That debate has been public and has involved the American people, Congress, and the President, but above all it has been played out in the courts.
The first cases to reach the Supreme Court grew out of these wartime measures aimed against disruption of the military as well as criticism of the government, and the Court initially approved them. The justices seemed to say that while freedom of speech is the rule, it is not absolute, and at certain periods – especially in wartime – speech may be restricted for the public good.
Justice Oliver Wendell Holmes, Jr., in Schenck v. United States (1919)
We admit that in many places and in ordinary times the defendants in saying all that was said in the circular [pamphlet] would have been within their constitutional rights. But the character of every act depends upon the circumstances in which it is done. The most stringent protection of free speech would not protect a man in falsely shouting fire in a theatre and causing a panic. The question in every case is whether the words used are used in such circumstances and are of such a nature as to create a clear and present danger that they will bring about the substantive evils that Congress has a right to prevent. It is a question of proximity and degree. When a nation is at war many things that might be said in time of peace are such a hindrance to its effort that their utterance will not be endured so long as men fight, and that no Court could regard them as protected by any constitutional right.
Holmes's test of a "clear and present danger" seemed to make a great deal of sense. Yes, speech ought to be free, but it is not an absolute freedom; common sense (the obvious need to punish someone who shouts the word "fire" in a crowded theater) as well as the exigencies of war make it necessary at times to curtail speech. The clear-and-present-danger test would be used in one way or another by the courts for nearly 50 years, and it seemed a handy and straightforward test to determine when the boundaries of speech had been overstepped. But there were problems with the test from the start, and the tradition of free speech in the United States was so strong that critics challenged the government's campaign against antiwar critics as well as the Court's approval of it.
One of the great voices in the history of free speech belonged to a mild-mannered Harvard law professor, Zechariah Chafee, Jr., the scion of a rich and socially prominent family who throughout his life defended the right of all people to say what they believed without fear of governmental retaliation. He suggested what to many people then and now is a radical idea – that free speech must be kept free even in wartime, even when passions are high, because that is when the people need to hear both sides of the argument, not just what the government wishes to tell them.
Zechariah Chafee, Jr., Freedom of Speech (1920)
Nor can we brush aside free speech by saying it is war-time and the Constitution gives Congress express power to raise armies. The First Amendment was drafted by men who had just been through a war. If it is to mean anything, it must restrict powers which are expressly granted to Congress, since Congress has no other powers, and it must apply to those activities of government which are most apt to interfere with free discussion, namely, the postal service and the conduct of war.
The true meaning of freedom of speech seems to be this. One of the most important purposes of society and government is the discovery and spread of truth on subjects of general concern. This is possible only through absolutely unlimited discussion, for . . . once force is thrown into the argument, it becomes a matter of chance whether it is thrown on the false side or the true, and truth loses all its natural advantage in the contest. Nevertheless, there are other purposes of government, such as order, the training of the young, protection against external aggression. Unlimited discussion sometimes interferes with these purposes, which must then be balanced against freedom of speech, but freedom of speech ought to weigh very heavily in the scale. The First Amendment gives binding force to this principle of political wisdom.
In war-time, therefore, speech should be free, unless it is clearly liable to cause direct and dangerous interference with the conduct of the war.
Chafee had made this argument earlier in articles, and, following Holmes's decision in Schenck, met with the jurist and convinced him that he had been wrong. When another sedition case came before the Court later that year, a majority used the clear-and-present-danger test to find the defendants guilty of seditious libel. But surprisingly, the author of that test, joined by his colleague, Justice Louis D. Brandeis, entered a strong dissent.
Justice Oliver Wendell Holmes, Jr., dissenting in Abrams v. United States (1919)
Persecution for the expression of opinions seems to me perfectly logical. If you have no doubt of your premises or your power and want a certain result with all your heart you naturally express your wishes in law and sweep away all opposition. To allow opposition by speech seems to indicate that you think the speech impotent, as when a man says that he has squared the circle, or that you do not care whole-heartedly for the result, or that you doubt either your power or your premises. But when men have realized that time has upset many fighting faiths, they may come to believe even more than they believe the very foundations of their own conduct that the ultimate good desired is better reached by free trade in ideas – that the best test of truth is the power of the thought to get itself accepted in the competition of the market, and that truth is the only ground upon which their wishes safely can be carried out. That at any rate is the theory of our Constitution. It is an experiment, as all life is an experiment. Every year if not every day we have to wager our salvation upon some prophecy based upon imperfect knowledge. While that experiment is part of our system I think that we should be eternally vigilant against attempts to check the expression of opinions that we loathe and believe to be fraught with death, unless they so imminently threaten immediate interference with the lawful and pressing purposes of the law that an immediate check is required to save the country. I wholly disagree with the argument of the Government that the First Amendment left the common law as to seditious libel in force. History seems to me against the notion. I had conceived that the United States through many years had shown its repentance for the Sedition Act of 1798, by repaying fines that it imposed. Only the emergency that makes it immediately dangerous to leave the correction of evil counsels to time warrants making any exception to the sweeping command, "Congress shall make no law . . . abridging the freedom of speech." Of course I am speaking only of expressions of opinion and exhortations, which were all that were uttered here, but I regret that I cannot put into more impressive words my belief that in their conviction upon this indictment the defendants were deprived of their rights under the Constitution of the United States.
Holmes's dissent in the Abrams case is often seen as the beginning of the Supreme Court's concern with speech as a key right in democratic society, and it put forward the notion of democracy as resting upon a free marketplace of ideas. Some ideas may be unpopular, some might be unsettling, and some might be false. But in a democracy, one has to give all of these ideas an equal chance to be heard, in the faith that the false, the ignoble, the useless will be crowded out by the right ideas, the ones that will facilitate progress in a democratic manner. Holmes's marketplace analogy is still admired by many people, because of its support for intellectual liberty.
The "marketplace of ideas" theory also relates to one of the foundations of democracy, the right of the people to decide. Two centuries ago, Thomas Jefferson based his belief in democracy upon the good judgment of the people to choose for themselves what would be the right thing to do. The people, and not their rulers, should decide the major issues of the day through free discussion followed by free elections. If one group is prevented from expressing their ideas because these notions are offensive, then the public as a whole will be deprived of the whole gamut of facts and theories that it needs to consider in order to reach the best result.
Neither Holmes nor anyone else has suggested that there are no limits on speech; rather, as we shall soon see, much of the debate in the last several decades has been over how to draw the line between protected and non-protected speech. At the heart of the debate has been the question, "Why should we extend the umbrella of constitutional protection over this type of speech?" The one area in which there has been general consensus is that whatever else the First Amendment Speech Clause covers, it protects political speech. It does so because, as Jefferson and Madison so well understood, without free political speech there can be no democratic society. The rationale for this view, and what remains as perhaps the greatest exposition of free speech in American history, is the opinion Louis D. Brandeis entered in a case involving a state seditious libel law.
A majority of the Court, using the clear-and-present-danger test, upheld California's seditious libel law as constitutional because, it held, the state has the power to punish those who abuse their right to speech "by utterances inimical to the public welfare, tending to incite crime, disturb the public peace, or endanger the foundations of organized government and threaten its overthrow." Brandeis, along with Holmes, disagreed, and in his opinion Brandeis drew the lines that connected the First Amendment to political democracy, and in fact made it, as Cardozo later wrote, "the indispensable condition" of other freedoms.
Justice Louis D. Brandeis, in Whitney v. California (1927)
To reach sound conclusions on these matters, we must bear in mind why a State is, ordinarily, denied the power to prohibit dissemination of social, economic and political doctrine which a vast majority of its citizens believes to be false and fraught with evil consequence.
Those who won our independence believed that the final end of the State was to make men free to develop their faculties; and that in its government the deliberative forces should prevail over the arbitrary. They valued liberty both as an end and as a means. They believed liberty to be the secret of happiness and courage to be the secret of liberty. They believed that freedom to think as you will and to speak as you think are means indispensable to the discovery and spread of political truth; that without free speech and assembly discussion would be futile; that with them, discussion affords ordinarily adequate protection against the dissemination of noxious doctrine; that the greatest menace to freedom is an inert people; that public discussion is a political duty; and that this should be a fundamental principle of the American government. They recognized the risks to which all human institutions are subject. But they knew that order cannot be secured merely through fear of punishment for its infraction; that it is hazardous to discourage thought, hope and imagination; that fear breeds repression; that repression breeds hate; that hate menaces stable government; that the path of safety lies in the opportunity to discuss freely supposed grievances and proposed remedies; and that the fitting remedy for evil counsels is good ones. Believing in the power of reason as applied through public discussion, they eschewed silence coerced by law – the argument of force in its worst form. Recognizing the occasional tyrannies of governing majorities, they amended the Constitution so that free speech and assembly should be guaranteed.
Fear of serious injury cannot alone justify suppression of free speech and assembly. Men feared witches and burned women. It is the function of speech to free men from the bondage of irrational fears. To justify suppression of free speech there must be reasonable ground to fear that serious evil will result if free speech is practiced. There must be reasonable ground to believe that the danger apprehended is imminent. There must be reasonable ground to believe that the evil to be prevented is a serious one. . . .
Those who won our independence by revolution were not cowards. They did not fear political change. They did not exalt order at the cost of liberty. To courageous, self-reliant men, with confidence in the power of free and fearless reasoning applied through the processes of popular government, no danger flowing from speech can be deemed clear and present, unless the incidence of the evil apprehended is so imminent that it may befall before there is opportunity for full discussion. If there be time to expose through discussion the falsehood and fallacies, to avert the evil by the processes of education, the remedy to be applied is more speech, not enforced silence. Only an emergency can justify repression. Such must be the rule if authority is to be reconciled with freedom. Such, in my opinion, is the command of the Constitution. It is therefore always open to Americans to challenge a law abridging free speech and assembly by showing that there was no emergency justifying it.
To Brandeis, the most important role in a democracy is that of "citizen," and in order to carry out the responsibilities of that role a person has to participate in public debate about significant issues. One cannot do that if he or she is afraid to speak out and say unpopular things; nor can one weigh all of the options unless other people, with differing views, are free to express their beliefs. Free speech, therefore, is at the heart of the democratic process.
This truth seems so self-evident that one might wonder why it is not universally accepted even in the United States; the reasons are not hard to find. It takes civic courage to stand up for unpopular ideas, and as both Holmes and Brandeis pointed out, the majority rarely wants to hear ideas that challenge accepted views. To prevent the majority from silencing those who oppose it is the reason the Framers wrote the First Amendment. The principle of free thought, as Holmes famously wrote, is "not free thought for those who agree with us but freedom for the thought we hate."
This is not an easy concept, and in times of stress such as war it is often difficult to allow those who would assault the very foundations of democracy to use democratic tools in their attack. Certainly the lessons Holmes and Brandeis tried to teach seemed to be lost during the early years of the Cold War. In the late 1940s the government prosecuted leaders of the American Communist Party for advocating the forceful overthrow of the government and conspiring to spread this doctrine. A majority of the U.S. Supreme Court, which since the 1920s had seemed to take an ever more speech-protective view of the First Amendment, now apparently reversed itself. Though admitting that American communists posed little clear and present danger, the Court ruled their words represented a "bad tendency" that could prove subversive of the social order.
Just as Holmes and Brandeis had come to the defense of unpopular socialists a generation earlier, so now Hugo Black and William O. Douglas took their places as defenders of free expression and protectors of minority rights.
Justice William O. Douglas, dissenting in Dennis v. United States (1951)
There comes a time when even speech loses its constitutional immunity. Speech innocuous one year may at another time fan such destructive flames that it must be halted in the interests of the safety of the Republic. That is the meaning of the clear and present danger test. When conditions are so critical that there will be no time to avoid the evil that the speech threatens, it is time to call a halt. Otherwise, free speech which is the strength of the Nation will be the cause of its destruction. Yet free speech is the rule, not the exception. The restraint to be constitutional must be based on more than fear, on more than passionate opposition against the speech, on more than a revolted dislike for its contents. There must be some immediate injury to society that is likely if speech is allowed. . . .
In America [Communists] are miserable merchants of unwanted ideas; their wares remain unsold. If we are to proceed on the basis of judicial notice, it is impossible for me to say that the Communists in this country are so potent or so strategically deployed that they must be suppressed for their speech. This is my view if we are to act on the basis of judicial notice. But the mere statement of the opposing views indicates how important it is that we know the facts before we act. Neither prejudice nor hate nor senseless fear should be the basis of this solemn act. Free speech should not be sacrificed on anything less than plain and objective proof of danger that the evil advocated is imminent.
As the hysteria of the Cold War passed, Americans came to see the wisdom in the arguments that Holmes and Brandeis, and later Black and Douglas, put forth. The cure for "bad" speech is not repression, but "good" speech, the repelling of one set of ideas by another. Truly, many things believed right and proper in today's world were once considered heretical, such as the abolition of slavery or the right of women to vote. Although a majority will always find itself uncomfortable with radical ideas attacking its cherished beliefs, as a matter of constitutional law, the policy of the American democracy is that speech, no matter how unpopular, must be protected. In 1969, the Court finally put an end to the whole idea of seditious libel, and that people could be prosecuted for advocating ideas the majority condemned as subversive.
* * * * *
During the height of the protest against American involvement in Vietnam, many civil libertarians wondered if the fact that the United States was at war would once again let loose forces of repression, as had happened in World War I and during the Cold War. To the surprise of many who feared the worst, the country took the protests in stride. This is not to say that all Americans liked what the protesters were saying, or that they did not wish that some of them could be silenced or even jailed. Rather, they accepted the notion that in a democracy people had the right to protest – loudly, in some cases in a vulgar manner, but that in the great debate taking place over whether the United States should be in southeast Asia, all voices had to be heard.
Thirteen-year-old Mary Beth Tinker and other students wore black armbands to high school in Des Moines, Iowa, as a symbol of their opposition to the war in Vietnam, and school authorities suspended them, on grounds that the action disrupted the learning process. In fact no disruption had taken place; rather, school officials worried about the town's response if it appeared that they were permitting antiwar protests in the school.
In one of the most important cases that grew out of the war, the Supreme Court held that when it came to political speech, high school students did not lose their constitutional rights when they entered the school door. Rather, if schools are indeed the training ground for citizenship, then it is necessary that students have the opportunity to learn that they also have the right to express unpopular political views and not be punished by the school authorities.
Mary Beth Tinker
There was a teen group that had its own activities . . . and we decided to wear these black armbands to school. By then [1965] the movement against the Vietnam War was beginning to grow. It wasn't nearly what it became later, but there were quite a few people involved nationally. I remember it all being very exciting; everyone was joining together with this great idea. I was a young kid, but I could still be part of it and still be important. It wasn't just for the adults, and the kids were respected: When we had something to say, people would listen.
So then we just planned this little thing of wearing these armbands to school. It was moving forward and we didn't think it was going to be that big a deal. We had no idea that it was going to be such a big thing because we were already doing these other little demonstrations and nothing much came of them. . . .
The day before we were going to wear the armbands it came up somehow in my algebra class. The teacher got really mad and he said, If anybody in this class wears an armband to school they'll get kicked out of my class. The next thing we knew, the school board made this policy against wearing armbands. . . . Any student who wore an armband would be suspended from school.
The next day I went to school and I wore the armband all morning. The kids were kind of talking, but it was all friendly, nothing hostile. Then I got to my algebra class, right after lunch, and sat down. The teacher came in, and everyone was kind of whispering; they didn't know what was going to happen. Then this guy came to the door of the class and he said, Mary Tinker, you're wanted out here in the hall. Then they called me down to the principal's office…. The principal was pretty hostile. Then they suspended me.
[Reprinted with the permission of The Free Press, a Division of Simon & Schuster Adult Publishing Group, from The Courage of Their Convictions by Peter Irons. Copyright 1988 by Peter Irons.]
Years later, opponents of a different administration's foreign policy burned an American flag in protest, and were immediately arrested. They pursued their legal defense in this case all the way to the Supreme Court, which held that their action, reprehensible as it was to most Americans, nonetheless represented "symbolic political speech" and as such was protected by the First Amendment. Perhaps the most interesting opinion in that case is one by a conservative member of the Court, Anthony Kennedy, who explained why he believed the Court had to allow the flag-burner to go free, even though he along with millions of Americans found the act distasteful.
Justice Anthony Kennedy, concurring in Texas v. Johnson (1989)
The hard fact is that sometimes we must make decisions we do not like. We make them because they are right, right in the sense that the law and the Constitution, as we see them, compel the result. And so great is our commitment to the process that, except in the rare case, we do not pause to express distaste for the result, perhaps for fear of undermining a valued principle that dictates the decision. This is one of those rare cases. . . .
Though symbols often are what we ourselves make of them, the flag is constant in expressing beliefs Americans share, beliefs in law and peace and that freedom which sustains the human spirit. The case here today forces recognition of the costs to which those beliefs commit us. It is poignant but fundamental that the flag protects those who hold it in contempt.
Although there was a hue and cry over the decision, it died down over time, as voices of common sense began to be heard. And none was more poignant in its defense of free speech than that of James H. Warner, a former prisoner of war in Vietnam.
James H. Warner, letter to Washington Post, 11 July 1989
As I stepped out of the aircraft [after being released from captivity in Vietnam], I looked up and saw the flag. I caught my breath, then, as tears filled my eyes, I saluted it. I never loved my country more than at that moment. . . . I cannot compromise on freedom. It hurts to see the flag burned, but I part company with those who want to punish the flag burners. . . .
I remember one interrogation [by the North Vietnamese] where I was shown a photograph of some Americans protesting the war by burning a flag. "There," the officer said. "People in your country protest against your cause. That proves that you are wrong."
"No," I said. "That proves I am right. In my country we are not afraid of freedom, even if it means that people disagree with us." The officer was on his feet in an instant, his face purple with rage. He smashed his fist on the table and screamed at me to shut up. While he was ranting I was astonished to see pain, compounded by fear, in his eyes. I have never forgotten that look, nor have I forgotten the satisfaction I felt at using his tool, the picture of the burning flag against him. . . .
We don't need to amend the Constitution in order to punish those who burn our flag. They burn the flag because they hate America and they are afraid of freedom. What better way to hurt them than with the subversive idea of freedom? Spread freedom. . . . Don't be afraid of freedom, it is the best weapon we have.
The lesson Justice Brandeis taught more than 70 years ago has borne fruit-the response to bad speech is more speech, so that people may learn and debate and choose.
* * * * *
If the people in general accept the notion of untrammeled political speech, what about other forms of expression? Is the First Amendment prohibition absolute, as Justice Hugo Black (on the Court between1937 and 1971) argued, so that government cannot censor or punish any form of speech? Or are certain types of speech outside the umbrella coverage of the Speech Clause? May the writer or artist or business person, the bigot or protester or Internet correspondent say anything, no matter how offensive or unsettling, claiming protection of the Constitution? There are no easy answers to these questions. There is no public consensus, nor are there definitive rulings by the Supreme Court in all areas of speech. As public sentiments change, as the United States becomes a more diverse and open society, and as the new electronic technology permeates every aspect of American life, the meaning of the First Amendment appears to be, as it has so often been in the past, once again in flux, especially in relation to non-political speech.
In the early 1940s the Supreme Court announced in rather definitive terms that the First Amendment did not cover obscene or libelous speech, fighting words, or commercial speech. Yet in the last few decades it has addressed all of these issues, and while not extending full protection, has certainly brought many aspects under the protection of the Speech Clause. The decisions have not been without criticism, and it is safe to say that just as the Court has wrestled with these areas, so there has been confusion and disagreement in the sphere of public comment as well. This, again, is as it should be. The Supreme Court cannot hand down dicta and simply expect the people to obey. Rather, the Court often reflects changing social and political customs; while trying to discover what the original intent of the Framers may have been, the justices must also attempt to apply the spirit of that intent to the facts of modern life. Sometimes this is relatively easy to do, but even when the Court hands down a difficult and controversial opinion, such as in the flag burning case, there must be some reservoir of public understanding as to why this decision is necessary and how it fits into the broader tapestry of contemporary life.
The difficult question for the Court and for the people is where one draws the line between protected and non-protected speech. In some areas, such as obscenity, the effort to draw a legal distinction has not garnered public support, because obscenity itself is not an objective and easily defined subject. As the Court noted, one man's obscenity is another's lyric; what offends one person may not offend another. But is this the type of material the First Amendment was intended to protect? Is artistic expression, especially when it goes against current aesthetic or moral norms, the type of expression the Frames intended the First Amendment to protect?
Similarly, there has been debate in the United States for more than two decades about the allegedly corrosive effect that money has on the electoral process. There have been several efforts to control how money for election campaigns is raised and spent, and to impose limits on the amount that any one contributor could give. But the Supreme Court held years ago that money is in some ways speech, and when money is used to further the expression of political ideas, it cannot be controlled. Here one finds another area in which it is not clear just how far one can take the notion of free speech without running head-on into other and equally cherished concepts of democracy, such as fair elections.
Perhaps the most daunting task facing the American people as well as the judicial system is to determine how the First Amendment will apply to the new electronic technology. Is the Worldwide Web just another example of Justice Holmes's marketplace of ideas? Does the likelihood that some day every household in the world will have access to material already on the Web, and that each individual will have the opportunity to go online and say to the whole world what he or she wants make the First Amendment irrelevant?
These and other questions continue to be debated in the United States – in the courts, in congressional hearings, in presidential commissions, in universities, in public forums, and in individual households. Among the rights of the people none is so treasured as that of free speech, and none is so susceptible to changing views. Most Americans recognize, however, that as Justice Brandeis pointed out, their responsibilities as citizens require them to have the opportunity not only to propose unpopular views but also to hear others espouse their beliefs, so that in the end the democratic process can work. And while people are not always comfortable with the idea, they admit the truth that Justice Holmes declared when he said that the First Amendment is there not to protect the speech with which we agree, but the speech that we hate.
For further reading:
Lee C. Bollinger & Geoffrey R. Stone, Eternally Vigilant: Free Speech in the Modern Era (Chicago: University of Chicago Press, 2002).
Zechariah Chafee, Jr., Free Speech in the United States (Cambridge: Harvard University Press, 1941).
Michael Kent Curtis, Free Speech: The People's Darling Privilege (Durham: Duke University Press, 2000).
Harry Kalven, A Worthy Tradition: Freedom of Speech in America (New York: Harper & Row, 1988).
Cass R. Sunstein, Democracy and the Problem of Free Speech (New York: The Free Press, 1993).