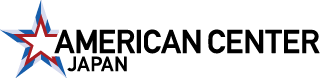国務省出版物
権利章典 – 近代における宗教の自由
南北戦争の後、米国の経済、社会、人口構成は著しい変化を遂げた。それに伴って、宗教の自由についても新たな問題が浮上してきた。1868年、合衆国憲法修正第14条が議会を通過すると、合衆国憲法修正第1条の規定が、全米各州に徐々に適用されるようになった。宗教の自由に関して、新しい問題も浮上した。それは、憲法制定時代の世代の人々には、おそらく理解できそうもないものだった。アレクシス・ドゥ・トクビルが、ひと昔前に指摘したように、米国で、ほとんどすべての重要な問題の決着は、最終的に裁判所に持ち込まれる。19世紀の後半以降、裁判所は、合衆国憲法修正第1条の2つの「宗教条項」が意味することについての、難しい問題の解決を迫られることになった。その傾向は20世紀に入りさらに強まった。
権利章典の採択から150年の間、連邦議会は、ほぼ例外なく、合衆国憲法修正第1条の規定が命ずるままに従ってきた。その結果、公認宗教の条項に関与するような訴訟はほとんどなく、また事例があったとしても、前例としてはほとんど意味を持たなかった。その後1947年、最高裁は、2つの宗教条項は各州にも適用されるという判断を示した。ヒューゴ・L・ブラック判事は「エバーソン対教育委員会事件」の多数派意見の中で、米国での宗教の自由が歴史的にどのように展開してきたかについて、詳しく述べている。
合衆国憲法修正第1条で守られている個人の良心の自由に含まれるのは、いかなる宗教上の信念をも選択する権利、あるいはまったく選択しない権利である。尊敬に値する宗教上の信念は、信仰心の厚い人々が自由かつ自発的な選択の産物である。
「エバーソン対教育委員会事件」(1947年)での賛成意見 「合衆国憲法修正第1条の『宗教の公認禁止』条項は、少なくとも次のことを意味している。州政府も連邦政府も教会を設立することできない。州政府と連邦政府の両者とも、特定の宗教を支援したり、すべての宗派を支援したり、もしくは、特定の宗教を優遇する法律を制定することはできない。州政府と連邦政府の両者とも、個人の意思に反して教会に行くこと、あるいは行かないことを強制したり、そのように仕向けたりすることはできない。また、どのような宗教であれ、信仰していること、あるいは信仰していないことを、無理に告白させることはできない。宗教を信仰することや信仰しないことを理由に、あるいはそれを告白したことを理由に人を罰することはできない。また教会への出席、ないしは欠席を理由に処罰することはできない。どんな名称であれ、宗教の普及や実践にどのような形態をとろうと、宗教的な活動や機関を支援するための税金は、その税額の多寡にかかわらず、徴収することはできない。州政府も連邦政府も、公然、非公然を問わず、どのような宗教機関、あるいは団体の行事にも参加することはできない。その逆も同じである。(トーマス)ジェファソンの言葉を借りれば、法律による宗教の公認を禁ずるこの条項は「政教を分離する壁」を構築することを意図したものである。 |
この章では、過去50年の間、宗教関連の訴訟のほとんどすべての判断に際して最高裁が適用した論理的根拠について述べる。そこには、宗教の公認禁止条項(政府が宗教的役割を奨励することを禁じている)も、宗教自由活動条項(個人が忠実に宗教的な慣習を行うことを政府が制限することを禁じている)も含まれる。エバーソン訴訟の判決は、我々の時代で最も大きな論争のひとつを引き起こした。すなわちそれは、宗教活動への財政支援に止まらず、公的機関における宗教的慣行に関し、宗教の公認禁止条項は政府の行動にどのような制約を課しているのか、という問題である。
ひとつだけ例を示そう。長年、全米の各学校で始業の際に、必ずある儀式を行っていた。公立学校の教師は、生徒たちに忠誠の誓い、短い祈り、「アメリカ」あるいは国歌「星条旗」の斉唱、聖書の一部の朗読を行わせてきた。この儀式の具体的な選択は、州法、地域の慣習、教師や校長の好みによっていろいろな形式があった。たいていの米国人は、この広く普及した慣習に何の疑問も抱くことはなかった。多くの人々は、これは米国の歴史的遺産の一部だと思い、ウィリアム・O・ダグラス判事がかつて書いたように「至高の存在を前提とする諸制約を持つ信仰心の厚い人々」の重要な文化的所産だと考えていた。ニューヨークでは、州政府が、公立学校向けに「非宗派的」な祈りの言葉を作成した。しかし、生徒の親のグループが、州政府からの通達は親と子供たちが持つ信条、宗教、あるいは宗教慣行に背くと抗議した。1960年代に至るまでに、米国は文化的、宗教的にますます多様な国家になっていた。このため多くの人々は、子供や親の宗教的信条を無視して、子供たちに特定の祈りを朗読させる慣習に違和感を覚えるようになっていた。
この親たちのグループは問題を法廷へ持ち込み、最終的には最高裁が「エンゲル対ビターレ事件」の判決で、親たちの主張を支持する判断を示した。ヒューゴ・L・ブラック最高裁判事は20年以上も日曜学校で教鞭をとっていた人物だが、どのように宗教的中立を維持しても州政府が義務づける祈りという概念そのものが「宗教の公認条項とまったく相容れない」という見解を示した。どのように定義しても、祈りは宗教活動に該当するのであり、合衆国憲法修正第1条は「政府が(公立学校制を通して行う)宗教プログラムの一環として公的な祈りを作成することは、どのような米国民の集団が朗誦するためのものであれ、少なくとも公務の一部ではないということを意味するはずである」として、ブラック判事は宗教の公認条項の背後にある哲学について、次のように自説を述べている。
「エンゲル対ビターレ事件」(1962年) 「ある特定の宗教に対して、政府の権力や威信、財政的支援が与えられた場合、宗教的少数派に対して公認宗教に従うように強制する、間接的な圧力がかかることは明らかである。しかし宗教の公認条項が意味する目的は、もっと深いところにある。その目的の第一の基盤は、政府と宗教が一体化することになれば、政府は破壊され、宗教は堕落する傾向があるという信念である。もうひとつの目的は、政府公認の宗教と、宗教上の迫害は表裏一体だという、歴史的な事実認識に基づいている」 |
ブラック判事にとって、祈りの内容、その具体的な言葉、あるいは、それが非宗派的な性質のもので宗教的に中立だという事実は、この事案の審理にまったく関係なかった。祈りそのものが本質的に宗教行為であり、祈りを奨励することを通じて、政府は特定の宗教活動を選択して後援し、宗教の公認条項を侵害した。最高裁は強制を示す証拠は発見しなかった。子供たちが祈ることを強いられたことはなかった。また、その祈りが、ある特定宗派の利益を促進したという判断も示さなかった。そうではなく、政府が公立学校における宗教的行事を促進したこと自体が、むしろ合衆国憲法修正第1条の侵害にあたると判断した。
この「エンゲル対ビターレ」裁判の判決を受けて、最高裁への批判の嵐が吹き荒れた。それは一時的に弱まることはあっても、収まることはなかった。公立学校での祈りという慣習は、時おり少数の反慣習主義者や変わり者を、被害者の立場に追いやってはいたが、この社会的に重要な目的を果たしてきた伝統的行為を、最高裁が打ち壊してしまったと多くの国民の目には映ったのである。ある新聞には「最高裁、神を非合法化」という見出しが躍った。プロテスタントの宣教師ビリー・グラハムは「神に救いを求めることが、もはやできなくなり、神はわれわれの国を嘆き悲しんでいる」と、激しく非難した。ニューヨークのスペルマン・フランシスコ会枢機卿は、この判決が「長年にわたり、米国の子供たちが育ってきた聖なる伝統の心臓部」を直撃したと非難した。
しかし一方には、最高裁の立場を擁護する人々もいた。多くの宗教集団は、この判決が意味のない公的な儀式から宗教を切り離し、自分たちが真摯に行っている慣習を守る方向への重要な動きだと評価した。リベラル派と正統派の宗派の連合体である全米教会評議会は、エンゲル対ビターレ裁判の判決は、少数者の権利を守ったと称えた。ジョン・F・ケネディ大統領は1960年の大統領選挙戦で、凶暴で偏狭な信念を持つ人々(その多くが現在、最高裁を攻撃している)の標的となったが、この判決を支持するよう求め、記者会見で次のように述べた。
「この問題には非常に簡単な解決方法がある。それは、自分たちで祈ることだ。このことを米国中の家庭が、喜んで思い出してくれると私は信じている。自分の家でなら、もっともっと長い時間をかけて祈れるし、もっともっと誠実な気持ちで教会に行くことができる。そして私たちのすべての子供たちの生活の中で祈ることの本当の意味を、もっと大切なものに変えることができる」
大統領の良識ある取り組みは、最高裁がこのエンゲル事件判決で意図したものを的確にとらえていた。大多数の人々は、祈りや宗教に反対したのではなく、憲法起草者たちが権利章典で、個人の自由を徹底的に守ろうとしたと信じていた。個人の宗教の自由を守るためには、たとえ「中立な」祈りと称するものでも、政府は宗教上の義務をいっさい課すことはできない。ブラック判事によれば、政府の権力と威信が特定の宗教の信仰や実践の後ろ盾になるや否や「主流の公認された宗教に従うよう、宗教的な少数派に強制するような圧力がかかることは明白である」
翌年、最高裁は、「アビントン学校区対シェンプ事件」の判決を下した。ペンシルベニア州法は「すべての公立学校は、毎日始業時に少なくとも10編の聖書からの詩を注釈なしに読むこと」を義務付けた。「いかなる子供も、親ないしは保護者が書面で要請すれば、聖書を朗読する義務、あるいは聖書朗読に立ち会う義務を免除される」さらに、生徒は全員で声をそろえて「主の祈り」を朗読することが義務とされた。この裁判では、通常は保守派と見られていたトム・クラーク判事が、聖書朗読義務を棄却する多数派意見を言い渡した。判事は、憲法が定めた宗教に関する中立性は、歴史の苦い教訓から生まれたものであり、教会と国家が融合すれば、公認の正統派的宗教慣行に従っている者以外の人々への迫害につながるということが、その教訓だと述べた。
米国では諸権利は憲法で宣言されているが、その意味は最高裁によって定義される。最高裁は、信頼できる決定的な法律解釈を行うために憲法で設置された。過半数の市民は、あるいは多分大多数の市民は、学校での祈りや聖書朗読で心を傷つけられことはないかもしれない。しかしそのことは、概して、憲法上の判断に関係することはない。権利章典の目的は、多数派を守ることではなく、少数派を守ることである。かつてオリバー・ウェンデル・ホームズ・ジュニア判事が述べたように、言論の自由とは、我々が賛成する言論のためではなく、嫌悪する言論のためにある。宗教の自由は、言論の自由と同様にもちろん多数派を保護する。しかし合衆国憲法修正第1条の宗教の公認条項で定められている保護規定が、引き合いに出されて意味を持ってくるのは、多数派が国家権力を行使して、自分たちの宗教上の慣習を押しつけようとする時である。1人の反体制派、1人の不信心者を守るために、多数派が困惑させられることは、よくあることかもしれない。これは建国の父たちが、宗教の自由のために進んで払おうと明言した代償である。
この考え方は、個人の良心を守ることは、同時に宗教のためにもなるという考え方と同様、多くの米国人に今なお共有されている。ジョン・ポール・スティーブンス判事は、最近の判例の中で「合衆国憲法修正第1条によって守られている個人の良心の自由は、いかなる宗教をも選択する自由、あるいはいかなる宗教も全く選択しない自由を保障している。尊敬に値する宗教的信仰は、忠実な人々の自由かつ自主的な選択の産物である」と述べている。
この考えは、すべての米国民によって受け入れられているわけではない。だが、21世紀初頭の米国のような異分子から成る社会では、多数派の規範を受け入れない者は、サンドラ・デイ・オコーナー判事が述べたような「政治社会の正式メンバーといえない部外者」と見なされるかもしれない、と大半の人々が考えていた。それはまさに、合衆国憲法修正第1条の起草者や最高裁判事、そしてほとんどの米国民が、何としても避けようとしていることである。自由な社会では、宗教的な異端者の存在を単に黙認するとか、彼らに社会の劣った一員だという気持ちを抱かせるようなことがあってはならない。見解の相違は、複雑多彩に織りなした文化の一部として重んじられるべきであり、それが米国の独自性を際だたせている。
一部の宗教集団は、エンゲル判決やシェンプ判決に異議を唱え続けてきたが、主流の宗教団体の多くは、最高裁は宗教を阻害したのではなく、実は奨励したのだと認識するようになった。ジェームズ・マディソンは、200年以上前に書かれた「宗教上の課税に反対する請願書と抗議」の中で、宗教に対する国家の敵対心だけでなく、宗教への支援もまた、宗教と宗教的自由を損なう恐れがあるとの考えを述べていた。そうしたマディソンらの考えを引き継いだ人々も、そうした趣旨の主張を続け、国家は決して宗教を支援することはできず、ただ妨害することだけだという考えを持っている。どんな形式であれ、政府公認の宗教活動を学校で行うことは、宗派間の敵対心を生むことになりかねない。それどころか、本当の信仰者にとって必要なのは、政府の助けではなく、誰も構わないで、ほっておいてもらうことである。信仰の厚い人々は、神への義務を果たすため、統治者の助けを必要とはしていないのである。
しかしながら、真の信仰者の中にも、信仰は個人の問題だということには同意するものの、宗教を米国の市民生活には欠かせない部分だと考える人々もいる。そのような人々は、宗教の公認は望まないが、特定の宗派を優遇しない平等な形であれば、政府が宗教関係団体に支援の便宜をはかることを望んでいる。最高裁は過去50年以上にわたり、慈善団体への政府補助金の問題と取り組んできた。しかし、これまでのところ、その判断に一貫性があったとは、とても言えない。確かに、信者獲得のための財政支出が許されないことについては決着している。しかし、たいていのキリスト教会やユダヤ教寺院は、さまざまな社会奉仕や教育プログラムを営んでおり、それらが失われれば、公的制度に大きな負担がかかってくる。最高裁は、これらプログラムのいくつかを支援するために、政府補助金の禁止の原則に例外を設けてきた。そして2002年6月、最高裁は、宗教団体への便宜供与の容認へ大きな一歩と広く見なされる決定を行った。
それは、学童家族に対する授業料支払い証書(バウチャー)を州政府が発行することを、最高裁が僅差で承認した判決である。宗教に関連する私立学校であっても、その証書を使って授業料を払うことができるようにしたもので、これにより、バウチャー推進派にとっては、法律上の主要な障害が取り除かれた。しかしバウチャー計画を全面的に採用するかどうかは、米国50州の州議会の判断に委ねられた。これからの論議は、もはやバウチャー計画の合憲性についてではなくなり、世論調査によれば過半数がバウチャーに反対しているとされる一般市民の、政治的な意思の問題へと移っていくだろう。今後10年間の展開が、米国における教会と国家の関係の性質に大きな影響を与えるだろう。
合衆国憲法修正第1条には2つの宗教条項がある。宗教の公認条項は、たとえ多数派を代表する行為であろうと、政府が、画一的な宗教行為を課すことを禁じている。宗教の自由活動条項は、主流の宗教が支配している政府から、異端派を守ることを特に念頭において作られた条項である。少数派を守ることの意義は、米国が史上最も多元的な民主主義国となったこの21世紀初頭、ますます明白になるだろう。
憲法起草者たちは、政府を宗教から守るだけでなく、宗教を政府から守ることも望んだ。ジェームズ・マディソンは、支配的な宗教の公認を阻止するために戦っただけでなく、あらゆる宗教論争に政府が口をはさまないようにするつもりでもあった。憲法起草者たちは、政府が宗教の手に支配されれば、どれだけ猛威を振るう武器になるかを、経験からも知識からも承知していた。だから決してそうはならないことを望んでいた。ここで、再び問題に直面する。政府を宗教問題に関して完全に中立的なものにしておくことと、米国の市民生活で宗教が担ってきた強力な役割に、どう折り合いをつけるのかという問題である。宗教は、多くの米国民にとって市民文化の一部として重要であり、政府がまったく関与しないかのように見せかけることなど、とうていできるものではない。
宗教の自由活動条項は、さまざまな宗教的な教義を保護し、あらゆる種類の信仰者そして不信仰者に対して、完全で平等な市民権を保障するためのものである。言い換えれば、社会の多元性を育み、それぞれの個人とそれぞれの団体が、自らの思想や信仰を十二分に表現できるようにするものである。我々は、植民地は主として英国から移住してきた人々が作り上げたものだと考えがちである。しかし実際は、1776年までの新大陸への移住者は、スカンジナビア半島や、西欧、中欧からやって来ていたし、無論、奴隷売買によってアフリカからもやって来た。新生国家は、多元性という点で、その後の米国社会とは比較にならなかったが、当時の英国やその他の欧州諸国と比べれば、既にさまざまな国籍や宗教の寄せ集めになっていた。活気に満ちた民主的な社会を維持するためには、知的な交流が必要とされるが、これは、個々人の生活でもっとも大切な側面、すなわち、宗教的信条に政府が干渉しないことによってのみ実現できると多くの学識者は信じ続けている。
宗教集団は、時おり不人気になったりしたものの、それでも生き永らえてきた。そして結局のところ、大多数の人々は、信教の自由とは、たとえ、さげすむべき宗教集団に対してであれ、彼らの良心が命じるままに神を信仰できる寛容さを持つことなのだと悟るようになった。もっとも、時には多数派は道徳的な立場から主張を譲らないこともあった。たとえば重婚制への反対は、自由な宗教活動の意味において、最も重要な初期の法的判断のひとつにつながった。
モルモン教徒、つまり末日聖徒イエス・キリスト教会は、19世紀初頭に米国で起こり、一夫多妻制に熱心だったことから、他のキリスト教団体の反感を招いた。西部の辺境の地へと追われたモルモン教徒は、現在のユタ州に繁栄の地を築いた。彼らの居住地は、最終的に合衆国の州に加盟するための要件を満たすまで拡大したが、モルモン教徒が一夫多妻制にしがみついている限り、それは実現不可能なことだった。連邦法は一夫多妻制を犯罪としたため、モルモン教徒は最高裁に提訴し、宗教活動の自由が保障されている以上、政府は一夫多妻制を容認すべきだと主張した。
国民の95%以上が非難している一夫多妻という慣習に、最高裁は、憲法上の承認を与えようとはしなかった。一方、憲法は、宗教活動に明快な保護を与えているようにみえた。この難解な問題を、モリソン・ウェイト最高裁長官は巧妙に解決策を見出したが、その論理は今日もなお、宗教活動の自由に関するあらゆる訴訟に影響を及ぼしている。即ち、ウェイト長官は、宗教上の信条と実践の違いを厳密に区別した。長官が引用したのは「宗教は人と神の間だけに存在する事柄である・・・。政府の立法上の権限は、行為のみに適用され、見解には及ばない」というトーマス・ジェファソンの言葉である。この論拠に基づいて、最高裁は「連邦議会は、単なる見解に関しては、あらゆる立法権を奪われている。しかし、社会的義務に背いたり、公序良俗に反したりする行為に関しては対処する自由がある」と裁定した。最高裁の決定では、一夫多妻制は明らかに公序良俗を破壊するものであり、従って議会はこの慣習を犯罪と見なすことが可能であるという内容だった。
「連邦議会は、自由な宗教活動を妨げる法律を準州のために制定してはならない。合衆国憲法修正第1条は、明確にそのような立法を禁じている。連邦議会の干渉に関する限り、宗教的自由は、米国全土のいかなる場所でも保障されている。判断されるべきことは、目下審理中の法律が、この禁止に該当するかどうかである・・・」 「法律は、政府が人々の行為を統治するために作られる。法律は、単なる宗教的信条や見解に干渉することはできないが、それが実践に移されれば介入することができる。ある人が、人間の生贄は、宗教的礼拝に必要な一部だと信じていた場合、その人が住む社会の市民政府は、生贄を防ぐための介入ができないと、まじめに議論するだろうか。あるいは、ある妻が、亡くなった夫の火葬用の薪の上でわが身を焼くのが宗教上の義務だと信じていた場合、彼女がその信念を実行するのを阻止することは、市民政府の権限を超えることなのだろうか」 「つまり、合衆国が独占的に統治している社会組織の法律では、重婚は容認できないと規定されている。この規定に逆らって、個人の信仰を理由に重婚を実践することは、許されるのだろうか。これを容認することは、宗教的信念として教義を明言すれば、一国の法律に優先させることになり、事実上、あらゆる市民が自分で自分の法律になることを認めるものである。このような状況下では、政府は名ばかりの存在となる」 |
興味深いことに、この裁判は、特定の個別の宗教集団による自由な宗教活動の請求の中で、最高裁がその主張を認めなかった稀な訴訟の1つである。最高裁がこのような判断を下したのは、争われた行為、すなわち一夫多妻制が、市民社会への脅威になると見なしたからである。しかしながら、行為と信仰の間に一線を画したことで、信仰それ自体を理由に攻撃したり、法律で禁止したりすることはできないという、憲法上の重要な原則を生み出した。
宗教活動の自由に関して、間違いなく最もよく知られている訴訟は、エホバの証人が星条旗への敬礼を拒んだ事件である。エホバの証人は、米国内の数多い小さな宗教集団の1つに過ぎないが、宗教活動の自由を保障する条項の基本的な意味を理解した上で、最高裁に何度も足を運び、その理想を現実に変えた。
エホバの証人は、昔も今も、人々に改宗を働きかける宗派である。改宗者を獲得し、パンフレットを配布しようとする活動は、地方当局との間にしばしば摩擦を起こした。彼らの評判は、第2次大戦の直前、最悪になった。というのも、エホバの証人の信仰では、旗に対する敬礼は、偶像に頭を下げることを禁じている聖書の教えに背くという信念に従い、エホバの証人は自分の子供たちに、星条旗に敬礼する朝の儀式には参加しないよう指示したからである。開戦が迫る中で、自らの信念に従ったため、多くのエホバの証人の子供たちが学校から追い出され、親たちは罰金を科せられ、刑事裁判の被告席に引き出された。その子供たちの1人だったリリアン・ゴビタスの言葉に耳を傾けてみよう。
「私は学校が好きでした。周りには素敵な仲間がいました。実は、これでも人気者でした。7年生の学級長でした。成績もよかった。私はこう思っていました。もし星条旗に敬礼するのをやめたら、生活のすべてが台無しになってしまうと。そして私は実行しました。思っていた通りになりました。本当に怖かったので、先生が私の方を見たら、忠誠の誓いをたてようと思わず手を上げて、口を動かしてしまうのではないかと思いました」 「弟のウィリアムは、当時1935年の秋、5年生でした。その翌日、ビルは帰宅するなり、旗への敬礼はやめたと言いました。「大事な瞬間がやってきた!」と、私にはわかっていました。両親から押しつけられたわけではありません。両親ははっきりしていました。自分がやることは、自分でそう決めたこと、自分のしていることは、よく理解しなきゃだめよ、と。それで私は、聖書を何度も読んで考え、本当に自分で態度を決めました」 「真っ先に、担任のアンナ・ショフスタル先生のところに行きました。途中で怖くなって逃げ出せないようにするためです。先生は私の説明を聞いてくれ、驚いたことに私を抱きしめて、そんな勇気を持つことは、とても素晴らしいと思うわと言ってくれました。でもクラスの仲間の態度はひどいものでした。クラス全体に説明すればよかったのですが、怖くてできませんでした。その間、座っていた方がいいのか、立っていた方がいいのかわかりませんでした。今なら、敬礼自体が行動であり、言葉であることがわかりますけれど。だから、私が座ったら、クラスのみんなは本当に驚きました。それ以来、私が学校に行くと、みんなが小石を一斉に投げつけ「エホバが来た!」などと、はやし立てたりするようになりました。みんなが私のことを嘲っていました・・・」 「星条旗への敬礼について、態度を明らかにしてから50年以上になります。でももう一度やり直すとしても、同じことをするでしょう。ためらいはありません! エホバの証人は、聖書の教えを守ろうとしているのだと思っています。そしてイエスは、こう言いました。「彼らは私を迫害した。彼らはあなたたちも迫害するだろう・・・」この裁判は私たちの生活に大きな影響を及ぼしました。そして私たちは、その教訓を自分の子供たちに伝えました」 〔この一節は、フリープレス(サイモン&シュースター・アダルトパブリッシンググループの一部門)の許可により、ピーター・アイアンズ著『勇気ある信念』(The Courage of Their Convictions)(© 1988)から転載した。〕
|
最高裁は、1939年、この事件を審理することに合意した。折しも、米国民のほとんどが、米国の第二次世界大戦への参戦は避けられないと考えていた時期だっただけに、愛国心を育むことは、公立学校の非常に重要な役割として評価されていた。ユダヤ人のフェリックス・フランクファーター判事は、どのような集団にも宗教の自由を認めたいという気持ちと、公立学校には、生徒に星条旗への敬礼を義務づける憲法上の権利があるという信念の間で、彼自身、大きく揺れ動いた。判事は、最高裁の同僚に宛てて、次のように書き送った。「最高裁判事に就任して以来、この事件ほど、私の良心に重くのしかかってくる裁判は他にはなかった。私のすべての偏見と先入観は、あらゆる種類の宗教的、政治的、経済的な意見に、最大限の居場所を与える方に傾いている・・・。しかしこの問題は、一方に憲法上の権限があり、もう一方には、自由と寛容、良識に関する私個人の観念がある、そういう領域に入っている」結局、最高裁判事9人のうち8人が、管轄学区の主張を支持した。
エホバの証人が孤立無援の立場に追い込まれたことは、ほどなく明らかになった。彼らの訴えが棄却されると、特に小さな町や農村地域で、エホバの証人に対する襲撃が何百件と発生した。1940年末までに、襲われたエホバの証人は1,500人を越え、そのうち350件を越える事件では、多くの信徒が容赦なく殴打された。このような状況は、少なくとも2年間続いた。米国にとって、とても最良とは言い難い時代だったが、経験から学んだ時代でもあった。米国人は、エホバの証人への襲撃について学ぶと同時に、欧州の無力な少数派をヒトラーが大量殺りくしたことや、宗教的信条だけを理由として600万人に上る男女や子どもを抹殺したヒトラーの「究極の解決策」についても学んだ。最高裁は、その後、星条旗への敬礼にかかわる別の事件を審理することに合意した。この審理には、後にニュルンベルク裁判で、米国側検察官を務めることになる、新任判事のロバート・H・ジャクソンが加わった。判事は、エホバの証人が他の国民と異なる生き方をする権利を認め、憲法が課している政府の行動への制約を支持した。
「ウエストヴァージニア州教育委員会対バーネット事件」(1943年) 「権利章典の主眼は、時の流れの中で変転する政治論争の中から、ある特定のテーマを抜き取り、それらを議会の多数派や役人の手の及ばないところに据えて、裁判所が適用すべき法的原則として確立することにあった。人間の生命、自由、財産権、言論の自由、報道の自由、信仰と集会の自由、その他の基本的な人権は、投票に付すべきものでない。これらの権利は、どのような選挙の結果にも左右されてはならない」 「この裁判を困難なものにしているのは、判断を下す原則があいまいだからではなく、審理の対象になった旗が、我々自身の国旗であるからである。しかしながら、知的および精神的な多様性を容認する自由や、相反することをも容認する自由が、社会組織を崩壊させることを恐れることなく、我々は憲法上の制約を適用する。愛国主義的な儀式が、日常義務としてではなく、自発的で自然発生的に行われるなら愛国心は育たないと信じるなら、それは、我々の制度には、自由な精神に訴えかける魅力が欠けるとあからさまに評価することに等しい。我々は、知的個人主義や豊かな文化的多様性を持ちうるが、それには代償がある。それらをもたらす優れた人々には、時折極端な行動や常軌を逸したな態度を示す者がいることである。今審理している人々のように、他人や国家にまったく無害である時は、そうした代償はさほど大きいものではない。そもそも、他の人と違う自由は、影響の小さな問題に限定されているわけではない。限定されていれば、自由とは名ばかりのものになる。自由に実質が伴っているかどうかは、現存する秩序の心臓部に触れる問題に関して、他人と異なる権利が保障されているか否かで審査される」 「もし、憲法という星座に、位置を変えない恒星があるとすれば、それは、地位の高低に関係なく政府の役人が、政治、民族主義、宗教あるいはその他の意見で何が正しいことか規定することを禁じていることである。あるいは、言葉や行動で、信ずる宗教を国民に告白するように強要することを禁じている点である。これらに関して、例外を認める何らかの状況があるとしても、今、我々の目の前にはない」 |
最高裁は、星条旗の裁判に続いて、他の事件も数多く審理した。しかし、その事例はすべて、ジャクソン判事の「恒星」という雄弁な思想、つまり政府の役人は、何が正しいのかを規定することはできないという考えの上に積み上げられたものだった。すべての判決で、他とは異なる思想を持つ宗派が支持されたわけではなかったが、政府は思想自体を罰することはできないという考え方は、半世紀前も、建国の時代でもそうであったように、今日も変わらぬ真理である。
宗教は、米国民の市民生活と個人生活の中で、重要な役割を演じ続けている。宗教は国の公の問題に関して、より重要な役割を果たすべきだと考える人もいるが、その逆を信じている人もいる。一般の信徒や学者、議員、法律専門家は、教会と国家の活動の間のどこに線を引くかについて、また、異端派に、どこまで宗教的信条の遂行を許すかについて、議論を続けている。この論議は、民主主義手続きのまさに核心にある。常に意見の一致につながるわけではない。すべての人がすべての論争で勝つわけではないことも明らかである。しかし米国民は、言論の自由の制約について議論するときに示す真剣さと熱意を持って、この論争に臨んでいる。そのことが、憲法上の自由をより強力なものにしている。宗教の自由は、米国民にとって抽象的な理念ではない。それは、生き生きとした自由である。その自由への挑戦に、国民は日々の生活の中で直面しているのである。
参考文献:
- Gregg Ivers: “Redefining the First Freedom: The Supreme Court and the Consolidation of State Power” (New Brunswick: Transaction Books, 1993)
- Leonard W. Levy: “The Establishment Clause: Religion and the First Amendment (2nd ed., Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1994)
- John T. Noonan, Jr., The Lustre of Our Country: The American Experience of Religious Freedom (Berkeley: University of California Press, 1998)
- Frank J. Sorauf, The Wall of Separation: The Constitutional Politics of Church and State (Princeton: Princeton University Press, 1976)
- Melvin I. Urofsky, Religious Freedom (Santa Barbara: ABC-CLIO, 2002)
*上記の日本語文書は参考のための仮翻訳で、正文は英文です。
Religious Liberty in the Modern Era
(The following article is taken from the U.S. Department of State publication, Rights of the People: Individual Freedom and the Bill of Rights.)
After the Civil War, the United States underwent significant economic, social, and demographic changes, and with them came new problems of religious freedom. With the passage of the Fourteenth Amendment in 1868, the strictures of the First Amendment gradually came to be applied to the states as well. New questions relating to religious freedom arose, questions that might well have seemed incomprehensible to the Founding Generation. As Alexis de Tocqueville noted long ago, in America, nearly all important issues ultimately become judicial questions. Starting in the latter part of the 19th century, and accelerating in the 20th, the courts had to resolve difficult questions relating to the meaning of the two "religion clauses" in the First Amendment.
For most of the first 150 years following the adoption of the Bill of Rights, Congress obeyed the injunctions of the First Amendment; as a result very few cases implicated the Establishment Clause, and those had little value as precedent. Then, in 1947, the Supreme Court ruled that both religion clauses applied to the states. Justice Hugo L. Black, in his majority ruling in Everson v. Board of Education, expounded at length on the historical development of religious freedom in the United States.
Justice Hugo L. Black, in Everson v. Board of Education (1947)
The "establishment of religion” clause of the First Amendment means at least this: Neither a state nor the Federal Government can set up a church. Neither can pass laws which aid one religion, aid all religions, or prefer one religion over another. Neither can force nor influence a person to go to or remain away from church against his will or force him to profess a belief or disbelief in any religion. No person can be punished for entertaining or professing religious beliefs or disbeliefs, for church attendance or non-attendance. No tax in any amount, large or small, can be levied to support any religious activities or institutions, whatever they may be called, or whatever form they may adopt to teach or practice religion. Neither a state nor the Federal Government can, openly or secretly, participate in the affairs of any religious organization or groups and vice versa. In the words of [Thomas] Jefferson, the clause against establishment of religion by law was intended to erect "a wall of separation between church and State.”
In this paragraph we find the root rationale for nearly every religion case decided by the Supreme Court in the last fifty years, whether it involves the Establishment Clause (which forbids the government to promote a religious function) or the Free Exercise Clause (which forbids the government to restrict an individual from adhering to some practice). And with the ruling, Everson began one of the most contentious public policy debates of our time, namely, What are the limits that the Establishment Clause puts on governmental action, not just in terms of monetary aid for programs, but on religious observances in the public sector?
To take but one example, for many years, a particular ritual marked the beginning of each school day all across America. Teachers in public schools led their students through the Pledge of Allegiance, a short prayer, singing "America" or the "Star-Spangled Banner," and possibly some readings from the Bible. The choice of ritual varied according to state law, local custom, and the preferences of individual teachers or principals. Most Americans saw nothing wrong with this widespread practice; it constituted part of America's historical heritage, an important cultural artifact of, as Justice William O. Douglas once wrote, "a religious people whose institutions presuppose a Supreme Being." In New York, the state had prepared a "non-denominational" prayer for use in the public schools, but a group of parents challenged the edict as "contrary to the beliefs, religions, or religious practices of both themselves and their children." By the 1960s, America's growing cultural as well as religious diversity made many people uncomfortable with the practice of forcing children to recite a prayer regardless of their – or their parents' – religious beliefs.
A group of parents went to court, and eventually the United States Supreme Court ruled in their favor in a case entitled Engel v. Vitale. In his opinion, Justice Hugo L. Black (who had taught Sunday school for more than 20 years) held the entire idea of a state-mandated prayer, no matter how religiously neutral, as "wholly inconsistent with the Establishment Clause." A prayer by any definition constituted a religious activity, and the First Amendment "must at least mean that [it] is no part of the business of government to compose official prayers for any group of the American people to recite as part of a religious program carried on by government [through the public school system]." Black went on to explain what he saw as the philosophy behind the Establishment Clause:
Justice Hugo L. Black, in Engel v. Vitale (1962)
When the power, prestige and financial support of government is placed behind a particular religious belief, the indirect coercive pressure upon religious minorities to conform to the prevailing officially approved religion is plain. But the purposes underlying the Establishment Clause go much further than that. [Its] most immediate purpose rested on the belief that a union of government and religion tends to destroy government and degrade religion. [Another] purpose [rested upon] an awareness of the historical fact that governmentally established religions and religious persecutions go hand in hand.
For Black the content of the prayer, its actual words, or the fact that its non-denominational nature allegedly made it religiously neutral, had no relevance to the case. The nature of prayer itself is religious, and by promoting prayer, the state violated the Establishment Clause by fostering a religious activity which it determined and sponsored. The Court did not find evidence of coercion – no child had been forced to pray. Nor did the Court find that the prayer furthered the interests of any one denomination. Rather it was the state's promotion of religious practices in the public school in and of itself that violated the First Amendment.
The Engel decision unleashed a firestorm of criticism against the Court which, while it has abated from time to time, has never died out. In the eyes of many, the Court had struck at a traditional practice which served important social purposes, even if it occasionally penalized a few non-conformists or eccentrics. One newspaper headline screamed "COURT OUTLAWS GOD." Protestant evangelist Billy Graham thundered, "God pity our country when we can no longer appeal to God for help," while Francis Cardinal Spellman of New York denounced the ruling as striking "at the very heart of the Godly tradition in which America's children have for so long been raised."
The Court had its champions as well. Many religious groups saw the decision as a significant move to divorce religion from meaningless public ritual, and to protect its sincere practice. The National Council of Churches, a coalition of liberal and orthodox denominations, praised the Engel decision for protecting minority rights. President John F. Kennedy, who had been the target of vicious religious bigotry in the 1960 campaign (from many of the groups now attacking the Court), urged support of the decision, and told a news conference:
We have, in this case, a very easy remedy. And that is, to pray ourselves. And I would think that it would be a welcome reminder to every American family that we can pray a good deal more at home, we can attend our churches with a good deal more fidelity, and we can make the true meaning of prayer much more important in the lives of all of our children.
The President's commonsense approach captured the Court's intent in Engel. The majority did not oppose either prayer or religion, but did believe that the Framers had gone to great lengths to protect individual freedoms in the Bill of Rights. To protect the individual's freedom of religion, the state could not impose any sort of religious requirement, even in an allegedly "neutral" prayer. As soon as the power and prestige of the government is placed behind any religious belief or practice, according to Justice Black, "the inherently coercive pressure upon religious minorities to conform to the prevailing officially approved religion is plain."
The following year the Court handed down its decision in Abington v. Schempp. A Pennsylvania law required that "at least 10 verses from the Holy Bible shall be read, without comment, at the opening of each public school on each school day. Any child shall be excused from such Bible reading, or attending such Bible reading, upon the written request of his parent or guardian." In addition, the students were to recite the Lord's Prayer in unison. This time Justice Tom Clark, normally considered a conservative, spoke for the majority in striking down the required Bible reading. The neutrality commanded by the Constitution, he explained, stemmed from the bitter lessons of history, which recognized that a fusion of church and state inevitably led to persecution of all but those who adhered to the official orthodoxy.
In the United States, rights are proclaimed in the Constitution, but they are defined by the Supreme Court, which the Constitution has established to provide a reliable and definitive interpretation of the law. The fact that a majority of citizens – even perhaps a large majority – may not be affronted by prayer in the school or Bible reading is, to a large extent, irrelevant in constitutional adjudication. The purpose of the Bill of Rights is not to protect the majority, but the minority. As Justice Oliver Wendell Holmes, Jr., once said of freedom of speech, it is not for the speech we agree with, but for the speech we detest. Freedom of religion, like freedom of speech, does of course protect the majority. However, the protection of the First Amendment's Establishment Clause is invoked in a meaningful way when the majority, attempting to use the power of the state, tries to enforce conformity in religious practice. Very often, to protect one dissident, one disbeliever, the majority may be discomfited; it is the price the Founding Fathers declared themselves willing to pay for religious freedom.
It is a view that many Americans still share, along with the belief that this protection of individual conscience is good for religion as well. Justice John Paul Stevens wrote in a modern case that "the individual freedom of conscience protected by the First Amendment embraces the right to select any religious belief or none at all. . . . Religious beliefs worthy of respect are the product of free and voluntary choice by the faithful."
While this view is not accepted by all Americans, a majority recognizes that in such a heterogeneous society as the United States is at the beginning of the 21st century, those who do not accept the norms of the majority, as Justice Sandra Day O'Connor wrote, may be characterized as "outsiders, not full members of the political community." That is a situation that the Framers of the First Amendment, members of the Court, and most Americans are determined to avoid. Religious dissenters in a free society are not to be merely tolerated and made to feel as inferior members of the society; their differences are to be valued as part of the tapestry of cultures that make the United States so unique.
While some religious groups have continued to oppose the decisions in Engel and Schempp, many of the mainstream religious bodies have come to see that the Court had actually promoted religion rather than subverted it. James Madison, in the "Memorial and Remonstrance," written over 200 years ago, believed that not only the state's antagonism, but its efforts at assistance, could damage religion and religious liberty. Their intellectual descendants have argued along similar lines, and believe that the state can never help religion, but only hinder it. To establish any form of state-sanctioned religious activity in the schools threatens to introduce denominational hostility. Moreover, the sincere believer does not need the state to do anything for him except leave him alone; those with confidence in their faith do not need Caesar's assistance to render what is due to God.
There are also sincere believers who, while agreeing that belief is an individual matter, nonetheless see religion as an integral aspect of America's civic life. They do not seek to establish a religion, but rather want there to be an accommodation, in which state aid may be given to religiously affiliated organizations provided it is done fairly, with no preference given to any single group. The Supreme Court has wrestled with this problem of some state aid to charitable organizations for more than 50 years, and its decisions have been far from consistent. While it is settled that money may not be given for religious proselytizing, most churches and synagogues run a variety of social service and educational programs, whose loss would place great strain on the public systems. The Court has carved out exceptions to the general rule of no state aid in order to assist some of these programs, and in June 2002, took what many considered a major step toward the accommodationist position.
By a narrow margin, the justices approved the issuance of state vouchers to the families of school children, which could then be used to pay tuition in private schools, even if these schools were religiously affiliated. The decision removed a major legal hurdle facing proponents of vouchers, but the ultimate decision on whether to adopt a full voucher plan will rest on the legislatures of the 50 states. The debate will no longer be over the constitutionality of the plan, but instead will be over the political wishes of the citizenry, a majority of whom, according to the polls, oppose vouchers. How this issue plays out in the next decade will have a great deal to say about the nature of church and state relations in the United States.
* * * * *
There are two religion clauses in the First Amendment. The Establishment Clause prohibits government, even when acting on behalf of a majority, from attempting to impose a uniform religious practice. The Free Exercise Clause was specifically designed to protect dissident sects from government under the control of the mainstream religions. The value of protecting minorities will become ever more apparent as the United States, at the beginning of the 21st century, becomes the most pluralistic democratic country in history.
The Framers wanted not only to protect government from religion, but also to protect religion from government. James Madison not only fought to prevent the establishment of one dominant religion, he also intended for the government to stay out of all religious controversies. The Framers had both experience and knowledge of how potent a weapon government could be in the hands of religion, and they wanted nothing to do with it. Here again, one runs into the problem of how to reconcile keeping government totally neutral in religious matters with the strong role religion has played in American civic life. Religion is very important to many Americans as part of civic culture, and to pretend that government is completely uninvolved is quite unrealistic.
The Free Exercise Clause is a way to protect different sources of religious meaning and assure full and equal citizenship for believers – and non-believers – of all stripes. In other words, it helps to foster pluralism and thus allow each person and each group full play of their ideas and faiths. Although we tend to think of the colonies as having been settled primarily from the British Isles, in fact by 1776 immigrants had arrived from Scandinavia, western and central Europe, and, of course, from Africa through the slave trade. Although the new country was nowhere near as pluralistic as the United States would later become, compared to England and other European nations of the time, it was already a hodge-podge of nationalities and religions. Many scholars continue to believe that the intellectual cross-fertilization needed to remain a vibrant and democratic society is only possible if one of the most important aspects of each person's life – religious belief – is left untouched by government's hand.
Sometimes religious groups have been unpopular, and yet they persisted, and eventually the majority learned that religious freedom meant allowing even despised groups latitude in which they could worship God according to the dictates of their consciences. Sometimes the demands of the majority could not be swayed on moral grounds; opposition to polygamy, for example, led to one of the most significant early decisions on the meaning of free exercise.
The Mormons, or the Church of the Latter Day Saints, arose in the early 19th century in the United States, and offended many Christian groups by their enthusiasm for multiple marriage. Forced to migrate west to the frontier, the Mormons established a prosperous settlement in what is now the State of Utah. Eventually the colony grew to the point where it met the requirements to be admitted as a state into the Union, but this could not happen so long as Mormons continued to cling to polygamy. Federal law criminalized the practice, and the Mormons turned to the Supreme Court, claiming that the free exercise of their religion demanded that the government tolerate polygamy.
The Court clearly was unwilling to put the stamp of constitutional approval on a practice condemned by more than 95 percent of the country. On the other hand, the Constitution did seem to give unequivocal protection to religious exercise. Chief Justice Morison Waite finessed the problem in a way that still affects all free exercise cases; he drew a sharp distinction between religious belief and practice. Waite quoted Thomas Jefferson that "religion is a matter which lies solely between man and his God; . . . the legislative powers of the government reach actions only, and not opinion." Following this reasoning, the Court held that "Congress was deprived of all legislative power over mere opinions, but was left free to reach actions which were in violation of social duties or subversive of good order." Polygamy, according to the Court, clearly was subversive of good order and Congress could thus make the practice a crime.
Chief Justice Morrison R. Waite, in Reynolds v. United States (1879)
Congress cannot pass a law for the government of the Territories which shall prohibit the free exercise of religion. The First Amendment to the Constitution expressly forbids such legislation. Religious freedom is guaranteed everywhere throughout the United States, so far as congressional interference is concerned. The question to be determined is, whether the law now under consideration comes within this prohibition. . . .
Laws are made for the government of actions, and while they cannot interfere with mere religious belief and opinions, they may with practices. Suppose one believed that human sacrifices were a necessary part of religious worship, would it be seriously contended that the civil government under which he lived could not interfere to prevent a sacrifice? Or if a wife religiously believed it was her duty to burn herself upon the funeral pile of her dead husband, would it be beyond the power of the civil government to prevent her carrying her belief into practice?
So here, as a law of the organization of society under the exclusive dominion of the United States, it is provided that plural marriages shall not be allowed. Can a man excuse his practices to the contrary because of his religious belief? To permit this would be to make the professed doctrines of religious belief superior to the law of the land, and in effect to permit every citizen to become a law unto himself. Government could exist only in name under such circumstances.
Interestingly, this is one of the few cases where the Supreme Court ruled against the Free Exercise claims of a distinct and separate group, and it did so because the practice involved – polygamy – was seen as a threat to civil society. The distinction between action and faith, however, created an important constitutional principle, that faith in and of itself could not be attacked or outlawed.
Undoubtedly the most famous of the free exercise cases involved the Jehovah's Witnesses and their refusal to salute the American flag. Although only one of many small religious sects in the United States, the Witnesses understood the basic meaning of the Free Exercise Clause, and in their repeated visits to the Supreme Court, helped to turn that ideal into a reality.
The Witnesses were and are a proselytizing sect, and their efforts to gain converts and distribute their literature have often brought them into conflict with local authorities. They gained enormous notoriety just before World War II when, in obedience to their belief that saluting a flag violated the biblical command against bowing down to graven images, they instructed their children not to join in the morning ritual of saluting the American flag. For this adherence to their beliefs as war approached, many Witness children were expelled from school, and their parents were subjected to fines and criminal hearings. Listen to the words of Lillian Gobitas:
Lillian Gobitas
I loved school, and I was with a nice group. I was actually kind of popular. I was class president in the seventh grade, and I had good grades. And I felt that, Oh, if I stop saluting the flag, I will blow all this! And I did. It sure worked out that way. I really was so fearful that, when the teacher would look my way, I would quick put out my hand and move my lips.
My brother William was in the fifth grade at that time, the fall of 1935. The next day Bill came home and said, I stopped saluting the flag. So I knew this was the moment! That wasn't something my parents forced on us. They were very firm about that, that what you do is your decision, and you should understand what you're doing. I did a lot of reading and checking in the Bible and I really took my own stand.
I went first to my teacher, Miss Anna Shofstal, so I couldn't chicken out of it. She listened to my explanation and surprisingly, she just hugged me and said she thought it was very nice, to have courage like that. But the students were awful. I really should have explained to the whole class but I was fearful. I didn't know whether it was right to stand up or sit down. These days, we realize that the salute itself is the motions and the words. So I sat down and the whole room was aghast. After that, when I'd come to school, they would throw a hail of pebbles and yell things like, Here comes Jehovah! They were just jeering at me. . . .
It has been more than fifty years since I took a stand on the flag salute, but I would do it again in a second. Without reservations! Jehovah's Witnesses do feel that we're trying to follow the Scriptures, and Jesus said, They persecuted me, and they will persecute you also. . . . The case affected our lives so much, and we have passed its lessons on to our children.
[Reprinted with the permission of The Free Press, a Division of Simon & Schuster Adult Publishing Group, from The Courage of Their Convictions by Peter Irons. Copyright ? 1988 by Peter Irons.]
The Supreme Court agreed to hear the case in 1939, and at a time when nearly everyone expected the United States would have to enter World War II, the value of promoting patriotism seemed a very important function of the public schools. Justice Felix Frankfurter, himself a Jew, found himself torn between his attachment to religious freedom for all groups and his belief that constitutionally the schools had a right to require students to salute the flag. To a colleague on the Court he wrote, "Nothing has weighed as much on my conscience, since I have come on this Court, as has this case. All my bias and pre-disposition are in favor of giving the fullest elbow room to every variety of religious, political, and economic view . . . but the issue enters a domain where constitutional power is on one side and my private notions of liberty and toleration and good sense are on the other." Eight of the nine members of the Court voted to uphold the school district.
How helpless the Witnesses were soon became apparent. In the wake of the adverse decision, there were hundreds of attacks on Witnesses, especially in small towns and rural areas. By the end of 1940, more than 1,500 Witnesses had been attacked, and many beaten brutally in over 350 incidents, and this pattern continued for at least two years. It was not one of the nation's finest moments, but it was a learning experience. At the same time that Americans learned about the attacks on the Witnesses, they also learned about Hitler's mass murders of helpless minorities in Europe and of his "final solution" that would liquidate six million men, women, and children for no other reason than their religious beliefs. The Supreme Court agreed to hear another case on the flag salute, and this time, a new member of the Court, Justice Robert H. Jackson, later to be American prosecutor at the Nuremberg trials, upheld the right of the Witnesses to be different and the limits that the Constitution put on government action.
Justice Robert H. Jackson, in West Virginia Board of Education v. Barnette (1943)
The very purpose of a Bill of Rights was to withdraw certain subjects from the vicissitudes of political controversy, to place them beyond the reach of majorities and officials and to establish them as legal principles to be applied by the courts. One's right to life, liberty, and property, to free speech, a free press, freedom of worship and assembly, and other fundamental rights may not be submitted to vote; they depend on the outcome of no elections.
The case is made difficult not because the principles of its decision are obscure but because the flag involved is our own. Nevertheless, we apply the limitations of the Constitution with no fear that freedom to be intellectually and spiritually diverse or even contrary will disintegrate the social organization. To believe that patriotism will not flourish if patriotic ceremonies are voluntary and spontaneous instead of a compulsory routine is to make an unflattering estimate of the appeal of our institutions to free minds. We can have intellectual individualism and the rich cultural diversities that we owe to exceptional minds only at the price of occasional eccentricity and abnormal attitudes. When they are so harmless to others or to the State as those we deal with here, the price is not too great. But freedom to differ is not limited to things that do not matter much. That would be a mere shadow of freedom. The test of its substance is the right to differ as to things that touch the heart of the existing order.
If there is any fixed star in our constitutional constellation, it is that no official, high or petty, can prescribe what shall be orthodox in politics, nationalism, religion, or other matters of opinion or force citizens to confess by word or act their faith therein. If there are any circumstances which permit an exception, they do not now occur to us.
There have been many other cases since the flag salute decisions, but all of them have built upon Justice Jackson's eloquent idea of a "fixed star," that no government official can prescribe what is orthodox. Not all decisions have gone in favor of the dissenting sects, but the notion that government cannot penalize thought remains as true today as it did a half century ago and at the time of the nation's founding.
* * * * *
Religion continues to play an important role in the civic and individual lives of American citizens. Some believe that it should play a greater role in the nation's public affairs, while others believe just the opposite. Laymen, scholars, legislators and jurists continue to debate where the line should be drawn between the activities of church and state, and how far dissenting groups may go in carrying out their religious beliefs. This debate is at the very heart of the democratic process. It does not always lead to consensus, and clearly not everyone can win every debate. But the sincerity and enthusiasm that Americans bring to this debate, as they do in dealing with the limits of free speech, is what makes the constitutional liberty stronger. Religious freedom is not an abstract ideal to Americans; it is a vibrant liberty whose challenges they confront every day of their lives.
For further reading:
Gregg Ivers, Redefining the First Freedom: The Supreme Court and the Consolidation of State Power (New Brunswick: Transaction Books, 1993).
Leonard W. Levy, The Establishment Clause: Religion and the First Amendment (2nd ed., Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1994).
John T. Noonan, Jr., The Lustre of Our Country: The American Experience of Religious Freedom (Berkeley: University of California Press, 1998).
Frank J. Sorauf, The Wall of Separation: The Constitutional Politics of Church and State (Princeton: Princeton University Press, 1976).
Melvin I. Urofsky, Religious Freedom (Santa Barbara: ABC-CLIO, 2002).