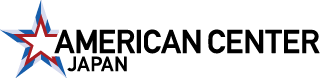国務省出版物
米国政府の概要 – 人民による政府 ― 市民の役割
「政府が誤りを犯さないようにすることは、市民の役目である」
— ロバート・H・ジャクソン、連邦最高裁判所陪席判事、1950年「米国通信協会対ダウズ事件」
1787年の合衆国憲法起草によって、米国の建国の父たちは、新しい形態の政府を創造した。その背後にある概念は、当時としてはかなり革新的だったが、一見したところでは、単純かつ直接的なものである。すなわち、統治の権限は、直接人民に由来するものであり、世襲や軍事力ではなく、米国市民による、自由で開かれた選挙を通じて得られるものだ、という概念である。これは、理論としては単刀直入で整然としているかもしれないが、実際には包括的と言うにはほど遠いものだった。当初から状況を複雑にしたのは、誰が投票を許され、誰が許されないかという投票資格の問題だった。
当然のことながら、建国の父たちは、当時の人間だった。彼らにとっては、社会に利害関係のある者だけが、その社会の統治者を決める際に発言権を持つべきであることは、自明の理だった。彼らは、財産と個人の自由を守るために政府は作られたのだから、その政府の選択に関与する者は、ある程度の財産と自由を所有しているべきだと考えた。
これは当時、財産を所有するプロテスタントの白人男性だけが投票できることを意味した。女性、貧困者、契約奉公人、カトリック教徒、ユダヤ教徒、アフリカ出身の奴隷、アメリカ・インディアンは、問題外だった。歴史家マイケル・シュドソンは、「女性は、奴隷や奉公人と同様、他人に依存する者とされていた。市民権を持っていたのは、自らの生活の主人である者だけだった」と述べている。こうした制約の結果、生まれたばかりのアメリカ合衆国で、1789年にジョージ・ワシントンを初代大統領に選出したのは、全人口のおよそ6%にすぎない人々だったのである。
これらの新しい米国民は、王室や貴族制度を廃止したことを誇りとしていたにもかかわらず、当初は「庶民」が相変わらず「紳士」階級に一目置いていた。そのため、財産と人脈を持つ一族の人々が、強力な反対もなしに公職を獲得することが多かった。しかし、こうした状況は長くは続かなかった。民主主義の概念は極めて強力であり、これを封じ込めることはできなかった。そして、あまり財産も人脈もない人々が、自分たちも行政に貢献する機会が与えられるべきだと考えるようになった。
19世紀を通じて米国の政治は、速度は緩やかだが、着実に、より包括的なものとなっていった。旧来の習慣が崩れ、それまで除外されていた集団が、政治のプロセスに関与するようになり、選挙権を与えられる人々が少しずつ増えていった。まず、宗教と財産所有に基づく制限がなくなり、19世紀半ばまでに、成人の白人男性の大半が投票できるようになった。
そして、奴隷制度問題を巡って戦われた南北戦争(1861~65年)の後に、合衆国憲法に付加された3つの修正条項が、米国の民主主義の範囲と性質を大きく変えた。1865年に批准された修正第13条は、奴隷制を廃止した。1868年に批准された修正第14条は、米国で出生し、ないしは帰化した人はすべて、米国と居住する州の市民であり、連邦政府は、彼らの生命、自由、財産の権利の保障と、法による平等な保護を履行しなければならない、と宣言した。1870年に批准された修正第15条は、連邦政府や州政府が、人種、肌の色、または過去の隷属状態を理由に、有権者となり得る者を差別することを禁止している。
上に列挙した理由の中に、「性別」という重要な言葉が抜けているのは、手違いではなかった。女性は依然として選挙権を阻まれていたのである。旧奴隷にまで選挙権が拡大されたことは、長い間噴出の機会を伺っていた女性参政権運動に新たな息吹きを与えた。この運動がようやく勝利を収めたのは1920年のことだった。同年、憲法修正第19条により、「性別を理由として」投票権を拒否してはならないことが定められた。
皮肉なことに、この時点で、状況が逆転した。すなわち、女性は投票できるようになったが、黒人の米国民の多くは投票ができなかったのである。1890年代から、米国南部の白人は、各種の選挙規則を設けることによって、組織的に黒人を選挙から排除していた。そうした規則には、1868年以前に先祖が投票権を持っていなかった市民に識字試験を義務付けた「祖父条項」もあった。人頭税の課税などもあった。また身体的な威嚇もしきりに行われた。こうした形の選挙権の剥奪は、20世紀に入っても長く続いた。1950年代に始まった公民権運動の結果、不公正選挙を違法とし、南部の選挙を司法省が監督することを義務付けた投票権法が、1965年に制定された。1964年に批准された修正第24条は、投票資格が持てる人頭税を廃止した。人頭税はアフリカ系米国人と貧困者の投票を妨害するための、州が持つ残り少ない手段のひとつで、これが除去された。
参政権を拡大するため、最後にもうひとつ憲法修正条項が追加された。1960年代と70年代の初めに、米国がベトナム戦争に関与したことによって、最初は独立戦争中に論議され、それ以降、戦争のたびに蒸し返されてきた概念が、新たな力を得た。それは、国のために武器を持てる年頃の者は、投票できる年頃でもある、という考え方である。1971年に批准された修正第26条は、投票年齢を21歳から18歳に引き下げた。今日では、18歳以上の米国市民は、米国生まれか帰化市民かを問わず、ほぼ全員が投票権を持つ。法的に投票権を制限されるのは、一部の重犯前科者と心神喪失を宣言された者だけである。
現在の米国の選挙制度が抱える最も重要な問題は、誰に投票権があるかではなく、投票権を持つ者のうち何人が、実際に手間と時間をかけて投票所へ行くか、ということである。ほぼ半分、というのが、現在の大統領選の場合の答である。1876年に、投票率は史上最高の81.8%に達した。1880年代から90年代を通じて、投票率は平均80%前後だったが、その後徐々に低下し、1924年には最低記録の48.9%となった。1930年代の大恐慌時代には、民主党の「ニューディール連合」によって有権者の関心が復活し、投票率は平均60%前後に上昇した。しかし、1968年には再び低下を始め、1996年の大統領選の投票率は49.1%まで下がった。
こうした投票率の低さは、多くの人々を嘆かせている。政治学者A・ジェームズ・ライクリーは、著書『アメリカ型の選挙(Elections American Style)』で、次のように述べている。「現在、世論調査や有識者の苦情が示しているように、米国の選挙制度には問題がある、という意識が広まっている。これは小さな問題であり、穏健な改革で対処できる、という意見もあれば、問題の根は深く、抜本的な政治的処置、そしておそらく、より広範な社会秩序の大きな変化が必要だ、という意見もある。現状に対する苦情には、選挙運動の膨大な費用と期間の長さ、候補者に対する一般市民の見方を形成するマスコミの力、そして候補者指名と総選挙の双方における『特別利益団体』の不当な影響力、などがある」
多くの解説者は、米国の選挙制度が必要としているのは、より直接的で、より代議制の度合いの少ない民主主義だ、と考えている。例えば、有権者が公選の政治家や候補者と直接話すことのできる、タウンホール・ミーティング(市民集会)のテレビ中継が、一般市民に「力を与える」手段のひとつとして推進されている。また、住民発議や住民投票、リコール選挙の実施が急速に増えている。正確な仕組みは州によって違うが、一般的に言って、住民発議は、有権者が十分な署名を集めることによって、法案や、州によっては憲法修正条項を、州議会を通さずに直接、投票にかけることのできる制度である。住民投票制度では、特定の種類の法案、例えば債券発行による融資のための法案などを、一般市民の承認を得るために投票にかけることが義務付けられている。また、州議会がすでに可決した法律でも、有権者が住民投票によって無効にすることができる。リコール選挙では、公職者を任期終了前に解任するかどうかを一般市民が決めることができる。
この住民発議(イニシアチブ)は、現在24州で認められているが、特に米国西部でよく使われており、オレゴン州では300回以上、カリフォルニア州では250回以上、コロラド州では200回以上実施されている。各州で多種多様な発議が投票にかけられており、例としては、職業や商取引の規制、禁煙法、自動車保険料、人工妊娠中絶の権利、賭博の合法化、大麻の医療使用、原子力の利用、銃砲規制などがある。
米国の市民には、すべての人々にとって貴重な様々な自由を可能にする、多くの権利が与えられていることは明らかである。思考の自由。そうした思考に基づく意見を公選の代議員に対して個人的に、あるいは大小の集会で集団として、伝える自由。心のままに礼拝する自由、あるいは全く礼拝しない自由。そして、身体や住居や私文書を不当に捜索されない自由、などである。しかし、民主政治の理論によると、こうした権利には義務が伴う。それは、法律を守り、合法的に賦課された税金を納め、要請された場合には陪審を務め、選挙の論点と候補者について見識を持ち、また先人が労苦と涙によって多くの人々のために勝ち取ってきた投票の権利を行使する義務である。
もうひとつの主要な義務は、公的奉仕である。これまで国家の非常時には、何百万人もの米国人男女が、国を守るため軍隊に入隊してきた。さらに何百万という米国民が、平和時に国家の軍事力を維持するため軍務に就いてきた。また米国人は老いも若きも、国内外で、平和部隊などのボランティア組織に参加してきた。
しかし、最も永続的な違いを生む義務は、政治の過程に関与することである。政治学教授のクレーグ・リマーマンは、著書『新しい市民―既成概念を超えた政治、行動主義、奉仕(The New Citizenship: Unconventional Politics, Activism, and Service)」で、次のように述べている。「参加型民主主義を擁護する人たちの説によると、より大きな地域社会の中で人々が自らの役割と責任を認識するためには、地域社会や職場の意思決定への市民参加の拡大が重要である。例えば、地域の市民集会では、市民が他の市民の要求を知ることができる。真の参加型民主主義においては、市民は各自の利益を追求する自立的な個人として行動するのではない。それどころか、決断、討論、および譲歩の過程を通じて、最終的には、自らの関心事を地域社会の要求に結び付けるのである」
アイオワ州選出のトム・ハーキン連邦上院議員の言葉によると、初期の公民権運動、ベトナム反戦運動、そして環境運動を推進した活動家たちが、今はそのエネルギーを「より身近なところ」に集中し、近隣の住民を組織して、住宅供給の改善、公正な課税、公共料金の引き下げ、有毒廃棄物の清掃などの課題に取り組んでいる…。こうした活動は、人種や階級、そして地理的な境界を超えて、共通の利害の方が相違よりはるかに大きいことを、何百人もの人々に示してきた。(彼ら全員にとって、)市民運動のメッセージはひとつ。怒らず、いら立たず、くじけず、組織して応戦しよう―である」
現状を憂慮する米国の有権者の中には、公選の政治家、特に大統領や自州選出の上院議員・下院議員に連絡を取ることによって関与を続けている人々もいる。彼らは、手紙、電報、あるいは電話で意見を伝えたり、ワシントンまたは地元の州や選挙区で、政治家の事務所を直接訪れたりしている。しかし、ここ数年の間に、新たな通信媒体が突如として登場し、有権者に多大な力を与えている。それは有権者が世界中の出来事を知り、それについて意見を発信し、不満な点を変えるために働きかけることを可能にする力である。この媒体こそ、インターネット、ワールドワイド・ウェブ、情報スーパーハイウェーと呼ばれる媒体である。どのように呼ばれようと、この媒体は、米国の政治を急速に、決定的に変えつつある。
政治活動家のエド・シュワルツは、著書「ネットアクティビズム―市民によるインターネットの使い方(NetActivism: How Citizens Use the Internet)」の中で、インターネットは「集団行動の手段として使おうとするならば、その強力な手段」となり得るとし、「それは、この50年間に開発された政治組織ツールの中で、最も強力な、しかも誰でも使えるものとなる可能性がある。地域の活動家がしばしば最も必要とするのは、政府機関および特定の制度や、政治制度の機能についての、確実な情報である」と述べている。インターネットを使えば、活動家はこうした情報を容易に、事実上無料で入手することができる。
インターネット上では、同じような関心を持つ人々から成る、「バーチャル・コミュニティ(仮想共同体)」で、何千マイルも離れた町に住み、インターネットがなければ決して知り合うことのなかったような人たちが、団結しつつある。こうした人々は、直接顔を合わせることはめったにないが、強い関心を持つ問題について、長期にわたる知的な対話を続けることによって、お互いを良く知ることになる。
もうひとつの著しい変化は、インターネットによって、政府や政治、そしてさまざまな課題について、以前は入手が不可能あるいは困難であった情報を、市民が迅速に入手できるようになったことである。
例えば「EnviroLink」という、環境問題専門のウェブサイトがある。地域の組織や団体は、このサイトで、温室効果ガスの排出、有害廃棄物、有毒化学物質などに関する具体的な情報を得ることができる。以前は、こうした組織や団体も、これらの課題について、大まかなことしか発言しかできなかったかも知れない。しかし今では、EnviroLinkのおかげで、詳しい資料が直ちに入手できる。このサイトには、教育センター、政府機関、環境団体、環境出版物などのリンク先が、分野別に記載されている。また、特定の環境問題について、担当者の氏名とメールアドレスを記載し、直接行動を取るための情報とアドバイスを提供しているほか、同サイトのユーザーが討論し意見の交換ができる「チャット・ルーム」を設けている。
地域レベルの活動家にとって、インターネットは特に便利である。こうした人々は、自分たちの住む地域や地域社会の状況を改善するひとつの手段として、政治に関与している。彼らは、町内の清掃、ゴミのリサイクル、犯罪監視グループ、成人識字教育などを組織する。エド・シュワルツは、「地域奉仕は彼らの目的のひとつだが、それだけが目的ではない。彼らは、住民が自らの福祉に貢献するため個人的に献身しない限り、健全な地域社会は実現しない、と愚直に信じている」と述べている。
こうした人々によるインターネット利用の一例として、シュワルツが全米の地域活動を促進するために設置した、「Neighborhoods Online」というウェブサイトがある。組織者、非営利組織のスタッフ、公選の政治家、ジャーナリスト、大学の教授や学生、そして一般市民など、近隣の問題を解決するための新たな手段を求める人々が、毎日何百人も、このサイトを訪れている。
シュワルツは、「当初は小規模だったが、今では、ほぼすべての地域開発公社、地域顧問委員会、成人識字教育プログラム、雇用訓練機関、そして福祉サービス供給者が、すでにつながっているか、ないしはそのための手段を検討している」と述べている。
上記のような団体は、全体の利益を求め、それが必ずしもその団体の構成員の利益になるとは限らないという点で、公益団体と呼ばれる。これは、そうした団体の立場が正しいということではなく、単に利潤や、特定の自己利益を求める要素が少ないことを意味する。
これに対して、私益団体は、通常、支持する政策に、経済的な利害が絡んでいる。事業組織は、法人税の引き下げやスト権の制限を支持する。これに対して労働組合は、最低賃金法や団体交渉の保護を支持する。また、その他の教会や民族団体などの私益団体は、彼らの組織や信条に影響を及ぼすような、より広範な政策課題に関心がある。
近年、数の上でも影響力の上でも拡大している私益団体に、政治活動委員会(PAC)がある。PACとは、単一の、または一連の争点を中心に組織され、連邦議員や大統領を選出するための政治運動に資金を提供する独立団体である。連邦選挙においてPACが直接候補者に寄付できる金額には制限がある。しかし、PACが特定の視点を支援したり、候補者の当選を促したりするために、独自に費やすことのできる金額には制限がない。今日、PACの数は数千に上る。
マイケル・シュドソンは、著書『良き市民―アメリカの市民生活史(The Good Citizen: A History of American Civic Life )」で、次のように述べている。「利益団体が急増し、ワシントンDCに事務所を設置して、自らの代表を直接連邦議会や連邦機関に直接送り込む団体が増えていることは、各政党にとって脅威となっている。ワシントンを監視する組織の多くは、一般市民から、財政的、精神的な支援を求めている。そうした組織の多くは、狭い範囲の課題、あるいは単一の争点に焦点を絞っている。そうした単一争点アプローチは、往々にして感情に訴える力が非常に強い。このため、各政党を相手に、一般市民の資金、時間、情熱を奪い合う存在となる。」
選挙運動費がますます増大するに従い、こうした「特別利益団体」の費やす資金は増加を続けている。多くの米国民は、企業、組合、PACを問わず、豊富な資金を持つ利益団体の力が極めて強いため、一般市民がそうした団体の影響力に対抗することはほとんど不可能だ、と感じている。
しかし、一般市民にもできることはある。それは、情報を入手し、それに基づいて行動することである。おそらく、その手段として最も迅速かつ効率的なのは、インターネットを利用して、地元選出の政治家の動向を追跡することである。市民は、どの特別利益団体がどの政治家に寄付をしているか、またその政治家が最近の法案についてどのように投票しているかを、ものの数分もたたないうちに知ることができる。そして、こうした情報をもとに、自分の意見を発信することができる。
争点について考え、それに関する情報を集め、友人や地域の住民と話し合っても、政治家がどう行動するか、どう投票するかには、関係ない。それが、政治の厳しい現実である。しかし政治家は、地元の有権者が再び自分に票を投じるかどうかを、ひどく気にするものだ。地元選挙区から手紙や電話、ファックス、電子メールが届き始めると、政治家は注意を払う。最終的な力を持つのは、それぞれが選択して1票を投ずる市民なのである。
1787年の合衆国憲法起草から現在までの道は、真っすぐなものではなかった。有権者は、その時々の激情や出来事によって、最初は右へ、次は左へと動かされてきた。しかし、彼らは常に、どこかの時点で、中道近くで一休みするために戻ってくる道を見つけてきた。実利と理想、地方と連邦、公共と民間、利己と利他、そして州の権限と国家全体の利益の間のどこかに、合意点が存在する。米国民は、長年にわたって、その合意点を基盤として、強く豊かで自由な国を、欠点はあるが、常に未来のより良い日々を目指してまい進する国を、築いてきたのである。
米国の建国の父の多くは、政党という概念を嫌った。対立する「派閥」は、共通の目標に向けて協力するより、互いに争うことに力を入れるに違いない、と彼らは考えたのである。そして、組織集団の介入を受けずに、個々の市民が個々の候補に投票することを望んだ。しかし、現実にはそうはならなかった。
1790年代までには、この新国家の進むべき方向について、いくつかの異なる見解が生じた。対立する意見を持つ人々は、それぞれ党派を組むことによって支持を得ようとした。アレグザンダー・ハミルトンの支持者は、自らを「連邦派」と称し、商工業の利益を支持する強力な中央政府を推進した。トーマス・ジェファーソンの支持者は、「民主共和派」と称し、連邦政府の権限が制限された、地方分権の農業共和国を推進した。1828年までに、組織としての連邦派は消失し、代わりに、同年大統領となったアンドリュー・ジャクソンに対抗するためにホイッグ党が誕生した。民主共和派は民主党となった。かくして今日まで続く2大政党制が生まれたのである。
1850年代には、奴隷制問題が脚光を浴び、特に、米国西部の新たな領土で奴隷制を認めるべきかどうかが争点となった。この問題に関して賛否を明らかにしなかったホイッグ党は消滅した。これに代わって1854年に誕生した共和党は、すべての領土から奴隷制を排除することを主な政策とした。この新党は、わずか6年後の1860年には、エイブラハム・リンカーンを候補に立てて、大統領の座を獲得した。その頃には政党は、米国の圧倒的な政治組織として確立し、ほとんどの人々の意識の中に、政党への忠誠が重要な位置を占めるようになっていた。政党への忠誠は、父から息子へ受け継がれ、制服姿の隊列行進やたいまつ行列も登場する派手な選挙運動イベントなど政党活動が、多くの地域で社会生活の一部となった。
しかし、1920年代までに、こうした陽気で庶民的な雰囲気は弱まった。市政改革や公務員制度改革、汚職防止法、そして政治家が牛耳る全国党大会に代わって、大統領予備選が行われるようになったことによって、政治が浄化され、同時に娯楽性もかなり薄くなった。
なぜ米国は2つだけの政党による政治に落ち着いたのか。米国の公職者の多くは、1選挙区1人制の選挙区から選出され、「比較多数得票」制で対立候補を破って当選する。これは、最多票を得た候補が勝者となる制度で、比例配分は行われない。こうした制度は、2党支配を助長する。すなわち、ひとつの政党が権力を握れば、もうひとつは力を失うが、力を失った者が結束すれば、権力の座にある者を破る可能性が高まる。時には第3党が現われ、少なくともしばらくの間は、ある程度の票を獲得することもある。近年、最も成功を収めた第3党は、1992年と1996年の大統領選挙でかなり健闘した、H・ロス・ペローの改革党である。1998年にミネソタ州知事に当選したジェシー・ベンチュラは、州レベルで官職に当選した初の改革党候補となった。しかし、第3党にとって今は、存続するのが辛い時期である。2大政党のどちらか、または両方が、第3党の人気のある主張を横取りし、ついでに第3党の支持者まで奪ってしまうことが多いからである。
政治学教授のネルソン・W・ポルスビーは、著書『新フェデラリスト・ペーパーズ―憲法擁護論(New Federalist Papers: Essays in Defense of the Constitution)」で、「米国においては、民主党または共和党という政治的分類が、ほぼすべての公職者に当てはまり、従って全国各地のほぼすべての有権者は、この2大政党のいずれかの下で動員される」と前書きしながらも「ただ、各地の民主党員と共和党員は、すべて同じだとは限らない。50州それぞれの政治文化には、時には微妙な、時には明白な相違がある。その結果、全体的には、民主、共和両党の党員であること、あるいは両党の候補に投票することの意味が、かなり異なってくる。こうした相違を考慮すると、米国の2大政党制は、現実には100政党制に近いものを覆い隠している、という見方にも正当性があるかもしれない」と述べている。
米国民は、米国の新しい民主制が正しく機能するためには、情報を容易に入手できることが不可欠であることに、早くから気付いていた。情報がなければ、候補者や政策について、正しい判断を下すことはできない。そして、こうした情報が役立つためには、入手しやすく、広く配布されなければならない。
この要求に応えられるのは、新聞だった。米国初の日刊紙は、1783年にペンシルベニア州フィラデルフィア市で発行された。1800年までには、フィラデルフィア市で日刊6紙、ニューヨーク市では5紙、メリーランド州ボルティモア市では3紙、そしてサウスカロライナ州チャールストン市では2紙が発行されており、このほかにも全米各地で250紙(主に週刊紙)が発行されていた。1850年までに、全米で2000紙があり、うち200紙が日刊紙だった。
米国では、建国当初から、ジャーナリスト特有の頑固さが、多くの政治家との衝突の原因となってきた。ジョージ・ワシントンは、1792年に、「政府とその職員が、常に新聞による嫌がらせの対象となり、しかも動機や事実の調査もせずにそうした嫌がらせが行われるならば、どのような生身の人間にとっても、指揮を取ったり、組織を統率したりすることは不可能だ、と私は考える」と書いた。一方で、政治家たちは、有権者に情報を与える上でマスコミが果たす重要な役割も認識していた。トーマス・ジェファーソンは1787年に、「新聞のない政府を取るか、政府のない新聞を取るかの決定を私が任されたら、私は一瞬たりとも迷うことなく後者を選ぶ」と書いた。
1924年には、全国党大会の議事進行が初めて生中継のラジオで放送され、ラジオが政治において重要な役割を果たすようになった。この年、両政党はラジオ広告費を払い始め、共和党は12万ドル、民主党は4万ドルを費やした。その4年後には、両政党ともに、ラジオ広告費が100万ドルに跳ね上がって、選挙資金支出の急増が始まった。この傾向は近年ますます加速している。
1934年に、ジョージ・ギャラップが、主な選挙区の少数のサンプルを手始めに、世論調査の実施を始めた。こうした調査は、「津々浦々で議員や教育者、専門家、編集者、そして一般市民が、民主主義の鼓動をより確実に知るための、迅速かつ効率的な手段」を提供する、と彼は考えた。今日の世論調査は、経験に基づいて質問が微調整され、分析に近代技術が取り入れられて、はるかにきめ細かいものとなっている。時には誤差があるものの、一般的に世論調査は、世論を追跡する効果的な方法とみなされている。
政治的な大会が初めてテレビで放送されたのは1940年で、視聴者数は10万人だった。1950年代までに、米国家庭の3分の1にテレビが普及していた。1952年の選挙運動では、両政党がテレビ広告に350万ドルを費やしたが、テレビ広告費でも共和党が民主党を大きく引き離していた。1960年のケネディ・ニクソン両大統領候補によるテレビ討論会は、近代の選挙運動におけるテレビの重要性や役割を不動のものとした。
英国の歴史家フィリップ・ジョン・デイビースは、著書『選挙USA(Elections USA)』で次のように述べている。「ほとんどの米国人にとって、テレビは最も重要な情報源となっている。主要な公職の候補は、強い印象を売り込もうとするならば、テレビのニュース報道を無視することはできない立場にある。またこの媒体を通じて宣伝をする機会を見逃すこともできない…。しかも、一般市民は、少なくとも主な公職の候補には、テレビ出演を期待するようになっている。連邦や州レベル、あるいは主要な地方の候補者は、引き続きラジオや活字媒体の広告を効果的に使っているが、テレビで売り込まないと、選挙運動に説得力がなくなってしまう。」
Outline of U.S. Government - Government of the people: The Role of the Citizen
"It is the function of the citizen to keep the government from falling into error."
– Robert H. Jackson, Associate Justice of the U.S. Supreme Court, American Communications Association v. Douds, 1950
With the drafting of the U.S. Constitution in 1787, the country’s Founding Fathers created a new system of government. The idea behind it — quite revolutionary at the time — appears at first glance to be simple and straightforward. The power to govern comes directly from the people, not through primogeniture or the force of arms, but through free and open elections by the citizens of the United States. This may have been tidy and direct as a theory, but in practice it was far from inclusive. Complicating things from the very beginning was the question of eligibility: who would be allowed to cast votes and who would not.
The Founding Fathers were, of course, men of their time. To them, it was self-evident that only those with a stake in society should have a voice in determining who would govern that society. They believed that, since government was established to protect property and personal freedom, those involved in choosing that government should have some of each.
This meant, at the time, that only white Protestant males who owned property could vote. Not women, not poor people, not indentured servants, not Catholics and Jews, not slaves from Africa or Native Americans. “Women, like slaves and servants, were defined by their dependence,” says historian Michael Schudson. “Citizenship belonged only to those who were masters of their own lives.” Because of these restrictions, only about 6 percent of the population of the brand-new United States chose George Washington to be the country’s first president in 1789.
Even though these new Americans were proud of the fact that they had gotten rid of royalty and nobility, “common” people, at first, continued to defer to the “gentry.” Therefore, members of rich and well-connected families generally won political office without much opposition. This state of affairs, however, did not last long. The concept of democracy turned out to be so powerful it could not be contained, and those who were not so rich and not so well-connected began to believe that they, too, should have the opportunity to help run things.
Extending the Franchise
Throughout the 19th century, politics in the United States became, slowly but inexorably, more inclusive. The old ways broke down, groups previously excluded became involved in the political process, and the right to vote was given, bit by bit, to more and more of the people. First came the elimination of religious and property-owning restrictions, so that by the middle of the century most white male adults were able to vote.
Then, after a Civil War was fought (1861–1865) over the question of slavery, three amendments to the U.S. Constitution significantly altered the scope and nature of American democracy. The Thirteenth Amendment, ratified in 1865, abolished slavery. The Fourteenth, ratified in 1868, declared that all persons born or naturalized in the United States are citizens of the country and of the state in which they reside, and that their rights to life, liberty, property and the equal protection of the laws are to be enforced by the federal government. The Fifteenth Amendment, ratified in 1870, prohibited the federal or state governments from discriminating against potential voters because of race, color or previous condition of servitude.
The crucial word “sex” was left off this list, not through oversight; therefore, women continued to be barred from the polls. The extension of suffrage to include former slaves gave new life to the long-simmering campaign for women’s right to vote. This battle was finally won in 1920, when the Nineteenth Amendment said that voting could not be denied “on account of sex.”
Ironically, at this point the situation was reversed. Women could now vote, but many black Americans could not. Beginning in the 1890s, southern whites had systematically removed blacks from electoral politics through voting regulations such as the “grandfather clause” (which required literacy tests for all citizens whose ancestors had not been voters before 1868), the imposition of poll taxes, and, too often, physical intimidation. This disfranchisement continued well into the 20th century. The civil rights movement, which began in the 1950s, resulted in the Voting Rights Act of 1965, a federal law that outlawed unfair electoral procedures and required the Department of Justice to supervise southern elections. The Twenty-fourth Amendment, ratified in 1964, abolished the imposition of a poll tax as a qualification for voting, eliminating one of the few remaining ways that states could try to reduce voting by African Americans and poor people.
One final change was made to the Constitution to broaden the franchise. U.S. involvement in the Vietnam War during the 1960s and early 1970s gave new impetus to the idea, first discussed during the Revolutionary War and revived during every war fought since, that people old enough to bear arms for their country were also old enough to vote. The Twenty-sixth Amendment, ratified in 1971, reduced the voting age from 21 to 18 years. Now, nearly all adult citizens of the United States, native-born or naturalized, over the age of 18 are eligible voters. Legal restrictions deny the vote only to some ex-felons and to those who have been declared mentally incompetent.
Direct Democracy
The most important question in U.S. electoral politics these days is not who is eligible to vote, but rather how many of those who are eligible will actually take the time and trouble to go to the polls. The answer now, for presidential elections, is around half. In the election of 1876, voter participation reached the historic high of 81.8 percent. Throughout the 1880s and 1890s, it averaged around 80 percent, but then began a gradual decline that reached a low of 48.9 percent in 1924. The Democratic Party’s “New Deal Coalition” during the Great Depression of the 1930s caused a revival of interest on the part of voters, resulting in averages up around 60 percent. Turnouts started back down again in 1968, reaching a low of 49.1 percent in the presidential election of 1996. Turnout went up to 62.2 percent in the 2008 presidential election and slipped to 58.7 percent in 2012.
The fact that more people do not vote is distressing to many. “There is currently a widespread sense, shown by public opinion surveys and complaints by informed observers, that the American electoral system is in trouble,” says political scientist A. James Reichley in his book Elections American Style. “Some believe that this trouble is minor and can be dealt with through moderate reforms; others think it goes deep and requires extensive political surgery, perhaps accompanied by sweeping changes in the larger social order. Complaints include the huge cost and long duration of campaigns, the power of the media to shape public perceptions of candidates, and the undue influence exerted by ‘special interests’ over both nominations and general elections.”
Many commentators believe that what the U.S. electoral system needs is more direct, less representative, democracy. Televised town hall meetings, for example, at which voters can talk directly to elected officials and political candidates, have been encouraged as a way to “empower” the people. And the use of ballot initiatives, referendums and recall elections is growing rapidly. The precise mechanisms vary from state to state, but in general terms, initiatives allow voters to bypass their state legislatures by collecting enough signatures on petitions to place proposed statutes and, in some states, constitutional amendments directly on the ballot. Referendums require that certain categories of legislation, for example, those intended to raise money by issuing bonds, be put on the ballot for public approval; voters can also use referendums to rescind laws already passed by state legislatures. A recall election lets citizens vote on whether to remove officeholders before their regular terms expire. A 2012 recall election in Wisconsin resulted in the incumbent Republican governor, Scott Walker, remaining in office.
Initiatives, now allowed by 24 states, have been especially popular in the West, having been used more than 300 times in Oregon, more than 250 times in California, and almost 200 times in Colorado. All sorts of issues have appeared on the ballot in the various states, including regulation of professions and businesses, anti-smoking legislation, vehicle insurance rates, abortion rights, legalized gambling, the medical use of marijuana, the use of nuclear power, and gun control.
Responsibilities of Citizenship
Citizens of the United States, it is clear, have a great many rights that give them freedoms all peoples hold dear: the freedom to think what they like; to voice those opinions, individually to their elected representatives or collectively in small or large assemblies; to worship as they choose or not to worship at all; to be safe from unreasonable searches of their persons, their homes or their private papers. However, the theory of democratic government holds that along with these rights come responsibilities: to obey the laws; to pay legally imposed taxes; to serve on juries when called to do so; to be informed about issues and candidates; and to exercise the right to vote that has been won for so many through the toil and tears of their predecessors.
Another major responsibility is public service. Millions of American men and women have entered the armed forces to defend their country in times of national emergency. Millions more have served in peacetime to maintain the country’s military strength. Americans, young and old alike, have joined the Peace Corps and other volunteer organizations for social service at home and abroad.
The responsibility that can make the most lasting difference, however, is getting involved in the political process. “Proponents of participatory democracy argue that increased citizen participation in community and workplace decision-making is important if people are to recognize their roles and responsibilities as citizens within the larger community,” says Craig Rimmerman, professor of political science, in his book The New Citizenship: Unconventional Politics, Activism, and Service. “Community meetings, for example, afford citizens knowledge regarding other citizens’ needs. In a true participatory setting, citizens do not merely act as autonomous individuals pursuing their own interests, but instead, through a process of decision, debate and compromise, they ultimately link their concerns with the needs of the community.”
Tom Harkin, U.S. senator from Iowa, says that the kind of activists who fueled the earlier civil rights, anti-Vietnam War, and environmental movements are now focusing their energies “closer to home, organizing their neighbors to fight for such issues as better housing, fair taxation, lower utility rates, and the cleanup of toxic wastes. ... Cutting across racial and class and geographical boundaries, these actions have shown millions of people that their common interests far outweigh their differences. (For all of them) the message of citizen action is the same: ‘Don’t get mad, don’t get frustrated, don’t give up. Organize and fight back.’”
Digitalizing Democracy
Some concerned American voters have chosen to stay involved by being in touch with their elected officials, in particular the president and their senators and representatives. They have written letters, sent telegrams, made telephone calls, and gone in person to the official’s office, whether in Washington or in the home state or district.
More and more now, communication between government and citizens has gone digital. Candidates running for office employ websites, email and social media such as Facebook and Twitter to energize their supporters; many of them continue reaching the public by tweeting after they take office. Citizens conduct discussion of issues and register complaints through social media. Local and state governments go online to let residents renew their auto registrations, notify them of school closings because of bad weather, and remind them that a library book is overdue; and libraries are lending more books online as e-books. On some occasions people can participate digitally in virtual town hall–style meetings.
The federal government has pursued a strategy aiming to provide to citizens high-quality information and services whether they use desktop personal computers, tablets or smartphones.
Private Interest Groups
The groups discussed above and others like them are called public interest groups, in that they seek a collective good, the achievement of which will not necessarily benefit their own membership. This does not mean that such groups are correct in the positions they take, only that the element of profitable or selective self-interest is low.
Private interest groups, on the other hand, usually have an economic stake in the policies they advocate. Business organizations will favor low corporate taxes and restrictions of the right to strike, whereas labor unions will support minimum wage legislation and protection for collective bargaining. Other private interest groups — such as churches and ethnic groups — are more concerned about broader issues of policy that can affect their organizations or their beliefs.
One type of private interest group that has grown in number and influence in recent years is the political action committee, or PAC. These are independent groups, organized around a single issue or set of issues, that contribute money to political campaigns for Congress or the presidency. PACs are limited in the amounts they can contribute directly to candidates in federal elections. There are no restrictions, however, on the amounts PACs can spend independently to advocate a point of view or to urge the election of candidates to office. PACs today number in the thousands.
“The political parties are threatened as the number of interest groups has mushroomed, with more and more of them operating offices in Washington, D.C., and representing themselves directly to Congress and federal agencies,” says Michael Schudson in his book The Good Citizen: A History of American Civic Life. “Many organizations that keep an eye on Washington seek financial and moral support from ordinary citizens. Since many of them focus on a narrow set of concerns or even on a single issue, and often a single issue of enormous emotional weight, they compete with the parties for citizens’ dollars, time and passion.”
The amount of money spent by these “special interests” continues to grow, as campaigns become more and more expensive. Many Americans have the feeling that these wealthy interests — whether corporations or unions or PACs organized to promote a particular point of view — are so powerful that ordinary citizens can do little to counteract their influence.
But they can do something. They can inform themselves and then act on that information. Perhaps the quickest and most efficient way is by using the Internet to keep track of each of their elected officials. Within a matter of minutes, they can find out which “special interests” have given political contributions to an official and how that official has voted on recent pieces of legislation. These citizens can then use this information to make their opinions known.
A fact of political life is that thinking about issues, gathering information about them, and discussing them with friends and neighbors make no difference in how elected officials act — or, more important, vote. These officials care a great deal, though, about whether those who elected them are likely, or not likely, to elect them again. When letters, phone calls, faxes and email messages from constituents start to arrive, attention is paid. It is still the people, each one with a vote whenever he or she chooses to cast it, who have the ultimate power.
The road from 1787 and the drafting of the U.S. Constitution to the present has not been a straight one. Voters have been moved by passions and events first in one direction, then in another. But, at some point, they have always found a way to come back to rest near the center. Somewhere between the pragmatic and the ideal, between the local and the national, between the public and the private, between selfishness and altruism, between states’ rights and the good of the nation as a whole, exists a common ground on which the people of the United States have, through the years, built a strong, prosperous, free country — a country that is flawed, granted, but always spurred on by the promise of better days to come.
Political Parties
Many of America’s Founding Fathers hated the thought of political parties, quarreling “factions” they were sure would be more interested in contending with each other than in working for the common good. They wanted individual citizens to vote for individual candidates, without the interference of organized groups — but this was not to be.
By the 1790s, different views of the new country’s proper course had already developed, and those who held these opposing views tried to win support for their cause by banding together. The followers of Alexander Hamilton called themselves Federalists; they favored a strong central government that would support the interests of commerce and industry. The followers of Thomas Jefferson called themselves Democratic-Republicans; they preferred a decentralized agrarian republic in which the federal government had limited power. By 1828, the Federalists had disappeared as an organization, replaced by the Whigs, brought to life in opposition to the election that year of President Andrew Jackson. The Democratic-Republicans became Democrats, and the two-party system, still in existence today, was born.
In the 1850s, the issue of slavery took center stage, with disagreement in particular over the question of whether or not slavery should be permitted in the country’s new territories in the West. The Whig Party straddled the issue and sank to its death; it was replaced in 1854 by the Republican Party, whose primary policy was that slavery be excluded from all the territories. Just six years later, this new party captured the presidency when Abraham Lincoln won the election of 1860. By then, parties were well established as the country’s dominant political organizations, and party allegiance had become an important part of most people’s consciousness. Party loyalty was passed from fathers to sons, and party activities — including spectacular campaign events, complete with uniformed marching groups and torchlight parades — were a part of the social life of many communities.
By the 1920s, however, this boisterous folksiness had diminished. Municipal reforms, civil service reform, corrupt practices acts, and presidential primaries to replace the power of politicians at national conventions had all helped to clean up politics — and make it quite a bit less fun.
Why did the United States end up with only two political parties? Most U.S. voting districts elect only one representative. Candidates win office by beating out their opponents in a system for determining winners called “first-past-the-post” — the one who gets the most votes wins, and there is no proportional accounting. This encourages the creation of a duopoly: one party in power, the other out. If those who are “out” band together, they have a better chance of beating those who are “in.”
Occasionally third parties do come along and receive some share of the votes, for a while at least. The most successful third party in recent years has been H. Ross Perot’s Reform Party, which had some success in the presidential elections of 1992 and 1996. Jesse Ventura became the first Reform Party candidate to win statewide office when he was elected governor of Minnesota in 1998. Some Democrats criticized consumer advocate Ralph Nader’s 2000 presidential campaign as the Green Party candidate for siphoning support from their candidate, Vice President Al Gore, who narrowly lost the election. Third parties have a hard time surviving, though, because one or both of the major parties often adopt their most popular issues, and thus their voters.
“In America the same political labels — Democratic and Republican — cover virtually all public officeholders, and therefore most voters are everywhere mobilized in the name of these two parties,” says Nelson W. Polsby, professor of political science, in the book New Federalist Papers: Essays in Defense of the Constitution. “Yet Democrats and Republicans are not everywhere the same. Variations — sometimes subtle, sometimes blatant — in the 50 political cultures of the states yield considerable differences overall in what it means to be, or to vote, Democratic or Republican. These differences suggest that one may be justified in referring to the American two-party system as masking something more like a hundred-party system.”
The Media
Americans realized early on that easy access to information would be fundamental to the proper functioning of their new democracy. They would not be able to make sound decisions about candidates and policies without it. To be effective, moreover, this information would have to be readily available and widely distributed.
The answer was newspapers. America’s first daily paper appeared in Philadelphia, Pennsylvania, in 1783. By 1800, Philadelphia had six dailies; New York City had five; Baltimore, Maryland, had three; and Charleston, South Carolina, had two, with almost 250 other papers, most of them weeklies, scattered around the country. By 1850, there were 2,000 papers, including 200 dailies.
The independent obduracy of journalists has caused conflict with many American politicians from the country’s earliest days. George Washington wrote in 1792 that “if the government and the officers of it are to be the constant theme for newspaper abuse, and this too without condescending to investigate the motives or the facts, it will be impossible, I conceive, for any man living to manage the helm or to keep the machine together.” On the other hand, politicians have recognized the media’s crucial role in keeping the electorate informed. Thomas Jefferson wrote in 1787 that “were it left to me to decide whether we should have a government without newspapers, or newspapers without a government, I should not hesitate a moment to prefer the latter.”
Radio became important to politics in 1924, when the proceedings of the national political party conventions were first broadcast live. In that year, the parties began paying for radio advertisements — the Republicans spent $120,000; the Democrats, $40,000. Four years later, expenditures by the two parties had leaped to a million dollars, beginning the upward spiral in campaign spending that has accelerated in recent years.
George Gallup began conducting public opinion polls in 1934, starting with small samples in key districts. He believed that these polls would provide “a swift and efficient method by which legislators, educators, experts and editors, as well as ordinary citizens throughout the length and breadth of the country, can have a more reliable measure of the pulse of democracy.” Today, polling has become far more sophisticated as questioning has been refined by experience, and analysis has been aided by the introduction of modern technology. In spite of occasional errors, polling is generally considered to be an effective way to keep track of public opinion.
The first television broadcast of a political convention came in 1940, with an audience of 100,000 viewers. By the 1950s, television was reaching one-third of America’s households. The two parties spent $3.5 million on television ads during the 1952 campaign, with the Republicans continuing to outspend the Democrats by a large margin. The 1960 Kennedy-Nixon debates clinched the crucial role of television in modern campaigning.
Cable television has allowed vastly increased public scrutiny of government itself. Every minute of U.S. House of Representatives and U.S. Senate sessions plus a number of congressional committee meetings are televised by the nongovernmental C-SPAN channels. State and local governments likewise broadcast meetings of legislatures, councils and boards to their constituents.
Citizens have more ways than ever to get news about their governments. While the number of newspapers is shrinking, the survivors continue to report local, national and international news online, providing important scrutiny of government while trying to find ways of remaining profitable in the digital age. People have long taken for granted getting news from radio and television reporters. Now citizen journalists can bring neglected news stories to their community through online blogs.