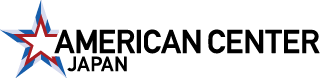国務省出版物
米国の歴史の概要 – 西への拡大と各地域の特徴

19世紀、米国中西部で馬に引かせたコンバインでの小麦刈り入れ作業 (© Bettmann/CORBIS)
1812年戦争は、ある意味で米国の第2の独立戦争であり、英国からの分離を確実なものとする出来事だった。この若い共和国が独立革命以降直面してきた深刻な問題の多くが、1812年戦争の終結とともに消滅した。合衆国憲法の下での国家統一は、自由と秩序をもたらした。国家債務は減少し、広大な大陸が開拓を待っており、平和と繁栄と社会の前進の可能性が国家の目の前に広がっていた。
通商が国家の統一を堅固なものにした。戦争による欠乏によって、多くの人々は米国が外国との競争に自力で立ち向かえるようになるまで、国内の製造業を保護することの重要性を痛感した。多くの人々が、経済的な独立は政治的な独立と同様に不可欠だと主張した。自給自足を促進するため、連邦議会の有力者だったケンタッキー州のヘンリー・クレーとサウスカロライナ州のジョン・C・カルフーンは、米国の産業発展を促すため輸出品を制限する保護主義政策を推進した。
関税の引き上げに絶好の時期が到来していた。バーモント州やオハイオ州の牧羊農家は、英国産羊毛の流入からの保護を求めた。ケンタッキー州では、地元でとれる麻を織って綿花用の袋を作る新興産業が、スコットランドの袋製造業からの脅威を感じていた。すでに鉄製錬の中心地となっていたペンシルベニア州ピッツバーグ市は、英国やスウェーデンの鉄供給業者に挑戦しようとしていた。1816年に制定された関税は、国内の製造業者に実質的な保護を提供できるような高率だった。
これに加えて、米国西部の人々は東部の都市や港湾と西部を結び、辺境の開拓地への移住を容易にする道路や運河の全国的な交通網を提唱した。しかし、連邦政府に国内の改善に関与するよう求めた彼らの要求は、ニューイングランドや南部の人々の反対にあって、実現しなかった。1916年に連邦補助道路法が可決されるまで、道路や運河は州政府の管轄下に置かれた。
この時期に、最高裁は連邦政府の立場を大きく強化するいくつかの判決を下した。熱心な連邦主義者だったバージニア州のジョン・マーシャルが、1801年に最高裁長官となり、1835年に死亡するまで長官を務めた。それまで弱い存在だった最高裁は、マーシャルの長官就任とともに、強力な法廷に変身し、連邦議会および大統領と同等の地位を占めるようになった。マーシャルは、一連の歴史的な判決によって最高裁の権限を確立するとともに、連邦政府を強化した。
マーシャルが草分けとなって、その後代々の最高裁判事は、合衆国憲法の意味と適用を形成する判決を下していくことになった。マーシャルが長い任期を終えるまでに、最高裁は明らかに憲法問題がからむ50件近い訴訟の判決を下した。マーシャルの最も有名な意見のひとつに、「マーベリー対マディソン事件」(1803年)の際のものがある。彼はこの中で、最高裁が連邦議会または州議会のあらゆる法律の合憲性を審査する権利を、決定的に確立した。また「マカロック対メリーランド事件」(1819年)では、合衆国憲法は、明示的に記された政府の権利以外の権利をも、暗黙のうちに政府に与えている、というハミルトンの理論を支持する大胆な判決を下した。
それまでほとんど国民の注意を引かなかった奴隷制度が、国家的な課題として重要性を増し始めていた。共和国設立の初期に、奴隷を直ちに、あるいは徐々に解放することを北部諸州が定めた時、多くの指導者は奴隷制はいずれ消滅すると考えた。1786年に、ジョージ・ワシントンは、 「奴隷制が、ゆっくりと確実に、それとわからないうちに廃止されていくような」計画が採用されることを心から願う、と書いた。バージニア州のジェファーソン、マディソン、モンローをはじめとする南部の指導者たちも、同様の声明を出した。
1787年の北西部条例は、北西部準州での奴隷制を禁止した。その後1808年になって、国際奴隷貿易が廃止されたとき、多くの南部人は奴隷制は間もなく廃止されるだろうと考えていた。しかし、この予想は誤っていた。その後1世代を通じて、新たな経済要因によって奴隷制は1790年以前よりもはるかに大きな利益をもたらすようになり、南部は奴隷制の支持で固まっていった。
そうした経済要因の中でも最大のものは、南部の大規模な綿花栽培産業の台頭だった。新種の綿花の導入、そして1793年にイーライ・ホイットニーが、綿花から種子を取り除く綿繰り機を発明したことによって、綿花産業が促進された。同時に、産業革命によって繊維産業が大規模工業化したため、原料となる綿花の需要が大きく増えた。そして、1812年戦争の後、西部で新たな土地が開拓されたことによって、綿花栽培に利用できる土地が大幅に拡大された。綿花栽培は、東部沿岸諸州から、南部の大半、ミシシッピ州のデルタ地域、そしてテキサス州にまで、急速に広がっていった。
同じく労働集約型の作物であるサトウキビの栽培も、南部での奴隷制の拡大を促した。ルイジアナ州南東部の高温で豊かな土地は、サトウキビ栽培で利益を上げるために理想的な環境だった。1830年までには、ルイジアナ州は米国内の砂糖のおよそ半分を供給していた。さらに、タバコ農家も、奴隷制を伴いながら西方へ移動していった。
北部の自由社会と南部の奴隷制社会がいずれも西方へ拡大するに伴い、西部の準州を分割して作られる新しい各州の間で均衡を保つことが、政治的な得策と思われた。1818年にイリノイ州が連邦に加盟し、10州が奴隷州、11州が奴隷禁止州となったが、その後アラバマ州が奴隷州として加盟し、均衡状態が復活した。北部の方が人口増加が急速だったため、下院では北部諸州が明確な多数派を占めた。しかし上院では、北部と南部の均衡が保たれた。
1819年に、1万人の奴隷を持つミズーリ州が、連邦加盟を申請した。北部諸州は、ミズーリが自由州として加盟する以外は認めない、と反対し、抗議の嵐が全国に広がった。連邦議会は、一時こう着状態となったが、ヘンリー・クレーがいわゆる「ミズーリ協定」を妥協案として提唱した。メーン州が自由州として加盟すると同時に、ミズーリ州が奴隷州として加盟することを許す、というものである。また、連邦議会は、ルイジアナ買収で得られたミズーリ州の南の境界線より北の地域では、奴隷制を禁止した。当時、この議会の条項は、南部諸州にとっての勝利に見えた。「広大な米国の砂漠地帯」と呼ばれたこの地域が開拓される可能性は低いと思われていたためである。こうして論争は一時的に解決されたが、トマス・ジェファーソンは、友人への書簡で次のように述べた。「この極めて重要な問題は、夜間の半鐘のように、私の目を覚まし、恐怖の念を起こさせた。私は、これを、連邦の弔鐘であると考えている。」
19世紀初頭の何十年間かにわたって、中南米では革命が進行していた。英国の植民地が自由を得たときから、自由の概念が中南米の人々を奮起させた。1808年にナポレオンがスペインとポルトガルを征服したことが、中南米の人々に反乱を起こして立ち上がるきっかけを与えた。1822年までに、シモン・ボリバル、フランシスコ・ミランダ、ホセ・デ・サンマルティン、ミゲル・デ・ヒダルゴたちの有能な指導者の下で、南はアルゼンチンやチリから、北はメキシコまで、スペイン領アメリカの大半が独立を勝ち取っていた。
米国の人々は、欧州の支配から脱出するという自らの体験を再現するような中南米の出来事に強い関心を示した。中南米の独立運動は、米国民にとって、自治に対する信念を再確認させるものだった。1822年に、ジェームズ・モンロー大統領は、国民からの強い圧力を受けて、中南米の新興国家を承認する権限を背負わされ、間もなくそれらの諸国と公使を交換した。これによって、大統領は中南米諸国が欧州との関係を完全に絶ち切った真の独立国家であることを追認したのである。
ちょうどそのころ、ロシア、プロイセン、オーストリアが、革命に対する防護策として「神聖同盟」を結成した。ナポレオン後のフランスも参加した。この同盟は、大衆運動が君主制を脅かしている国に干渉することによって、革命の拡大を防ぐことを目指していた。こうした政策は、人民の自決という米国の原則とは正反対に位置するものだった。
神聖同盟の活動が旧世界にとどまっている限りは、米国が不安を感じることはなかった。しかし、同盟がスペインの旧植民地を同国に返還することを発表すると、米国民は大きな不安を抱いた。中南米との貿易が非常に重要なものになっていた。英国はそのような動きを阻止する決意を固めた。英国政府は、中南米に対する英米合同の保障を提唱したが、米国のジョン・クインシー・アダムズ国務長官は、次のように述べて、米国が単独で行動するようモンロー大統領を説得した。「英国の軍艦の後についていく小船になるよりも、ロシアやフランスに対して、自らの信条を明確に述べる方が、より率直であると同時に、より威厳がある。」
1823年12月、英国海軍が中南米を神聖同盟やフランスから守ることを認識した上で、モンロー大統領は、連邦議会への年次教書で、欧州による米州支配の拡大を一切拒否する「モンロー主義」を宣言し、次のように述べた。
アメリカ大陸は、……今後、いかなる欧州勢力によっても、いっそうの植民地化の対象として考えられることはない。 われわれは、彼らが自らの(政治)制度をこの半球のいかなる部分に対しても拡大しようとすることは、われわれの平和と安全にとってすべて危険であると見なすべきである。 欧州の大国の既存の植民地または属国に対して、われわれは干渉をしておらず、今後も干渉しない。しかし、独立を宣言し、独立を維持し、その独立をわれわれが……承認している政府に関しては、欧州の大国がそうした政府を抑圧するため、あるいはその他の手段でそうした政府の運命を支配するために介入することは、合衆国に対する非友好的な性向の表れと見なさざるを得ない。
モンロー主義は、中南米の新興独立共和国との連帯の精神を表したものだった。そして、これらの諸国もまた多くの場合、合衆国憲法を自国の新憲法の模範とすることによって、合衆国に対する政治的な親近感を示したのである。
国内的には、モンロー政権時代(1817~25年)は、「好感の時代」と呼ばれた。これは連邦党が国家的勢力としては崩壊し、共和党が政治的に勝利したことを表すものだった。とはいえ、この時期は、派閥間および地域間の激しい対立の時期でもあった。
連邦党の終焉によって、短期間、派閥政治が続き、連邦議会の党員集会で大統領候補を指名するという慣行に混乱をきたした。しばらくは、州議会が候補者を指名した。1824年には、テネシー州とペンシルベニア州が、アンドルー・ジャクソンを大統領候補に、またサウスカロライナ州のジョン・C・カルフーン上院議員を副大統領候補に指名した。ケンタッキー州はヘンリー・クレー下院議長を、またマサチューセッツ州は、第2代大統領ジョン・アダムズの息子のジョン・クインシー・アダムズ国務長官を、それぞれ大統領候補に指名した。非民主的だとして広く愚弄されていた連邦議会の党員集会は、ウィリアム・クローフォード財務長官を候補に指名した。
大統領候補の人柄と地域性が、選挙結果を大きく左右した。ニューイングランドとニューヨーク州の大半では、アダムズが選挙人投票で勝利した。ケンタッキー、オハイオ、ミズーリの各州ではクレーが、南東部とイリノイ、インディアナ、両カロライナ、ペンシルベニア、メリーランド、ニュージャージーの各州ではジャクソンが、そしてバージニア、ジョージア、デラウェアの各州ではクローフォードがそれぞれ勝利した。どの候補者も選挙人団の過半数票を得ることができなかったため、合衆国憲法の規定に従い、選挙結果の決定は下院に委ねられた。下院で最大の有力者だったクレーがアダムズを支持し、アダムズが大統領となった。
アダムズ政権時代に、新たな政党の色分けが生じた。旧連邦党を含むアダムズ支持派は、拡張する国家の発展に強力な役割を果たす連邦政府を支持する立場を象徴する名称として、「国民共和党」を名乗った。アダムズは、誠実かつ効率的な統治を実行したが、人気のある大統領ではなかった。彼は、全国的な道路・運河網を導入しようとしたが、これは失敗に終わった。冷ややかで知的な気質のアダムズは、すぐ友人になれるタイプではなかった。対照的に、ジャクソンは大衆に多大な人気があり、強力な政治組織を持っていた。ジャクソン支持派は合体して「民主党」を創立し、ジェファーソンの民主共和党の直系を自認した。そして、概して小規模で分散化した政府を提唱した。彼らは、強力な反アダムズ活動を開始し、アダムズ大統領がクレーを国務長官に指名したことを、「腐敗した取引」だと非難した。1828年の大統領選挙では、ジャクソンが圧倒的にアダムズを破って当選した。
テネシー州出身の政治家であり、南部の辺境地域でのアメリカ原住民との戦いの闘士であり、そして1812年のニューオーリンズの戦いで英雄となったジャクソンは、「一般大衆」を支持基盤としていた。彼は、大衆民主主義の台頭の波に乗って、大統領に就任した。1828年の大統領選挙は、投票参加者の拡大に向かう動きにおけるひとつの出発点となった。それまでに、ほとんどの州は、白人男性全員に投票権を与えるか、または有権者の土地所有の要件を最小限に抑えるようになっていた。1824年には、6州で、依然として州議会が選挙人団を選出していたが、1828年までには、デラウェアとサウスカロライナの2州を除く全州で、大統領選挙人は一般投票で選ばれるようになっていた。こうした事態の進展は一般国民が統治するべきであり、従来のエリート層による統治は終わりを告げた、という考え方が広まったことの産物だった。
ジャクソン大統領は、第1期目の終盤に、保護関税の問題をめぐってサウスカロライナ州と対決することを余儀なくされた。同州は、台頭する深南部の綿花産出州の中でも、最も重要な州であった。サウスカロライナ州の商業や農業の関係者は、1828年の関税法を「忌むべき関税」と呼び、ジャクソンが大統領の権限によってこの法律を修正することを望んだ。彼らの見解によると、関税による保護の恩恵はすべて北部の製造業者に流れ、農業州であるサウスカロライナはさらに貧困化していた。1828年に、同州の指導的な政治家で、1832年に辞任するまでジャクソン政権の副大統領を務めたジョン・C・カルフーンが、『サウスカロライナの主張と抗議(South Carolina Exposition and Protest)』を著し、その中で、各州には抑圧的な連邦法を無効とする権利がある、と主張した。
1832年に、連邦議会が、1828年に定められた関税率を引き下げる法案を可決し、ジャクソンがこれに署名したが、ほとんどのサウスカロライナ州民は、これだけでは満足しなかった。同州は、1828年および1832年に定められた関税を、いずれも同州内では無効とする「連邦法無効宣言」を採択した。またサウスカロライナ州議会は、軍隊招集の権限と兵器調達に関する法律など、無効宣言を実施するために必要な法律を可決した。無効化は、以前から、連邦政府による過剰と思われる行為に対する抗議の主題となっていた。ジェファーソンとマディソンが、外国人法と動乱法に抗議するために、1798年のケンタッキーおよびバージニア決議で、無効宣言を提案していた。1814年のハートフォード会議では、1812年戦争への抗議として無効宣言が発動された。しかし、州が実際に無効化を実施しようとした例は、それまで一度もなかったのである。若い国家は、かつてない大きな危機に直面していた。
サウスカロライナ州からの脅威に対し、ジャクソン大統領は1832年11月、海軍の小型艦艇7隻と軍艦1隻を同州チャールストンに派遣した。12月10日、ジャクソンは、無効論者に対して、明確な声明を発した。大統領は、サウスカロライナ州は「謀反と反逆の瀬戸際」に立っていると言明し、州民に、連邦への忠誠を再確認するよう訴えた。また彼は、必要ならば自ら米国の軍隊を率いて法を執行する意志があることを明らかにした。
連邦議会で関税の問題が再び取り上げられたとき、ジャクソン大統領の政敵だったヘンリー・クレー上院議員が妥協案を提出した。クレーは保護政策の強力な支持者だったが、熱心な連邦主義者でもあった。1833年に迅速に可決されたクレーの関税法案は、輸入品の価格の20%を超える関税を毎年引き下げ、1842年までには、すべての品目の関税を1816年当時の妥当な関税率とすることを定めていた。同時に連邦議会は、法執行のために軍事力を使う権限を大統領に与える強制法を可決した。
サウスカロライナ州は、南部諸州の支持を期待したが、実際には孤立していた。(サウスカロライナ州を支持する可能性が最も高いとされたジョージア州政府は、州内からアメリカ原住民を退去させるために米国の軍隊の出動を求め、これを与えられた。)結局、サウスカロライナ州は無効条例を撤回したが、双方とも勝利を宣言した。ジャクソンは、強力に連邦を守った。しかし、サウスカロライナ州も、抵抗を示すことによって、要求事項の多くを実現させ、ひとつの州が連邦議会に対してその意志を強硬に押し通せることを証明した。
連邦法無効宣言の危機には内戦の種子が含まれていたが、政治的な問題としては、国家の中央銀行、すなわち第2の合衆国銀行の存続をめぐる紛争ほど深刻ではなかった。1791年にアレギザンダー・ハミルトンの指導の下に設立された最初の合衆国銀行は、20年間の認可を受けていた。この銀行は政府が株式の一部を保有していたが、英国銀行や、当時のその他の中央銀行と同様に、民間の法人であり、その利益は株主に配分されていた。合衆国銀行の公的な機能は、政府収入の預託機関となること、政府に短期の融資をすること、そして何よりも、州の認定した銀行が兌換能力を超えて発行した紙幣を額面価額で受け取ることを拒否することによって、健全な通貨を確立することだった。
北東部の実業・経済界にとって、中央銀行は慎重な通貨政策の執行者として必要な存在だったが、南部および西部の人々は、当初から、自己の繁栄と地域の発展には十分な通貨と信用が必要であると考え、中央銀行の存在を嫌った。ジェファーソンとマディソンの共和党は、中央銀行の合憲性に疑問を抱いた。合衆国銀行の認可は1811年に期限切れで失効し、更新されなかった。
その後数年間は、各州の州認定銀行が銀行業を支配し、通貨を過剰に発行して、多大な混乱を生じさせインフレを促進した。州銀行には、信頼できる通貨を提供する能力のないことがますます明らかになった。1816年に、第2合衆国銀行が設立された。これは最初の合衆国銀行と同様の機関で、認可期間も同じ20年間だった。 第2の合衆国銀行は、当初から新しい州や準州では人気がなかった。特に、州や地方の銀行家は、合衆国銀行が全国の信用と通貨に関する業務をほぼ独占していたことに不満を抱いていた。だが、全米各地のあまり裕福でない人々からも、合衆国銀行は少数の富裕層の利益を代表していると思われて、反感を買っていた。
概して、合衆国銀行は順調に経営され、価値あるサービスを提供した。しかし、ジャクソン大統領は長年にわたって、共和党特有の金融機関に対する不信感を抱いていた。一般国民の擁護者として選出されたジャクソンは、貴族的な合衆国銀行総裁ニコラス・ビドルを、与しやすい攻撃目標だと感じていた。合衆国銀行支持派が連邦議会で、早期の認可更新を推進しようとした時、ジャクソンは、独占と特権を糾弾する辛らつな意見を述べて、拒否権を行使した。拒否権を覆そうとする試みも、失敗に終わった。
それに続いて行われた大統領選では、選挙運動を通じて銀行問題をめぐる根本的な意見対立が明らかになった。商工業および金融業界で地歩を固めた人たちは、健全な通貨を支持した。金儲けに熱心な地方の銀行家や起業家は、通貨の供給増と低金利を望んだ。その他の債務者、とりわけ農民たちも同じ気持ちだった。ジャクソンとその支持派は、中央銀行を「怪物」呼ばわりした。そして、対立候補のヘンリー・クレーに楽勝した。
ジャクソン大統領は、この勝利によって、中央銀行を二度と復活しないように叩きつぶすための国民の信任を得たと考えた。1833年9月、彼は、合衆国銀行に政府の資金を新たに預金することを停止すること、そしてすでに存在する預金を徐々に引き出すことを命令した。政府はいくつかの州銀行を選んで預金を行った。反対派は、これらの銀行を「ペット・バンク(お気に入り銀行)」と呼んだ。
その後、米国は1世代にわたり、比較的規制の緩い州銀行制度の下で、何とかしのいでいくことになった。このために低利金融の西方への拡張が推進される一方で、定期的な金融不安に悩まされ続けた。南北戦争中に、米国は、地方と地域の銀行の国家認定制度を開始した。しかし、米国が連邦準備制度を設立して中央銀行制度を再び導入したのは、1913年になってからだった。
ジャクソンの政敵たちは、主としてジャクソンに反対するという点だけで団結し、最終的にはホイッグ党と呼ばれる政党にまとまった。「ホイッグ」とは、ジャクソンの「君主的支配」に反対するところから、英国のホイッグ党にちなんで付けられた名称である。ホイッグ党が組織されたのは、1832年の大統領選挙運動の直後だったが、党内で意見の相違が調整され、党綱領が作成されたのは、それから10年以上後のことだった。ホイッグ党は主として、党内で最も優れた政治家だったヘンリー・クレーとダニエル・ウェブスターの魅力によって、党員の団結を固めていった。しかし、1836年の大統領選挙では、まだ党内があまりにも分裂していたため、ホイッグ党として1人の候補者の下にまとまることできなかった。この大統領選では、ジャクソンの副大統領だったニューヨーク州のマーティン・バンビューレンが当選した。
しかし、バンビューレン大統領の美点は、経済不況の発生と、前任者の並外れた個性の陰に隠れてしまった。ジャクソンは、行動のひとつひとつが、人をひきつける指導力と芝居じみた華やかさを伴っていたが、バンビューレンにはそうした素質がなかったため、彼の公的活動が国民の熱意を喚起することはなかった。1840年の大統領選は、米国が厳しい時代を迎え、国民が低賃金に苦しんでいる中で行われ、民主党は守勢に立たされた。
ホイッグ党は、オハイオ州のウィリアム・ヘンリー・ハリソンを大統領候補に立てた。ハリソンは、アメリカ原住民との戦いと1812年戦争の英雄として非常に人気があった。彼はジャクソンと同様に、民主的な西部の代表として抜擢されたのである。ハリソンの副大統領候補は、バージニア州のジョン・タイラーだった。州権と低関税に関するタイラーの意見は、南部で広く支持されていた。そして、ハリソンは圧勝した。
ところが、68歳のハリソン9代大統領は、就任後1カ月もたたないうちに急死し、タイラーが大統領に就任した。タイラーの信念は、連邦議会で依然として影響力のあったクレーやウェブスターの考え方とは大きな隔たりがあった。その結果、新大統領と、彼を選出した政党との間に断絶が生じることになった。タイラー大統領には、大統領が死亡した場合、副大統領が完全な権限を与えられて残りの任期を引き継ぐ、という前例を確立したこと以外に、ほとんど実績はなかった。
このほかにも、米国民の間には、より複雑な意見の相違があった。19世紀前半に、主にアイルランド人とドイツ人の大勢のカトリック教徒が移民として米国に渡ってきたことは、米国生まれのプロテスタントの米国人に反発を誘発した。移民は、奇妙な新しい慣習と宗教上のしきたりを米国の地にもたらした。また、東海岸の各都市で、米国生まれの米国人と職を求めて競争した。1820年代と30年代に、白人男性全員に普通選挙権が与えられるようになったため、移民の政治的影響力は増大した。落選した貴族出身の政治家たちは、権力を失ったことを移民のせいにした。カトリック教会が禁酒運動を支持しなかったことから、ローマ法王庁は酒を使って米国を堕落させようとしている、という非難の声が聞かれるようになった。
この時期に続々と誕生した移民排斥主義の組織の中で最も重要なものは、1849年に創設された「星条旗騎士団」という秘密組織だった。この組織は、メンバーが身分を明かすことを拒否したため、「ノウナッシング(何も知らない)」党と呼ばれるようになった。同党は、数年のうちに、かなりの政治的権力を持つ全国組織に成長した。
ノウナッシング党は、移民の帰化に要する期間を5年から21年に延長することを提唱した。また、外国生まれの者やカトリック教徒を公職から排除しようとした。1855年には、ノウナッシング党がニューヨーク・マサチューセッツ両州の議会で多数派を占め、そのころには連邦議会にも同党とつながりのある議員がおよそ90人いた。しかし、それが頂点だった。間もなく、奴隷制の延長をめぐって北部と南部の間で危機が高まり、党内に致命的な分裂が生じた。そして19世紀の第2四半期に米国を支配したホイッグ党と民主党の間の論争が蒸し返され、ノウナッシング党を消耗させていったのである。
ジャクソンの大統領選出で例証されるような、政治における民主主義的な激変は、すべての国民の権利と機会の拡大を目指す、米国の長期にわたる努力のひとつの側面にすぎない。別の側面は、主として熟練・半熟練労働者による労働組合の誕生である。1835年に、ペンシルベニア州フィラデルフィア市の労働者たちが、古くから「日の出から日の入りまで」とされていた1日の労働時間を、10時間に短縮することに成功した。1860年までには、この新たな労働時間の規定が数州で法制化され、一般に認められた基準となった。
選挙権の拡大は、新たな教育の概念をすでに生んでいた。各地の先見の明のある政治家は、普通選挙には、教育を受けた読み書きのできる選挙民が必要であることを理解していた。労働者の組織は、すべての子どもたちを受け入れる、税金によって支えられた無料の学校を要求した。徐々に、そのような無料の教育を実施する法律が、州から州へと制定されていった。中でも、マサチューセッツ州のホレス・マンの指導力は大きな効果を発揮し、北部では公立学校制度が普及した。しかしながら、他の地域では公教育を求める闘いが何年も続いた。
この時期に発生したもうひとつの重要な運動は、酒類の販売と消費に反対する禁酒運動だった。この運動は、宗教的な信条、酒が労働力に及ぼす悪影響、大量飲酒者による女性や子どもに対する虐待など、さまざまな懸念や動機に由来するものだった。1826年に、ボストン市の牧師たちが、禁酒促進協会を設立した。7年後には、同協会がフィラデルフィア市で全国大会を開き、米国禁酒連合が結成された。この連合は、あらゆるアルコール飲料の禁止を求め、各州議会にそうした飲料の製造・販売を禁止するよう圧力をかけた。1855年までに、13州がこれを立法化したが、これらの法律は後に法廷で異議を申し立てられ、ニューイングランド北部だけで継続された。しかし、1830年から1860年までの間に、禁酒運動により、米国の国民1人当たりの酒類消費量は減少した。
監獄の問題や、精神障害者のケアの問題に取り組んだ改革論者もいた。懲罰を強調する監獄を、罪人の更正を行う刑務所に変える努力がなされた。マサチューセッツ州では、ドロシア・ディックスが、悲惨な状態の救貧院や監獄に閉じ込められていた精神障害者を救済する運動を主導した。彼女は、マサチューセッツ州での改善に成功した後、南部にも運動を拡大した。1845年から1852年までの間に、南部の9州が精神病院を設立した。
これらの社会改革によって、多くの女性は自分たちが社会で不平等な地位に置かれていることを認識するようになった。植民地時代から、未婚の女性には男性と同様の権利の多くが与えられていたが、慣習によって女性は早く結婚することを求められた。そして女性は、結婚と同時に、法律的観点からは、独立した個人としての存在を事実上失った。女性は投票が許されていなかった。17世紀および18世紀の女性の教育は、主として読書、作文、音楽、ダンス、裁縫に限られていた。
米国の女性が目覚めるきっかけとなったのは、スコットランドの講演者兼ジャーナリスト、フランセス・ライトの訪米だった。ライトは、1820年代を通じて、全米で女性の権利を公然と推進した。女性が公共の場で話すことがしばしば禁じられていた時代に、彼女は、自分の意見をはっきりと述べただけでなく、女性が避妊や離婚に関する情報を求める権利を支持して、聴衆にショックを与えた。1840年代までに、米国の女権拡張運動が出現した。その先頭に立ったのが、エリザベス・キャディ・スタントンだった。
1848年に、キャディ・スタントンと仲間のルクレシア・モットが、ニューヨーク州セネカフォールズ市で、世界史上初の女権拡張会議を開催した。代表団は、「所感宣言」を起草し、法に基づく男性との平等、投票権、そして教育や雇用における機会均等を要求した。これらの決議は、ひとつの例外を除いて満場一致で採択された。その例外とは、女性の投票権に関する決議だったが、黒人の奴隷廃止論者、フレデリック・ダグラスによる熱のこもった演説の結果、過半数で採択された。
セネカフォールズの会議で、キャディ・スタントンは、女権推進の雄弁な演説家・著述家として、全国的な知名度を得た。彼女は、早い時期から、投票権がなければ女性は決して男性と同等の地位には立てないことを認識していた。キャディ・スタントンは、奴隷廃止論者のウィリアム・ロイド・ギャリソンを手本に、成功のカギは政党活動ではなく、世論を変えることである、と考えた。セネカフォールズの会議は、その後の変化の触媒となった。間もなく、他にも女権拡張会議が開かれ、他の女性たちが、女性の政治的・社会的平等を求める運動の先頭に立つようになった。
同じく1848年に、ポーランド人移民のアーネスティン・ローズが中心となって、ニューヨーク州で、既婚女性が自分の名義で財産を所有し続ける権利を認める法律を可決させた。この既婚女性財産法は、この種の法律としては全米で最も初期に定められたもののひとつであり、他州の議会が同様の法律を制定するきっかけとなった。
1869年に、エリザベス・キャディ・スタントンと、同じく女権運動の指導者だったスーザン・B・アンソニーが、女性の参政権を認める憲法修正を推進するために、全米婦人参政権協会(NWSA)を設立した。この2人は、女権拡張運動の最も雄弁な推進者となった。後にキャディ・スタントンは、2人のパートナーシップについて、「私が雷を作り、彼女がそれを落とした」と語った。
辺境地域は米国社会の形成に大きな役割を果たした。大西洋岸の各地域の状況は、新しい土地への移住を促進するものだった。貧しい土壌で多量の収穫が望めないニューイングランド地方の人々は、沿岸地帯の農場や村を後にして、大陸内地の豊かな土地へ、次々と移住していった。南北カロライナやバージニア州の僻地の住民は、沿岸の市場へ通じる道路や運河がないために不利な状況に置かれていたこと、また沿岸地帯の農園主の政治的優勢に憤慨していたことなどから、やはり西部へ移動していった。1800年までには、ミシシッピ川およびオハイオ川の流域が、広大な辺境地域となっていた。「Hi-o, away we go, floating down the river on the O-hi-o(ハイオー、どんどん行こう、オハイオ川を流れて下ろう)」という歌が、大勢の移住者に愛唱された。
19世紀初めの西部への人口流入によって、古い準州が分割され、新たな境界線が引かれた。新しい州が連邦に加盟するに従い、ミシシッピ川以東の地域の政治地図が安定していった。1816年から1821年までの間に、インディアナ、イリノイ、メーン(いずれも自由州)と、ミシシッピ、アラバマ、ミズーリ(いずれも奴隷州)の6州が新設された。 入植当初の辺境地域は、欧州とのつながりが緊密だったが、第2の辺境地域は、沿岸地帯の入植地とのつながりが強かった。しかし、ミシシッピ川流域は、独立した存在であり、そこに住む人々の目は、東部ではなく西部に向いていたのである。
辺境の開拓者には、さまざまな人たちがいた。ある英国人旅行者は、次のように書いている。「非常に粗末な小屋に住む、大胆で頑健な男たちである。……彼らは、無骨だが、人を温かく迎えてくれる。見知らぬ人にも親切で、正直であり、信頼できる。トウモロコシやカボチャを栽培し、ブタを育て、時にはウシを1、2頭飼っている。……しかし、彼らの主な生活手段は、ライフルである。」彼らは、オノ、わな、釣り糸を使いこなし、道を切り開き、最初の丸太小屋を建て、アメリカ原住民と対決して、その土地を占領していった。
さらに多くの開拓者が荒野に入っていくにつれて、狩猟だけでなく農耕を行う者も増えた。掘っ立て小屋に代わって、ガラス窓、煙突、そして複数の部屋のある、住み心地の良いログハウス(丸太造りの家)が建てられるようになった。また、泉に代わって、井戸が使われるようになった。勤勉な開拓者たちは、木を切り倒して急速に土地を切り開き、木材を燃やして(灰から)炭酸カリウムを作り、切り株は腐朽させた。自家用の穀物、野菜、果物を育て、森でシカや野生のシチメンチョウを獲り、ハチミツを集め、近くの川で魚を釣り、ウシやブタを飼った。土地投機家が広大な土地を安く買い占め、所有地の価格が上昇すると売却し、さらに西へ進出していった。
農民に続いて、医師、弁護士、商店主、編集者、牧師、機械工、そして政治家といった人々も、間もなく西部へ移動した。しかし、西部の堅固な基盤となったのは農民だった。彼らは、開拓した土地に定住する意志を持ち、子どもたちにもその土地に残ることを望んだ。彼らは大きな納屋と、レンガ造りまたは木造の住居を建てた。そして、家畜を改良し、耕作の技術を高め、生産性の高い種子をまいた。製粉所、製材工場、蒸留所などを建てる農家もあった。また、整備された道路を敷設し、教会や学校を設立した。わずか数年の間に、信じられないほどの変容が達成された。例えば、イリノイ州シカゴ市は、1830年には、単に砦のある交易の村で、特に将来性もなかったが、当初の開拓者たちがまだ生きているうちに、全米有数の裕福な大都市となっていた。
農場は容易に手に入れることができた。1820年以降、公有地は、ほぼ半ヘクタール当たり1ドル25セントで購入することができた。そして、1862年の自営農地法によって、公有地に住み、その土地を改良する者には、その土地の所有権が与えられることになった。土地を耕すための道具の入手も容易だった。インディアナ州の新聞記者ジョン・スーレが述べ、「ニューヨーク・トリビューン」紙の編集者ホレス・グリーリーが広く普及させた言葉にあるように、若者が「西部を目指し、国と共に育つ」ことが可能な時代だった。
メキシコの領土だったテキサスへの移民を除けば、農業の辺境地域の西方への進出は、1840年以後までは、ミズーリ川を越えて、ルイジアナ購入で得られた広大な西部地域に至ることはなかった。1819年に、米国は、米国民の対スペイン請求権500万ドルを肩代わりすることと引き換えに、スペインからフロリダを買収するとともに、極西部のオレゴンの所有権もスペインから買収した。そのころ、極西部では毛皮貿易が非常に盛んになっていたが、それは毛皮の価値だけにとどまらない意義を持つことになった。フランス人がミシシッピ川流域を探検した初期のころと同様、ミシシッピ川以西においても、貿易商人は開拓者に先立って道を切り開く役目を果たした。フランス人およびスコットランド系アイルランド人の猟師たちは、大きな川やその支流を探検し、ロッキー山脈やシエラ山脈を越える道を発見することによって、1840年代における陸路の進出と、その後の内陸部の開拓を可能にしたのである。
全体としては、米国の成長は途方もなく大きいものだった。1812年から1852年までの間に、米国の人口は、725万人から2300万人以上に増えた。また、開拓可能な土地は440万平方キロメートルから、780万平方キロメートルに増えた。この増加分は、ほぼ西ヨーロッパの総面積に匹敵するものだった。しかし、地域的な相違に基づく基本的な対立は解決されておらず、これが爆発して1860年代の南北戦争の勃発につながった。また当然のことながら、西部へ進出した開拓者たちは、もともとその土地に住んでいたアメリカ原住民との紛争に巻き込まれることになった。
19世紀初頭に、こうした紛争に関連して最も著名な存在となったのは、後に「西部人」として初めて大統領となるアンドルー・ジャクソンだった。1812年戦争の最中に、テネシー州民兵軍を指揮していたジャクソンは、アラバマ州南部へ派遣され、クリーク・インディアンの蜂起を容赦なく鎮圧した。間もなく、クリーク族は所有地の3分の2を米国に譲渡した。後にジャクソンは、スペイン領フロリダに安住していたセミノール族の諸集団を追い払った。
1820年代に、モンロー大統領の下で陸軍長官を務めていたジョン・C・カルフーンは、旧南西部に残っていたインディアンの部族を追い出し、ミシシッピ川以西に再定住させる政策をとった。ジャクソン大統領は、この方針を継続した。1830年に連邦議会は、インディアン強制移住法を可決し、東部のインディアン諸部族をミシシッピ川以西に移動させる費用を提供することを定めた。1834年には、現在のオクラホマ州に、アメリカ原住民の特別居住地区が作られた。ジャクソン大統領の2期にわたる在職中に、諸部族は合わせて、何百万ヘクタールもの土地を連邦政府に譲渡する、合わせて94の条約に署名した。そして何十もの部族が先祖代々住んだ土地から撤退することになった。
この不幸な歴史の中でも最も悲惨な1章は、チェロキー族に関するものだった。ノースカロライナ州西部とジョージア州に居住していたチェロキー族は、1791年の条約によって、その土地の所有を保障されていた。チェロキー族は、東部有数の進歩的な部族だったが、1829年に居住地内で金が発見されると、追い出されるのは必至となった。チェロキー族は1838年に、オクラホマへの長く過酷な徒歩の旅を強制され、その途中で大勢が病気や食糧不足で死亡した。この旅は後に,「涙の道」と呼ばれるようになった。
|
Westward Expansion and Regional Differences
(The following article is taken from the U.S. Department of State publication Outline of U.S. History.)
“Go West, young man, and grow up with the country.”
-- Newspaper editor Horace Greeley, 1851
BUILDING UNITY
The War of 1812 was, in a sense, a second war of independence that confirmed once and for all the American break with England. With its conclusion, many of the serious difficulties that the young republic had faced since the Revolution disappeared. National union under the Constitution brought a balance between liberty and order. With a low national debt and a continent awaiting exploration, the prospect of peace, prosperity, and social progress opened before the nation.
Commerce cemented national unity. The privations of war convinced many of the importance of protecting the manufacturers of America until they could stand alone against foreign competition. Economic independence, many argued, was as essential as political independence. To foster self-sufficiency, congressional leaders Henry Clay of Kentucky and John C. Calhoun of South Carolina urged a policy of protectionism – imposition of restrictions on imported goods to foster the development of American industry.
The time was propitious for raising the customs tariff. The shepherds of Vermont and Ohio wanted protection against an influx of English wool. In Kentucky, a new industry of weaving local hemp into cotton bagging was threatened by the Scottish bagging industry. Pittsburgh, Pennsylvania, already a flourishing center of iron smelting, was eager to challenge British and Swedish iron suppliers. The tariff enacted in 1816 imposed duties high enough to give manufacturers real protection.
In addition, Westerners advocated a national system of roads and canals to link them with Eastern cities and ports, and to open frontier lands for settlement. However, they were unsuccessful in pressing their demands for a federal role in internal improvement because of opposition from New England and the South. Roads and canals remained the province of the states until the passage of the Federal Aid Road Act of 1916.
The position of the federal government at this time was greatly strengthened by several Supreme Court decisions. A committed Federalist, John Marshall of Virginia, became chief justice in 1801 and held office until his death in 1835. The court – weak before his administration – was transformed into a powerful tribunal, occupying a position co-equal to the Congress and the president. In a succession of historic decisions, Marshall established the power of the Supreme Court and strengthened the national government.
Marshall was the first in a long line of Supreme Court justices whose decisions have molded the meaning and application of the Constitution. When he finished his long service, the court had decided nearly 50 cases clearly involving constitutional issues. In one of Marshall’s most famous opinions – Marbury v. Madison (1803) – he decisively established the right of the Supreme Court to review the constitutionality of any law of Congress or of a state legislature. In McCulloch v. Maryland (1819), he boldly upheld the Hamiltonian theory that the Constitution by implication gives the government powers beyond those expressly stated.
EXTENSION OF SLAVERY
Slavery, which up to now had received little public attention, began to assume much greater importance as a national issue. In the early years of the republic, when the Northern states were providing for immediate or gradual emancipation of the slaves, many leaders had supposed that slavery would die out. In 1786 George Washington wrote that he devoutly wished some plan might be adopted “by which slavery may be abolished by slow, sure, and imperceptible degrees.” Virginians Jefferson, Madison, and Monroe and other leading Southern statesmen made similar statements.
The Northwest Ordinance of 1787 had banned slavery in the Northwest Territory. As late as 1808, when the international slave trade was abolished, there were many Southerners who thought that slavery would soon end. The expectation proved false, for during the next generation, the South became solidly united behind the institution of slavery as new economic factors made slavery far more profitable than it had been before 1790.
Chief among these was the rise of a great cotton-growing industry in the South, stimulated by the introduction of new types of cotton and by Eli Whitney’s invention in 1793 of the cotton gin, which separated the seeds from cotton. At the same time, the Industrial Revolution, which made textile manufacturing a large-scale operation, vastly increased the demand for raw cotton. And the opening of new lands in the West after 1812 greatly extended the area available for cotton cultivation. Cotton culture moved rapidly from the Tidewater states on the East Coast through much of the lower South to the delta region of the Mississippi and eventually to Texas.
Sugar cane, another labor‑intensive crop, also contributed to slavery’s extension in the South. The rich, hot lands of southeastern Louisiana proved ideal for growing sugar cane profitably. By 1830 the state was supplying the nation with about half its sugar supply. Finally, tobacco growers moved westward, taking slavery with them.
As the free society of the North and the slave society of the South spread westward, it seemed politically expedient to maintain a rough equality among the new states carved out of western territories. In 1818, when Illinois was admitted to the Union, 10 states permitted slavery and 11 states prohibited it; but balance was restored after Alabama was admitted as a slave state. Population was growing faster in the North, which permitted Northern states to have a clear majority in the House of Representatives. However, equality between the North and the South was maintained in the Senate.
In 1819 Missouri, which had 10,000 slaves, applied to enter the Union. Northerners rallied to oppose Missouri’s entry except as a free state, and a storm of protest swept the country. For a time Congress was deadlocked, but Henry Clay arranged the so-called Missouri Compromise: Missouri was admitted as a slave state at the same time Maine came in as a free state. In addition, Congress banned slavery from the territory acquired by the Louisiana Purchase north of Missouri’s southern boundary. At the time, this provision appeared to be a victory for the Southern states because it was thought unlikely that this “Great American Desert” would ever be settled. The controversy was temporarily resolved, but Thomas Jefferson wrote to a friend that “this momentous question, like a fire bell in the night, awakened and filled me with terror. I considered it at once as the knell of the Union.”
LATIN AMERICA AND THE MONROE DOCTRINE
During the opening decades of the 19th century, Central and South America turned to revolution. The idea of liberty had stirred the people of Latin America from the time the English colonies gained their freedom. Napoleon’s conquest of Spain and Portugal in 1808 provided the signal for Latin Americans to rise in revolt. By 1822, ably led by Simón Bolívar, Francisco Miranda, José de San Martín and Miguel de Hidalgo, most of Hispanic America – from Argentina and Chile in the south to Mexico in the north – had won independence.
The people of the United States took a deep interest in what seemed a repetition of their own experience in breaking away from European rule. The Latin American independence movements confirmed their own belief in self-government. In 1822 President James Monroe, under powerful public pressure, received authority to recognize the new countries of Latin America and soon exchanged ministers with them. He thereby confirmed their status as genuinely independent countries, entirely separated from their former European connections.
At just this point, Russia, Prussia, and Austria formed an association called the Holy Alliance to protect themselves against revolution. By intervening in countries where popular movements threatened monarchies, the alliance – joined by post-Napoleonic France – hoped to prevent the spread of revolution. This policy was the antithesis of the American principle of self-determination.
As long as the Holy Alliance confined its activities to the Old World, it aroused no anxiety in the United States. But when the alliance announced its intention of restoring to Spain its former colonies, Americans became very concerned. Britain, to which Latin American trade had become of great importance, resolved to block any such action. London urged joint Anglo‑American guarantees to Latin America, but Secretary of State John Quincy Adams convinced Monroe to act unilaterally: “It would be more candid, as well as more dignified, to avow our principles explicitly to Russia and France, than to come in as a cock‑boat in the wake of the British man-of-war.”
In December 1823, with the knowledge that the British navy would defend Latin America from the Holy Alliance and France, President Monroe took the occasion of his annual message to Congress to pronounce what would become known as the Monroe Doctrine – the refusal to tolerate any further extension of European domination in the Americas:
The American continents ... are henceforth not to be considered as subjects for future colonization by any European powers
We should consider any attempt on their part to extend their [political] system to any portion of this hemisphere, as dangerous to our peace and safety.
With the existing colonies or dependencies of any European power we have not interfered, and shall not interfere. But with the governments who have declared their independence, and maintained it, and whose independence we have ... acknowledged, we could not view any interposition for the purpose of oppressing them, or controlling, in any other manner, their destiny, by any European power in any other light than as the manifestation of an unfriendly disposition towards the United States.
The Monroe Doctrine expressed a spirit of solidarity with the newly independent republics of Latin America. These nations in turn recognized their political affinity with the United States by basing their new constitutions, in many instances, on the North American model.
FACTIONALISM AND POLITICAL PARTIES
Domestically, the presidency of Monroe (1817-1825) was termed the “era of good feelings.” The phrase acknowledged the political triumph of the Republican Party over the Federalist Party, which had collapsed as a national force. All the same, this was a period of vigorous factional and regional conflict.
The end of the Federalists led to a brief period of factional politics and brought disarray to the practice of choosing presidential nominees by congressional party caucuses. For a time, state legislatures nominated candidates. In 1824 Tennessee and Pennsylvania chose Andrew Jackson, with South Carolina Senator John C. Calhoun as his running mate. Kentucky selected Speaker of the House Henry Clay; Massachusetts, Secretary of State John Quincy Adams, son of the second president, John Adams. A congressional caucus, widely derided as undemocratic, picked Secretary of the Treasury William Crawford.
Personality and sectional allegiance played important roles in determining the outcome of the election. Adams won the electoral votes from New England and most of New York; Clay won Kentucky, Ohio, and Missouri; Jackson won the Southeast, Illinois, Indiana, the Carolinas, Pennsylvania, Maryland, and New Jersey; and Crawford won Virginia, Georgia, and Delaware. No candidate gained a majority in the Electoral College, so, according to the provisions of the Constitution, the election was thrown into the House of Representatives, where Clay was the most influential figure. He supported Adams, who gained the presidency.
During Adams’s administration, new party alignments appeared. Adams’s followers, some of whom were former Federalists, took the name of “National Republicans” as emblematic of their support of a federal government that would take a strong role in developing an expanding nation. Though he governed honestly and efficiently, Adams was not a popular president. He failed in his effort to institute a national system of roads and canals. His coldly intellectual temperament did not win friends. Jackson, by contrast, had enormous popular appeal and a strong political organization. His followers coalesced to establish the Democratic Party, claimed direct lineage from the Democratic-Republican Party of Jefferson, and in general advocated the principles of small, decentralized government. Mounting a strong anti-Adams campaign, they accused the president of a “corrupt bargain” for naming Clay secretary of state. In the election of 1828, Jackson defeated Adams by an overwhelming electoral majority.
Jackson – Tennessee politician, fighter in wars against Native Americans on the Southern frontier, and hero of the Battle of New Orleans during the War of 1812 – drew his support from the “common people.” He came to the presidency on a rising tide of enthusiasm for popular democracy. The election of 1828 was a significant benchmark in the trend toward broader voter participation. By then most states had either enacted universal white male suffrage or minimized property requirements. In 1824 members of the Electoral College in six states were still selected by the state legislatures. By 1828 presidential electors were chosen by popular vote in every state but Delaware and South Carolina. These developments were the products of a widespread sense that the people should rule and that government by traditional elites had come to an end.
NULLIFICATION CRISIS
Toward the end of his first term in office, Jackson was forced to confront the state of South Carolina, the most important of the emerging Deep South cotton states, on the issue of the protective tariff. Business and farming interests in the state had hoped that the president would use his power to modify the 1828 act that they called the Tariff of Abominations. In their view, all its benefits of protection went to Northern manufacturers, leaving agricultural South Carolina poorer. In 1828, the state’s leading politician – and Jackson’s vice president until his resignation in 1832 – John C. Calhoun had declared in his South Carolina Exposition and Protest that states had the right to nullify oppressive national legislation.
In 1832, Congress passed and Jackson signed a bill that revised the 1828 tariff downward, but it was not enough to satisfy most South Carolinians. The state adopted an Ordinance of Nullification, which declared both the tariffs of 1828 and 1832 null and void within state borders. Its legislature also passed laws to enforce the ordinance, including authorization for raising a military force and appropriations for arms. Nullification was a long-established theme of protest against perceived excesses by the federal government. Jefferson and Madison had proposed it in the Kentucky and Virginia Resolutions of 1798, to protest the Alien and Sedition Acts. The Hartford Convention of 1814 had invoked it to protest the War of 1812. Never before, however, had a state actually attempted nullification. The young nation faced its most dangerous crisis yet.
In response to South Carolina’s threat, Jackson sent seven small naval vessels and a man-of-war to Charleston in November 1832. On December 10, he issued a resounding proclamation against the nullifiers. South Carolina, the president declared, stood on “the brink of insurrection and treason,” and he appealed to the people of the state to reassert their allegiance to the Union. He also let it be known that, if necessary, he personally would lead the U.S. Army to enforce the law.
When the question of tariff duties again came before Congress, Jackson’s political rival, Senator Henry Clay, a great advocate of protection but also a devoted Unionist, sponsored a compromise measure. Clay’s tariff bill, quickly passed in 1833, specified that all duties in excess of 20 percent of the value of the goods imported were to be reduced year by year, so that by 1842 the duties on all articles would reach the level of the moderate tariff of 1816. At the same time, Congress passed a Force Act, authorizing the president to use military power to enforce the laws.
South Carolina had expected the support of other Southern states, but instead found itself isolated. (Its most likely ally, the state government of Georgia, wanted, and got, U.S. military force to remove Native-American tribes from the state.) Eventually, South Carolina rescinded its action. Both sides, nevertheless, claimed victory. Jackson had strongly defended the Union. But South Carolina, by its show of resistance, had obtained many of its demands and had demonstrated that a single state could force its will on Congress.
THE BANK FIGHT
Although the nullification crisis possessed the seeds of civil war, it was not as critical a political issue as a bitter struggle over the continued existence of the nation’s central bank, the second Bank of the United States. The first bank, established in 1791 under Alexander Hamilton’s guidance, had been chartered for a 20-year period. Though the government held some of its stock, the bank, like the Bank of England and other central banks of the time, was a private corporation with profits passing to its stockholders. Its public functions were to act as a depository for government receipts, to make short-term loans to the government, and above all to establish a sound currency by refusing to accept at face value notes (paper money) issued by state-chartered banks in excess of their ability to redeem.
To the Northeastern financial and commercial establishment, the central bank was a needed enforcer of prudent monetary policy, but from the beginning it was resented by Southerners and Westerners who believed their prosperity and regional development depended upon ample money and credit. The Republican Party of Jefferson and Madison doubted its constitutionality. When its charter expired in 1811, it was not renewed.
For the next few years, the banking business was in the hands of state-chartered banks, which issued currency in excessive amounts, creating great confusion and fueling inflation. It became increasingly clear that state banks could not provide the country with a reliable currency. In 1816 a second Bank of the United States, similar to the first, was again chartered for 20 years. From its inception, the second bank was unpopular in the newer states and territories, especially with state and local bankers who resented its virtual monopoly over the country’s credit and currency, but also with less prosperous people everywhere, who believed that it represented the interests of the wealthy few.
On the whole, the bank was well managed and rendered a valuable service; but Jackson long had shared the Republican distrust of the financial establishment. Elected as a tribune of the people, he sensed that the bank’s aristocratic manager, Nicholas Biddle, was an easy target. When the bank’s supporters in Congress pushed through an early renewal of its charter, Jackson responded with a stinging veto that denounced monopoly and special privilege. The effort to override the veto failed.
In the presidential campaign that followed, the bank question revealed a fundamental division. Established merchant, manufacturing, and financial interests favored sound money. Regional bankers and entrepreneurs on the make wanted an increased money supply and lower interest rates. Other debtor classes, especially farmers, shared those sentiments. Jackson and his supporters called the central bank a “monster” and coasted to an easy election victory over Henry Clay.
The president interpreted his triumph as a popular mandate to crush the central bank irrevocably. In September 1833 he ordered an end to deposits of government money in the bank, and gradual withdrawals of the money already in its custody. The government deposited its funds in selected state banks, characterized as “pet banks” by the opposition.
For the next generation the United States would get by on a relatively unregulated state banking system, which helped fuel westward expansion through cheap credit but kept the nation vulnerable to periodic panics. During the Civil War, the United States initiated a system of national charters for local and regional banks, but the nation returned to a central bank only with the establishment of the Federal Reserve system in 1913.
WHIGS, DEMOCRATS, AND KNOW-NOTHINGS
Jackson’s political opponents, united by little more than a common opposition to him, eventually coalesced into a common party called the Whigs, a British term signifying opposition to Jackson’s “monarchial rule.” Although they organized soon after the election campaign of 1832, it was more than a decade before they reconciled their differences and were able to draw up a platform. Largely through the magnetism of Henry Clay and Daniel Webster, the Whigs’ most brilliant statesmen, the party solidified its membership. But in the 1836 election, the Whigs were still too divided to unite behind a single man. New York’s Martin Van Buren, Jackson’s vice president, won the contest.
An economic depression and the larger-than-life personality of his predecessor obscured Van Buren’s merits. His public acts aroused no enthusiasm, for he lacked the compelling qualities of leadership and the dramatic flair that had attended Jackson’s every move. The election of 1840 found the country afflicted with hard times and low wages – and the Democrats on the defensive.
The Whig candidate for president was William Henry Harrison of Ohio, vastly popular as a hero of conflicts with Native Americans and the War of 1812. He was promoted, like Jackson, as a representative of the democratic West. His vice presidential candidate was John Tyler – a Virginian whose views on states’ rights and a low tariff were popular in the South. Harrison won a sweeping victory.
Within a month of his inauguration, however, the 68-year-old Harrison died, and Tyler became president. Tyler’s beliefs differed sharply from those of Clay and Webster, still the most influential men in Congress. The result was an open break between the new president and the party that had elected him. The Tyler presidency would accomplish little other than to establish definitively that, if a president died, the vice president would assume the office with full powers for the balance of his term.
Americans found themselves divided in other, more complex ways. The large number of Catholic immigrants in the first half of the 19th century, primarily Irish and German, triggered a backlash among native-born Protestant Americans. Immigrants brought strange new customs and religious practices to American shores. They competed with the native-born for jobs in cities along the Eastern seaboard. The coming of universal white male suffrage in the 1820s and 1830s increased their political clout. Displaced patrician politicians blamed the immigrants for their fall from power. The Catholic Church’s failure to support the temperance movement gave rise to charges that Rome was trying to subvert the United States through alcohol.
The most important of the nativist organizations that sprang up in this period was a secret society, the Order of the Star-Spangled Banner, founded in 1849. When its members refused to identify themselves, they were swiftly labeled the “Know-Nothings.” In a few years, they became a national organization with considerable political power.
The Know-Nothings advocated an extension in the period required for naturalized citizenship from five to 21 years. They sought to exclude the foreign-born and Catholics from public office. In 1855 they won control of legislatures in New York and Massachusetts; by then, about 90 U.S. congressmen were linked to the party. That was its high point. Soon after, the gathering crisis between North and South over the extension of slavery fatally divided the party, consuming it along with the old debates between Whigs and Democrats that had dominated American politics in the second quarter of the 19th century.
STIRRINGS OF REFORM
The democratic upheaval in politics exemplified by Jackson’s election was merely one phase of the long American quest for greater rights and opportunities for all citizens. Another was the beginning of labor organization, primarily among skilled and semiskilled workers. In 1835 labor forces in Philadelphia, Pennsylvania, succeeded in reducing the old “dark-to-dark” workday to a 10-hour day. By 1860, the new work day had become law in several of the states and was a generally accepted standard.
The spread of suffrage had already led to a new concept of education. Clear-sighted statesmen everywhere understood that universal suffrage required a tutored, literate electorate. Workingmen’s organizations demanded free, tax-supported schools open to all children. Gradually, in one state after another, legislation was enacted to provide for such free instruction. The leadership of Horace Mann in Massachusetts was especially effective. The public school system became common throughout the North. In other parts of the country, however, the battle for public education continued for years.
Another influential social movement that emerged during this period was the opposition to the sale and use of alcohol, or the temperance movement. It stemmed from a variety of concerns and motives: religious beliefs, the effect of alcohol on the work force, the violence and suffering women and children experienced at the hands of heavy drinkers. In 1826 Boston ministers organized the Society for the Promotion of Temperance. Seven years later, in Philadelphia, the society convened a national convention, which formed the American Temperance Union. The union called for the prohibition of all alcoholic beverages, and pressed state legislatures to ban their production and sale. Thirteen states had done so by 1855, although the laws were subsequently challenged in court. They survived only in northern New England, but between 1830 and 1860 the temperance movement reduced Americans’ per capita consumption of alcohol.
Other reformers addressed the problems of prisons and care for the insane. Efforts were made to turn prisons, which stressed punishment, into penitentiaries where the guilty would undergo rehabilitation. In Massachusetts, Dorothea Dix led a struggle to improve conditions for insane persons, who were kept confined in wretched almshouses and prisons. After winning improvements in Massachusetts, she took her campaign to the South, where nine states established hospitals for the insane between 1845 and 1852.
WOMEN’S RIGHTS
Such social reforms brought many women to a realization of their own unequal position in society. From colonial times, unmarried women had enjoyed many of the same legal rights as men, although custom required that they marry early. With matrimony, women virtually lost their separate identities in the eyes of the law. Women were not permitted to vote. Their education in the 17th and 18th centuries was limited largely to reading, writing, music, dancing, and needlework.
The awakening of women began with the visit to America of Frances Wright, a Scottish lecturer and journalist, who publicly promoted women’s rights throughout the United States during the 1820s. At a time when women were often forbidden to speak in public places, Wright not only spoke out, but shocked audiences by her views advocating the rights of women to seek information on birth control and divorce. By the 1840s an American women’s rights movement emerged. Its foremost leader was Elizabeth Cady Stanton.
In 1848 Cady Stanton and her colleague Lucretia Mott organized a women’s rights convention – the first in the history of the world – at Seneca Falls, New York. Delegates drew up a “Declaration of Sentiments,” demanding equality with men before the law, the right to vote, and equal opportunities in education and employment. The resolutions passed unanimously with the exception of the one for women’s suffrage, which won a majority only after an impassioned speech in favor by Frederick Douglass, the black abolitionist.
At Seneca Falls, Cady Stanton gained national prominence as an eloquent writer and speaker for women’s rights. She had realized early on that without the right to vote, women would never be equal with men. Taking the abolitionist William Lloyd Garrison as her model, she saw that the key to success lay in changing public opinion, and not in party action. Seneca Falls became the catalyst for future change. Soon other women’s rights conventions were held, and other women would come to the forefront of the movement for their political and social equality.
In 1848 also, Ernestine Rose, a Polish immigrant, was instrumental in getting a law passed in the state of New York that allowed married women to keep their property in their own name. Among the first laws in the nation of this kind, the Married Women’s Property Act encouraged other state legislatures to enact similar laws.
In 1869 Elizabeth Cady Stanton and another leading women’s rights activist, Susan B. Anthony, founded the National Woman Suffrage Association (NWSA), to promote a constitutional amendment for women’s right to the vote. These two would become the women’s movement’s most outspoken advocates. Describing their partnership, Cady Stanton would say, “I forged the thunderbolts and she fired them.”
WESTWARD
The frontier did much to shape American life. Conditions along the entire Atlantic seaboard stimulated migration to the newer regions. From New England, where the soil was incapable of producing high yields of grain, came a steady stream of men and women who left their coastal farms and villages to take advantage of the rich interior land of the continent. In the backcountry settlements of the Carolinas and Virginia, people handicapped by the lack of roads and canals giving access to coastal markets and resentful of the political dominance of the Tidewater planters also moved westward. By 1800 the Mississippi and Ohio River valleys were becoming a great frontier region. “Hi-o, away we go, floating down the river on the O-hi-o,” became the song of thousands of migrants.
The westward flow of population in the early 19th century led to the division of old territories and the drawing of new boundaries. As new states were admitted, the political map stabilized east of the Mississippi River. From 1816 to 1821, six states were created – Indiana, Illinois, and Maine (which were free states), and Mississippi, Alabama, and Missouri (slave states). The first frontier had been tied closely to Europe, the second to the coastal settlements, but the Mississippi Valley was independent and its people looked west rather than east.
Frontier settlers were a varied group. One English traveler described them as “a daring, hardy race of men, who live in miserable cabins. ... They are unpolished but hospitable, kind to strangers, honest, and trustworthy. They raise a little Indian corn, pumpkins, hogs, and sometimes have a cow or two. ... But the rifle is their principal means of support.” Dexterous with the ax, snare, and fishing line, these men blazed the trails, built the first log cabins, and confronted Native-American tribes, whose land they occupied.
As more and more settlers penetrated the wilderness, many became farmers as well as hunters. A comfortable log house with glass windows, a chimney, and partitioned rooms replaced the cabin; the well replaced the spring. Industrious settlers would rapidly clear their land of timber, burning the wood for potash and letting the stumps decay. They grew their own grain, vegetables, and fruit; ranged the woods for deer, wild turkeys, and honey; fished the nearby streams; looked after cattle and hogs. Land speculators bought large tracts of the cheap land and, if land values rose, sold their holdings and moved still farther west, making way for others.
Doctors, lawyers, storekeepers, editors, preachers, mechanics, and politicians soon followed the farmers. The farmers were the sturdy base, however. Where they settled, they intended to stay and hoped their children would remain after them. They built large barns and brick or frame houses. They brought improved livestock, plowed the land skillfully, and sowed productive seed. Some erected flour mills, sawmills, and distilleries. They laid out good highways, and built churches and schools. Incredible transformations were accomplished in a few years. In 1830, for example, Chicago, Illinois, was merely an unpromising trading village with a fort; but long before some of its original settlers had died, it had become one of the largest and richest cities in the nation.
Farms were easy to acquire. Government land after 1820 could be bought for $1.25 for about half a hectare, and after the 1862 Homestead Act, could be claimed by merely occupying and improving it. In addition, tools for working the land were easily available. It was a time when, in a phrase coined by Indiana newspaperman John Soule and popularized by New York Tribune editor Horace Greeley, young men could “go west and grow with the country.”
Except for a migration into Mexican-owned Texas, the westward march of the agricultural frontier did not pass Missouri into the vast Western territory acquired in the Louisiana Purchase until after 1840. In 1819, in return for assuming the claims of American citizens to the amount of $5 million, the United States obtained from Spain both Florida and Spain’s rights to the Oregon country in the Far West. In the meantime, the Far West had become a field of great activity in the fur trade, which was to have significance far beyond the value of the skins. As in the first days of French exploration in the Mississippi Valley, the trader was a pathfinder for the settlers beyond the Mississippi. The French and Scots-Irish trappers, exploring the great rivers and their tributaries and discovering the passes through the Rocky and Sierra Mountains, made possible the overland migration of the 1840s and the later occupation of the interior of the nation.
Overall, the growth of the nation was enormous: Population grew from 7.25 million to more than 23 million from 1812 to 1852, and the land available for settlement increased by almost the size of Western Europe – from 4.4 million to 7.8 million square kilometers. Still unresolved, however, were the basic conflicts rooted in sectional differences that, by the decade of the 1860s, would explode into civil war. Inevitably, too, this westward expansion brought settlers into conflict with the original inhabitants of the land: the Native Americans.
In the first part of the 19th century, the most prominent figure associated with these conflicts was Andrew Jackson, the first “Westerner” to occupy the White House. In the midst of the War of 1812, Jackson, then in charge of the Tennessee militia, was sent into southern Alabama, where he ruthlessly put down an uprising of Creek Indians. The Creeks soon ceded two-thirds of their land to the United States. Jackson later routed bands of Seminoles from their sanctuaries in Spanish-owned Florida.
In the 1820s, President Monroe’s secretary of war, John C. Calhoun, pursued a policy of removing the remaining tribes from the old Southwest and resettling them beyond the Mississippi. Jackson continued this policy as president. In 1830 Congress passed the Indian Removal Act, providing funds to transport the eastern tribes beyond the Mississippi. In 1834 a special Native-American territory was set up in what is now Oklahoma. In all, the tribes signed 94 treaties during Jackson’s two terms, ceding millions of hectares to the federal government and removing dozens of tribes from their ancestral homelands.
The most terrible chapter in this unhappy history concerned the Cherokees, whose lands in western North Carolina and Georgia had been guaranteed by treaty since 1791. Among the most progressive of the eastern tribes, the Cherokees nevertheless were sure to be displaced when gold was discovered on their land in 1829. Forced to make a long and cruel trek to Oklahoma in 1838, the tribe lost many of its numbers from disease and privation on what became known as the “Trail of Tears.”